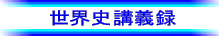世界史アプローチ研究会
『史料から考える 世界史20講』(岩波書店)読書会 2016年5月28日
「12 エジプトの早すぎた明治維新」報告

|
高校世界史教師で行っている勉強会での、私の報告です。 テキストとして、 『 史料から考える 世界史二〇講 』を使っています。 |

|
レジュメを用意させてもらいました。読んでおられなくても参加できるように要約を作りましたので、最初に要約を読んで、そこに引用している資料を見ながら説明していきます。そのあとに、考えた事を論点として3つ書かせてもらいましたので、それを提示して討論という形にしていただければと思います。レジュメの最後に、この部分を扱った時の授業プリントを資料的につけました。教科書のまとめ的な形ですが、こんな風にやっているという参考です。
では、本に従って内容の紹介をしていきます。
まず「はじめに」です。「ユーラシア大陸を挟んで東西にある日本とエジプトは先進国と途上国であるが、150年前のエジプトは日本に先行して近代化に取り組んでいた。日本の近代化の特性を西欧との比較で見るのではなく、アジア・アフリカ諸国との比較に留意して評価するべき時に来ている。」西欧と比べて日本の明治維新は…、という視点は日本ではいくらでもあるのですが、西欧ではなくアジア・アフリカとの、特に日本に先んじていたエジプトとの比較で見てみたらどうかという提起です。
1節は「エジプトにおける国民国家の建設」。国民国家は、加藤博さんがメインで取り上げているテーマだと思います。「国民国家という政治理念はヨーロッパに発するが、英仏を別にして現実の国民国家建設において、ヨーロッパが非ヨーロッパに先行していたわけではなく、同時並行的に進行していた。イタリア統一1861年、明治維新1868年、ドイツ統一1871年。オスマン帝国は18世紀の後半に近代国家への脱皮を試み、エジプトは19世紀前半においてアジア・アフリカで最も早く国民国家への道を歩み出した。」とあります。年表的に並べてみるとエジプトの改革、近代国家への取り組みは半世紀早いと見ることができます。「ムハンマド・アリーによる強力な近代的軍隊の創設による富国強兵、近代的工場制工業の創設をめざした殖産興業の実施である。ムハンマド・アリーはアラブ各地に進出を図り、スーダン、シリアなどを軍事占領、そこにエジプトと同じ統治システム導入をはかり、これらの地域でも『近代』が本格的に開始した。」最初に視点を提示して、これだけエジプトは早いと言っています。19世紀後半のイタリア統一、明治維新、ドイツ統一を並べていますが、すべて1860年代に起きていることで、世界が国民国家に移行するのはこの時期だろう。僕が授業でやるときは、ロシアの農奴解放、合衆国の南北戦争も60年代で、これも国民国家形成として、いつも生徒には並べて言っています。この60年代から70年代にかけて国民国家を作ったところが先進国に移行できたと授業では話しています。で、エジプトはそれよりも早いという事です。
資料で示しているのは88番です。ここで言っているのは、エジプトがオスマン帝国を凌駕するほど強くなったという事です。これは、教科書に第一次エジプト・トルコ戦争として出てくる戦争の最後の局面です。ムハンマド・アリーの長男イブラーヒームがエジプト軍を率いてシリアに攻め込んでいる。本を読んでいると、イブラーヒームという人は軍事的才能があったようで、連戦連勝。ナポレオンのような紹介のされ方をしています。彼が現れると兵士が奮い立つとか、そんな言い方をしていて、オスマン軍を打ち破り進撃していきます。この書簡の最後に「キャタヒヤより」と、彼がこの手紙を出した場所が書かれています。ここは、シリアを飛び越えアナトリア地方に入り込んで、イスタンブルから385キロの地点。このまま進撃してイスタンブルを攻め落とすか、というところです。この段階で、オスマン朝がロシアに助けを求め黒海艦隊とロシア陸軍が南下してアナトリア地方に上陸する。それを見て、英仏も介入を始めて、ここで進撃をストップさせられた。これ以上戦争はできないので、オスマン政府と交渉に入っている局面での、こういう条件ならどうだろうと息子から父親へ進言しているものです。資料の解説でも、5月に和平が成立したと書いてあります。オスマン朝を滅ぼす勢いがあったことが確認できればいいと思います。ここで一番目に要求するのは独立だとあって、あとは領土的な条件が書いてあります。結局、この第一次エジプト・トルコ戦争では独立は認められない。ただしシリアの領有は認められる。それから、アナトリア地方の一角でアダナ州の徴税権を取ったと解説には書いてあります。とにかく強かったことを確認できればいいと思います。
資料の107、108は、この結果シリアを統治する事になったエジプトの政策に関するものです。107は、イェルサレムの非ムスリムにそれまで課されていた通行税の廃止、地方長官の財源となっていた非ムスリム諸宗派への課税の廃止が書いてあります。平等に行政をしますよと、イブラーヒームがシリアで宣言している資料です。この資料を提示する事によって、加藤さんはエジプト統治をシリアにまで広げて近代国家を作ろうとしていたことの証拠としているのだと思います。ただ、この資料をそういう風に読めるかどうかはまた別問題です。新しい地域を占領すれば、当然そこに善政をしくことを宣伝的に、こんないい事をやりますよと呼びかけるのはありがちなことだと思うので、これ一つだけからは分からないと思いました。ただ、他の本を読んでいても、この時にイブラーヒームはアラブ民族再生をうたってシリア統治をしているようです。山口直彦さんの『エジプト近現代史』を読んで、結構参考になったのですが、山口さんはシリア統治に関しては「国民国家の誕生を予感させる面があった」という評価をしていますが、実際にはこのあとシリア各地で反乱がおきる。それは、ムスリム以外の者にも平等な徴兵をし、課税をしないという事で、各宗派の不満を招いて反乱があちこちで起きている。それが108の資料で、レバノンで農民反乱が起きていることが、そのあとのお話として載っています。だからエジプトの統治下にはいったシリアの人たちが、「よかった」と諸手を挙げて万歳をしているのではない。こうして並べていくとシリア統治が近代国家を作りだすものと言えるかどうかは疑問でした。加藤さんは、全体的にエジプトの政治は近代国家を目指していると主張しているので、そういう資料としてあげてはいるが、そう思えるかなと?いう事です。108の資料では、「家族をとらえる命令」を地方長官が出したり、民衆に「様々な拷問」を行ったり、「助命を乞うとカネをせびられる」とか、「山地の民を直接動員してこれ(炭田)を掘らせ」たとか、いろいろな物資を「運送する費用は(エジプト軍の)師団長が思いのままにした」とか、めちゃくちゃに使役して収奪している様子が描かれていいて、近代国家的かなとは思います。イブラーヒームが善政を布くと言っても、やっている事は征服王朝としての姿のように見えます。
次に、「エジプトにおける徴兵制の施行」で、国民国家を作ろうとしていたのだと加藤さんは主張します。それを突き詰めると強兵の実現であるという事で、エジプトの国民国家建設の性格は兵制改革、とりわけ徴兵制の施行に端的に示されているとします。エジプトの徴兵制度が1822年、日本は1873年なので、60年先んじて行われたのだ。これが近代国民国家建設の証拠だと取り上げている。「平等な」徴発によりエジプト「国民」を作り出す手段として機能した。ただし、徴兵制は労働力を奪うことで農家を疲弊させ、農民は徴兵を忌み嫌った、と書いています。
もうひとつ、近代国家建設の財源を得るため、農業改革を進めていて、それまでの自然灌漑ではなく人口通年灌漑システムを導入した。年中水を引けて作付面積を広げることをやったと書いています。通年作付けが可能となり綿花栽培が拡大し、それまでナイル川の洪水に浸からない高地にしか集落がなかったのが、低地にも集落が建設されるようになったということです。ムハンマド・アリーはこのエジプト統治で農地の国有化をしていて、そのことも少し触れています。ただし国有化はムハンマド・アリーの晩年にはだめになって私有地化が進んでいくことにも触れています。最後に農民は小作人へ転落していったということです。
この節の一番のポイントは、徴兵制を敷いた、だから国民国家なのだということです。近代国家を作るためには強い軍隊を作ることが必要だったということで、エジプトに先立ってオスマン帝国が兵制改革をやっていたというのが67の資料で、セリム3世がやった改革の紹介です。ただし、この18世紀末に行われたセリム3世の改革は、このあと保守化およびイエニチェリの反対によって潰され、洋式軍隊は解散し、失敗している。これに続くのがムハンマド・アリーの兵制改革で、90にその資料が挙げられています。徴兵にあたった村の村人が地方官に訴えている手紙です。これを読むと僕らがイメージするような徴兵制ではない。強制徴募というもので、プロイセンのフリードリヒ2世のお父さんのフリードリヒ=ヴィルヘルム1世が、農村を回って健康そうででっかい男がいればさらってきて兵隊にしたような徴発の仕方であって、近代的徴兵制といえるかは疑問です。この90の資料は再び写真付きで紹介されていて、この論文のメインとなるものです。また、後で話をさせてもらいます。
92は、土地国有化や灌漑システムを作った事の流れで提起された資料です。国有化して徴税も徴税請負人にやらせていたのを近代的な徴税システムに切り替えるのですが、ムハンマド・アリー没後はだめになって、土地が私有化されていくという資料です。ムハンマド・アリーの孫に当たる総督サイード時代のものです。サイード土地法は5年間継続して耕作・納税した農民に、その土地の販売・譲渡・貸借の権利を認めるというもので、事実上の土地の私有化を促したと別の本にはありました。この資料そのものは、この章の論旨にはあまり関係のない、単なる資料の紹介だと思います。
次に、「地方行政制度改革と農民支配」です。エジプト社会の変容のなか、ムハンマド・アリーの一連の近代化政策の多くは失敗。その最後の一押しが1840年のロンドン4国条約。エジプト総督位の世襲と引き替えに、不平等条約の下での経済的「開国」と、占領地の放棄を強いられた。その後彼の子と孫に積極的欧化政策が引き継がれた、ということです。当時の農村行政の解説があり、19世紀末に混合裁判所と国民裁判所という近代的な裁判所が設置されるまで、直訴という形での異議申し立てが認められており、行政当局がその訴えの妥当性を認めたとき、適宜「マザーリム(不正の意)法廷」という行政裁判が開廷された。資料90は、住民が男子家族の徴発に関して村長に異議を申し立てたもの。エジプトの伝統的な集落は、それぞれの地区の長老(シャイフ)によって司られ、村の行政は複数の長老の合議によって成されていた。1930年代になると、一村に一人の村長(ウムダ)が任命されるようになる。村長は国家に代わり村民を支配する村役人としての性格が強く、様々な情報が集中し利権が生じたため、だれが村長に任命されるかが村落政治の最大の関心事となった。村長創設当時は、徴税と徴兵を巡って職権濫用が多発した、ということです。
資料96は、1876年に混合裁判所が設置されるときの文書で、これ以前は直訴が認められていたという話です。104ページを見ると、江戸時代との違いが書いてあり、江戸時代は平民のお上への直訴が御法度であったということで、それとの比較として19世紀末には混合裁判所が設置されたし、それ以前は公の領域でのお上への異議申し立てが認められていたとある。論旨としては日本と比べてエジプトの方が進んでいた、明治維新でひっくり返るけれどその前を見てみるとエジプトの方が先に行っていたし、国民の直訴という権利を認めていたと言いたいがために、この資料をあげていると思いました。資料はこれだけのものですが、この資料の解説にもあるように、混合裁判所ができたからといって領事裁判権がなくなったわけではないので、混合裁判所の設立がエジプトの近代化にとってよかったという評価はしていないようです。半植民地化されていく過程のひとつとして見ておけばよいのかと感じました。
「徴兵制と農民支配」です。106頁には徴兵免除嘆願資料の写真も載っています。加藤さんはこれを見て欲しかった。こういう行政処理がありますというのを示したいがために、いろいろ書いているかなと思いました。嘆願書の余白に審査報告が順次書き込まれている。行政がちゃんと機能していて、中央当局の文章はトルコ語で、地方当局はアラビア語で書いて、訴えの真偽が「住民簿」「徴兵登録簿」「死亡登録簿」という完備されている名簿に従って確認され、訴えが認められ、徴発した村長は職権濫用により処分されたと思われる、とあります。きっちりと国家によって酷い行政官に対するチェックがなされたのだと言いたい。だから、近代国家がここに出来上がりつつあるということを言いたいのだと思います。そういう意味で、ここがメインで取り上げたかったのだろう。
ただこの資料をよく読むと、兄弟が4人いて1人がすでに兵隊になっていて、1人は死んで、残り2人でそのうちの1人がさらに兵隊に行くことになったということで訴えているのですが、ルールでは一つの生計の中で働ける男を1人は残せということなので、この訴えでは1人残っているので少し変なのです。解説と資料の中身がバチッと合っているのではないので、少し疑問は残りましたけどね。
93「エジプトにおける農民反乱(1860年代半ば)」がここで挙げられています。徴兵制を敷いた結果、男の働き手が抜かれていって農家家計の疲弊と農村荒廃をもたらした。その結果あちこちで反乱が起きた例として挙げられていますが、この資料はエジプトの農村の反乱ではない。資料にアフマド=タイーブという人名が出てきますが、これはスーダンのマフディーの反乱のマフディーなのです。反乱を起こしかけて一旦砂漠に逃げるのです。そのあと勢力を盛り返してマフディー国家建設をする前段階の、逃げる時の話です。エジプトではなく遠いスーダンの話。しかも、農村の荒廃ではなく、救世主が出現するという流れの中の話なので、本文で解説している内容と資料があっていない。強引な紹介だなと思いました。資料の書き手がの女性がゴードンとあるので、太平天国にかかわってマフディーの反乱で殺されたゴードンの奥さんかなと思ったら、全然違うゴードンさん。あのゴードンの奥さんとして紹介したかったのかなと思ったら、それでもなかったので拍子抜けというか、なんだろうなという資料ではあります。
全体として、言っている事はわかるけれど引用している資料は、趣旨に沿っていない。強引な紹介の仕方をしている。資料一つ一つを読んでいくときに方向性がないと解釈ができないので、ある方向性を持って読むのは当然なのですが、ちょっと強引だなと思います。一番思ったのは、日本語に翻訳してあるので、僕らにはニュアンスが分からない。翻訳を信じるしかないのですが、それでいいのかなというのはあります。101頁にムハンマド=アリーが登場する前に、「くにの長」(シャイフ=アル=バラド)を頂点に実質的な独立体としての歴史を歩みだしていたと紹介しているのですが、シャイフ=アル=バラドを「くにの長」と書けばそんなように気がしますが、山口さんの本ではこれを「カイロ知事」と訳していました。山内昌之さんは「くにの長」のような訳をしていた。素直に訳したらそうなるのかなと思うけれど。ただ、このシャイフ=アル=バラドが何者かというと、マムルークのボスです。マムルークはエジプトの人たちに忌み嫌われているので、そういう称号を名乗っているからといってエジプトが一つの国民国家としてまとまりつつあったかどうかはまた別問題だろうと思います。めくっていくと、そうとは言えないのじゃないかという事実が出てくるので、ある意味面白いし、中途半端な知識を振り回してもなんですが、考える余地はあるなと思いました。以上が、本と資料の紹介です。
思ったことですが、ムハンマド・アリーが国民国家を目指したというのが加藤さんの主張です。本当にそういえるのかということです。国民国家が何かというのは、またあとで議論してもらえたらよいですが、近代国家とか近代国民国家とか、ほとんど同じ意味で辞書的には出てくるので、市民革命以後の国家なのだろうと漠然とした状態で話をします。
国民意識みたいなものが国民国家には必要だろうと思うのですが、加藤さんが山川出版社で出している『ムハンマド・アリー』では、「オスマン帝国の住民のアイデンティティは宗教的なもの」だと。「なに人」というよりは「なに教」を信じているか。コプト教だとかスンナ派だとか、そういう宗教的なアイデンティティが一番だと書いていました。それから、岩波講座『世界歴史』で三木亘さんは「トルコ系支配層とアラブ人の被支配大衆とのエスニックなレベルでの断絶は深いものがあった。前者は、…アラビア語住民の社会や文化と隔絶した存在であり、…アラブ諸地域のまったく寄生的な異質物であった。」(岩波世界歴史21「オスマン帝国のアラブ支配とその解体」)ということで、アラブ人と支配層は全く断絶しているという書き方をしています。
ムハンマド・アリー自身の発言として「シャイフ(長のことです)であれ、コプト教徒であれ、カイロの住民であれ、農民であれ、そのほかの階層の犠牲のもとに、一つの階層を優温することはしない、すべては平等だ」があって、この発言をとらえてみんな平等に扱うから「国民の創設」なのだ。「ワタン(祖国)の概念」が生まれ、「国民意識」を醸成しようとしたのだと、加藤さんは『ムハンマド・アリー』で述べていましたが、国民意識を醸成しようとした事に関する具体例は載っていません。平等に扱う、特権は認めないぞ、という発言ではあるけれど、これが国民の創生と言えるかどうかは議論の余地があると思います。
4番目に、この論文では、ムハンマド・アリーはアラビア語を話せなかったと書いてありましたが、山口さんの本では、ハンマド・アリーは「オスマン人」(帝国のエリート層)という強い自意識のため、アラビア語を解しながら、決して話そうとしなかったと書いてあります。こっちの方がリアルな気がします。ムハンマド・アリーがそういう意識であるならば、先ほどの支配層とアラブ人の間の深い断絶という指摘と呼応する。こういう意識でエジプトの国民国家というものが果たして生まれてくるのかは大きな疑問です。
それから、カイロ市民の状況ということで、ムハンマド・アリーがカイロの人びとに擁立されて総督になっているという状況は実際にある。三木さんの『世界歴史』の論文を長いですが読みます。「1735~70年にかけては、経済市況が安定し、民衆運動はまったくみられないが、アリー=ベイ(18世紀末にエジプトの独立を図ったムハンマド・アリーのさきがけのような人です)没後の混乱のなかに、はるかに高度な運動が展開しはじめた。同職組合・スーフィー同朋衆・地区などの組織を背景とした大衆指導者があらわれて、運動がより意識的・組織的になるとともに、指導的なウラマーや大商人からアーヤーン(名士層)がこれに結びついて、運動がたんなる貧民暴動ではなく、全市民的な様相を呈する。…イスラーム的な価値原理と土着民的な価値原理とが、マムルーク=ベイたちをもふくめた、異民族支配への抵抗のなかに結びついてゆく。それは「国びと」という、一種市民的ないし国民的主体意識の形成過程であった。『国民的』とあえていったのは、ウラマーの媒介で、都市民と農民との結びつきもうまれはじめていたからである。」ということで、カイロでは一定の名士層、富裕層、ウラマーの間に市民的な意識が生まれかけていたということです。「カイロ市民の武装蜂起を背景に、ウラマー独力で総督を交替させ、ウラマーがカイロの政治の『主人公となった』(ドロヴェッティ)(エジプト史家です)のは、はじめてであった。イブン=タイミーヤ(ウラマーです)の政治学が実現し、『国びと』の論理が貫徹したのだともいえよう。ムハンマド=アリーも、『その公正と慈恵を認知したが故に、国びとの定めた条件に従って』推戴されたのであり、その公式記録にも、ウラマーのひとりムハンマド=アルマフディーが、『古来の伝統と神の法によれば、すべての国民は支配者を任じまた廃する権利を持つ。暴君は法のまことの道をはずれるが故に、諸国民のそれを廃する権利が存する』と、書きつけていた。」革命権みたいなことを言っているウラマーがいたようで、そういう流れの中で、ムハンマド・アリーは総督に推戴された。ムハンマド・アリー自身の言葉として、「主人が二人いる。スルタンと百姓(フエツラーフ)だ」ということで、自分を擁立したカイロ民衆を確実に意識し、これを利用したということです。ただし、総督になった後、彼はそういったカイロ民衆の運動を解体、徐々につぶしていき、専制的な支配をやっていくようです。カイロ市民の動きはあったものの、ムハンマド・アリーが国民国家を目指したと言えるかどうかが一つの論点です。
論点2として、近代化の内実。国民意識は別として、近代国家を目指したその中身はどうかということです。早すぎた「明治維新か、遅れてきたサラディンか」というのは、僕が勝手につけたのですが、有能な支配者ではあっただろうが、実際やったことは何か。
徴兵制を早い段階で始めたと加藤さんは書いていたけれど、実態としてはスーダンで黒人奴隷を挑発して新軍という新しい軍隊を拡充しようとしたのですが、うまい具合に黒人奴隷が手に入らない。スーダンから黒人奴隷をエジプトにつれてくると気候が合わずに死んでいく。それでは困るので、農民を徴発する方式に変えたと清水書院の人物シリーズ『ムハンマド・アリー』で岩永さんが書いていました。ここに載せていませんが、そもそもスーダンで黒人奴隷を徴発しようとしたのはなぜかというと、ムハンマド・アリーが自立しようとするのでオスマンのスルタンが新しい兵隊たち、マムルーク系、チュルク系の新兵がエジプトに行くのを阻止した。中央アジア方面から兵隊を募集するのを阻止したので、スーダンで集めるしかなく、それも失敗したのでエジプト農民を挑発したというのが、加藤さんが言う徴兵制が始まった経緯のようです。「各県(ムディーリーャ)ごとに、一定数を割り当て、兵を強制徴発した。兵員数が村に割り当てられると、村長は贈賄者を除いてできるだけ多数をかき集めようとした。軍の一小隊が村を包囲して、農民をとらえた。かれらは鎖でつながれて、医師のいる地区に連行され、適性によって陸軍と海軍に振り分けられた」ということで、奴隷狩りと同じようなやり方で兵隊を集めている。ただし、評価する面も書いてあって、「新軍(ニザーム-ジャディード)は、比較的無規律な外国傭兵に比して、民衆への暴行に走らず、規律をもった。エジプト民衆を敵のように扱うこともないし、行軍のあとに荒廃を残さなかった。新軍の組織は、ある程度民衆教育と行政の改革に貢献し、かつ国民的意識を根付かせるのに役立った。(岩永博『ムハンマド・アリー』清水書院)」と、プラス面も書いています。ただ、それ以前の兵隊がどれだけひどかったか、ということかもしれませんが。
農業、工業です。ムハンマド・アリーは農地を国有化します。ある本では「公地公民制」をはじめたと書いてあり、分かりやすいと思いました。「農民は自由に居住地を変えられず栽培作物の自由な決定権無し」。ムハンマド・アリーは土地国有化と同時に専売制をやります。農作物を固定価格で買い取って、それを外国に売る。差額で儲けて商売したので、農民には自由に経営する権利がなかったようです。あと、近代工場をたくさん作ったと教科書にも載っていますが岩永さんによれば、内実は、軍需工場では囚人が強制労働させられていた。労働者は農村からも強制的に徴発した者を使用していた。技術能力が低く、機械労働を嫌い怠業する。一番びっくりしたのは、動力に蒸気機関を使うものは少なかった、ということです。石炭が高くて買えなかった。機械を買い入れたけれど、動力には、牛、ろば、らくだが用いられた。綿織物工場でも機械は牛力で動かされた。いきなり止まったり動いたりするので、製品は均一性を欠いて品質が悪かったということです。「利潤は政府が吸いあげ、無能で技術力のないサラリーマン官僚が経営に当たり、高価な輸入機械を低能率で使用するばかりで、民間人の利潤意欲と勤勉性を失わせている。世界経済は自由主義の原理で、世界市場で原料を自由に購入し、製品を自由に販売する体制をめざしていた。ムハンマド=アリーのとった原料の売買と製品の専売制は、全くこの原理に反していた。1838年の通商協定は、エジプトの政策に対する西欧資本主義の総攻撃であった。」(岩永)ということでした。
財政です。財政は健全化され、効率よく徴税するシステムをつくりあげることに成功したようです。ムハンマド・アリー治世を通じて、地租収入は約9倍、為替換算率を考慮すると約4倍だったということです。ムハンマド・アリーが総督になる前は、徴税請負人が土地の三分の二を保有して、しかも徴税分の多くを手数料としてキープして総督に納めない。徴税請負人の一掃、マムルークの大虐殺もやる。徴税請負人にも300人ほどマムルークがいたようなので、マムルーク勢力の一掃はそういう意味もあったようですが、これらを通じて税収が上がったようです。専売制でも収入が増えます。国家の独占貿易、管理貿易体制なので税収は上がります。ただし、ワッハーブ派との戦争、ギリシア独立戦争への派兵、エジプト=トルコ戦争とか、戦争が続くので常に財源は不足していた。しかし、ムハンマド・アリー時代は一度も外国からの借金はしなかったということで、健全財政を貫いたようです。外国からの借金で首が回らなくなるのは、サイードがスエズ運河を建設した辺りからです。そういう意味では近代国家建設は順調に行ったのかもしれない。
論点3は、いろいろ読みながら考えたところです。教科書ではエジプトは実質上独立したと書いてあるのですが、調べていくと本当に独立しているのかなと感じるところが大きい。常に、総督であったり副王であったりという地位がエジプトの足かせになっていて、自由にいろいろなことができていなかった。一番大きいのは1838年のイギリス・オスマン通商条約。これはオスマン帝国とイギリスとの間に結ばれた初の不平等条約で、関税自主権を放棄し領事裁判権を認める中身です。エジプトは形式的にはオスマン帝国の一地域なので、この条約によって、エジプトに不平等条約が適応されます。ムハンマド・アリーはこのイギリス・オスマン通商条約で、関税自主権がないことをエジプトに適応されることを避けたいが故に、どうしても独立をしなければ、ということで、この年に第2次エジプト・トルコ戦争を始めます。目標は正式な独立の獲得。ここで、イギリスがまた介入してきて1840年のロンドン会議が開かれ、独立は認められず、シリアは放棄させられた。エジプト総督位の世襲は認められますが、結局何も手に入らない。以後、不平等条約を適応されて、ここからエジプトはだめになる。ムハンマド・アリーの努力はすべて水の泡になっていくと思います。
資料にエジプトの輸出入相手の表を載せました。加藤さんの『ムハンマド・アリー』にあったもので、非常に面白いと思います。1831年段階のエジプトの輸出入相手国では、輸出も輸入もトップがトルコ。オスマン帝国ですね。具体的には分からないのですが、シリア地方がこの中では大きいのではないかと思います。牛やラクダを動力にして毛織物や綿織物を作って、製品は粗悪なのにどこに売っていたかというと、シリアに売っていたらしいです。エジプトがシリアを統治していて、そこにエジプト製綿製品が売られるので、イギリス製綿製品がシリアに売れない。これが、イギリスがエジプトからシリアを取り上げ、不平等条約を適用させる大きな動機ではないかと、前後を読んでいるとそんな感じがしました。貿易相手国としては、トルコに次いでオーストリア、トスカーナ、イギリス、フランスです。イギリスもフランスも輸出も輸入も大きいとは言えるけれど、そんなに大きな比重を占めているわけではないし、オーストリアの内実はヴェネツィアということで、ヴェネツィア商人が出入りしている。トスカーナもリヴォルノのユダヤ人商人ということなので、1838年のイギリス・オスマン通商条約が適応される前は、エジプトはまだ近代世界システムの中に組み込まれていない状態だと思います。ロンドン条約を受け入れさせられた後のエジプトの輸出入相手国が次の統計で、輸出入相手の69.5%がヨーロッパで、英が42.2%、仏が12.7%、輸出先は英76.6%で綿花を輸出している。綿織物工業がつぶれて原料の綿花の輸出国として、世界システムにがっちりと組み込まれて周辺国、従属国の地位にはまっていった。実質的な独立ではないことが足かせになったということです。
それから、総督位世襲が認められたと教科書にも書いてありますが、1840年に世襲が認められたときに総督位継承のルールが定められ、ムハンマド・アリー一族の最年長者が継ぐことになっていたそうです。系図を見ると、ムハンマド・アリーの長男のイブラーヒームが死んだ後、その子供に位が行かず、弟が継いでいるのは最年長者が継ぐというルールが適応されている。3代目の総督がそのルールの適用をやめるために、オスマン皇帝や要路に献金をしたり貢納金を増やしたり、わいろを贈ったりいろいろしています。エジプトは19世紀後半になっても貢納金をオスマン帝国に毎年払い続けています。途中で、総督の称号が副王に変わっているのですが、なぜかというと、貢納金をめちゃくちゃたくさんにしたのです。そのかわりに称号を副王にしてくれということで、スルタンが「よっしゃ」と副王に称号が変わった。1873年にもさらに貢納金を倍増する事の引き換えに、さまざまな内政面の特権をスルタンから認められている。全然独立国じゃないと感じました。1879年に新しい副王が即位するのですが、1873年に様々な特権を与えたスルタンは、新副王即位を機会にその特権を回収した。その結果、軍隊の兵員を減らさなければならなくなり、エジプトは縮軍します。そのとき、だれを首にするのかということになったのですが、エジプト軍の中で特権を持っているのは非エジプト人系の将校グループなのです。エジプト人系の将校グループのリーダーがウラービーで、非エジプト系を温存し、エジプト系を首にしようとしたことが、ウラービーが政府に対して改革を要求していくきっかけとなったそうです。意外なことで、19世紀後半になっても、エジプトの中では総督・副王が頼りにしているのは非エジプト人系のグループだったということで、国民国家とは違って征服王朝的な雰囲気がかなり強いなと思いました。
論点4は、明治維新との比較を最後皆さんに検討していただければよいと思います。国民国家ということが、加藤さんがここで言っていることですが、国民国家ができるには国民意識があるのだけれど、国民意識が生まれる前提として国民経済の成熟が大事だと思う。国民経済を担うのは産業ブルジョアジーだと、僕は発想します。明治維新の場合も薩長政権ではあるけれど、殖産興業で国家独占ではない形で産業の育成をする。エジプトは国家独占の産業育成であったし、エジプト人の産業ブルジョアジーを育成するという観点が、あったかどうかは分かりませんが、どの本を読んでいても出てこないし、根本問題としてイスラームの中からは産業資本家があらわれにくい。前回イスラーム銀行の話が出てきましたが、最近ようやく現代社会に対応するなかで出てきたのであって、資本を蓄積して産業を興すという発想、資本の蓄積という発想がムスリムの富裕層の中に出てくるのか等、根本的な問題がいろいろあると思いました。
最後、授業プリントを載せました。実際にはさっと流すだけです。スエズ運河の開通に関してはフランス人レセップスの提案で、当時の総督が子供のころレセップスが家庭教師をしていたとか、ムハンマド・アリー時代からエジプトとフランスの関係が強いのです。なぜかというと、ムハンマド・アリーが強い軍隊を作ろうとした時に、当時ヨーロッパで一番陸軍が強かったのはフランス。しかも、政変によってナポレオン系の将校たちが大量に失業していたこともあって、エジプトに招きやすく、急速にフランスと接近したようです。
それから、スエズ運河の株式売却でイギリスが買うのですが、買っているのはイギリス政府なのですね。残りの株式はだいたいフランスが持っているのだけれど、フランスの株式は多くの株主に分散している。なのでイギリスが一番強くなったようです。なぜ、フランスがこの時にスエズ運河株式を買わなかったかというと、普仏戦争のあとでドイツに賠償金を支払う過程にあって、余裕がなかったようです。
「ウラービーの反乱」とプリントには書いてありますが、この時使っていた山川の教科書が「反乱」だったのでそのまま使っているだけです。教科書によって反乱とか革命とかいろいろな表現があります。この時に、改革を要求してアレキサンドリアなどでエジプト民衆が外国人を襲って大混乱になる中で、イギリスが出兵します。このとき、イギリスはフランスにも共同出兵を呼びかけていますが、フランスが断ったため単独出兵になります。フランスが断ったのは、このときアルジェリアでアブデル=カーデルの反乱があるのです。それにてこずっていたのと、1881年にチュニジアを保護国化したばかりで、そのテコ入れに手を取られていたためです。この間、調べていて疑問が解けたところなので紹介しました。
(以下討議、省略)
【参考文献】
『 ムハンマド=アリー―近代エジプトの苦悩と曙光と (1978年) (Century books 人と歴史シリーズ―東洋〈20〉) 』 岩永博、清水書院、1984
『 ムハンマド・アリー―近代エジプトを築いた開明的君主 (世界史リブレット人) 』 加藤博、山川出版社、2013
『 新版 エジプト近現代史 ――ムハンマド・アリー朝成立からムバーラク政権崩壊まで 世界歴史叢書 』 山口直彦、明石書店、2011
「オスマン帝国のアラブ支配とその解体」(岩波講座『世界歴史21』)三木亘、1971