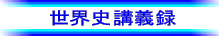世界史アプローチ研究会
『史料から考える 世界史20講』(岩波書店)読書会 2018年3月24日
「10 牝牛保護と不殺生(アヒンサー)~インド・ナショナリズムの運動と「倫理」」報告

|
高校世界史教師で行っている勉強会での、私の報告です。 テキストとして、 『 史料から考える 世界史二〇講 』を使っています。 |

|
「はじめに」では1910年代、ヒンドゥー至上主義(ヒンドゥトヴァ思想)とその政治実践が広がり始め、これがヒンドゥーとムスリムの対立を強める一要因となり、これが第二次世界大戦後のインド・パキスタン分離独立へつながると指摘しています。このヒンドゥドヴァ思想はガンディーが思い描いていたインド・ナショナリズムと食い違うところがあり、ヒンドゥー至上主義の価値観の象徴の一つが牝牛保護の問題です。ガンディーも牝牛保護に関心を持っていて言及しているのですが、その視点はヒンドゥー至上主義とは少し違っているので、のちにガンディーは難しい立場に立つことになる、と書いてあります。
先回りして言うと、独立直後ガンディーは暗殺されますが、暗殺したのはムスリムではなく、ヒンドゥー至上主義の団体の人に殺されている。徹底的に牝牛保護を考えるヒンドゥー至上主義とガンディーはニュアンスが違う。その違いが、至上主義の人には許されなかったということです。
以下、文章に従って説明していきます。
「1 牝牛保護運動とヒラーファト運動」です。
第一次世界大戦後、独立の約束を反故にされたことで、第一次サティヤグラハ運動(1919~1922)が盛り上がります。このときに南アフリカから帰ってきたガンディーが国民会議派のリーダーとして、サティヤグラハ運動を指導していきます。このなかで、オスマン帝国が大戦で敗北し、ムルタファ・ケマルによってオスマン帝国が滅び、スルタン制がなくなり、カリフ制もなくなっていくのではないかと言うことで、カリフ制を守れという運動がイスラーム圏全体で広がっていきます。このなかでインドのムスリムもカリフ制を守る運動を始める。これをヒラーファト運動といいます。イギリスはカリフ制に関しても鍵を握っている、帝国主義のリーダー国なので、イギリスに対してカリフ制をなくなという抗議が起きる。これはムスリムたちの反英運動なので、サティヤグラハ運動も同様に反英運動ということで、共闘が生まれてくる。ムスリム側もサティヤグラハ運動の盛り上がりを利用したいし、ヒンドゥー側もヒラーファト運動と連携して、インド一帯としてイギリスに抵抗するということで、両者が足並みをそろえます。
このときにガンディーがヒラーファト運動のところに出かけていって演説をしている(1921.1.26)。この本には「牝牛を救いたいと欲するならば、カリフ制を助けに行きなさい」という形で紹介されています。この一言でも、牝牛が出てきて、ヒンドゥー教徒にとっては切実な問題だったことが分かります。
牝牛がいつ頃インドのヒンドゥーにとって問題になってくるかというと、19世紀末です。この頃から、大衆的基盤を持つ民族運動が形成され、ヒンドゥー的価値観が支柱となったのが牝牛に対する尊崇の感情、「ゴー・マーター」(母なる牝牛)という心情、これが彼らの芯のところにある。一方、イスラームのお祭り「犠牲祭」、巡礼月に動物を生贄にするお祭りがあって、ムスリムが牛や水牛を生贄に捧げていた。「バカル・イード」(牛祭り)といいます。ヒンドゥー的価値観が民族運動の中心になってくる中で、犠牲祭のたびにヒンドゥー側の批判と攻撃が強まってきて、19世紀末になると、特にきたインドで犠牲祭のたびにムスリムとヒンドゥーが衝突するようになります。ただ、19世紀前半までは、ヒンドゥー・ムスリム間の血なまぐさい争いは起こっていないということなので、民族運動の盛り上がりと宗教的な対立が並行的に始まってくるのですね。ヒンドゥーは各地で牝牛保護協会を設立したり、屠殺・老牝牛保護などを展開しながらムスリムの犠牲祭を攻撃していきました。
こういう流れの中で、ヒラーファト運動とサティヤグラハ運動は両者融和のチャンスであり、画期的なことだったわけです。ガンディーは第1回全インド・ヒラーファト会議(1919.11.23@デリー)に呼ばれ、次のように演説します。「私はヒンドゥーに対して、牝牛保護問題をこの場に持ち出さないように提案する」"ヒラーファト運動への協力と、牛屠殺の中止をバーター取引のようにしてはならない"というのがガンディーの立場です。しかし、これは高度な論理なので、個別問題の取引を超えてインドでヒンドゥーとムスリムが協力しなければならいという彼の立場は、理解しがたくて、先ほどの「牝牛を救いたいと欲するならば、カリフ制を助けに行きなさい」という少し後の発言なのですが、こういう発言も含めて、交換条件と受け止められる面もあったし、多くの人はそうとらえていただろうと言うことです。ヒンドゥーとムスリムの絆の弱さ取引としてつながっているだけなのです。
このあと、チャウリー・チャウラ事件(1922.2.5)という警官焼き討ち殺傷事件があって、そのニュースを知ったガンディーは、サティヤグラハ運動中止を宣言します。この中止によって、ヒンドゥー・ムスリムの団結の機運もしぼみ、逆に両者の対立が激化していきます。チャウリー・チャウラ事件で運動を中止したというのは、おもしろいテーマでこのことにも関心があるのですが、授業ではさらっとやっています。今年岩波新書に『ガンディー』という本がでましたが、こういう運動中止に関する評価が全くなくおもしろくなかったです。ガンディーのファンの人が書いたような本です。歴史の一番ダイナミックなところで、国民会議派が運動を中断していくことにすごく興味があるのですが、底は書いていなかったです。ホブズボームはインド独立運動を押さえてきたのはインド国民会議派だ、インド民衆の運動が自分たちの指導を乗り越えていこうとするたびに、国民会議派は運動を中止するという分析をしていましたが、それは別の話なので。
運動が急速しぼんだ後、ガンディーは牝牛保護運動に注力していきます。その保護団体の議長にもなっていきます。ヒンドゥー教徒のナショナリズムを維持していくためには、こういうテーマを捨てることはできなかったのだろうと思います。
「2 不殺生と牝牛保護」です。
ガンディーの考え方を書いている章だと思いますが、ガンディーの非暴力は不殺生という彼の持っている倫理観に含まれている。不殺生の中の一つのテーマです。これをガンディーが取り上げていったのは、イギリス的肉食文化に対するインド(ヒンドゥー文化)の精神的優越を表現するものであったと書いてあります。こういう立場から、ガンディーは非暴力運動を訴えていくのですが、僕らは何気なく不殺生はインド人みんながそう考えているのかと思っていたのですが、もともと不殺生戒はバラモン(人口の5%)に課された戒律であり、インド(ヒンドゥー)文化全体を律する規範ではなかった。後から出てきますが、バラモン化現象というのかな、インド全体の様々なカーストやジャーティの人々が、自分たちの属しているジャーティが、より上なものだと主張したいがために、バラモンの風俗をどんどん取り入れバラモン化を目指す、階級上昇運動みたいなものがあるのですよ。不殺生戒もこういう流れの中で、下へ下へと広がっている。有名な寡婦自殺(サティ)も、バラモンだけのものだったのが、どんどん他のカースト、ジャーティのものにまねされていきました。
ガンディーの言葉です。「牝牛を…保護することだけで…解脱を得られるとは信じていない。…牝牛保護は、その本性からして、すべての感覚を持つ存在の保護を含まねばならない」牝牛保護運動をガンディーも言うのですが、彼にとっては一つの象徴であり、不殺生戒をみんなに守ってもらう手段として牝牛を取り上げていくと言うことだと思います。「しかし、当面のところ、牝牛保護とは主として牝牛およびその小牛を残酷な行為や屠殺から守ることを意味し…」でも、当面は牝牛を保護すると言うことですね。
「不殺生」というもともとバラモンだけのものだった戒律を、インド、ヒンドゥー全体の大義として掲げ、現実には牝牛保護をヒンドゥー的価値観を主張している、と受け取られても仕方がない、ということです。ですから、ヒラーファト運動と牝牛保護をバーターにしてはいけないと言いながら、牝牛保護はヒンドゥーの価値観としてみんなが死守しなければならないようなものとして受け取られていく。「はじめに」であったガンディーの本当の思いと受け取られ方の「齟齬」が生まれてくる。それはガンディーの主張自体の中にもある程度含まれているのだと言うことです。
牝牛保護の問題はイギリス統治下にあっても、ヒンドゥー・ムスリム間の問題として継続しますが、次は独立後どうなったかという話です。
「3 独立インドの牝牛保護法」です。
1947年、インド・パキスタン分離独立し、1948年ガンディーが暗殺されます。分離独立した後の宗教分布を紹介しておきます。
インドの人口13.3億人、ヒンドゥー教徒79.8%、イスラーム教徒14.2%。15%近いインド人がムスリムです。キリスト教徒2.3%、シク教徒1.7%、仏教徒0.7%、ジャイナ教徒0.4%。仏教との大部分は不可触民の人たちで、新仏教と呼ばれるものです。
パキスタンは人口2億人。こちらはムスリムの割合が多くて、イスラーム教徒96.1%、キリスト教徒2.5%、ヒンドゥー教1.2%。
バングラデシュは、人口1.6億人。イスラーム教徒89.6%、ヒンドゥー教徒9.3%。意外とムスリムが多いですが、それでもヒンドゥーも10%近くいる。(以上データブック・オブ・ザ・ワールド 2017年版)
よく世界最大のイスラーム教国はインドネシアだと言います。インドネシアの人口は2億6千万なのですが、実はインドネシアのムスリム比率は56%。とするとインドネシアのムスリム人口は、1億4千5百万人ですよ。13億3千万のインド人の14.2%のムスリムは1億8千万。実はインドネシアのムスリム人口よりインドのムスリム人口より多い。日本の人口よりも多い。全然少数派ではない。もちろんヒンドゥーに比べれば少数派ですが。多分世界最大のイスラーム教国はインドだと思います。今はね。ニジェールも2億人近いですが、インドのムスリムには及ばないと思います。ちょっと参考までに述べさせてもらいました。
こういうなかで、独立後のインドです。ネルーはヒンドゥー・ムスリム両派の対立を避けるように国家雲形をするのですが、それに不満なヒンドゥー至上主義の団体が作り上げたのが、ジャン・サン党(ヒンドゥー至上主義政党)です。この党は牝牛保護法制定運動をずっとやっています。この党は、牝牛保護は言いますが、不殺生の倫理は全く持っていない牝牛保護に特化している。それが反ムスリム運動なのですが。
この党は1951年第1回総選挙に牝牛保護をかかげ、92名の候補者を出しますが、当選は3議席。そんなに支持を集めていなかったのですが、1966年くらいから牝牛保護運動が急速に盛り上がり、1967年第4回総選挙では35議席に躍進、特徴率が9.1%。1980年にインド人民党に改名し、1998年総選挙で第1党となり人民党中心の連立政権が発足しています。2009年総選挙では国民会議派与党連合が勝利し政権の座から降りるのですが、 2014年総選挙ではインド人民党が勝利し、現在はインドの政権を担っています。ヒンドゥー至上主義の運動を今ガンガンやっているようです。
参考までに去年の朝日新聞の記事を出しておきました。インドの牛肉産業の記事です。約2億のムスリムがいるので、インドは世界1の畜牛飼育国で、牛肉輸出も世界一だそうです。ですが、インド人民党政権のもとで、攻撃されています。写真の食肉加工工場も、2本のラインのうち1本が止まっている。なぜなら、原料となる売りが手に入らない。肉牛運搬トラックがヒンドゥー至上主義者に襲われて、業者が失明したとか、そういうことが書いてあります。写真は「シェルターで保護された牛」と書いてあります。インドでは野良牛がいるのですが、食肉業者が野良牛を捕まえて屠殺しないように、牝牛保護団体がシェルターに集めて保護している、という写真です。牝牛だけではないけれど、こういう牛の保護が現在も焦点になっているとことを紹介しました。
1950年制定されたインド憲法にこういう条文があります。48条「国は農業及び牧畜業を…振興するように努めなければならない。とくに、品種を維持・改良し、牛、子牛その他の搾乳用及び農役用家畜の解体処理を禁止する措置を採らなければならない」乳牛と役牛、農差が行に使う家畜の解体処理は禁止ですが、そうではない牛はやっていけないわけではない。連邦政府としては牝牛保護法未制定ですが、地方においてはほとんどの州で牝牛保護法存在しています。(1966年までに牝牛屠殺完全禁止の州法を制定したのは6州、部分禁止は3州、全く制定していなかったのは2州)。 厳しい罰則もあって、ヒンドゥー以外からの反発や、訴訟のケースも多数あるということです。
「おわりに」です。インドの牝牛保護という、ヒンドゥー教の教えと結びついた問題を取り上げているので、世界の動物保護はどうかと言うことで、小谷さんはイギリスの法律を取り上げています。イギリスのマーチン法(1822)です。これ以前にも動物保護の法はあるのですが、だいたいは貴族のスポーツとしての狩猟の獲物をとっておくためのものでした。純粋に虐待禁止は、このマーチン法が初めての法律です。最初は牛とか馬だけなのですが、だんだんと範囲が広がり、いわゆる一般的な動物保護法が1911年に作られている。
日本では動物保護法のようなものは特になかったのですが、明治時代に財産としての動物を保護する法律はありましたが、「動物の保護及び管理に関する法律」は1973年。これは、外国人からペットを虐待しているという避難を避けるために作られたものです。これが発展し、「動物の愛護及び管理に関する法律(1999)」ができます。動物保護の法律は世界に多くあるのですが、牝牛に特化した問題は、インド文化に特有のもので、これが普遍的倫理につながるか?という形で筆者は締めています。
レジュメを読むだけになりますが、『ラーム神話と牝牛』(小谷)から関連することを抜き書きしたようなものです。ヒンドゥー・ムスリムの対立がこの章のメインテーマですが、そもそもイギリスがインド統治をし始めた頃のことから書いてあります。
当初、 東インド会社はインドにおけるキリスト教布教に積極的ではありませんでした。なぜかというと、宣教師が布教するということは、ヒンドゥー・イスラムを攻撃することになる。それによって生まれる宗教対立がインド支配の基礎を覆しかねないと考えたからです。ですが、1813年にインドでの布教認めるようになります。その理由は、イギリス人がみたインドの専制支配とカースト制でした。イギリス人からすると、ヒンドゥー教徒は道義が欠落している。それは何かというと、どんな罪も「浄めの儀式」、喜捨といった外的行為により贖罪され、内面的倫理を形成しないということです。専制支配もそういうインド人の倫理形成をさせない原因だったと。それをイギリス的視点から改善するためにはキリスト教布教が必要だと考えました。
宣教師たちからみて、19世紀前半まで諸宗教共存していたということです。宣教師に対してもインド人たちは好奇心をもって接することはあっても、排斥することはなかった。あるバラモンが言うには、「キリスト教は優れたものです。しかし、私たちの宗教もよいものです。それぞれの宗教の教えに従って生きるならば、人は救われるのです」。これは宣教師が書き留めていることです。このあたりは、我々日本人にはわかりやすい発想です。このバラモンの発言は、僕らにはよく分かる。非一神教で似たような感じだったのかなと思います。
宣教師のヒンドゥー批判の論点は、多神教であること。そのこと自体がもう許せないのですね。様々な神々を信じていて、しかもその神々は神話の中で悪行をしている。そして、ヒンドゥーは偶像を崇拝している。これはだめだと宣教師たちは考えた。
これに対するヒンドゥーの反論です。M=ダーンデーカルの発言。「魂は何か執着すべきものをもたないければ、一瞬たりともいられない。しかるに神は形を持たない。それゆえ、聖典では祈りの対象が考え出され形作られた」。これは偶像崇拝に対するヒンドゥーのお坊さんからの反論です。これは合理的説明です。魂はよりどころがないとだめなので形を作ったという説明です。こういう合理的理性的説明は、ヒンドゥー一般の宗教感情からほど遠い。一般信者の気持ちとは違うところでの反論。だからこの反論はヒンドゥー教徒にも共有されない。相手の土俵に立った反論でしかなかったわけです。
イギリス宣教師側がキリスト教の方が優れていると主張する根拠が、植民地支配の「神義論」です。イギリスがインドを支配したことが、キリスト教が唯一真実である証明であると。「イギリスは偶像を捨てて神に呪われたと思いますか?祝福されたと思われますか?」と宣教師がヒンドゥーに問いかけると、もう反論できない。「業(カルマ)」の考えでは反論できない。今ある現実は、過去のカルマの結果なのだとする考えでは反論できない。これがヒンドゥー側の「やり場のない怒り」になっていきました。
そのインド人ヒンドゥーがイギリス人の弱点を見つけた。「牛食い人種」としてのイギリス人です。われわれヒンドゥーは肉食しない。肉食しないヒンドゥーという自己像を徐々に形成していきました。先ほど不殺生はもともとバラモンの習慣で、それが徐々に下の階層に広がっていったと話しましたが、この段階でも肉食をしなかったのはバラモンだけで、他のカーストは肉食をしていたと書いてあります。ただ、牛食い人種イギリス人と彼らを定義することによって、虚構としてのアイデンティティとして肉食忌避規範を取り入れるカーストが増加していきます。ヒンドゥーがイギリス人よりも優れているのは肉食しないことだと言うことが、彼らのナショナル・アイデンティティになっていきます。ところが、ヒンドゥーが周りを見渡してみると、ムスリムも牛を食べている。ということで、1875年、インド・ムスリムの牛屠殺に対して「牝牛保護協会」が設立され。牝牛保護の運動が広がっていきます。ムスリムが牛を殺してお祭りをしていることを差し止める裁判があちこちで起こされていきます。ただ、伝統的にやっていたことをやめさせる根拠はなかなかないので、これらの法廷闘争はイギリスの管轄なのですべて失敗しますが。
そのなかで、奉献牡牛問題というのがあります。家族に死者が出た場合、死者の供養に牡牛を放ち自由にどこへでも行けるようにするという供養があります。この放たれた自由になった牛を、ある不可触身分の人が捕まえて、それをムスリムに売り、それをムスリムが屠殺して肉にするという事件があった。これが裁判になります。この牛は財産か、無所有権物かという裁判になる。最終的に裁判所は話したのだから無所有物だから、捕まえてどうしようとかまわないという判決になりますが、こういうものがこの頃から問題になってきて、ヒンドゥー・ムスリム間の緊張が増してきます。さっき野良牛の話をしたのですが、いまインドに行くと野良牛がうろちょろしているのですが、誰の所有物でもないので、捕まえて屠殺して肉処理してもいいはずなんですよね。19世紀終わりに、奉献牡牛をつかまえたことが裁判になっていると言うことは、この頃は牛はうろちょろしていなかったのかとも思う。野良牛がたくさんいるのなら、いくらでも捕まえて生贄でも牛肉にでもできる。今インドで野良牛がたくさんいる風景は、現代的な風景かもしれないと、これを読んでちょっと思いました。
そのころからムスリムの牛の犠牲祭でのトラブルが起きるようになります。ガンジス川支流沿いにアヨーディヤという町があり、そこで1893年、牛の犠牲祭で、ヒンドゥー教徒がムスリム織物カーストを襲い10人以上を殺害しています。以後、両者協定を結び自重しています。この『ラーム神話と牝牛』という本の最初と最後に出てくるのが、このアヨーディヤでの衝突事件なのです。1990年代にもアヨーディヤで大きな衝突で人が死んだ事件があって、その事件からこの本は説き起こしています。この町にはバーブルのモスクというモスクがある。これは、バーブルが作ったわけではないのですが、ムガル帝国初期に作られた。ただ、このバーブルのモスクの場所には、もともとヒンドゥーのラーマという神様、ラーマーヤナのラームですが、その生誕地だったという伝説がある。その生誕地にムスリムがモスクを作ったということで、現在も焦点になっているそうです。
1905年にベンガル分割令がでます。これによってインド・ナショナリズムが高揚しますが、ムスリムにはヒンドゥー・ナショナリズムであったという書き方もしてありました。
1908年、アラハーバード高裁判決があります。ムスリムが私有地で牛を屠殺するのは何ら問題はない。「私的所有権の神聖不可侵」という一般論で裁判所はムスリムが牛を屠殺する権利を認めました。「ムスリムによる牛屠殺の慣行が確立している場所では、ヒンドゥー側もそれを黙認するが、その慣行が今までなかったところでは、ムスリム側が牛の屠殺をひかえるという妥協によって辛くも保たれていた安定状態を突き崩す」ことになります。牝牛とは限りませんが、屠殺問題はだんだん焦点になってきます。
第1次世界大戦末期、1916年ラクナウ協定で、国民会議派とムスリム連盟の協力・提携が合意されます。指導者レベルでこのような妥協が成立するものの、底辺、庶民レベルでは「牛の犠牲祭」をめぐる対立・抗争が激化していて、1917年はそういう暴動の頂点だったそうです。
1919年、全インド・ヒラーファト会議が開かれ、カリフ制擁護と牝牛保護とを双方がそれぞれ自発的・無条件に支持しあうことが、ムスリム・ヒンドゥー両コミュニティの指導者たちにより提唱されました。これは、この章にははっきりと書いてありませんでしたが、カリフ制擁護を全インド的反英運動である非暴力運動と結びつけることで推進しようと考えたムスリム側がヒンドゥー側に協力を呼びかけて開催されたものです。ムスリム側がヒンドゥーのサティヤグラハ運動を悪い言い方をすれば利用したわけですが、結果としては、宗教アイデンティティ強化の方向に作用しました。
ガンディーにとって、牝牛保護は不殺生という普遍的倫理まで高めるべき課題なのです。不殺生こそ反英ナショナリズムの価値的・倫理的基礎にすべきだと考えていました。しかし、不殺生の課題は牝牛保護という小さなところに修練して、現実には反英から反ムスリムへつながることになります。不殺生は称揚されますが、肉食を忌避するカーストが増加することは、ヒンドゥー・ナショナリズムに結実するだけで、インドナショナリズムには結びつきませんでした。
インド国民会議派はよく分からない組織だったのですが、この本を読んではっきりしました。1920年に国民会議は政党化し、運動も組織化されます。それまでは、単発的な会議を開くだけだったのですが、組織化され、全国大会を最高決議機関として、全国委員会、執行委員会を設置、党費(年間四分の一ルピー)支払えば誰でも党員となれる大衆政党として活動を始めます。議会政党という性質も持っているので、大衆運動体としての面のあいだを振幅します。ガンディーが運動を盛り上げながら、急に中止したりするのは、そういう側面と対応するのだと思います。
1922~23以降、パンジャブ中心にヒンドゥー・ムスリムの衝突が多発します。反英闘争後退とともにヒンドゥー・マハーサバー(ヒンドゥー大連合)の活動が活発化します。(ガンディー暗殺者もここから出ます。)反英運動のエネルギーの矛先が、ヒンドゥー至上主義者の強化に向かう。ヒンドゥー自強運動といって、ヒンドゥーが強くなれば紛争は終わるという考えです。弱いから攻撃される。そういうなかで、1925年 全インド牝牛保護会議がボンベイで開かれ、ガンディーが(心ならずも)その議長になります。この運動がムスリムとの対立をさらにあおることになるのは分かっているのですが、議長になることを拒否もできないという立場でした。ただ、ガンディーは「ヒンドゥーはイギリス人の牛の屠殺については何も言わない」とは言っています。
1919年インド参事会法改訂(モーリー・ミントー改革)により、1920年より各州に立法参事会が成立します。独立は認めないが、自治を少し認めるというインド倒置法です。ただ、参事会は立法権はなくて、州政府に質問し答弁を求める権利はあるが議決権はありません。ただ、そこで参事たちが、州政府に様々な注文をつけるのです。屠殺禁止または制限を求める質問が多数州政府に出されるようになります。
たとえば、ビルマ向け乾し肉生産問題(1910~20年アーグラ・アウド連合州立法参事会で議論)があります。インドではビルマに乾し肉輸出する産業がありました。これにたいして議論がおこなわれます。乾し肉を輸出するために、連合州で「家畜の減少、農耕用家畜の購入価格上昇」という問題が起きているのではないかと参事会員が州政府に質問し、問題視します。ただし、これは表面的理由で、本心は牛の屠殺の妨害です。州政府の中で、牝牛問題、牛の屠殺問題が議論されるようになりました。
1935年、円卓会議が終了し、新インド統治法が成立、1937年に州立法議会選挙がおこなわれます。議決権を持つ州立法議会にインド人が議員として参加します。多くの州でインド国民会議派中心の内閣が成立します。しかしこの直後第2次世界大戦が始まり、1939年インド中央政府がドイツに宣戦したことに各州立法議会は抗議し、各州インド国民会議派内閣一斉辞職したため、牛の屠殺問題などの議論は実質的になされませんでした。唯一、この間の1938年にボンベイ州立法議会でヒンドゥー議員が牝牛と農業用牛を保護する法案提出したが、1939年の州立法議会機能停止で討論もおこなわれないままですぎさります。すべての問題は、第2次世界大戦後の、独立インドに持ち越されていきます。
3節の終わりにあったように、インド憲法では、牧畜牛の振興、品種維持改良、牛・子牛その他搾乳用および農役用家畜の解体処理を禁止すると書かれ、各州では牝牛保護に関する様々な法律が制定されているというのが流れです。
参考ですが、ホブズボーム『極端な時代 上』によれば、「第三世界の人々は、西欧人に対してと同様、近代化を不可欠と思っている自国のエリート層にも反対」「中流階級による民族主義運動の主要な課題は、自らの近代化計画をあやうくすることなく、本質的に伝統主義的で反近代の大衆の支持をいかにして獲得するかにあった」p315.316。インドのリーダーたちがインドの近代化を図ろうとするときに、一般大衆の反感を招かないように、伝統主義的な装いで大衆を組織化することが必要だったわけですね。この牝牛保護運動は、ぴったりこれに当てはまりますよね。ホブズボームはティラクを取り上げていました。ティラクは「牛の神聖さと10歳の少女の結婚を守り、古来のヒンドゥーないし『アーリア』文明とその宗教が近代『西欧』文明とそれを尊敬するインド人よりも精神的にすぐれていると主張することを考えた」。インド人は西欧文明よりも優れていると、ティラクは言っている。そのために取り上げたのが少女の結婚問題です。インドの伝統では少女は10歳で決行できる。ところがイギリスは1891年 承諾年齢法で、女性の結婚による性交が許される下限を10歳から12歳に引き上げようとしたことに対して、ティラクは反対して、10歳でかまわないという。これはまさしくインドの大衆を引きつけるためですね。(イギリスの不介入とヒンドゥー自身が決定すべきという立場から)。
またティラクは1893年ガネーシュ・フェスティバルの組織化し、1895年シヴァージーの祭り組織化に成功します。伝統的な神様や民族英雄の祭りを作り組織化していった。こうしてヒンドゥー・ナショナリズムの組織化に成功したのですが、一方でヒンドゥーとムスリムの間の悪感情をさらに増幅させた。新たな伝統の創出ですよね。ガンディーのあの服装も伝統的なものではなく、ガンディーが考案したもののようです。ネルーがかぶっている帽子もガンディー帽といって、ガンディーが考案した。ガンディーがかぶっているのをみたことはないのですが、そういう演出を国民会議派の人たちはしていたのかなあと思います。
それでいえば、明治初期の廃仏毀釈運動は牝牛保護運動に通じるなあと思います。み維持政府が近代化する中で、復古的な精神を組み込みながらやっていく。ホブズボームの見解と重なります。
また、ビルマ向け乾し肉輸出問題で、乾し肉のために牛を殺すために農耕用家畜の値段が上昇するなどと言う論点があったのですが、これに関して、1587年バテレン追放令を出す前に、秀吉が宣教師に詰問状を出している。そのなかに、「なぜ有用な道具である牛や馬を食べるのか?」というのがあって、前近代では、役牛は凄惨に欠かすことのできない手段であり、それを食することに対する抵抗感があった。インドの牝牛保護がどこから来ているのか分かりませんが、こういう論点もあるのかなと思いました。
最後に動物保護法と言えば、やはり生類哀れみの令かなとおもったので、すこしレジュメで触れておきました。以上です。
(以下討議、省略)
【参考文献】
『20世紀の歴史 上 (ちくま学芸文庫)』ホブズボーム