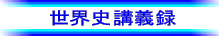世界史アプローチ研究会
『名著で読む世界史120』(山川出版社)読書会 2018年11月3日
トルストイ『戦争と平和』

|
高校世界史教師で行っている勉強会での、私の報告です。 テキストとして、 『 名著で読む世界史120 』を使っています。 |

|
最初にストーリーを紹介し、授業で使うならどんなふうに使えるかを紹介します。その後、トルストイの生きた19世紀ロシア史のおおざっぱな流れを紹介し、それとトルストイとの作品の関係を考えてみたい。最後のほうは、どうしてこれがトルストイ?と思う人がいるかもしれませんが、自分がトルストイに触発されて長年気になっていることをお話ししておきたいと思います。これは直感的な感想なので、トルストイを読んでこんなことを考えるやつがいるのか、くらいに聞いてもらえばよいと思います。
今回戦争と平和を選んだのは、好きなんですよ。高校時代に読んで以来、3回くらいかな、読み直しています。高校時代は長編小説シリーズだったんです。本屋に行って、とにかく長い小説を読んでいた。吉川英治の『三国志』からはじまって。トルストイははまったのですが、ドストエフスキーははまらなかった。わけもわからず『静かなるドン』なんかも読みましたね。さきほど、浅田先生と話をしていたら、一巻で終わったということで。最初の名前さえ克服すれば、何とか行くのかと思うので、ストーリーも紹介していきたいと思います。
『戦争と平和』はどんな物語か。ストーリーは、1805年アウステルリッツの三帝会戦から1812年のナポレオンのロシア遠征までの時代を舞台に、ロシアの貴族階級の人々の日常の暮らしと戦場の様子を描きます。主要登場人物であるピエールとアンドレイの精神的彷徨が丹念に描かれ、何組かの男女の恋愛が、ストーリーを牽引します。
アウステルリッツだけでなく、ロシア遠征のボロディノの戦いもかなり丁寧に描いています。戦場のシーンと貴族のサロンのシーンがはんはんくらい。あと、トルストイが自説を展開している部分もかなりあります。ここは彼の考え丸出しで、小説とはあまり関係ない。そういう部分は面白くないので,読んでいてその部分がきたと思ったら飛ばしてもらって全然かまいません。
岩波文庫の新版『ロシア文学案内』での要約です。「歴史を動かす民衆の精神を体現して、将軍クトゥーゾフがフランス軍に勝利する過程が物語の第一の柱、開放的なモスクワ貴族ロストフ伯爵一家と、高踏的ペテルブルグ貴族ボルコンスキー公爵親子、大富豪の庶子ピエール・ベズーホフ、外見の美と内面の醜で際立つクラーギン公爵一族などが、互いにくりひろげる愛憎生死のドラマが第二の柱」(小野)。その通りかなと思います。
ストーリーを細かく説明させてもらいます。主な登場人物(年齢は1805年段階)は、小野さんの要約で出てくるロストフ家、ボルコンスキー家、それからベズウーホフ家のピエールですが、物語の中心になるのはピエールです。
ピエール・ベズウーホフ伯爵のキャラクターは永遠の青年です。最初から自分探しをやっています。フランスで暮らしていて、父親が病気になって呼び戻される。呼び戻されるところから、物語は始まります。サロンに来るのですが、貴族社会の空気が読めなくて、とんちんかんなことをやっていて、周りからはあほ扱い。体は大きいのですが、、ウドの大木のような扱いをされています。内面はピュアで、本当の自分は何だろうとか、真実はどこにあるのだろうと最後まで模索しています。最後の最後で何をつかむという形で、この話は終わります。今ならセミナーなどに行きまくる感じの人です。
ピエールの親友が、アンドレイ・ボルコンスキイ公爵(20代)、陸軍将校、クトゥーゾフ将軍の副官です。クツゥーゾフはモスクワ遠征の時にロシア軍の司令官になった人で、戦略的に退却したのか逃げたのか、いろいろな評価があるのですが、トルストイはクトゥーゾフを褒め称えています。こういう実在の人もちょこちょこ出てきます。1巻の最後にアウステルリッツでアンドレイが大けがをしたときに、ナポレオンが登場します。4巻のモスクワ遠征の所でも、ナポレオンが登場して台詞もあります。トルストイはたくさんの資料を読み込んで小説を書いているので、史実も反映しているのではないかと思います。
アンドレイは、自己に厳しく、精神の高みを目指す人です。だから、貴族社会のサロンのおべんちゃらのやりとりにうんざりしています。逆に、貴族社会に浸かっている、泳いでいる人から見ると、融通の利かない堅物、ダメなやつと見られています。アンドレイとピエールは仲が良い。二人とも嘘はつかない、自分の内面に正直なので親友です。ピエールは社交辞令もろくに言えないので、アンドレイはそこを気に入っている。二人とも父親同士が仲が良く、ともにエカチェリーナ2世時代の顕官だった。その縁で二人は知り合ったらしい。アンドレイの父親はちょくちょく出てきます。引退しているけれど。
ピエールの父親は危篤状態でベッドにいるので、登場はしません。その父親ベズウーホフはロシア一の大富豪。ピエールは庶子なので、長い間フランスで暮らしていた。父親が呼び戻せと命令したのでロシアに帰ってくる。庶子なのに、瀕死の父親が呼び戻したのは、父親が自分の財産をすべてピエールに譲るつもりではないかという噂が、社交界で流れている。だから、ピエールが社交界でとんちんかんなことを言う。みんなはぼんくら扱いするけれど、父親の財産を相続する可能性があるので、邪険にはされない。そういう立ち位置です。体も大きいし、なにかこの人は器量が大きいかもしれない、潜在的には大人物かもしれないという書き方はされています。
ロシアの帰ってくるのですが、父親の周りには娘たちや取り巻きがいるので、父親の屋敷も呼ばれない。小遣いだけはたくさん与えられているので、ペテルスブルクで近衛将校たちと毎晩どんちゃん騒ぎをして遊んで暮らしている。そのうちに、ひどい騒ぎを起こして、ペテルスブルクを追放になって、モスクワにやってきます。庶子なので、財産相続権はなかったのですが、父親が皇帝アレクサンドル1世に、自分の全財産をピエールに譲る勅許を求め、エカチェリーナ2世時代の顕官なので特別に許されます。財産を相続し、ロシア一の大富豪になる。そうすると色々な人がよってくる。
その中で、クラーギン家のエレンという女性がいる。色々な夜会とかサロンに登場するたびに、父親クラーギンがエレンを連れてやってきて、くっつけようとする。ピエールは、エレンを好きではないのですが、流れとして結婚しなければいけないのかなと考えて、最終的にプロポーズして結婚します。エレンの設定はものすごい美人です。クラーギン家は皆美形のひとたちばかり。その美しさに抗しきれず、愛していないことを心の中で知りながらも、若気の至りで結婚します。
財産目当てなので、結婚生活はすぐに破綻します。エレンは自分を、間抜けで粗暴な夫を持ったかわいそうな美人な人妻として設定して、社交界に出てきます。ピエールはかっとなると手がつけられないところがあった。エレンは同情されて社交界のスターになります。エレンには愛人の噂もたくさんあって、それがピエールの耳にも入る。屈辱的ですよね。ある夜会で、ピエールは愛人の噂のある男ともめて決闘騒ぎまで起こします。それをきっかけにして、二人は別居するようになり、エレンはますます同情されていく。
この頃から、ピエールはますます自分探しに熱中し、フリーメーソンにも入会します。入会のための様々な儀式も描かれいます。ここはけっこう興味深いです。入ってみると、知り合いばかりだったりするのですが、なかにはメンターのような老人もいて、ピエールはその人が好きなので、けっこうまじめに活動をします。財布が大きいし、みんながおだてるので、おだてられるままに支部長になったりして、様々な経費をどんどん出していきます。
この時代に関わるかもしれませんが、自分の領地で農奴の賦役免除の改革にも取り組みます。ただ、実際的な人ではないので、領地の管理人に、「また、若旦那がわからんことをいっとるわ」みたいな形で、あまり相手にされず、改革は不十分に終わる。うまくいかなくて、ますます悩んだりします。
ただし、ピエールの気立ての良さ、人の良さは、次第に人々に浸透して、変人と思われながらも、独自の位置を確立していくようです。ピエールの雰囲気をうまく伝えるのはこんな文章です。「モスクワ中の人々が、老婆から子供たちまで、いつも場所を用意してあけておいた、かねてから待望の客を迎えるように、ピエールを迎えた。モスクワの社交界にとってピエールはもっとも愛すべき、善良で聡明な、陽気な、心おおらかな変人で、ぼんやりしているが情を知る、昔気質のロシアの旦那だった。彼の財布はみんなに開放されているので、いつもからだった。」(第2巻第5部1)
最後に、フランス軍がモスクワを占領したときに、彼は避難しない。見てみたいという好奇心で、モスクワにとどまっているうちに、フランス軍に捕まり捕虜になる。収容所でおなじく捕虜のプラトン・カラターエフと出会います。農民プラトンの生き方は彼に深い印象を残し、のち自由の身になったピエールは、精神的にある境地を獲得します。悟りをひらいた感じ。最終的には処刑されずに解放されるのですが、のちのちまでこのときに出会ったプラトンの生き方を何度も思い返すと書かれています。このプラトンが、たぶんロシア民衆の象徴です。
それからナターシャです。かの場はロストフ家の娘。かつてのアンドレイと婚約しています。ところがこの婚約は破れて、物語の最終盤ではピエールと結婚します。エレンはどうなっているかというと、ロシア軍が攻めてくるときに病気で死にます。うまい具合に死ぬんです。
ナターシャはアンドレイと婚約していたのですが、いろいろあってダメになって、自分が悪いのですが、滅茶苦茶傷ついてふさぎ込んでいるその心を開いたのがピエールです。徐々に恋愛感情が芽生えていく。エピローグがあって、1820年のシーンがある。その中ではもう結婚していて、子供も何人かいる。トルストイはここで、ナターシャを「多産の雌豚」という、変な表現で呼んでいます。ここで、彼らはモスクワに住んでいるのですが、ピエールはペテルスブルクの会合の出かけていて、帰ってくる。この会合がデカブリストの会合らしい。本文を読んでも、そのことは読み取れないのですが、解説書を読むと、ピエールは最後にデカブリストに接近していくと書いてあり、このことらしい。こういう話を潜ませています。
アンドレイに話を戻します。謹厳なアンドレイは、社交界を嫌悪しています。妊娠中の美しい妻リーザがいますが、社交界で水を得た魚のように振る舞う妻リーザにうんざりし始めている。最初のサロンでそういうシーンがあります。リーザはアンドレイの気持ちが離れていく理由が理解できず不安。
アンドレイにとって率直に話すピエールだけが心を許せる友人であり、軍人としてはナポレオンを高く評価している。その理由は強いから。自分もあんな英雄になりたいという願望を持っている。彼が副官として仕えているクトゥーゾフ将軍は、大勢いる副官の中で特にアンドレイを買っています。その理由は、クトゥーゾフとアンドレイの父親との友情、アンドレイの能力の高さ、そして勤務態度です。前線に出ずに楽をしようとか、出世の踏み台として副官になったのではないところです。
アンドレは第一部の最後、アウステルリッツの戦いで敗走する自軍を立て直そうと、落ちていた連隊旗を掲げてフランス軍に突入し、瀕死の重傷を負います。戦場で倒れているところを、ナポレオンが戦場視察に来る。死に直面して、ナポレオンの愚かさと、倒れた彼の目に映る青空の美しさを悟ります。
九死に一生を得て、ロシアに生還しますが、出征中に妻リーザは出産するのですが、産褥で亡くなっています。生まれた男の子は、彼の妹マリアが面倒を見ています。帰還したアンドレイは、軍務を離れて領地の経営改革を成功させ、その後政権中枢の政治家と懇意になり、政治改革に取り組むのですが、その間に、一回り以上年の離れたナターシャを知り、愛し合い、プロポーズします。きっかけは、ある用事でアンドレイがロストフ家を訪問する。宿泊することをすすめられて、彼はロストフ家に一泊するのですが、夜なかなか眠れないので、窓を開けていると、上の階にナターシャがいて友達とおしゃべりをしている。窓の上から聞こえてくる彼女の楽しげなおしゃべりに、心が癒されていくのです。そのあたりから、気になるようです。次に舞踏会の時です。ナターシャが舞踏会デビューしたときに、誰にもダンスに誘われないので、泣きそうになって壁際にいるところへアンドレイがよっていって、ロストフ家に泊まったときにしゃべっていたのは彼女だなとわかっているのでダンスに誘う。すると、泣きそうだった彼女が非常に生き生きし出して、ダンスも上手で、会場のみんなが注目するような踊りを披露する。基本的には、生き生きした子なのです。アンドレイはすっかり魅せられてしまって、求婚する。しかし、アンドレイの発案で、彼女が若すぎるため、婚約は両家の秘密とし、1年間の猶予期間をおくこととします。先の戦争で負った怪我の療養のため、アンドレイがロシアを離れている間に、エレンの兄アナトーリが、ナターシャを誘惑。クラーギン家はみな美形なので、アナトーリもすごいイケメンなのです。アンドレイが遠くいて、寂しい気持ちにアナトーリが入り込むのです。ナターシャは心惹かれ、アンドレイに婚約破棄の手紙を書きます。二人は駆け落ちをはかります。ちゃんとプロポーズをすればいいのに、駆け落ちを図るのは、実はアナトーリはポーランドで結婚している。だから、駆け落ちを提案する。ナターシャはそのことを知りません。でも、のぼせ上がっているので駆け落ちに同意します。
ピエールはロストフ家によく出入りしていたのですが、なぜか様子がおかしいので、なんだろうなと思う。そして、ナターシャのいとこから駆け落ちの計画を知ります。ピエールは、アナトーリが自分の嫁の兄なので、アナトーリがすでに結婚していることを知っている。そこで、アナトーリを呼びつけ、しかりつけ、金を渡して、立ち去れと命じます。アナトーリは金を受け取って立ち去ります。駆け落ちは秘密だったけれど、アナトーリはプレイボーイだから、色々言いふらしていたので、こんな事件があったらしい、男と逃げようとしていたらしいという噂が流れる。ナターシャはショックですよね。自分でも、一次の気の迷いで婚約者のアンドレイにひどいことをしたと思う。それ以後、性格は暗くなって、屋敷に引き籠もりがちになります。しばしばロストフ家を訪れるピエールが、彼女の気持ちを慰め、やがて二人が結びついていく。それが一つの流れです。
帰国して婚約破棄を受け取り、自分が不在中に起きた事件の顛末を知ったアンドレイですが、そのことについての動揺は誰にも見せず、1812年のフランス軍の侵攻に際して再び軍務につきます。ボロジノの会戦で再び重傷を負い、馬車に乗せられ後方へ。さらにモスクワから避難する際に、偶然ロストフ家と同道することとなり、アンドレイの重傷を知ったナターシャは謝罪して、許され、必死に看病しますが、アンドレイは看病を受けながら死んでいきます。
マリア(アンドレイの妹)は、篤い信仰心をもち、父親の元で暮らしています。人見知りが激しく、社交界には出入りせず、婚期を逸しかけています。容貌は醜いと表現されますが、時に瞳が美しく輝き、醜さが消える。それは、控えめな彼女が能動的になっているときです。心から尊敬する父や兄を思いやって行動したり、信仰心が厚いので、こっそりと物乞い・巡礼を屋敷に招き入れて、彼らの話を聞くときなど。ボロジノの会戦直前に、父公爵が死に、兄は戦場に行っている。彼女一人の時に農民が一揆を起こします。その対応に困っているときに、ナターシャのお兄さんのニコライが、物資調達でたまたま屋敷にやってきて、彼が一括して農民一揆を封じて、二人は知り合う。彼女は自分の中で、恋愛は自分には向かないと思っているのですが、ロマンスが少し芽生える。物語の本当の終わりで、二人は結婚することになります。
ニコライ・ロストフ伯爵(10代後半)。アウステルリッツの戦いを前に志願して、士官候補生となり、従軍します。最後の方では軍の上の方になっています。『戦争と平和』の戦争、軍隊部隊における将校の暮らしぶりの多くは、彼を通して描かれます。キャラクター的には、アメリカの青春映画に出てくるような元気で活発な男の子です。プロム・キンウみたいな感じ。何も考えていない、精神的には平凡ですが、マリアの中にある美しい心に気づくだけの感性はある。基本的にロストフ家の人たちは、何も考えていない。楽しく暮らせればよい。
ロストフ家の父親伯爵も何も考えていない。物語の進行の中で、父伯爵の農場経営の失敗と放漫な暮らしによってロストフ家は巨大な負債を抱えていきます。最後には、フランス軍のモスクワ占領によって完全に破産する。最後は何もかむ失って、ニコライは母親とアパート暮らしをしています。父と兄を失った公爵令嬢マリアとの結婚は、結果として財政の困窮を救うことにもなった。ただ、ニコライは農地経営には才能があって、ナポレオン戦役後は領地経営に熱中し、また手腕も発揮し、借財を返済、父が手放した領地も買い戻していきます。安定した領地経営は農民は暮らしも向上させ、農民から見て「よい旦那」として描かれます。
ナターシャ(ニコライの妹、最初の登場は15歳)。本小説最大のヒロイン。映画化されるとナターシャを主人公にすることが多いですが、たぶん本当の主人公はピエールです。やはり読んでいて楽しいのは、この人が出てくるシーンです。舞踏会のシーンとか、田舎の領地で歌を歌うシーンとか、うきうきして楽しくなります。無邪気で、自然に振る舞うだけで人を惹きつける存在として、トルストイは魅力たっぷりに描いています。読者としても、彼女の登場が楽しみです。アンドレイもその魅力にやられた。もちろんピエールも心を引かれているのです。アンドレイの手前、最小はその気持ちを抑えていますが。
さて、長々と『戦争と平和』を説明してきましたが、授業に使うならばどんな場面で利用できるでしょうか。
まずは、「ロシアはアジアかヨーロッパか」です。長らくモンゴルの支配下にあったロシアは、ヨーロッパなのか、アジアなのか。教科書では、こんな感じです。
「15世紀になると商業都市モスクワを中心としたモスクワ大公国が急速に勢力をのばし,大公イヴアン3世のときに東北ロシアを統一、1480年にはようやくモンゴル支配から脱した。かれは…ローマ帝国の後継者をもって自任し,はじめてツァーリ(皇帝)の称号をもちいた。」
「ピョートル1世が,みずから西欧諸国を視察し,これを模範に改革をすすめた。」(山川 詳説世界史改訂版 2006)
客観的に見て、ロシアはピョートル1世時代からヨーロッパ化をめざした国であって、そのあとヨーロッパの仲間入りをする。ところが、ロシアはヨーロッパと思い込んでいる生徒は多いと思うのです。そこで、これを使えるのではないか。19世紀半ばのトルストイが、この小説の中で、フランス人がロシアをアジアと呼ぶ場面を描くのです。先ほども述べましたが、トルストイは『戦争と平和』を書くに当たって、徹底的に資料に当たったようですから、典拠があるかもしれません。
「〈無数の寺院を持つこのアジアの都、モスクワ、聖なるモスクワ! ついに来たぞ、この有名な都へ! ついに〉」と言って、ナポレオンは馬をおり、自分の前にこのモスクワの地図をひろげるように命じて、通訳のルロルム・ディドヴィーユを呼んだ。(第3巻第3部19)
この部分を、イヴァン4世か、ピョートル1世のところで紹介すると、ロシアとヨーロッパの距離がわかりやすくつかめると思います。〈 〉はフランス語で話している部分です。
改めて考えると、ロシアで国会が開かれるのは、イランと同じ1906年ですから、この二カ国は同列です。日本よりもヨーロッパから遠いと言えるかもしれません。
19世紀のロシア人の中でも、アイデンティティは問題になっていて、西欧主義者とスラヴ主義との対立というものがあります。
ロシアでは西欧化に対して二つの思想的潮流ができました。一つは西欧主義者。特徴は、ロシアの後進性の自覚。西欧近世社会の基盤は啓蒙思想と解放思想にあると考え、農奴解放がロシアの課題としてとらえられます。トルストイは、西欧主義者最大の思想家であるゲルツェンをその亡命先に訪ねており、西欧主義に属するでしょう。
もう一つの潮流がスラブ主義。ロシアをヨーロッパにしなくてもよいと考える。特徴は、ギリシア正教信仰、皇帝の独裁政治支持、民族主義。パン=スラヴ主義をとなえます。農奴制や官僚制は、ピョートル1世以来の欧化政策の悪しき結果と考えます。帝政末期には国是となります。ただし思想としては1860年代以降は退潮していて、スラブ主義を述べ立てる人はいないようです。ただ、ドストエフスキーはシベリア流刑になった後は、熱烈な皇帝独裁支持者になる。スラブ主義者といって良いと思います。
話を授業での活用に戻します。
ルイ14世の政策の成果として取り上げることができそうです。ヨーロッパ文化の中心としてのフランスを強調したかったら、使えるかなと思います。「貴族のあこがれ、フランス語」です。
「『…ところでいまわが国のどこにいますかな、スヴォーロフのような名将が?〈ひとつあなたにおうかがいしたいものですな〉』とのべつロシア語とフランス語のあいだを往復しながら、彼は言った。(第1巻 第1部 16)
山形括弧はフランス語です。最初のサロンのシーンでも山形括弧頻出です。ロシア人しかいないところで、ロシア語、フランス語がまぜこぜで話されています。
「アンドレイ公爵は、父がどうしても引きさがりそうもないのを見て、自分でも気づかずに話の途中からフランス語に移りながら、予想される会戦の作戦計画を語りだした。」(第1巻第1部23)
自分でも気づかずにフランス語になっている。教科書ではこんな部分に対応します。
「彼(ルイ14世)は…,大規模な宮殿をヴェルサイユに建造し,その宮廷には貴族や芸術家が集められた。宮廷生活は細部にいたるまで儀式化され,それが国王の権威を高めた。」(山川)
「この宮殿(ヴェルサイユ)では、貴族だけでなく多くの芸術家が活躍し、ヨーロッパ文化の中心となった。」(帝国 新詳世界史B 2014)
ロシア以外の国こんなにフランス語が使うことがあったかどうかわからないのですが、ないような気がするのですが、ヨーロッパにあこがれている分だけ、こういうことがあるのかなあと思いました。
三つ目は、フランス革命の波及力の例として。
「…ピエールは、返事もしないで、自分の意見を述べつづけた。『いいえ』と彼はますます勢いこみながら言った。『ナポレオンは偉大です、なぜなら彼は革命の上に立ったからです。その悪用をおしつぶして、市民の平等、言論の自由などいっさいのよいものを守ったからです。だからこそ政権を掌握することができたのです』」(第1巻 第1部 4)
最初のシーンで、サロンでナポレオンが偉大だと言っているシーンです。サロンでそんなことを言ってはダメなので、ピエールがダメな人という烙印を押される最初の発言なのですが、本音で言っているわけです。ロシア人でもこんなふうにあこがれを持ったとして使えるかな。設定として、ピエールはフランス帰りなので、ナポレオンにかぶれていても仕方がないのですが。
また、フランス革命に付随して、ナポレオンの影響力というものがあります。ピエールがフランス革命の理念の共鳴しているように、アンドレイはナポレオンの強さ(フランス軍の強さなのだが)に、あこがれを抱いています。ナポレオン戦争を通じて、ロシアの将校が感じたロシアの後進性が、のちのデカブリストの反乱につながります。
『人類の知的遺産 トルストイ』(川端)によれば、「トルストイの父親の世代は、フランスの啓蒙思想によって育まれ、ナポレオンに抗して立ち上がり、ロシアの皇帝の専制に対しても抵抗した世代である。…トルストイの父の親友にはデカブリストが何人かいる。」ということで、彼の身近にもそういう人がいて、影響を受けたのだろうと思います。
それから、これは授業で紹介するのは難しいと思うのですが、私たち教師がバックグラウンドとして知っておいた方がいいと思うのが、ここで描かれる軍隊の日常生活です。登場人物が貴族出身の士官、または士官候補生であるためか、不自由はしていませんが、先頭があるとき以外は、自由気ままに軍隊生活を楽しんでいます。兵卒の立場ではまた違うでしょうが。
読んでいて、びっくりした場面がありました。モスクワ放棄後のことですが、ある部隊の司令官が、駐屯場所を抜け出して、地方貴族の夜会に出席しています。モスクワが占領されているのに、近隣の地区で夜会が開かれていることもさることながら、夜会出席の理由が“直上の司令官が嫌い、その命令を聞きたくないから”部隊を離れている。そのために、クトゥーゾフの命令は伝達されず、孤立していたフランス軍部隊をたたくチャンスを逃すことになります。負けて当然?これが前近代の軍隊の統率の一般的なありかたでしょうか。
物語を読んでいると、各指揮官同士が連絡を取り合わず、勝手に行動していることが、これでもかと描かれている。ロシア軍は負けて当然とも思うし、これが前近代の軍隊、貴族たちが一国一城の主みたいに自分の部隊を率いている時代の、一般的な在り方なのかなとも思います。
そのほか、読んでいて気がつくのは、ロシア軍にはドイツ人の司令官が何人かいます。最初の最高司令官がドイツ人で、ロシア人の将校たちはあんなやつの命令なんか聞かないよ、と無視している。だから、滅茶苦茶になって負けていくのです。ともかく、意図的なものも偶発的なものも含めてコミュニケーション不全がロシア軍を覆っている印象です。
生徒に考えさせる課題として思いつくのが、「ロシア軍の退却、モスクワ放棄は単なる敗北か、それとも作戦か」。この本を見ると、すでに答えが出ているようですが、本当かどうかわからないので、好き勝手に話をさせたら面白いのではないか。
それから、「なぜモスクワ市民は、モスクワから避難したのか」。これは、考えるに値する問題だと思います。ウィーン市民も、ベルリン市民も、マドリード市民も町を放棄せずに、入城するフランス軍を迎えている。この違いはどこからくるのでしょうか?答えはないので、自由に話し合わせると面白いかもしれません。
『戦争と平和』から離れて、トルストイの生きた時代をロシア史の中に位置づけてみましょう。下線をつけてイタリックで書いてある部分は、トルストイとは直接関係のない事項です。
1825年 デカブリストの乱(5名絞首刑、約100名シベリア送り)
1827年 伯爵家の4男として誕生。
1844年 17歳。カザン大学入学(東洋学部アラビア・トルコ語科)。侍僕をしたがえ馬車で通学。平民の学生とは口もきかなかった。翌年法学部に転部。放蕩三昧の生活。
1847年 ゲルツェン亡命。
1852年 25歳。砲兵下士官となる。
1853年 クリミア戦争はじまる。
1854年 27歳。『少年時代』発表。セヴァストーポリで従軍
1855年 アレクサンドル2世即位。
1856年 29歳。中尉で退役
1858年 31歳。農事経営に没頭。
1861年 農奴解放令。
秘密結社「土地と自由」結成。
34歳。西欧旅行。ゲルツェン、プルードンと会う
ツルゲーネフと決闘騒ぎ、賭博で借金
1862年 35歳。結婚(9男3女)。
1863年 36歳。『戦争と平和』執筆開始。
ポーランド反乱。
1866年 ドストエフスキー『罪と罰』。
1869年 42歳。『戦争と平和』完結。
1870年 ゲルツェン死去。レーニン誕生。
1873年 46歳。『アンナ・カレーニナ』執筆開始
1874年 「人民のなかへ」(ヴ・ナロード)の運動最高潮。
1877年 50歳。宗教問題と深く関わり始める。
1878年 「土地と自由」(第二次)活動開始。
1879年 「人民の意志」結成。
1880年 ドストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』。
1881年 皇帝アレクサンドル2世暗殺。
1882年 モスクワ国勢調査に参加、貧民街に入る。国家権力と正教会への批判を強め、私有財産の放棄を考える。
1885年 58歳。『イワンの馬鹿』などの「民話」の発行
1898年 社会民主労働党結成。
1899年 72歳。『復活』刊行。
1910年 82歳。家出、死去。
トルストイの生きた19世紀は、ヨーロッパ、とくにイギリスの影響で、世界各地で近代化への対応が進む時代だと考えています。近代化に成功する国、挫折する国、中途半端な改革をする国と、結果は様々ですが、近代化への対応を見ることで、それぞれの地域の特徴がつかめるのではないかと思います。
日本とロシアを並べてみると、黒船来航は、ロシアではクリミア戦争敗北にあたる。幕末から明治維新が、農奴解放令前後の激動。国会開設要求・自由民権運動が、ヴ=ナロード運動。日本の自由民権運動は、明治憲法制定と国会開設で一つの区切りがつきますが、専制政治のつづいたロシアでは、ヴ=ナロード運動の挫折以降、ナロードニキのテロ活動・革命運動へと変えながら激しさを増し、1905年の第一次ロシア革命、そして1917年の二回の革命につながっていった。激動の時代です。
トルストイ作品に、時代はどのように反映しているでしょうか。ちなみにドストエフスキーはナロードニキの革命組織の内ゲバを題材に『悪霊』を描いています。しかし、トルストイにはこのような時代の空気を直接反映した作品はない世です。彼がこのような小説を書かなかったのは、あくまでも自分と同じ貴族を主人公にした小説か、農民を理想化した寓話しか書かなかったからでしょう。
トルストイはセヴァストーポリに従軍する経験を持ち、農奴解放令前には自分の領地で農奴解放を試みています(その試みは失敗に終わったようだが)。『戦争と平和』のなかでは、ピエールとアンドレイがそれぞれに農奴解放をおもわせる経営改革をおこなっています。思いつきで次々と命令を下すピエールは管理人に適当にあしらわれ、成果は上がらず、やがて本人の熱意も冷めてしまう。綿密に計画を立てるアンドレイは成功し、それはペテルブルクの貴族社会でも注目されている。トルストイ自身はピエールタイプだったようです。
農奴制の廃止は、大政奉還・廃藩置県にあたるでしょう。金子によれば、「19世紀ロシア史の上で60年代と呼ばれるこの時代は、セヴァストーポリ陥落、ニコライ1世が死んだ1855年から、革命家カラコーゾフ(1840~66)によるアレクサンドル2世暗殺未遂事件の起きた1866年までの11年間を指」(p128)し、特に1961年の夏から秋にかけては、農民の暴動、学生のデモ、学生・軍人・インテリゲンツィアの組織するいくつかの革命組織の活動で、革命前夜の様相だったといいます。
金子によれば、農奴解放後も農民の暮らしは変わらず、地主への経済的従属はかえって深まった。農民暴動と軍隊による鎮圧が頻発する。おもな都市で学生の反政府デモンストレーションがくりかえされ、ペテルブルク大学の学生大会には軍隊が出動。300人ほどの学生が投獄。学生や軍人やインテリゲンツィアの組織するいくつかの革命組織の活動がはげしさを加えた。こういう時期の直後に、トルストイは『戦争と平和』の執筆にかかるのですが、時代の直接的な反映は読み取りにくい。公爵令嬢マリアのもとで農民一揆が起きることくらいでしょうか。
ヴ・ナロードの運動
1860年代の農奴解放が期待していた農民解放につながらず、改革全体も中途半端に終わると、1870年代にはいると、ヴ・ナロードの運動が起きます(2万3千人が参加、三分の一が女子学生)(松田)。
ここで次の二点を確認しておきたい。ひとつは、反専制の政治運動が、「人民の中へ」として農村に向かったこと(労働者ではなく)。ふたつめは、その運動が、議会制・立憲体制ではなく(オスマン帝国のミドハト憲法や明治政府がそうであった)、社会主義に向かったことです。
この二つは非常にロシア的だと感じる点です。こうなったのは、人民と言えば労働者ではなく、農民しかいなかったこと。まだ資本主義が未発達であったロシアにおいて、議会制をめざすブルジョアジーが政治勢力として存在していなかったこと、が理由として考えられます。
また、社会主義を目指したのは、西ヨーロッパに比べて後発国であったがゆえに、先進地域のたどった道を飛び越えて、次の段階に接続することが可能と考えられたことがある(発展途上国が家庭電話や鉄道網を建設せずに、携帯電話や地方空港を備えるようなもの)。つまり、西欧が踏み入れた資本主義段階を経ずに、社会主義を実現しようとしたわけです。
マルクス主義陣営のヴェラ・ザスーリッチが、資本主義を経ずに農村共同体ミールを基盤として社会主義革命を実現できるか、マルクスと往復書簡をかわしているのは有名ですが、すでにマルクス主義が紹介される以前の思想家チェルヌイシェフスキー(1828~1889)は、将来の社会主義社会の不可避性を説き、農民を中心とした人民革命によって、資本主義を経ずに社会主義をめざそうとしていました。どうも、西欧主義の人々はロシアのあるべき将来像を社会主義として描いているようです。ゲルツェンは亡命先のフランスで労働者階級の窮乏を見て、資本主義を批判し、社会主義者となっています。ここから逆に、当時の西ヨーロッパにおける社会主義思想の流行ぶりが想像できそうです。
西欧主義者の代表であるゲルツェンは、1847年に亡命するが、ヨーロッパの議会制のもとで依然貧窮のプロレタリアートがいることから、議会制を軽蔑。ロシアにおいて、そのような議会制をツァーリからもらおうとしているロシア自由主義者の臆病を嘲笑。議会制を目指すことが政治革命ならば、ゲルツェンは社会革命を目指す。(ロシアのインテリゲンツィア、山本俊郎『西洋史物語8』1959)
トルストイはというと、西欧旅行中の1857年5月13日の日記「あらゆる政府は善悪という点で同じだ。最高の理想は無政府だ」(プルードンをよんだあと)(川端p79)と書いています。時代の影響を受けているわけです。
ロシアのインテリゲンチャの特徴としてここで強調しておきたいのは、農民と農村共同体に対する理想化です。ゲルツェンは、「ロシア農民こそ社会主義の理想を実現するための革命勢力となるべきもの」と考えており、チェルヌイシェフスキーも「ロシア農民は共同体のおかげで現在まで土地を確保できた。将来これによって社会正義を実現できる」と、ユリインは「社会主義実現の基礎が共同体のなかによこたわっている」としました。(山本)
これらは、インテリが頭のなかで思い描いた理想の農民像であり、農村に入っていった学生たちは、彼らの拒絶と皇帝崇拝とに直面し、運動は失敗に終わります。ヴ・ナロード運動およびナロードニキを描いたものトルストイの小説にはないが(と思う)、彼の農民の理想化は、いかにもロシア的であると同時に、学生たちと共通の感覚を感じさせます。
川端によれば「ルソーをはじめとする18世紀の思想家にとっては、自然の概念は、文明批判のための一つの仮説・神話という「戦略的」側面を持っていたが、トルストイにあってはロシアの農民の現実の生き方そのものが、実在する自然であるという形をとる。…農民の生き方がそのまま理想郷の生き方となり道徳律となる。」(川端p282)
トルストイにおける「農民の理想化」は『戦争と平和』ではプラトン・カラターエフの形象としてあらわれます。
『戦争と平和』におけるトルストイの価値観
ここから先は、退屈になるかもしれませんが、トルストイを読んで考えたことを自由に語らせてもらいます。ドストエフスキーとちがってトルストイ作品は非常にわかりやすい。登場人物に対する好悪がはっきり描かれるからです。作品からうかがわれる彼の価値観を整理してみました。
彼がもっとも嫌いな生き方が、計算ずくの生き方です。具体的には貴族社会の人々。ロストフ兄妹の親戚で幼なじみのボリスという人物がいるのですが、大人になると計算ずくで人間関係を構築し、上司にうまく取り入って出世していきます。結婚も持参金目当てで愛情は二の次です。戦争指揮官も計算するので、トルストイは嫌いです。川端によれば、 「ヒロイズムは、無意識的な集団行動の中に現れ、プランを立て戦争を指揮していると考えている指導者、将校はむしろ戯画化されている。」(川端p177)クトゥーゾフは計算せず、ロシア民族を信じて流れに身を任せたから偉大なのです。
若干好意的に描かれるのが、流れに任せる生き方。ニコライ、ナターシャの兄妹、その父ロストフ伯爵がその代表。父ロストフは、人はよいのですが、周りに流されてばかり。その結果莫大な借金をつくり、解決能力なく、問題を先送りするばかりの人物として描かれています。
微妙なののが、真理を求める生き方。タイプは違うのですが、アンドレイ(迷いはない)、ピエール(道に迷っているばかり)がこれです。マリアもここです。丹念に描きますが、中立的です。これはトルストイ自身を反映しているのだと思います。
「彼(アンドレイ)はピエールが指さした大空を見上げた、するとアウステルリッツ以来はじめて、彼はあの高い、永遠の空を見た。…すると彼の内部にあって、もういつからか眠っていた、よりよい何ものかが、ふいに喜ばしげに、若々しく、彼の心の中に目をさました。この感情は、アンドレイ公爵がまた日常の習慣的な生活条件の中にはいると、まもなく消え去ったが、しかし彼は、育てるすべを知らなかったこの感情が、やはり彼の内部に生きていたことを知ったのだった。ピエールと会ったことは、アンドレイ公爵にとって、たとい外面的にはそれほど変わりはなくても、内面の世界で彼の新しい生活がはじまる大きなエピックとなったのである。」(第2巻第2部12)
「ロストフは男性たちのなかに高度の宗教生活の現れを見ることは我慢ならなかったし(彼がアンドレイ公爵を好きになれなかったのもそれである)、自分でもそれを軽蔑して、哲学とか、空想とか呼んでいたのだが、令嬢マリアには、というよりも、彼には縁のない宗教的な世界の深さをあますところなく現わしているこの悲哀のうちには、彼は抗しがたい魅力を感じていたのでる」(第4巻 第1部 7)
理想的なのものが、何も求めない生き方。これは、ピエールの捕虜仲間プラトン=カラターエフです。捕虜となったことも含め、誰を恨むこともうらやむこともなく、運命を受け入れて単純に生きる農民です。
「ピエールが理解する意味での愛着、友情、愛情というものをカラターエフはまったく持っていなかった。しかし彼は人生でめぐりあったすべてのものを、それも特に人間を、愛し、睦まじく共に暮らすのだった。人間と言っても特定の誰というのではなく、現に自分の眼の前にいる人々なのである。彼は自分のスピッツを愛し、仲間を愛しフランス人を愛し、自分の隣にいるピエールを愛した。しかしカラターエフが自分に対してそれほど優しい態度を示しているにもかかわらず、…自分と別れる段になっても少しも悲しみはしまいとピエールは感じた。…しかしピエールは最初の夜の印象通り、素朴さと真実の精神の理解を越えた、完全な永遠の権化であり、そのような存在として終生彼の心に残ったのである。〔第四巻 第一部13〕
川端は「ナターシャやニコライ・ロストフの「自然人」としての生き方は知的なアンドレイよりも肯定的に描かれ、民衆の理想化された存在プラトン・カラターエフは他の教育ある人間たちの上位におかれている。」(川端p177)と書いていますが、ニコライやナターシャがアンドレイよりも上という指摘は、疑問です。
トルストイは、世間的な評価の低いものが、本当の価値を秘めているという考えも持っているようです。プラトンもそうですが、1部1巻にニコライが親戚の地主の主人と、近隣の領主と三人でウサギ狩りをする場面があります。猟犬がウサギを仕留めるのですが、ニコライと領主はものすごく高価な猟犬を持っていて、どちらの犬がウサギを捕まえるか競っているのですが、田舎地主のかわいがっている安い猟犬が最後のウサギを仕留める。世俗の価値は本物ではない。名もなき者が高い価値を持つというメッセージです。わかりやすいのです。世俗的なニコライですが、彼は醜いマリアの瞳が美しく輝くことには気がつく男、という点でこの小説の中で高い序列に位置づけることが出来るのです。
プラトン=カラターエフから『イワンの馬鹿』へ
トルストイがプラトン・カラターエフに具現化した理想の人間像は、虚飾と正反対の素朴さ、愚直なまでの正直さを持ちます。自分の損得を計算しない。ただ、「カラターエフが自分に対してそれほど優しい態度を示しているにもかかわらず、…自分と別れる段になっても少しも悲しみはしまいとピエールは感じた」とある。こういう文章が、すごいのです。これがなければ、トルストイの価値観はものすごく単純で平板でわかりやすいもので終わるのですが、この文章は怖い。プラトンは理想像かもしれないが、彼に親愛の情はあっても、友情はない。過去と切断された現在しか生きていない。これは人間といえるのか、という根本疑問です。この生き方は限りなく動物に近い。ナターシャがエピローグで「多産な雌豚」と呼ばれていることも併せて、こういう文が紛れ込んでいるから、筆力の高さとはちがうレベルで、文豪なのだろうと思います。
さて、このような愚直な、動物的な生き方は可能なのか。無理だと思います。だから、愚直さを目指して努力しなければならない。努力する段階で、すでに愚直ではないのですが。トルストイに独特の発想や行動をとらせることになります。
「ロシアのナロード(労働大衆)に現実の生き方の中に「善」を見出そうとした。民衆と関係のあるものはすべて賛美する傾向…農民の子の作文をゲーテよりも優れていると考え、ベートーベンの『第九』を社会の結びつきを乱すという理由で拒否した。民衆が理解できないものは悪であるという理由によってである。…ベートーベンやプーシキンが我々を喜ばすのは、絶対的な美があるからではなく、プーシキンやベートーベンのようにわれわれが腐敗しているからだ、と極言する。」(川端p34)という具合です。
また、トルストイは結婚した時「過度に道徳的な『良心』からソフィアに自分の古い日記を読ませた。」(川端p91)これは何かというと、放蕩生活を送っていたトルストイは、結婚前から肉体関係のあった女性が複数いるわけです。そのことを日記に書いている。それを新婚の妻に読ませるわけです。たしかに愚直ですが。彼は農奴の人妻とも長く関係を持っており、その女性は屋敷からすぐ側の村に今も住んでいる。奥さんはそれが一番ショックだったそうです。それはそうでしょう。でも、トルストイは素直で正直であれば、許される、分かってもらえると考えているわけです。こういう発想、若さと甘さは、貴族育ちのお坊ちゃんだとつくづく感じさせるところです。武者小路実篤の『友情』『真理先生』『馬鹿一』などを連想させます。
計算しない愚直な生き方、過去と切断された生き方を一言でいえば「馬鹿」となり、これを理想像として民話を借りて描いたのが『イワンの馬鹿』です。
計算高いものが金と権力を持っている社会では、愚者とされるものも、正しい社会であれば反転して賢者となる。
“本当は”愚者が、もっとも幸福に近く、愚者だけの社会がユートピアであるという思想がここにはあります。さらにこの話の特徴は、体を使って働くことが尊いという、否定しにくい命題に加えて、頭を使って働くことはずるいという教えを持つことです。これは反知性主義です。労働者・農民階級が虐げられている社会では、かれらの溜飲をさげ、カタルシスをもたらす話としておもしろいですが、これを実践したらどうなるか。それが、文化大革命であり、ポル・ポト政権のカンボジアです。
実は、『イワンの馬鹿』を初めて読んだときの感想は、これは文革とポル・ポトの教科書じゃないのか、というものでした。
「そこへ大臣の一人がやって来て言いました。『金がないので役人たちに払うことが出来ません。』『いいとも、いいとも。なけりゃ払わんでいい。』とイワンは言いました。『でも払わないと、役についてくれません。』『いいとも、いいとも。役につかないがいい。そうすりゃ、働く時間がたくさんになる。役人たちに肥料を運ばせるがいい。それは埃(ごみ)はたくさんたまっている。』」これは官僚主義、官僚制度に対する否定です。
「そこで賢い人はみんなイワンの国から出て行き、馬鹿ばかり残りました。誰も金を持っていませんでした。みんなたっしゃで働きました。お互いに働いて食べ、また他の人をも養いました。」これは貨幣の廃絶。
「唖娘は今までに、たびたびなまけ者にだまされていました。…そこで娘は手を見て、なまけ者を見分けることにしました。ごつごつした硬い手の人はすぐテイブルにつかせましたが、そうでない人は、食べ残しのものしかくれてやりませんでした。」反知性主義です。
だから、頭を使って働くということが、こんなラストシーンになります。
「『どうだな。少しゃ頭で仕事をしはじめたかな。』すると人民たちは言いました。『いいや、まだはじめません。先生あいからわずしゃべりつづけています。』年よった悪魔はまた次の日も一日塔の上に立っていましたが、そろそろ弱って来て、前につんのめったかと思うと、あかり取りの窓の側の、一本の柱に頭を打っつけました。それを人民の一人が見つけて、イワンのおよめさんに知らせました。するとイワンのおよめさんは、野良に出ているイワンのところへ、かけつけました。『来てごらんなさい。あの紳士が頭で仕事をやりはじめたそうですから。』」
川端は次のように指摘しています。「トルストイの場合は18世紀思想とつながり、その帰結として人民の道徳的発展、労働の意義の重視、働かざる抑圧者たちの機構としての教会・国家などの組織の否定という原初的な社会主義(あるいはユートピア社会主義ともアナーキズムとも今日定義されるような)への道に向かった。」(川端p295)
文化大革命
文化大革命は、今では毛沢東による奪権闘争という面からのみ語られがちですが、それだけではない多面性があった。そうでなければ、世界中に文革信者を生み、毛沢東が反体制青年たちのアイコンにならなかったはずです。アンディ・ウォーホールがマリリン・モンローと同じように毛沢東の肖像で作品を作ったほどなのです。
ここから先は、矢吹晋『講談社現代新書』(1989)をもとに話します。
文革の一面は反官僚主義です。「ソ連や東欧と同じく中国にもノーメンクラツーラ高級幹部が存在」しました。中国の党・政・軍幹部は、24等級あるのですが、1-13級が高級幹部(局長級、師団級以上)で、約10万人、人口の0.01%いました。「文革が打倒対象とした実権派とは、まさにこの階層」でした。
1966年8月「プロレタリア文化大革命のための16か条決定」という文書があります。文革の基本文書のひとつです。ここでは「大衆に対して、自分で自分を解放することを求め、大衆の解放を誰かにゆだねることはできないと強調」されました。「党の指導が命令主義、強圧主義に転化する中で窒息しそうになっていた中国の大衆、なかでも感受性の豊かな学生たちは、大衆の自己解放というアピールに大きな魅力を感じた」ということです。
反知性主義もあります。「毛沢東は、学校より実践の中で真に教育される例として、孔子、秦始皇帝、漢武帝、曹操、朱元璋などを挙げて、彼らは大学に行かなかったとしばしば語った。(たとえば1976年3月3日など)」
下放をささえる毛沢東のイデオロギーとして紹介されていたものですが、「階級闘争を極端に重視し、書物は読めば読むほど愚かになる。学校のカリキュラムは半減してよい。学制は短縮してよいなど、教育内容を単純化しつつ実践の場における再教育を重視。」書物を読めば読むほど愚かになるというのは、イワンの馬鹿-トルストイの系譜そのもので、笑ってしまいます。
貨幣廃絶、コミューンの創造。まさにイワンの王国ですが。文革発動前、大躍進期の毛沢東のものですが、「58年11月には賃金制度の廃止、供給制度の復活、すなわち月給による消費財の購買ではなく、消費財の貨幣によらざる分配を主張」しています。
1966年「五・七指示」の内容では、「分業廃棄、商品経済廃絶、平等主義」を唱えています。これは、労働者と農民、都市と農村、肉体労働と精神労働の差を減らすことが目的です。これを実際に移した共同体が人民公社です。
「人民公社は「共産主義への移行を目指す基礎組織」であり、行政権力と農業合作社が合体された組織」です。ここでは精神労働と肉体労働が合体されるということですね。そして「自主管理が目指され」「集団労働、労働点数制による収穫の分配が全面的に行われ」ました。
ただし、これらは生産力の発展段階を超えようとした空想論であり、失敗に終わりました。
失敗には終わりますが、当時は華々しく高く旗を掲げました。1966年「五・一六通知」では「旧世界をたたきつぶせ、新世界を建設せよ」と宣言する。ユートピアを目指すことをうたっているのですね。現状に不満を持ち、社会をよくしたいという理想を持つ志の高い若者たちは、国境を越えて、こういうスローガンにやられるわけです。サルトルの「君は自由だ、さあつくりたまえ」というのと同じです。別の世界に誘われる。そういう魅力があった。
ポル・ポト政権
こういう考え方で、一国を支配してしまったのがポル・ポト派です。ポル・ポト派はロン・ノル政権とゲリラ戦で戦っている時代から、中国共産党の援助を受け、また文革の影響も強く受けています。それが、極端な形で、しかも理論的裏付けなしに、直感的におこなわれた。
都市と農村の差をなくすという文革の目標が、カンボジアでは都市を無くすという形になる。1975年4月17日、ロン・ノル政府軍完全降伏すると、早速プノンペンではクメール・ルージュによる全市民の即時強制退去がはじまります。(山田p64)
反知性主義はこんなかたちです。「ポル・ポト政権は、毛沢東・中国の影響で、頭の中が白紙の子どもこそが信頼できると見なした。読み書き、算数など覚える必要はない。中学生の年齢の少年少女は、学校でなく、兵士から伝統医療の“裸足の医者”まで、社会の重要な仕事につかせて働かせなければならない。」(山田p90)読み書きそろばんの否定です。
通貨と市場の廃止も。「通貨があるから私欲物欲がおこり、革命推進に有害になるとして、全土「解放」後ただちに廃止。」私欲物欲の原因が通貨という、経済学など以前の問題です。常識的な人間理解さえ欠如している。足かけ4年で300万人を虐殺して、ポル・ポト派は政権を失いました。
(以下討議、省略)
【参考文献】
『人類の知的遺産〈52〉トルストイ』川端 香男里、講談社、1982
『ロシヤ文学案内 (1961年) (岩波文庫別冊 2)』金子幸彦、1961
『新版 ロシア文学案内 (岩波文庫)』藤沼貴・小野理子・安岡治子、2000
『19世紀ロシアの作家と社会 (中公文庫)』R・ヒングリー、1984
『世界の歴史〈22〉ロシアの革命 (河出文庫)』松田道雄、河出書房新社、1990
「ロシアのインテリゲンツィア」山本俊郎(『西洋史物語8』、河出書房新社、1959)
『文化大革命 (講談社現代新書)』矢吹晋、1989
『ポル・ポト〈革命〉史―虐殺と破壊の四年間 (講談社選書メチエ 305)』山田寛、2004