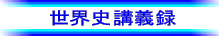世界史アプローチ研究会
『名著で読む世界史120』(山川出版社)読書会 2019年11月30日
トマス・アクィナス『神学大全』

|
高校世界史教師で行っている勉強会での、私の報告です。 テキストとして、 『 『 名著で読む世界史120 』を使っています。 |

|
はじめに、なぜトマス・アクィナスなのか、です。第一に、ほとんど勉強したことがないので、この機会に触れてみようと思いました。授業で、ヨーロッパ中世12世紀は、ヨーロッパ世界の拡大、商業の復活、都市の発展をざっとやり、最後に中世の文化をいろいろ喋る。そこで12世紀ルネサンスの紹介のなかでトマス・アクィナス『神学大全』と言うだけで終わっていた。一番、自分が勉強をしていなくい部分で、気にはなっていたところです。
調べてみた結果ですが、結局よくわかりませんでした。今日、一応報告しますが当然ながら『神学大全』は読んでいません。2012年邦訳完結、全45巻。この長さ、読めるわけがない。いろいろ参考文献を見ましたが、中世研究者も全部読んでいないだろうという確信に近いものがありました(誤解だったらごめんなさい)。
昔の中公の『世界の名著』に抄訳があり、そこから概要をコピーしておきました。一部・神、二部・人間の神への運動、三部・神に向かうための道なるキリスト、各部はさらに細かく分かれていて、第一部・神の二番目の「一なる本質」の第二問「神について、神は存在するか」の部分だけコピーして添付しました。
こんな感じで様々な設問をしながら、それに対して反論をのべ、最後に彼の回答を付すようなかたちですすんでいきます。このB4の裏表だけでも、とても読めない。「何のことだ?」という感じ。わからないなりに調べて、こんな感じかなというのを今日は報告させてもらいます。
まず、教科書・資料集にみるスコラ哲学です。
資料①で、教科書・資料集の説明載せています。キーワードと思われるところに下線部をつけています。詳説世界史B 改訂版
12世紀ルネサンスでアリストテレス哲学が必ず出てくる。このころアリストテレスがイスラーム世界を通じて西ヨーロッパに紹介され、12世紀ルネサンスが盛り上がったという書き方をしています。そこでトマス・アクィナスは何をしたか。アリストテレス哲学を神学に取り入れて大成した、という表現でどの教科書でも出てきます。彼が中世神学の頂点のような書き方をしている。そのあと、オッカムなどが出てきて中世哲学は終わりを告げる形です。
山川の教科書の普遍論争の脚注です。「普遍(個々別々のものをこえてあらゆるものに共通するもの)は、現実に実体として存在するか、それとも思考のなかに存在するに過ぎないのかの論争。前者を主張するのが実在論、後者を主張するのが唯名論である。」これだけで、もうわからないです。ヨーロッパの哲学に流れているこのような議論の本質をつかめたらいいなと、見ていったのです。最終的にはよくわからないのですが。
帝国書院『帝国書院 新詳 世界史B [世界史B312] 高校教科書
世界史用語集(2014年)も同じような形です。普遍論争の項目では「論争のなかで学問と信仰の分離が進んだ」という書き方をしている。トマス・アクィナス以降のことが書いてあると思います。山川ではスコラ哲学と言わず、スコラ学と書きますが、やはりアリストテレスの導入がポイントです。
実在論の項目では「普遍的なものを実在すると見なすスコラ学の立場。プラトン主義の影響を受け、神や普遍は事物にさきだって存在するとして、信仰の優越を主張した」。
唯名論「普遍的なものは実在せず、個物につけられた名前に過ぎないとするスコラ学の立場。無批判な信仰を退け、理性を重んじた。アベラールやウィリアム=オブ=オッカムが代表的論者」。
気になっていたのは、唯名論の説明を読むと、普遍は存在しない、名前だけだと。神学の中でそういう言い方をすると、神は普遍の最たるもので、神が存在しないという神学があるのかということが大いなる疑問で、どういう立場でこの唯名論が存在しているのかは、以前から疑問ではありました。古い用語集ではこう書いてありました。旧版山川用語集「唯名論(名目論):実在するものは個々の事物だけで、神とか普遍とかは抽象(名だけ)にすぎないとして、実在論と対立した。アベラールやオッカムに代表される。」
ここまで踏み込んで、神や普遍は抽象だけに過ぎないという書き方をしている。本当かよ、と思いますよね。今の用語集は改めていてここまで書いていませんが、微妙なラインの話なのかと思います。
第一学習社の資料集では「二重真理説」という言葉が出てくる。アリストテレス哲学が入ってくると、それを認める。しかし、キリスト教神学とは矛盾する。だから、それはそれで真実、これはこれで真実という、二つの真実が存在するという立場を取る神学グループがあり、これを二重真理説というのですが、二つあればそれは真実ではないだろうと思う。いろいろ矛盾したものがてんこ盛りなのが中世神学。そういう意味では面白いと言えば面白いですが、わからない。
なんとなくわかるような、しかしよく考えるとわからないというのが、教科書・資料集レベルのスコラ哲学。なんとなくわからないままに教えていました。どこがわからないのかはっきりさせようと調べてみた感じです。 <br><br> トマス・アクィナスの生涯です。 1225年、ナポリ近郊ロッカ・セッカ城に生まれる。南イタリア、アクィノの領主ランドルフ伯の7番目の末子。城も持っている領主で、父はもと皇帝派軍人。長兄が十字軍に参加して、捕虜となったときに教皇グレゴリウス9世の力添えで、多分身代金を払って解放された。以後、父は教皇派に鞍替したということです。
1231年、6歳。モンテ・カシノ修道院へ入る。貴族の長男以外はこういう身の振り方をするのでしょう。トマスのおじさんが、その修道院の院長だったということなので、有力な家だったのだと思います。
14歳までそこにいて、14歳でナポリ大学教養部入学。ドミニコ会修道士たちと知り合い、かなり影響を受けたようです。ドミニコ修道会は1206年にできた。できたばかりの修道院に接触して、それに惹かれて、1243年18歳の時にドミニコ修道会に入ります。これに反対した家族はロッカ・セッカ城に彼を幽閉します(~45年)。幽閉状態が足かけ3年続くのですが、それでも彼が気持ちを変えないので、あきらめて幽閉を解いたということです。
1245年、パリのドミニコ会修道院で3年過ごす。
1248年、ケルンにおけるドミニコ会神学校建設に従事。
1252年、27歳。パリの聖ヤコブ修道院で『命題集』(アリストテレス?)を講ずる。同神学講座はパリ大学の一部とあったのですが、これがパリ大学かどうかは、はっきりしませんでした。1257年にパリ大学の教授会に迎えられるとあるので、聖ヤコブ修道院で講義したというのは、どういう関連なのかわからずじまいです。
1259年、34歳。イタリアを中心に活動(~1267年)。そのころから著述活動を始めていて、1261年『対異教徒大全』(~63年)、1265年『神学大全』に着手。
『神学大全』が主著ということになっていますが、イギリスの20世紀前半の哲学者ラッセルは『対異教徒大全』の方が良いと言っています。なぜかというと、『対異教徒大全』はキリスト教徒ではないイスラーム教徒やユダヤ教徒を説得するために書かれた本なので、聖書を持ち出して説得するような論法を最後まで控えている。なので、こちらの方が純粋に彼の哲学の論理を追えるとありました。一方『神学大全』は初学者の入門書としてかかれています。それにしては膨大ですが。
1269年 パリ大学へもどり72年までそこで教えています。ここではドミニコ会への批判ということで攻撃されたのと、保守的アウグスティヌス派、これはアリストテレスの哲学を認めないグループ、それとラテン・アヴェロエス派、つまり二重真理説のグループ、との論戦に巻き込まれました。
『神学大全』そのものも教義問答集の形式で書かれており、テーマとそれに対する反論、さらにそれに対する反論という論争形式の叙述であり、こういう論争に役立つものでした。
1272年、ナポリに神学校設立のため移り、1273年、ミサ中に心境に大変化が起こった。彼によれば「たいへんなものを見てしまった。それに比べれば、これまでやってきた仕事はわらくずのように思われる。」『神学大全』はまだ完結していませんでしたが、以後著述を放棄します。
1274年、49歳でリヨンでの公会議出席途上で死去。40代に死んでいる割には、めちゃくちゃたくさんの本を書いている人だと思いました。
19世紀後半ですが、1879年レオ13世の法王答書(レスクリプタ)があって、以後、カトリックのあらゆる教育機関で、哲学を教える際、トマスを唯一の正しい体系として教えることとなります。哲学の影響力でいうと、デカルトやカントよりもトマスの方が大きいと書いてありました。教科書では、カトリックの正当な神学を確立したと書いてあるのですが、そうなったのは19世紀後半だということがこれでわかります。彼が生きている間は、アリストテレスを取り入れていることに関してカトリックの立場からも批判が結構あったようで、絶対的な権威であったというわけではないようです。
中世における哲学状況(大学の発展とスコラ哲学)について。
以上のように、トマスは13世紀に活動するのですか、その状況を整理してみました。
よく教科書にも「哲学は神学の婢(はしため)」という言葉が出てきます。考えてみると、なぜ、わざわざそんなことを言う必要があるのか。自由7学科で音楽とかありましよね。音楽は神学の婢とは言わない。言わざるを得ないのは、実は哲学はキリスト教神学を凌駕するほどの影響力があった、もしくはありつつあったので、それにたいする警戒心や、神学の領域を擁護するために、こういう言葉が出たのではないか。
この言葉を言ったのはペトルス・ダミアニ(1007~1072)で、彼はグレゴリウス7世と共に教会改革を推進した人物です。
このような発言の背景として、11世紀からの普遍論争の広まりがあります。論争の過程で、教会付属学校から世俗大学へ人気が移っていった。世俗の大学では哲学を教えている。人気が移っていくのに対して、上記の発言があったのではないか。
この頃の神学の論争テーマをちょっと見てみると、「神の存在は、哲学的にどのように証明されるのか」、「キリストの十字架上の死は哲学的にどのように説明されるのか」、「唯一神が3つのペルソナをもつとはどういうことか」、「天使の堕落はどう説明されるのか」、「聖母マリアは原罪を帯びた普通の女なのか」など。
僕らから見るとどうでもよいことを一所懸命議論していた。参考文献の中で一番読みやすかったのが、八木雄二『天使はなぜ堕落するのか―中世哲学の興亡
そういうなかで、最初に出てくるスコラ哲学の人名がアンセルムス(1033/4~1109)です。最初のスコラ哲学者です。イタリア生まれですが、最終的にイギリスのカンタベリー大司教になります。当時大学で哲学が流行始めているので、古代末期のアウグスティヌスの哲学を模範にして、大学哲学に対抗して、できるだけ聖書の権威に頼らず、理性によりキリスト教の信仰を考察しました。一方で神学者なので、理性に対する信仰の「絶対的先行性」主張しています。「わたしは信じなければ理解しない」とはアンセルムスの言葉です。かれは大学ではなく、生涯修道院で教えました。わざわざ修道院でこういう講義をしたのは、若者たちのあいだで、アリストテレスの論理学が流行し、先生教えてください、と若者たちに求められたからです。哲学的論争がブームになりつつある時期でした。神学校の生徒たちを逃がさないように講義をしたのです。
次はアベラール(1079~1142)。この人は当時のスーパースター的人物。パリの学界において討論と唯名論で人気を博し、その講義には、多くの学生が押し寄せた。時代の寵児。当時の大学では公開討論が盛んにおこなわれており、そのなかでアベラールは、完膚無きまでに論争相手を打ちのめすような議論が得意。端から聞いていると面白いので人気が出る。人気が出ると講義に学生が集まる。当時の大学は学生が寺銭を払うので、学生が集まるほど収入も増える。かなり人気をさらい、他の学者の恨みを買ったようです。そのなかで、教皇の政治顧問、神秘家ベルナールがアベラールを異端として告発、追放にいたらしめます。
それ以外に、エロイーズという娘との恋愛が有名ですよね。貴族の娘エロイーズの家庭教師をしているうちに、恋愛関係、男女の仲になり彼女は妊娠する。最終的には彼女は修道院に入れられる。二人の中は切れるのですが、アベラールはエロイーズの親戚に襲われて、男性性器を切り取られるというショッキングな結末になるのです。この二人の往復書簡が残っていて、それが本になったり物語になったりして、そういう意味でもスーパースターでした。この人が、唯名論でさまざまな議論を沸騰させました。
アベラールの時代までは、まだアリストテレス哲学は紹介されていなかったそうです。アリストテレス紹介以前に、論理学的、哲学的議論がどんどん流行始めていた。
プラトンはどうかというと、12世紀後半までプラトンの著作はそのままの形では伝わらず、アウグスティヌス経由、もしくは新プラトン主義というかたちでとりいれられていました。
アリストテレスに関していうと、古代末期のボエティウス(480~524)という神学者がいて、彼によるアリストテレスの『カテゴリア(範疇論)』と『命題論』をラテン語訳したものが伝わるのみでした。ボエティウスはアリストテレスの全著作をラテン語訳しようとしたのですが、二冊を訳したところで死んでしまった。僕にはよくわからないのですが、『カテゴリア(範疇論)』と『命題論』は論理学であって、形而上学ではないというのです。この本が伝わることにより、アリストテレスの論理学は伝わっていたが、いわゆる哲学、形而上学は伝わっていなかったらしい。このあと、アベラール以降、イスラーム圏からアリストテレスの形而上学が翻訳されて、入ってくるようになる。
プラトンやアリストテレスが直接西ヨーロッパに伝わっていなかったのは、やはり異教だからでした。
哲学が流行しはじめ、アリストテレスが入ってくる中で、12・13世紀以降、西欧各地で大学が成立、発展します。イタリアでは法学、医学の大学もありますが、パリ大学は神学の中心となります。八木さんの本には、大学の教師は聖職者とありました。大学の監督権限は所在地の司教が持っていたが、しだいに自治が確立してくる。
1213年、パリ大学で、教授認可状授与権限が文書局長(司教の大学監督権限代行者)から大学の教授に移ります。自治が確立していくのでしょう。そのころイスラーム経由でアリストテレスの著作が伝わる。このころから「哲学者」と言えばアリストテレスを指すようになります。
ただ、アリストテレスの流行に対して、キリスト教会は危機感と反発を持っていました。たとえば、「アリストテレスは信仰に役立たず、信仰を危うくする」(12世紀ベルナルドゥス)、「私たちの時代の多くの学生たちは、非常に熱心に学習や研究に向かい、他方、神の愛や隣人愛、徳の獲得については、すっかり冷めてしまっている」(フランシスコ会ヨハネス・オリヴィ(1248~98))。
こういうなか、アリストテレスは危険だということで、1210年パリ大学でアリストテレスの『自然学』『形而上学』の講義を禁止します。それでも、講義する教授がいたようで、1215、1228年にローマ教皇庁が禁令を更新しています。1229年、トゥールーズ大学創立の際、学生を集めるためパリで禁止されている書物について講義すると宣伝した。ようするに、こっそりとアリストテレスをやると言っているわけです。そうしたら学生が集まる。それくらい人気があった。
なぜ、アリストテレスは危険だったのか。12世紀末、アリストテレス哲学受容以降、以下の問題が「神学」に属する問題として浮上し議論されてきました。「理性は啓示によらずにどれだけのことを神について知ることができるのか」。「啓示は神についてどれだけのことを教えることができるのか」。「理性の限界を超える多くの事柄が神について啓示されたのは何故か」。「啓示に基づく神学に対し、理性に基づく神学はいかなる意味を有し、両者はどのように関係するのか」。
このあたりは危険な感じはしませんが、アリストテレス哲学における教会の教えと矛盾する命題がいくつかあり、これが危険だったそうです。危険だという教会の態度に対して、アリストテレスに対する3つの対応パターンがあらわれます。
1.保守的アウグスティヌス派は、アリストテレスを拒否。アウグスティヌスに代表される伝統神学にこもる。
2.ラテン・アヴェロエス派は、アヴェロエスの解釈とともに紹介されたアリストテレス哲学を全面受容。しかし、哲学と神学、理性と信仰の立場を明確に区別。理性の立場において考えるかぎり、アリストテレスに従い、魂の普遍的単一性と世界の永遠性とを「真理」として承認。それにもかかわらず、キリスト者であるかぎり、聖書に述べられている事柄を「真理」として承認。二重真理説です。アリストテレスは認めるけれど、それはそれ。キリスト教神学と矛盾することも認める。それはそれ。整合性は考えない。
3.中道的アリストテレス主義は、神学とアリストテレス哲学との融合をはかる。トマス・アクィナスです。拒否でも、並列でもなく、ちゃんと混ぜようとした。
トマス・アクィナスはパリ大学に2回在籍し(1252~1259、1269~72)、アリストテレス哲学を基礎に神学を構築しました。1277年(トマスの没後)、パリ司教が異端として断罪すべき219の命題一覧を作成しました。これはアリストテレス主義に対する攻撃ですが、そのなかにはトマスの教説に関連するものもありました。その例題をいくつか紹介します。
「死後の復活は、理性による検証が不可能であるゆえ、哲学者によって認められるべきではない」。 「神学は寓話の上に築かれている」。 「埋葬について配慮する必要はない」。「貞潔はそれ自体、美徳ではない」。「肉の交わりを完全に控えることは、徳と種をそこなう」。 「キリスト教の掟は他の宗教と同じく、嘘と誤りをふくむ」。「キリスト教の掟は学問の防げになる」。「至福は来世にではなく、現世に存す」。
見ると結構面白い。こんなことを中世の大学で議論していたと思うと、キリスト教から見れば危険だなと思います。トマスが死んだあとも、アリストテレス哲学への攻撃はあったようです。
5.トマス・アクィナスの思想について。
参考図書を挙げていますが、たとえば稲垣良典さんの『トマス・アクィナス 『神学大全』 (講談社選書メチエ)
山田晶さんは『神学大全I (中公クラシックス)
山本芳久『トマス・アクィナス 理性と神秘
トマスの著述形式は、「命題集註解」という形で、トマスだけでなくドゥンス・スコトゥスであろうとオッカムであろうと同じ。中世神学のオーソドックス、公開討論に対応している。「命題-異論-異論に対する反対-主文」という形式です。
山本芳久は、トマスの偉いところは、命題に対する異論で、自分とは違う考えの人の意見を述べる時に、手を抜かず丁寧にきっちりと異論を述べているので誠実である。だから信用できると書いている。ところが、バートランド・ラッセルによれば、異論がいい加減で反論しやすいようにゆがめて書いてあるという。正しいところはわかりませんね。
アリストテレス哲学の中身がキリスト教と相いれないところがあるのに受容した。そこがトマス・アクィナスの一番のポイントです。それはどのようにおこなわれたのか。
ⅰ「アリストテレスの質料と形相からなる実体という枠組みを使いながら、そこに神の被造物としての、神から「存在」を分かち与えられたものとしての実体、という発想を組み込むことで、事物における存在と形相(ないしは本質)との複雑な関係を明らかにしようとした。」わからないですよね。だからすごいらしいです。
ⅱ「『前もって感覚に与えられないものは知性にも与えられない』というアリストテレスの認識論の原則を保持。同時に現実態と可能態という柱を組み込み、認識能力の新たな説明方法を展開した。」これは少しだけ説明できそうな気がしました。あとでちょっと話します。
ⅲ「教会の教えと矛盾するアリストテレスの教説への見解」。アリストテレスは「知性の単一性」ということを言っていた。まとめる力がないので、読みます。
「アリストテレスによれば、人間には能動知性と受動知性がある。アヴェロエスは知性単一説をとなえ、人間は各人において身体が異なるに応じて感覚が違うが、知性は同じだと考えた。同一の知性が異なる感覚から異なる認識を生じてそれを各人に与える。これにより客観的知識は人類において共通となる。しかしこれでは知性による行為の責任が個人のものでなくなる。」
たくさんの個人がいても、何かを考えるときに同じ結論にたどり着く。それは人間の持つ知性は共通しているからだ。同じ客観的認識が得られるのだということだと思います。同じ知性を持っているとはどういうことか。それはプラトンのイデアのようなものがあり、その知性の同じイデアを分有しているので、知性は単一であり同じ結論にいたる。ただ、知性が単一であり、皆が同じ知性を分かち持っているということになると、知性を魂と読み替えると、同じ魂になる。
「教会の教えによれば、人間の魂は世の終わりに肉身をとって復活し、神の審判を受ける。この魂は自己の行為に対して責任を負うべき主体として、個々の人間の魂でなければならない。」知性が単一であると、裁きがおこない得ない。これはあり得ない。キリスト教と知性単一説は相いれない。
トマスも知性単一論を激しく批判する。その上で、知性単一論はアリストテレスの説ではないという。イスラーム世界でアリストテレスが受け入れられた際に、新プラトン主義的汎神論と結びついてアリストテレス解釈がゆがめられた。だから、アリストテレスが悪いのではない。彼の説ではないから、アリストテレスはよいのだとして教会を説得した。ラッセルはトマスの議論を強引だと言っていますが。
では、知性が単一ではないのに、別の個々人が同じ認識にたどり着くかというと、認識対象の内容の共通性によると主張しました。
「世界の永遠性」について。アリストテレスは、世界は永遠であると言っています。「事物の生成消滅は実体的形相の基体としての第一質量を前提するが、第一質量そのものは不生不滅であるから、世界は自らのうちにすべての生成消滅を含みながら、それ自体としては不生不滅であり、永遠である。」アリストテレスの言葉です。彼によれば世界は永遠であり、始まりもなければ終わりもない。
しかし、キリスト教によれば、神が世界を創造したので始まりはあり、いつか終わって最後の審判がある。だから、アリストテレスと矛盾します。
この問題に対するトマスのアリストテレス擁護は以下の通り。「神が世界を永遠から創造したか、時の始めを持つように創造したかは、神の意志によることであり、人間の理性を持ってして断定不能。いずれの説も、蓋然的に証明されうるが、絶対的証明はできない。われわれは、『世界に時の始めがある』ということを、啓示によって知る」。理屈ではどちらが正しいかわからない。しかし、啓示でわかりますよねと。最終は神の啓示に行ってしまう。ここがラッセルに言わせるとスコラ哲学は論ずるに値しないということになります。
その上で、アリストテレスの質料と形象というような枠組みを取り入れながらキリスト教神学を構築していったということです。トマスの思想に関しては、私はそれくらいしか言うことができません。
次に普遍論争についてです。
これは中世スコラ哲学の一番の論争だということで、トマスもこれに関わったはずですが、いろいろな本を読んでも普遍論争でどういう立場だったのかをはっきり書いていないし、それで項目を立てて説明をしていません。アベラール、ドゥンス=スコトゥス、オッカムの解説を見ても、その人たちの思想は、説明はあるのですが、普遍論争について独立して書いてくれていません。いろいろあさる中で、こんな感じなのかなとまとめたのが次の史料です。
自分がこうかなと思ったところを抜粋したものです。普遍論争の出発点は、古代末期のボエティウス(480頃~525頃)の仕事なのです。彼はアリストテレスの『カテゴリー論』、『命題論』の翻訳を残しました。それから、これも古代末期のポルフュリオスの『イサゴーゲー(範疇への手引き)』の注解を残しました。『イサゴーゲー』自体がアリストテレスの『カテゴリー論』の注解です。
ボエティウスが残した「ポルフュリオスの『イサゴーゲー(範疇への手引き)』の注解」のなかで、ポルフュリオスは、「プラトンのイデア、アリストテレスの形相はそもそも存在するのか、存在するとするなら、どのようなしかたで存在するのか」と問うています。
このなかでポルフュリオスは、普遍を「類」「種」「種差」など5種類に分類しました。例えば、人間という種は、動物という類に理性的という種差がくわわったものです。このように5種類で普遍を分類していった。これが普遍論争の出発点らしい。禁じ手ですが、ウィキペディアでは「ポルピュリオスの最も影響力の強い哲学的功績は、『イサゴーゲー(範疇への手引き)』でアリストテレスの論理学をネオプラトニズムと合体させたこと、特に、範疇という概念を実体的に理解したこと(後の哲学で言う普遍)である。ボエティウスによる『イサゴーゲー』のラテン語訳は中世ヨーロッパの学校・大学で標準的な教科書となり、それらの学校・大学で中世の論理学や普遍論争が哲学的・神学的に進展することとなった。」
話が飛ぶのですが、ラッセルが『西洋哲学史』でアリストテレスの論理学(三段論法)を分析しています。
「1すべての人間は死すべきものである。
2ソクラテスは人間である。
3故にソクラテスは死すべきものである。」
3のソクラテスが死すべき者という命題は、ソクラテスの死の証言を得ることによって保証される。
1の「すべての人間が死すべきものだと」いう大前提は、実は真実かどうかわからない。すべての人が死んでみないと本当かどうかわからない。今生きている人が皆死なないと証明できない。したがって、帰納的な知識であるとラッセルは分析しています。
2のソクラテスが主語であるのと同じ意味で、1の「すべてに人間」は主語ではない、とラッセルは言います。この二つを同じと考えることから、「すべての人間」がソクラテスと同じ種類の実体を指示しているという形而上学的誤謬が生じた。ラッセルは「すべての人間」は実体ではないと考えているのです。で、「アリストテレスをして、ある意味で一つの種は一つの実体であるといわしめた。アリストテレスはこの言明に注意深く条件つけていたが、ポルフェリオスは周到さに欠けた」(ラッセル)。ここでポルフェリオスが出てくるのです。だから、アリストテレスを紹介するときに、誤解されやすい形で「人間」という種を実体として紹介したのでしょう。具体的に書いていないので、僕も結論しかわかりません。しかし、ここから始まったのだろう。
シュヴェーグラーはこう書いていました。
「普遍をたんなる名称、実在を持たぬ空虚な表彰と考えた人々は、唯名論者と呼ばれた。唯名論によれば、普遍的概念、類、種は存在しない。有るものはすべて、まったく自立的な個物としてのみ存在する。したがってまた純粋な思考もなく、表象作用と感覚とがあるだけである。これに対して実念論(実在論のことだと思います)者は、プラトンにならって、あくまで普遍の客観的実在を主張した。(普遍は個物に先立つ)。」
アベラールは「唯名論であるとともに実念論的でもある調停的見解を作ってからは、この見解が大して重要な変更もなくずっと支配的であった(普遍は個物のうちにある)」。
アベラールは唯名論者だといろいろな本に書いてあるのですが、シュヴェーグラーによれば唯名論者ではないということです。中世哲学は、人によって言うことが違っていて、まだまだ研究の余地はありそうです。「普遍は思考され表象されたものにすぎないが、といってたんに表象する意識の産物ではなく、事物そのもののうちに客観的実在を持っている。もし事物のうちに本来含まれていなかったら、それは事物から抽象されえないであろう…。このような思考と存在との同一性こそ、スコラ哲学者の弁証的方法全体がもとづいている根本前提」(シュヴェーグラー)。
最後の、「思考と存在との同一性」が中世哲学、ギリシア哲学を考える際のキーワードだと思います。シュヴェーグラーのこの解説は割とわかりやすい。解説がわかるだけで、唯名論がわかるわけではないですが。
次に八木さんです。この人が、一番中世哲学を僕らに伝えようと四苦八苦している人です。ちょっと長いですが引用します。
「現代では、普遍をあらわす語は、ものについての概念を表していて、それは知性の中に抽象的存在として『在る』が、知性とは独立に、それだけで実体として在るのではない、といわれるだろう。概念として知性の中に存在しているだけである、と。」
これは僕らの感覚ですよね。これは概念じゃんと。先ほどS先生が言われた普遍論争も唯名論も、こんな感じかなと思って聞いていました。だけれど、違うのだと八木さんは言います。「中世においては、普遍が実在の基礎と見られていた。哲学者はまず普遍を理解しているのであり、個別者を理解しているのではない。個別者を正当に理解するためには、普遍からそれを理解しなければならないと考えられていた。」普遍が先なのだと。「これはプラトンのイデア論が持っていた問題」。出てきました。結局ここに来るのだと思います。
「イデアと呼ばれる普遍こそが実体。目に見える個々の事物はその影に過ぎない。」「哲学の伝統は、感覚に訴えてくるものよりも、知性が対象とするものを重視」する。「プラトンは、人間は感覚にだまされやすいものだと考え、感覚的認識を忌避して『ことば』がとらえている『普遍』こそ実在であるという考えを持っていた。」
僕らは、見たり聞いたり触れたりした感覚に頼って、それがとらえたものを実際のものだと考えているけれど、感覚はだまされやすいので、それが本当かどうかはわからない。全部嘘かも知れない。それが哲学の出発点。そう考えたときに、感覚で捉える個別ではなく、感覚が捉えられない普遍こそが本当に存在している、ということを頭に入れておかないと、普遍論争はわからないということだと思います。
「哲学は討議(ことばによる論議)を通じて互いの正しさを検討するもので、具体的な事物を使って真理を証明する学問ではない。」実験で証明できませんということですね。
「数学が数字ということばを使って数学的真理を証明するとの同じ」である。2πrという数字があって、僕らはそれをとらえることはできないけれど、それは無いのかというと、ある。そういうことかなと。哲学もそういうものだと。「哲学の基盤は感覚がとらえる個別的事物にあるのではなく、ことばがとらえている普遍概念にある。だから、プラトンが個々の事物の存在ではなく、ことばがとらえる普遍を実在と見なすのは、当然の主張。ことばに対応した普遍こそが実体(普遍実在論)という哲学の伝統的考え方として一般化」していた。「実在が言葉の論理をこえて、認められていること、不可視の実在の秩序が、神の存在証明の前提。「ことば」や「名前」や「法則」として理解される普遍が、中世の人々には「上位の実在」「高位の目に見えないもの」として疑いようもなく実感されていた。」この感覚がわからないと多分わからないと、八木さんは言っていると思います。
「アリストテレスは「普遍の実体性」を語りながら、他方で「個体こそは実は真の実体」という主張を自分の哲学に含ませていた。」「この論争は、さらに神の3つのペルソナと、3つのペルソナに共通する神の実体本質との区別の問題とからんで、大きな論争になった。」
「神:人間:普遍」=「父子精霊:ソクラテス:個別」
左側が普遍、それに対する右側が個別になります。ソクラテスというペルソナが実在するということは、人間という普遍が実在する。神という実在があれば、父・子というペルソナが存在するのだという議論と絡んで、普遍論争は展開したということらしいです。
アベラールによれば「ここにバラはない」というとき、一切のバラがない状態を指していながら、意味あるものになっている。「ことば」としては有意味で、その対象は無。バラはないけれど、「バラはない」という言葉には意味がある。「したがって、『ことば』は本質的に存在にコミットしない。」バラという言葉を使っているけれど、バラがあるかどうかは関係ない。これが唯名論の一番のキーポイントです。
「この立場では、真偽は存在において決定されるのではなく、論理の内側で決定されるものでなければならない。ならば、『神の存在』という『ことば』も、真に存在にコミットできない。」要するに論争しても、言葉の中の世界でしか真偽は判定できない。コミットしないから、神がないと言っているわけではない。唯名論は、ただ言葉の中でしか我々は触れられませんよ。神があるかどうかについては、この論争はコミットできない、というのが唯名論。だから、神がないと言っていない。というのが、八木さんによる唯名論の解説です。これが正しいかどうかは、わかりませんが一番腑に落ちました。
そうなると、論争は言葉遊びになる。神の存在を語ることは言葉に遊びにならないか。これが、実在論が唯名論に反対した理由だと。 言葉遊びの唯名論に対して、実在論がどう対処したのか。これに関して八木さんは、これは中世哲学研究者によってまだ研究されていない問題として放り出しています。なかなかわかっていないことがたくさんあるというのが結論なのです。
ここまで読むと、用語集レベルで概念だから存在しないというのとは、ちょっと違う。となると、神を信じているはずの神学者が唯名論になるのも理解できる。真実の存在とは違う世界だというレベルだと言うことがようやくわかった。
八木さんは、ドゥンス・スコトゥスが専門ですが、研究者は自分を含めて世界に6人しかいない。だから3人説得できれば自分の説は主流派になると豪語していますから、それが中世神学研究の世界だと思います。だから、何が正しいかはなかなかわかりません。以上が、僕が調べられた普遍論争の中身です。
あと、なぜキリスト教信者である聖職者は神を信じているはずなのに、なぜ神の存在証明をするのか。お坊さんは仏の存在証明をしないし、神主も神々の存在証明をしない。あることが大前提。だから、これも疑問だったのです。これも、ちょっと書いておきました。
「スコラ哲学における神の存在証明は、個人の信仰のよりどころとして追求されたものではなく、個々人の間の社会的紐帯の拠り所(教会)を権威づけるものとして追求された。」個人の問題ではないということで、ちょっと腑に落ちました。ということは、それを言わないと中世初期には信者が増えなかったのか、神を信じない人が多かったのかなとか、逆に思いますが、そのあたりはわかりません。
中世のキリスト教は、「社会的信仰であり、自分さえ信じていれば他人がどう考えるかどうでもいい、と考える個人的信仰ではない」。「土着の信仰に替わって新しい社会の紐帯として人々を結びつけようとしていたし、その義務を感じていた。」そのために、神の存在証明が必要だったということです。 代表的なのがアンセルムスによる神の存在証明です。前提として、新プラトン主義があります。これはプラトンとはあまり関係がありません。新プラトン主義の中心的主張は、「『善かつ一者であるもの』という最上位の存在から流れ出した存在の流れが、いくつかの段階を経て人間の魂に流れ込み、人間理性はこの存在の流れのなかにあって、身体を通じて物体との間を取り持っている。「一者から存在が流れ落ちてくる」「それを抽象によって理性が受け止めている」。より小さなものは、より大なるものによって初めて存在しうる」という大前提がまずあって、そのうえでアンセルムスは証明します。
『モノロギオン』という本の中で、「周囲に見られる不完全な善は、最高の善なしには説明できない。」より小さいものはより大きいものがあって存在しうるので、不完全な善は「存在上も完全な善によってしかありえない。したがって神は存在している」。最後の部分はどうもわからないのですが、こうして証明します。最高善の存在は疑うことができないともいいます。最高の存在が実在していることが、キリスト教の神の存在証明になるのかという論点もあるようですが。
あと『プロスロギオン』で「それより大いなるものが考えられないもの」という概念を使って証明しています。これは有名なようです。「それより大いなるものが考えられないもの」を知性のうちに構成します。「神を信じない者でも、この概念を考える知性は持っている。」頭の中で、それより大きいものが考えられないものを想像してくださいと言います。「単なる概念としての存在は、知性のなかにしかないのだから、知性のなかに在ってなおかつ知性の外にも在るものの方が『より大いなるもの』である」。わかりますか。頭の中でそれより大きいものがないものを想像する。それは頭の外にはない。ですが、頭の外にもあるものがあれば、それは頭の中のものよりもより大だから、頭の中で考えているものよりもより大なものが存在するという論理なんです。理解できないけれど。理性で考えたものは実在するという考えが、彼らの中にはあるのです。だから、知性の中にあり、なおかつ知性の外にも有るものがより大きい。それより大きいものが考えられないものは、だから実在するというのです。その論理の飛躍は僕もわかりませんが、だから実在するというのです。
なぜなら、なぜなら、実在しないと考えられるなら、実在する、と考えられたもの方が「より大いなるもの」だから。そんなも大きいものが実在しないと考えられるならば、実在すると考えられたほうが、より大きいものがあることになるから、あるのだ、というのです。だから神が存在する。存在証明おわり。わかりませんが、こういうのが、神の存在証明です。
評価。アンセルムスにとって、神の存在は論理的前提以上のものである。善のイデアと神のイデアを同一視し、神の存在を証明している。アンセルムスは「信じた」だけ。真の証明にはなっていない。弁護する人は、アインシュタインの相対性理論とよく似て、思考実験で神の存在を証明しようとしていると言います。これは初めて見たのですが、アナクシマンドロスの思考実験です。かれは、ものは何かに支えられて在る、ということを頭の中で探求していった。すべて何かに支えられているならば、最後のものは何に支えられているのか、と考えたときに、すべてを支えている大地は宙に浮いているのでなければならないと結論した。これはわかるのですが、こういう思考の過程で、より大きなものを考えていったときに神は存在しているとアンセルムスは考えたようです。アンセルムスの証明はトマス・アクィナスとカントが否定、ドゥンス・スコトゥスとデカルトが肯定しています。
トマス・アクィナスによる神の存在証明は次のとおり。「そもそもこの世界のなかで何者かが動いているということは確実であり感覚によって確認される事実である。ところで動いているものすべては、他者によって動かされている」。最初に動かすものがいる。「第一の動者が神」。これはアリストテレスの、自らは動かず動かされず、動かす『不動の動者』があるという考えの、『不動の動者』を神と言い換えたものです。ビッグバンが神だと言えばそうなるというのと同じです。
ドゥンス・スコトゥスによる神の存在証明。トマスへの批判です。「トマスの証明は自然学的すぎる。運動による証明は完全に自然を超えた存在である神の存在証明にはならず、せいぜい「神が最初に動かす自然界にあるもの」の存在証明にしかならない。」これはその通りだと思います。スコトゥスは次のように証明します。「因果関係から第一原因の存在を証明し、かつその第一原因は無限なこと(自然を超えたところに置く)が判明するから、それは神だと結論する。」この理屈もわかりませんが、無限はよく出てきます。のちにスピノザは、神は無限であると前提し、無限だから僕らもすべてそこに含まれている。そこで汎神論、すべてのものに神が宿るという考えになるのですが、西洋哲学は無限が好きですね。最高善とか。この証明は僕にはわかりませんが、そんなところでしょう。
八木さんの解説です。「われわれは特定の何かという限定を持たない存在に出会ったことはないし、想像もできない。『無限なもの』の存在は経験上確認できない。ドゥンス・スコトゥスは『存在』と『無限性』には矛盾はないから『無限な存在』は存在可能と主張。なぜ矛盾はないのか。信仰上、人間知性は神を信じているなら、死後に神を直接見る栄誉が約束されている。
ドゥンス・スコトゥスはここから、人間知性が持つ『存在』の概念は、無限な神をそのうちに受け止めることのできる概念なのだという結論を導出。」「理性のなかで論理的推論が実在と一致することは、その推論内部の妥当性のみで判断されることなのか、それとも感覚される事実によって最終的に検証される必要があることなのか。」論理の中で完結していればいい、その主張がプラトン主義者。実在でも感覚によって証明されなければならないと考えるのがアリストテレス主義者。「『無限な存在』の存在可能性を知性のなかで判断できると考えるドゥンス・スコトゥスは、プラトンやアンセルムスの系列。トマスやカントはアリストテレスの系列。」こんな感じです。こんな議論をくちゃくちゃやっていたということでこの話はおしまいです。
最後、中世スコラ哲学の衰退。トマス・アクィナスとあまり時期は変わらないのですが、経験論で教科書にも出てくるロジャー・ベーコン(1214?~94)です。「西欧人は長い間学問の基礎を言語、数学、光学にかかわるものにおいてきたので、私はいまや経験的知識によって保障される基礎に意をそそごうと思う。というのも経験なくしては、人は何事も十分に知ることができないからである。…火を見たことのない人が、火は物を焼くということを、推論をもとに論証して、事実を誤り伝え、それをゆがめる場合、これを聞く人の心は満たされず、…手あるいは可燃性のものを火の上においてみるまでは、火を避けることはないであろう。だがひとたび火によって焼かれるという体験が得られるや、心は確信にみち真理の光のなかに憩う。」
今まで見てきたスコラ哲学とは全然違う観点からベーコンは考えている。この系列の中で見るとすごく画期的な感じがします。
信仰と理性の分離ということでドゥンス・スコトゥス(1266~1308)です。「神はこの上なく自由なので、人間の理性ではとらえられない。」とポンと言います。「必然性や普遍性では確定しがたい存在となる。」こうなってくると哲学の議論から信仰の話は離れていきます。
ウィリアム・オッカム(1290頃~1349頃)は、実践的認識と理論的認識の絶縁を決定的にした。真理は二つの方法によってえられる。一方は、経験によって確証されるものにしかかかわらない証明である。他方は、思弁的な事柄に属し、何ら確実性へと導かず、せいぜい蓋然性にとどまる、それ以外の証明である。神はその全能という属性によってしか定義されないから「神は不確実性と同義になる。神はもはや万物の尺度ではない。…したがって理性はもはや信仰を支えたり、強めたりすることはできない。信仰は結局自由の余地を残して討論の場から離れるか、あるいは感覚以外のすべての領域を支配する懐疑に服するしかない。」このあたりでスコラ哲学は終わっていくということです。
最後です。わからないながら見ていくと、基本的にはギリシア哲学の枠組みの中で、形を変えて論争が続くのだなあということです。感覚の捉える世界は信じられなくて、理性の捉える世界が本当の世界だというのがギリシア哲学からの伝統だと先ほど言いましたが、それをまとめました。
自然哲学を僕らは最初に教えます。万物の根源は水だとタレスは言います。根源は火だとか。これはメガネケースですと僕らは言い、それで終わるのですが、根源を考えるということは、これではない世界があるということでしょう。今この形になっているに過ぎないというのが、万物の根源を考えるきっかけではないか。最初から存在の裏にある何かを、彼らは考えようとしている。
ものだと万物の根源は…、ということなのですが、ソフィストを経てソクラテスになると抽象的な話になってくる。ソクラテスはいわゆる徳・善などをいろいろな人に議論をふっかけます。相手を追い詰めていって、「私は善が何かわからない」と言わせる。これが対話法のポイントで、ソクラテスはわかっているのかというと、「私も善が何かはわからないのだが」と言っている。わからないことを証明して終わる。しかし、善を説明できないけれど、善なるものを見たときに、ああ、これは善だなと見たらわかる。徳が何かは説明できないけれど、徳のある人を見ればわかる。説明できないのになぜわかるのかというと、プラトンは、この世に生まれる前に魂がイデアの世界にあって、そのときに徳とか善を見ていてわかっている。この世に生まれてくるときに半分忘れてしまっている。だから、わかるけど説明できない。こんな風にイデアの世界をおいたと言われています。個別のものとイデアの二つに分ける。
アリストテレスは遠いところではなく、ここにイデアも含まれているとして形相と言った。これが新プラトン主義になると、個物があるけれど、一者・最高に善なるものがあって、それが流れ落ちてきてこういうものになっている。僕らの知性もそこから流れてきていると。同じように、個物と普遍が実在している。ここが普遍論争のバージョンかなと思う。
こういう流れが、決定的に変わるのがデカルトの『方法序説』(1637年)。彼は感覚的世界しかわからないという。「精神的実体」と「物質的実体」の二元論でスコラ哲学からは離れていく。自分の触覚や視覚などの感覚を全部疑って、最後は考えている自分しかないというところから出発する。あくまでも自分が捉えることができるのは、自分の感覚の世界だけで、本当の世界がどうなのかはわからない。完全に外の世界と精神世界を切り離したところから哲学を出発させた。
精神―観念-外界という認識モデル。精神を物質的世界全体から切り離す。精神が対象として直接に知覚するのは心の内なる「観念」。以後近代哲学者は皆、カントの時代に至るまで。「精神は直接には観念を知覚の対象とし、それによって外的世界を間接的に表象する」というデカルトのモデルを全面的に踏襲した。ここまでくると中世的な感覚はなくなります。
デカルトは物質と精神の二元論。一元論は二種類。物質のみというのが唯物論でホッブズから始まる。精神のみというのが観念論でバークリーから。多元論、多種多様な実体があるというのがライプニッツだということです。
なぜ、ヨーロッパ哲学は普遍や個物を越えた向こう側を考えるのかというと、古代ギリシアのパルメニデスという人がいます。この人は、「あるものはある」「ないものはない」と言う。あるものは今までずっとあったし、これかもずっとある。ないものは、これまでもなかったし、これからもずっとない。この人の弟子がタレスで、アルキメデスと亀の話を作った。アルキメデスが亀に絶対に追いつかないとか、放った矢は動かないという話を彼の考え。世界は動かないということを言いたくて、こういうパラドックスを持ち出した。根源にあるのは、存在そのものへの驚きと畏怖ではないか。「ある」ということへの驚き。小さいときに、夜眠れずに自分はなぜいるのだろうとか、世界はなぜあるのだろうとか、考えたことはありませんか。あることってやはり不思議ではないですか。それを考えると、普遍みたいのものが実在するとか、神が存在するという考えになるのだろうなという気はする。そういうのはわかるなと、パルメニデスで思いました。世界の存在や自分の存在に対する驚きが、こういう系列の哲学を生むのかなというのが、今回やった感想です。まとまりなくスミマセン。
-------------------以下、質疑応答(略)
【参考図書】
岩田 靖夫『ヨーロッパ思想入門
伊藤邦武『物語 哲学の歴史 - 自分と世界を考えるために
稲垣良典『トマス・アクィナス 『神学大全』
岡崎 文明『西洋哲学史―理性の運命と可能性
熊野純彦『西洋哲学史―古代から中世へ
ジャック・ルゴフ『中世の知識人―アベラールからエラスムスへ
シュヴェーグラー『西洋哲学史 (上巻)
冨田 恭彦『観念論の教室 (ちくま新書)
野田又夫『方法序説ほか (中公クラシックス)
水野宗明・山口義久・堀江聡編『新プラトン主義を学ぶ人のために
八木雄二『中世哲学への招待
八木雄二『天使はなぜ堕落するのか―中世哲学の興亡
八木雄二『神を哲学した中世―ヨーロッパ精神の源流
八木 雄二『カントが中世から学んだ「直観認識」: スコトゥスの「想起説」読解
山田晶『神学大全I (中公クラシックス)
山本芳久『トマス・アクィナス 理性と神秘
ラッセル『西洋哲学史 2―古代より現代に至る政治的・社会的諸条件との関連における哲学史 (2)中世哲学