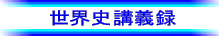世界史アプローチ研究会
『名著で読む世界史120』(山川出版社)読書会 2020年7月17日
レーニン『国家と革命』

|
高校世界史教師で行っている勉強会での、私の報告です。 テキストとして、 『 『 名著で読む世界史120 』を使っています。 |

|
『国家と革命
最初にどの程度の説明から入ったらいいのかわからないので、自分のメモ書なんですけども、それに沿って話します。この勉強会でも以前に社会主義と共産主義の違いは何かという話が何回か出ていました。言葉自体も揺らいでいるようですが、マルクス主義の立場からいったらすごく簡単ではっきりしているんですけれども、そんなところからレジュメに書きました。社会主義といっていますけども、僕らが授業で教えているようにそのマルクス達がいった空想的社会主義から、マルクスもあれば、フェビアン協会やイギリスの労働党もある。その中にマルクス主義がある。マルクス主義のなかにも、マルクスの考え方から出発して様々な革命理論とかあるのですけども、そのひとつがレーニン主義ということです。ただロシア革命が成功してソヴィエトが社会主義として存在していた頃は、マルクス・レーニン主義と続けて呼んでいたので、マルクス主義といったらレーニン主義だというように捉えている人もけっこう多いのではないかと思います。けれど、レーニン主義だけがマルクス主義ではないということです。
でレーニン主義は何かって言うと、これも結構難しいのです。マルクス主義ならば、資本主義的な生産様式の分析とか賃労働の分析、搾取の解明とかさまざまなことがあるのですが、レーニン主義というと『帝国主義論
ロシア革命が成功した後は、マルクス・レーニン主義といわれていましたけども、スターリン批判以降ソ連の実態が様々伝わってくる中で、スターリンがおかしいのは皆わかる。じゃあその元のレーニンはどうなのかということで、スターリンから遡ってレーニンに関する評価も1950年代後半ぐらいから、世界で割れてきたと思います。その中でレーニン主義の典型的な「聖典」である『国家と革命』に関する評価も20世紀後半には二分する。社会主義陣営、マルクス主義陣営の中でも評価する人、しない人が別れた問題の書だと思います。現在では多分この本を金科玉条のように考えている人ほぼいないのではないか。その意味では歴史的文書になったかなと思います。
2番目です。執筆の背景です。1917年二月革命臨時政府とソヴィエトという二重権力状態の中でレーニンはソヴィエトに権力集中するように主張していました。後でも説明しますが、6月・7月とペトログラードで大規模なデモが起きますが、7月の大規模な武装デモをボリシェヴィキが組織したのですが、直前にソヴィエトから中止命令が出て、それを受けてボリシェヴィキはデモを中止します。その後で勢力が大きくなりすぎたボリシェヴィキに対して臨時政府の弾圧がある。レーニンはフィンランドに一時亡命する。その亡命中に書かれた本。だからこの後どうなるかわかんないけども、革命続行臨時政府打倒と言っているレーニンが書いている。では今後くるべきこの、来るかどうかも分からないですけども、10月革命に向けて来るべき社会主義の国家をどのように考えたらいいのかを記した本です。
3番目です。1919年の状況をざっと見ておきたいと思います。政党の配置です。主に三つ。資本家リベラル西欧思想の立場に立った立憲民主党。カデットという名前で呼ばれています。これはあの1905年の第1次ロシア革命の時にドゥーマを設立するという時にできた。資本主義、民主主義の立場です。ナロードニキの政党としては社会革命党、エスエルと呼ばれるものがあります。1901年から02年にかけて結成された政党で、ヴ=ナロード運動の流れをくむ人たちが結成した政党で、基本的には土地の共同体所有を主張していて、社会主義政党と考えてよい。マルクス主義政党として存在しているのがロシア社会民主労働党です。1898年結成なので、実はこの中で一番古い。このロシア社会民主労働党は様々なマルクス主義系の政治団体が結集してできたのですが、組織論問題で1903年にはボルシェビキとメンシェヴィキに分裂した。これは教科書にも出てきますね。党員資格問題を発端にしても分裂した。執行委員会のなかではボリシェヴィキが多数なのですが、全体のメンバーとしては少数派だったということは有名な話だと思います。
1917年の経過です。二月革命後に二重権力状態ができます。焦点になるのがペトログラードにある臨時政府とペトログラード・ソヴィエトです。ソヴィエトというのはあちこちにできるし全国ソヴィエトもペトログラードにできるんですけども、革命情勢を左右しているのはあくまでもペトログラードの労老ソヴィエトです。これが一番ペトログラードの情勢を反映している組織だと思います。ソヴィエトはどのように結成されたかというと、軍隊の中隊ごとに兵士1名、工場は労働者千人につき1名。規模が小さい工場は全体で1名。ダビリーザ宮で最初の総会が開かれている。この時の人数がめちゃくちゃ大雑把なんですけども、代議員は150から250名。池田嘉郎さんの『ロシア革命』という本に拠っています。150から250名で、確かのことがわからない。フランス革命はたくさん本がでていろんな分析があるのですが、それに比べるとこのロシア革命は情報が限られていることもあるのか、なかなか正確な情報がわからない。混乱期なのでいろんなものが散逸しているのかなと思います。
この中では当初ボルシェビキは非常に少数で、メンシェヴィキとエスエルが手を携えて主導権を握っていました。この段階での彼ら社会主義者の認識です。2月革命は皇帝が退位して、西欧型ブルジョア民主主義体制ができる革命なのだ。ブルジョア革命がようやく20世紀初頭にロシアで起こった。マルクス主義社会主義の理論では、封建制社会の次に資本主義社会が来て、その中で資本主義の経済が発展した後で初めて社会主義の社会が可能になるというふうに考えている。したがって、これからロシアは資本主義社会として発展すべきであるので、社会主義革命はずっと先だという認識です。なので資本主義社会を担っていくであろう臨時政府を支えるべきだというふうにソヴィエトに結集したメンシェヴィキ、エスエルは認識していました。ただし戦争を継続するかどうかという点になると、臨時政府は戦争継続ということで連合国に承認されていましたから、戦争継続が臨時政府の大きな看板なのです。ソヴィエトは資本主義の発展のために臨時政府を支えようと考えてはいるけども、戦争継続には同調できないというところがジレンマです。ペトログラード・ソヴィエトを支えるペトログラード市民や兵士たちも、戦争はやめたい。それが。そもそも2月革命の発端だった。このジレンマからペトログラード・ソヴィエトは臨時政府を支えるのか、支えないのかということで非常にグラグラグラグラ揺れているという印象です。そこでレーニンが四月に帰ってきて四月テーゼ意を発表する。レーニンだけが認識が違う。今はもう社会主義に向かっているんだということです。革命は権力をブルジョアジーに与えた第一段階から労働者に権力を引き渡す第2段階移行しつつあるといい、「全ての権力をソヴィエトへ」と唱えました。ボリシェヴィキの中ですらレーニンがこのように言った時には同調する人はほとんどいなくて、レーニンはボリシェヴィキのメンバーを説得してまわったという話は有名です。
このかんのペトログラードの状態がなかなかわからないのですが、E・H・カーがまとめていますので紹介します。「二重権力の実態は権力の完全な拡散である。労働者農民の気分というのは恐るべき悪夢からの巨大な解放感、自分自身のことを自分たちの流儀で勝手にやりたいという根深い願望。これが実行可能であり本質的なことなのだという確信。熱狂の波。人類の解放というユートピア的ビジョン。」とにかくお祭り騒ぎ、みんなが熱狂して盛り上がって大騒ぎしているイメージですね・池田さんは「バケツの底が抜けた状態」と書いています。なんでもありという無政府状態的な感じなのかなというイメージです。この時にペトログラードに取材に行ったアメリカの新聞記者でジョン・リードという人がいます。『世界を揺るがした10日間
そういう中でペトログラードの労働者とか兵士の湧き上がってくるエネルギーをソヴィエトは制御できない。しかし臨時政府を支えなければいけないと考えている。そのなかでボリシェヴィキだけは、はっきりと戦争反対といって、ブルジョアジー・臨時政府に明確に対抗する姿勢をとったことによって、労働者兵士の間に深く浸透していきます。 臨時政府はドゥーマ、国会議員の中からできるのですけども、基盤が全くなく勝手に集まっている。民衆から支持されて成立したわけではない。臨時政府と名乗っている根拠は連合国が承認していることだけ。臨時政府の正式名称は「臨時政府」だそうです。もっとさかのぼると、そもそもこのときの議員を選んだ国会選挙は、例のストルイピンが法律を無視して勝手に改正した議会選挙法に基づいて選挙された国会議員なので、国会議員たちも俺たちの国会議員資格に根拠があるのかという深い疑問を持っていたそうです。そういった人々が勝手に作って正式名称「臨時政府」なので基盤がどこにもない。
基盤を作るためにはソヴィエトと連携するしかないということで、5月には閣僚を入れ替えて社会主義者の大臣を任命して、社会主義者と連立政権というのかな、ソヴィエトとの連立政権を作る。この辺になるとソヴィエトは明確に臨時政府を支える立場になりますから、民衆の直接行動、デモンストレーションを抑えこむ側に立つ。そこで、6月のデモや7月のボリシェヴィキが企画した武装デモに対しても厳しい態度を取る。ボルシェビキはその時は武装蜂起しても勝てる力はまだないという判断だったので、ソヴィエトと臨時政府の勧告に従ってデモを中止します。その後は、臨時政府はボリシェヴィキの弾圧をはじめトロツキーは逮捕されレーニンは亡命する。
こういう状況、大混乱している中でコルニーロフという司令官が前線の兵士への銃殺の復活をやって前線での秩序の回復に成功して名前を上げる。前線に物資がちゃんと送られてこないのは鉄道労働者や工場でストばかりやっているからだと、後方での秩序回復を要求する。臨時政府もそれに応えないといけないということで、録画戒厳令を敷こうとする。最初はケレンスキー首相とコルニーロフは歩調を合わせているのですが、だんだんケレンスキーがコルニーロフは自分を倒して独裁政治を目指しているのではないかという不安に駆られる。結局コルニーロフの反乱という形になります。反乱を鎮圧するためには民衆の力が必要となり、牢屋に入っていたボリシェヴィキは釈放され、市民の武装も許可されて、その力でコルニーロフの反乱は失敗に終わる。ここからボリシェヴィキは復活しレーニンも帰ってきます。
臨時政府は自分たちの存在根拠を作りたいので、いくつかの会議を開くのです。モスクワ国家会議、民主主義会議、予備会議など。なんとか大衆に基盤をつくろうとするんですが全部失敗していきます。その中でペトログラード・ソヴィエトではボリシェヴィキの勢力が主導権を発揮して武装蜂起にいたるということです。
二月革命から十月革命までの流れとして情勢の鍵を握っているのは、やっぱりペトログラード・ソヴィエトです。全ロシア・労兵ソヴィエトというのもペトログラードにあるんですが、これは全国から集まってきていて臨時政府側、メンシェヴィキ、エスエル側です。あとペトログラード守備隊2月段階で18万、これも大きなカギを握っている。フランス革命でパリの国民衛兵が全体の情勢を握っていたのと似た状態が1917年のロシアにも存在していたことがわかります。
1917年の経緯の補足です。2月23日に「パンよこせ」とい9万人のデモが始まるところから出発します。27日にはボルインスキー連隊が反乱を起こして労働者側について革命が始まります。
2月27日の2行目ペトログラード労働者ソヴィエト臨時執行委員会があります。これが多分その次のペトログラード労兵ソヴィエトに繋がっていくと思います。命令第一号が資料にソヴィエトが政府だという証拠としてよく出てきます。池田さんは立場的に臨時政府に拠っていて、あまりソヴィエトを政府として認めたくない人で、命令第一号を評価していませんが、これは簡単にいうと臨時政府が出した命令が労兵ソヴィエトの決定と違反しない限りそれを遂行してもいい、というものです。あくまでも兵士は労兵ソヴィエトの命令をまず優先しなさい、矛盾した場合は労兵ソヴィエトに従えと。もうひとつは、一切の武器は兵士の委員会が管理し要求があっても将兵に引き渡してはならない、というもの。将校に武器を渡すなというものです。この時にペトログラード・ソヴィエトは将校が武器を取り上げて弾圧することを恐れていたと、どこかに書いてありました。
6月4日、第1回全ロシア・労兵ソヴィエト大会、全ロ・ソビエト中央執行委員会選出とあります。これがペトログラード・ソヴィエトと違う組織で、エスエル、メンシェヴィキ側の組織です。ペトログラード・ソヴィエトとは結構対立している。またアナーキストのグループがすごく運動していて、6月7日のところにアナーキスト指導のデモ、とありますがこれが結構情勢を前へ進める、臨時政府がわからすると撹乱することをやっている。だいたいデモを起こしてプレッシャーをかけていくのはアナーキストグループかボリシェヴィキです。6月10日にボルシェビキがデモ中止決議とありますが、彼らが組織しようとしていたデモに臨時政府中止命令を出したのでやめたということです。
デモをするとボリシェヴィキとかアナーキストが主導権取って、彼らの支持者の多さが目立つので、そうじゃないことを示そうと6月18日にソヴィエト全国大会指導デモが行われます。ここでメンシェヴィキが自分たちの支持者の多さを見せつけたかったのですが、これも実際やってみたらデモ参加者の多くはボルシェビキだったということです。
あと憲法制定会議を始めからやると臨時政府はいっていますが、何回かの延期をしています。7月24日に臨時政府は社会主義者をさらにたくさん入れた内閣をつくりますが、この時にも9月に予定していた憲法制定会議を先延ばししています。実施したら不利になると思ったのか分かりませんが。結局十月革命の後11月の憲法制定会議が予定どおり行われて、その結果エスエルが第一党になるというのはご存知の通りです。
ボリシェヴィキが優勢になる中で、9月27日にトロツキーがペトログラード・ソヴィエトの執行委員会議長になります。これで、ペトログラード・ソヴィエトの舵取りを出来るようになる。これは大きいです。さらにペトログラード・ソヴィエトが軍事革命委員会を作ります。この議長になったのがトロツキー。10月革命はトロツキーが主導したといわれていますが、こういう立場で準備していったということですね。
9月ぐらいにレーニンが亡命先から帰ってきて、武装蜂起だ!やれやれ!といっているのですが、それに関してはボリシェヴィキの多くはそんなことは無理だと抵抗している。レーニンだけいっているのですが、4月と同じなのですが最終的には皆を説得していきます。今やれ、すぐやれ、といっていますけど。トロツキーは全ロシア・ソヴィエト大会に合わせてやりましょうということで、それに合わせて実行します。それが10月25日。午前2時蜂起始まると書いてあります。ちょうど第2回全ロシア・ソヴィエト大会が始まっているので、この大会で承認させる、そんな流れだったようです。
(質疑)略
みなさんの感想を聞いて思ったことついて、すこししゃべらせてください。授業で教える時にいつも戸惑うのは、今の生徒たちの社会主義との距離感が全然わからないことです。彼らはソ連崩壊を知らない。僕らはソ連がある時に生まれて、だんだん駄目になってるいね、ひどいね、っていわれて、やっぱり消えたね、というので、なにか否定的な感じを持っている生徒を前にして、そうじゃないよといういい方をしていたのですけども、今はもうまっさらな感じで、今はアメリカでも社会主義を良いと思う若者が増えているという50年前で信じられないような状況になっている。今の日本の高校生たちが、どういう距離感なのか私は戸惑っている。2月革命、十月革命の過程を教える中で、革命はプラス評価で言っておかないと、第1次対戦後の世界各地での女性参政権、ワイマール憲法の進歩性、日本でも中国でもインドネシアでも共産党ができているとか、米騒動の話にしても様々な地域で社会運動が盛り上がっていくことが、世界史の流れの一つとして伝えられないんじゃないかと思う。だから、否定的ではなく、肯定的に話しておかなければいけないという気持ちがあった。当然その後マイナス面がたくさんあるから、それも言わなきゃいけないと思うのですけども、そんな感じで以前はそのためにちょっと上げていたのですけども、今距離すらわからなくなっている。
あと、タイミングの話がありましたが、これはレーニンの戦略だと僕は思っています。ちゃんとみはからってやっている。「全ての帝国主義戦争を内乱へ」といって、今がチャンスと図っていると思います。 レジュメに戻ります。『国家と革命』の内容を簡単にまとめました。この『世界史120』の池田さんのまとめも、すごくよくまとめられていると思います。
簡単に4項目だけ書きました。1917年6月段階、執筆段階において、暴力革命によるブルジョア国家の破壊とその後のプロレタリアート独裁のプログラムを理論的に正当化したのがこの本です。民主主義も打ち倒すべきブルジョワ国家の一形態であることを繰り返し強調している。最初にこの本を読んだ時に、民主主義とか暴力革命とく言葉自体を、自分の中でこの文脈の中でどのように使っているいかを受け入れるまでに、抵抗感がありました。結構どんな人にも抵抗感あるかなと思う。僕は今では、なくなってしまったのですが。マルクス・レーニン主義の用語として、こういう言葉を使っているという事を、まず頭に入れなければいけないと思います。あえて論争的にこういう言葉を使っている面もあると思いますが、挑発するようなところがね。
この本では官僚機構を徹底的に批判しています。これは楽観論にも通じていて、社会主義革命後は官僚制度を打ちこわし、それに代わって人民による簡単な統治機構に置き換えられるのだという楽観論もこの中にはあります。これは革命後のロシア、ソ連がたどった官僚制を見るとすぐに裏切られていくことがわかるのですが、この段階では非常に楽観して簡単な統治機構で社会主義建設ができるとレーニンが考えているのが面白いところです。 簡単な統治機構に置き換えられるという根拠は、パリ・コミューン。1870年に第二帝政崩壊後のパリで一瞬成立したパリ・コミューンをマルクスは世界最初の社会主義政権と評価している。レーニンはその評価を引き継いで、パリ・コミューンではどのような自治組織ができたのかということを『フランスの内乱
一番気になるところが、この本の中で民主主義国家を打ち倒してプロレタリア独裁を作るのだというんですが、その中で共産党なりの政党の示す役割に関しては一切言及がありません。革命における党の役割とか、革命後の国家建設における党の役割については全く言及がない。これも後のソ連の歴史を鑑みる時に、触れてないということはどういうことなのか。これはすごく疑問であるとともに、興味深いところです。以上が大まかなまとめです。
もう少し細かく見ます。序文があり、国家論がいるのだといのが、この本の大前提です。現在帝国主義観戦争が行われている最中に、独占資本主義が国家独占資本主義に転化し、それがどんどん進んでいく。国際プロレタリア革命は明らかに成長している。この後の展開で明らかになるのですけども、ロシアで社会主義革命が成功するのですが、十月革命後、レーニンは単独では社会主義を維持できないと考えています。その後ドイツで、イギリスで、フランスで引き続き社会主義革命が起こることによって、ロシアの社会主義革命は継続するのだと。西側諸国における社会主義革命がロシアの社会主義革命の前提条件と考えています。のちのブレスト=リトフスク条約で大幅な領土割譲にゴーサインを出したのも、いずれドイツでも革命が起こるから、そのことはあまり気にしなくてもよいというのは、頭のどこかにあったと思う。レーニン達共産主義者の発想は、国家主義とか民族主義とかとは無縁。インターナショナルなので国境がない。国境とか民族とか国家主義とは無縁の発想をしている。そのなかで国際プロレタリア革命という言葉が出てきている。
来るべき革命は国家についての日和見主義的偏見と戦うことなしには不可能だと、序文にあります。彼が敵として見ているのは、ブルジョワの利害を代表する論者ではなくて、メンシェヴィキ、彼から見たら修正主義的社会主義。もうひとつはアナーキストです。メンシェヴィキによる国家論の間違いを正すというのが一番大きなポイントです。先ほどいったように、メンシェヴィキは当面は資本主義社会を継続すべきだという発想なので、それも含めた批判になるのだと思います。
第一章の「階級社会と国家」の1のところです。階級対立の非和解性の産物として国家というとこでエンゲルスの文書を引いています。この文はものすごく有名な文章でマルクス主義国家論の中核です。どこかで皆さんも読まれたことはあるか思います。「国家は一定の発展段階における社会の産物。社会が和解できない対立物に分裂。すなわちあい争い合う経済的利害を持つ諸階級が無益な闘争によって、自分自身と社会を滅ぼさないようにするために、外見的には社会の上に立って、この衝突を緩和しそれを秩序の枠内に保つべき権力が必要…。社会から生まれながら社会の上に立ち、社会に対してますます外的なものになっていくのがこの権力が国家」だと書いています。これが基本です。それに対するプチブル的修正が国家は諸階級を和解させる機関ということですが、そうじゃないんだという。マルクスは「国家は階級支配の機関である」「一階級が他の階級を抑圧する機関である」「被抑圧階級の解放は、暴力革命なしには不可能なばかりではなく、さらに、支配階級によってつくりだされ、この「疎外」を体現している国家権力機関を破壊することなしには不可能」と書いている。エンゲルスの弟子で資本論4巻の原稿を託されたカウツキーは「暴力革命なし、国家権力破壊なし」で社会主義に行けるとして、マルクスを歪曲していると批判しています。
マルクスの言葉で「国家権力機関を破壊することなしには不可能」と書いているのですが、別の本を見ていると、マルクスは国家権力機関が絶対王政の時に初めてできたと書いています。僕たちが考える国家機関とマルクスの考えるものとはちょっと違う。絶対王政時代にでき、フランス革命的に完成し、ナポレオンによりさらに巨大になると書いている。だから、この国家権力機関は具体的には官僚制と常備軍だと思います。
あと、エンゲルスの言葉で国家が「社会の上に立つ」とありますが、吉本隆明は『共同幻想論』の序文で、われわれ日本人は、国家は社会をすっぽり包む袋のようなものだと考えている。しかし、マルクスを読んで、彼らは国家は社会の上に載っていると考えている。全然考え方が違うと驚いている。だから、西欧人的な国家の観念と、アジア人が伝統的に抱いている国家の観念は少し違うのかなと、この文章で思ったところです。
国家は階級抑圧の帰還なのだけれど、見かけの上で階級の調停者に見えるときがあるということで、絶対君主制、フランスの第一、第二帝政、ドイツのビスマルク、ケレンスキー政府を挙げています。
普通選挙制度に対する間違った見方として、「労働者階級の成熟度の計器」「それ以上でもそれ以下でもない」。普通選挙が発展しても社会主義社会に移行する藻ではないと言っています。しかし、日和見主義者:「それ以上のもの」を期待しているとして批判しています。国家は階級抑圧機関なので、「階級が消滅するとともに、国家も不可避的に消滅」。
革命が起きて社会主義になると、階級がだんだん消えていくにしたがって国家は眠り込んでしまう。人に対する統治も変わって、物の管理と生産過程の指導が現れるということで、単純な生産管理だけで国家が運営できるようなことをレーニンはいっています。社会主義革命後の話ですけども。
日和見主義的解釈として、国家の死滅を「緩慢な変化」だと解釈する。これは革命を曖昧化する。権力が移行してドラスティックな変化が起きることを否定する意見につながるということで、これが1870年代ドイツ社会民主党綱領にそんなことが書いてあると批判していました。
第1章は大まかな話、第2章がマルクス・エンゲルスの文献を順番に見ていくなかで、色んなコメンをしている部分です。一番の革命の前夜ということで、最も初期の『哲学の貧困』『共産党宣言』において既にマルクスはプロレタリアート独裁の定式化を行なっていると、レーニンは言っています。そのことが今忘れられているとレーニンは言います。ちなみに『共産党宣言』の中にプロレタリアート独裁の語句は一つもありません。プロレタリアートには国家権力が必要だということで、革命後も階級がある限りは、今度はプロレタリアートが支配者階級となってブルジョア階級を抑圧する必要があるという理屈になります。
フランスの二月革命の総括。マルクスの『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日
第3章、パリ・コミューンの経験ということで、マルクスの本から引用しています。『共産党宣言』の1872年序文にこう書いてある。「コンミューンは労働者階級は出来合いの国家機構をそのまま奪い取って、自分自身の目的のために動かすことができないということを証明した」というマルクスの文章があります。そのまま奪い取って動かすことできないという部分を、日和見主義者は暫時的発展の思想表明としてとらえる。そのまま動かせないけれど、じわじわ変えていくと。レーニンはそうではなく出来合いの国家機構粉砕していくべきだとマルクスは言っているのだと解釈します。ただしイギリスは例外とマルクスは言っている。「軍閥がなく官僚制が未発達だから」ということで、この辺ちょっとよくわからないのですけども、そう認識しているようです。ただ1917年段階においては、イギリスにおいても打ち砕くべきものだとレーニンは考えています。
粉砕された国家機構を何に取り替えるかということで、そこからは反官僚機構みたいなことが書いてある。全ての公務員の完全な選挙制と解任制の採用。資本主義文化は大規模生産、工場、鉄道、郵便、電話を作り出した。すごく高度に発展したこういうものがあるので、これを管理するのは簡単だという結論なのです。旧国家機構の大部分は非常に単純化できる。僕らが管理できるといういい方をしている。
同じような主旨のことで、反官僚制の文言があります。国家管理に特有な指揮統率を監督と簿記係の単純な機能とに代える。これは都市住民の発達水準と労働者並みの賃金で遂行できる機能である。国民経済全体を郵便のように組織する事なのだということで、彼が考える社会主義のイメージは郵便局、電話、鉄道というイメージで捉えているようです。また後で出てくるけれど、革命後に社会主義とはロシアの電化であると言っています。そういうものであれば簡単に管理できる。そういう発想があったようです。
(休憩)
先ほど要約をかいつまんで話しましたが、まとめていうと現在の国家はブルジョワ独裁である。それを暴力革命によって打ち砕いてプロレタリアート独裁の国家を打ち立てる必要がある。その際に複雑な官僚機構は要らなくなって簡単な人民による管理機構だけに置き換えることができる。それも階級がなくなるに従って、徐々に死滅していって最終的には国家がなくなる、というのが大まかな流れです。
その際に議会制民主主義はどうなるかというと、あくまでも議会制民主主義は労働者の成熟の度合いを測る測りに過ぎなくて、いくらブルジョア民主主義、議会制民主主義を発展させてもそれはそのままでは社会主義に移行することはない、というのがレーニンの主張の主なポイントです。
この『国家と革命』の評価です。世界の革命運動への影響ですが、先ほども申しましたように、このレーニンの国家論・革命論はマルクス・レーニン主義といわれる考え方の聖典として長く祭り上げられてきました。がレーニン在世中も、異論は西ヨーロッパではかなりあります。レーニン死後スターリンの時代になって、とソヴィエトの実態を見るにつけ、その出発点であるこの『国家と革命』自体に問題はなかったのかということは、当然出てくる議論でした。議会制民主主義が発達して、共産党にも活動の自由が与えられた諸国家においても、この『国家と革命』の理論は貫徹すのかというのは、当初から疑問視されていた。
レーニンが活躍したこの1917年段階のロシアにおいては、それ以前にドゥーマという国会はあったけど、もうこの時点では国民に選挙された国会はなく、民衆の意思を反映させる手段はない。ソヴィエトがありますけれども、臨時政府があるのであればそれを暴力によって倒すしか、次へのステップは取りえないのは事実です。では逆に議会民主主義がある国においては、そんなことしなくていいのではないかということで、批判的な革命論はいくつかあります。
代表的なのがそこにあげたグラムシです。彼は第二次大戦中に投獄され獄中死していると思います。イタリアは結構マルクス主義であっても違う路線を考える人が多かった。この人の本を読んでいないので説明できませんけども、概説的には労働者の自主管理によって社会主義的なシステムに移行していこうと考えていたようです。グラムシの盟友にトリアッティという人がいますが、民主主義的土台を基礎にした上での構造改革による権力の獲得ということをいっていて、この言葉から1950年代「構造改革路線」が世界的にはやりました。地方自治体・コミューンというものを基盤において、徐々に社会主義に移行できるということが主張の核心のようです。ヨーロッパでは1970年代以降ユーロコミュニズムといういいかたで僕らの世代は聞いたことがあります。完全に暴力革命やプロレタリアート独裁を破棄します。レーニン主義とは全く違う路線をヨーロッパの社会主義政党は選択します。それは共産党とか社会党という名前のついた政党はみな同じだと思います。
日本共産党は、第二次世界大戦中ぼこぼこにされていましたが、戦後再建されて、そのあと実は武装闘争路線をとっています。1955年の第6回全国協議会でその路線を放棄するまでつづきます。ただ、これはレーニン的な暴力革命と意味合いが違っていて、この時日本共産党は、日本はアメリカの支配下にあると考えていて、民族独立革命的な意味あいで武装闘争といっていました。日本においても1950年代まで武力によって革命を起こすという発想があるあったことがわかります。日本がそうかわかりませんが、議会制民主主義が遅れている後進国においてはわりとレーニン主義的な議論は浸透力があったと思う。実際にキューバ革命はそうでした。僕が高校時代ぐらいに課題図書なったかどうかは忘れましたが、柴田翔という人の『されどわれらが日々
1970年に日本共産党の書記長に就任した不破哲三は、実は構造改革派だといわれていました。日本社会党という政党が昔ありましたが、社会党は右派の社会主義者からマルクス・レーニン主義の社会主義協会まで幅のひろい社会主義政党でしたが、1960年に構造改革路線を正式に採用します。江田三郎という僕らの世代が名前を憶えている人ですけども、この人が中心になって構造改革路線を採用した。この時にはマルクス・レーニン主義的な勢力も強く、ちょうど1960年は三井三池闘争と安保闘争がすごく盛り上がっている。日本史において総資本対総労働という形で教えるのですけども、資本と労働者階級の激突というような側面が現場にはあったので、江田三郎、社会党が構造改革路線を採用することは自民党政権に擦り寄っているというふうにとられる側面はすごくあった。その後も議論が続いていて、社会党は以後衰退していく。こういう議論すらしなくなっていくのですけどね。
レーニンはマルクス・エンゲルスの様々な本から引用して、立論をしているのですが、本当にマルクス・エンゲルスがレーニンのいう主張をしているかどうかなのですけども、都合のいいところだけ集めてきてこの本を作っているといえないこともない。現在ではそういう指摘がさまざまになされています。ちょっとだけマルクスの言葉を紹介します。
「イギリスでは政治的な力を発揮する方法は、労働者階級に解放されている。平和的な扇動の方が敏速且つ確実に仕事なしえるところでは蜂起は狂気の沙汰」とマルクス書いている。参考文献、伊藤誠・大藪龍介・田端実編『21世紀のマルクス―マルクス研究の到達点
レーニンの官僚制不要論ですが、かれの主張は渓内謙さんの『現代社会主義を考える
それからレーニンの社会経済の技術の把握の仕方ですけれども、テクノロジーの発展が統治機構を単純化する、というのがレーニンの基本的な発想。社会主義は国民経済全体を郵便のように組織することだ。ロシアの社会主義は電化だ、といっています。でもこれはあまりにも単純すぎて、20世紀の現実ではなかったということです。
ちょうど『国家と革命』が書かれた翌年、1918年にマックス・ウェーバーがドイツ革命の直前にオーストリアの将校団の前で講演をしています。「社会主義」という題の講演で、講談社現代文庫に、こんな薄い本ですが、はいっています。この中でウェーバーは社会のあらゆる部門で官僚制化は不可避だ、どの社会のどの分野でも官僚制は信仰していくといっています。レーニンがこんなこといっているけども、それはどうかな、ということで、実際に革命の翌年ロシアですでに工場の階層性が進み、軍の階級制度を復活していると指摘しています。
ウェーバーの指摘に関連して「世界史120」で池田さんがコメントしているなかで、『国家と革命』で語られた国家の死滅をボルシェビキのリーダーは本当に実現しようとしていたと書いており、内戦期にトロツキーが工場労働に軍事技術を持ち込んだのも云々かんぬんと347pに書いてあるのです。この部分は理解しがたかった。理解が違う、池田さんは誤解している、ウェーバーの方がたぶん正確なところ突いているんじゃないかと思います。あと、ロシアにおけるプロレタリアート独裁は下士官による軍事独裁だと身も蓋もないことをいっています。下士官が銃を突き付けてやっているのだと。
社会主義国家における党の役割について、この本には一切出てきません。過去においてボルシェビキ、メンシェヴィキが分裂するときに、党の組織問題でたくさん発言しているレーニンですが、革命において、もしくは革命後における党の役割が一切ない。プロレタリアート独裁との関係も全く不明です。1924年にロシアは憲法を初めて制定しますが、そこには党の記載が一切ない。1936年のスターリン憲法では党の規定が初めて出てきました。そこではこう書いてある。「社会的および国家的組織の指導的中核である。」それだけです。僕らが現実を見ていると、共産党の一党独裁であり、それをプレート独裁に繋げるのには、すごく細い論理の綱渡りをしなければいけないんですが、そこに関して一切何も言及しない形でなっている。
ソ連崩壊後ということで、現在の革命論です。ソ連があった時も、『国家と革命』、レーニン主義に関しては様々な異論がでていましたけども、崩壊後どうなったかということです。この間ちょっと読んでみました。
共産党からそうではない人までいろんな人たちの本を読んだのですが、面白い事に一切、革命をいっていません。社会主義革命という言葉がないです。レーニンが徹底的に批判し、ずるずると資本主義社会から社会主へ移行するなどありえない、カウツキー、日和見主義と批判していたものが、今は世界の常識のようです。40年間この手の本を読んでいなかったので、えらく変わったもんだなと思いました。権力の移行に関して言及している人も一人もいません。当然プロレタリアート独裁という言葉も誰の本にも出てきません。日本共産党は、すでに僕ら学生時代からプロレタリアート独裁はいわず、プロレタリアートの執権という言い方をしていた。これは独裁という言葉がすごく違和感があり、国民の支持を得難いので言い換えたのだろうとみんないっていました。北条氏のようだとも。ところが、いまはプロレタリアートの執権という言葉すら出てこないし、共産党もいっていない。プロレタリアート独裁にあたる期間のことを、ただ「過渡期」「長期にわたる緩やかな変革」、「過渡期の政体は民主共和制」といっている。それからレーニンの『国家と革命』でレーニンは『ゴータ綱領批判
社会主義という言葉も不破哲三は使っていない。かわりに未来社会といっている。びっくりしました。未来社会と出てきたら社会主義のことをなんとなく示唆している。そのぐらい時代は変わっている。未来社会では自由な結合的労働が起きるという。
こういう形で、マルクス・レーニン主義だったら、資本主義社会から社会主義社会に移行する時に権力の移行は絶対あって、それに加えて私的所有がなくなる。国家所有か公有かは分かりませんけども、それに切り替わるところがあるはずなのですが、そこについては誰も触れない。分からないことはいわないのかもしれませんが。
今、新進気鋭の斎藤幸平という人がいます。新進気鋭のマルクス主義経済学者です。この本『未来への大分岐
斎藤氏がなぜ有名になったかというと、マルクス主義の立場から気候変動問題を取り上げている。この人の言葉「気候危機を語らなければ左翼ではない」。所有や労働問題も言及していますが、命の問題として気候変動を取り上げている。そういうマルクス主義です。 この人の論点をいくつか書きました。労働時間の短縮はすべきだ。しかし、賃金は下げてはいけない。AIやオートメーションが失業を招くといわれているが、それはチャンスだ。働かなくても社会が成り立つということだ。「失業をしたら給料がなくなるから心配だ」ではなく、失業しても社会がまわるような生産力がある。生産力の発展を意味しているのであって、社会主義に移行するチャンスだといっています。
また今回初めて知った言葉でコモンという言葉があります。伊藤誠や大藪龍、不破哲三も、現在の社会主義の人たちはみな言及している。これは「民主的に共有され管理される社会的な富」のことで、共有化もしくは共同管理。鉄道、水と医療、教育、インターネットなど、これらを共有化、市民の共同管理に移すべきだという。これをコモンといいます。コモンを社会主義に移行する運動の始まりと考えているようです。例として書いてあったのは、2013年ベルリンの電力システムのコモン化。民間に移行されていた電力システムが再公有化される住民投票があった。ボリビアでも水道を民間委託することに反対する運動が起きたとか、アメリカの先住民の保有地を通ってパイプラインを作ることに対して、環境破壊だけでなく先住民の権利も含めてのコモンの問題として反対運動が起こった。そういう例を色々あげている。これが社会主義に向かう運動なのかどうか私には分かりませんが。
それからアソシエーションという言葉もたくさん出てきます。住民による管理自治のことをアソシエーションといっています。「階級及び階級対立をもつブルジョワ社会の代わりに、各人の自由な発展が万人の自由な発展のための条件である連合体、アソシエーションが現れる」と共産党宣言に書かれています。岩波文庫では Association を協力体、大月文庫では共同社会、角川文庫では社会組織と訳しています。この言葉がマルクス主義陣営では大流行しているようです。アソシエーションで検索してみると、大谷禎之介『マルクスのアソシエーション論
また斉藤幸平がいうには「リーダーなき社会運動と政党の水平結合の模索」ということでソ連の失敗や中国共産党の現在があるので、上下関係のあるような運動組織、党組織に対する拒否反応があり、リーダーなき社会運動を非常に持ち上げています。ウォール街のオキュパイ運動、学生ローンボイコット運動、バーニーサンダースやオカシオ=コルテスに非常に注目している。ギリシアのシリザ(急進左派連合)、スペインのポデモス(バルセロナ市長アダ・クラウと社会運動との関係)は、そのような勢力として齋藤幸平など新しい社会主義運動の人々が注目しているようです。先週だったか、スペインでは急進社会党とポデモスが連合してベーシックインカムを始めるというニュースが流れていました。全員に配るわけではないので本来の意味でのベーシックインカムではないそうですが、新たな社会的な流れが生まれている。そういう意味で現在の社会主義は僕たちの若い頃とは全然違う。ものすごく変わったというのが率直な印象です。
-------------------以下、質疑応答(略)
【参考図書】
池田嘉郎『ロシア革命――破局の8か月 (岩波新書)
伊藤誠、大藪龍介、田畑稔編『21世紀のマルクス―マルクス研究の到達点
カー『ロシア革命―レーニンからスターリンへ、1917‐1929年 (岩波現代文庫)
渓内謙『現代社会主義を考える―ロシア革命から21世紀へ (岩波新書)
不破哲三『『資本論』のなかの未来社会論
松田道雄『世界の歴史〈22〉ロシアの革命 (河出文庫)
マックス・ウェーバー『社会主義 (講談社学術文庫)
マルクス・ガブリエル他、斎藤幸平編『資本主義の終わりか、人間の終焉か? 未来への大分岐 (集英社新書)
ジョン・リード『世界を揺るがした10日間 (光文社古典新訳文庫)