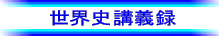第100回 イギリスのインド支配
--------------
インドの政治状況
----------------
インドは、16世紀以降、ムガル帝国が支配していましたが、第6代皇帝アウラングゼブ(位1658~1707)の死後、衰退していきました。各地で在地勢力が自立していきます。
代表的なものが、インド中部のデカン高原を中心とするマラータ同盟、インド北部パンジャーブ地方のシク教国です。マラータ同盟はマラータ族の諸侯連合でヒンドゥー教の国。シク教国は、その名の通りシク教という宗教によって建てられた国です。シク教は16世紀前半にナーナクという人物が始めた宗教で、イスラム教とヒンドゥー教を融合したものです。シク教徒の男性は長く伸ばした頭髪をターバンで包んでいて、名前の最後に必ずシング(シン)とつけるのが特徴で、現在でもそれは変わりません。シク教徒は勇猛果敢で知られていて、昔、プロレスラーにタイガー・ジェット・シンという人がいました。アントニオ猪木と死闘をくりかえしたんですが。彼が本物のシク教徒かどうかは知りませんが、勇猛なシク教徒ということを売りにしていたんですね。まあ、日本では、シク教徒のことをほとんどの人が知らなかったと思いますけど。
--------------------------------------
イギリス東インド会社によるインド征服
--------------------------------------
ちょうどムガル帝国が衰退していくのと入れ替わるようにして、イギリスがインドに登場します。イギリスは17世紀以降、マドラス、ボンベイ、カルカッタに商館を建設し、ここを拠点として貿易を本格化させます。商館といっていますが、実際には要塞のようなもので、商売をするだけでなく、地元の権力者との交渉や戦いによって土地も獲得していきました。
フランスも、17世紀後半には、同様に商館を建設しました。フランスが拠点にしたのはシャンデルナゴルとポンディシェリで、シャンデルナゴルはベンガル地方にあってカルカッタに近い。ポンディシェリも南インドでマドラスに比較的近い。当然、イギリスとフランスは競合することになります。
一時は、フランスがイギリスを圧倒した時期もあったのですが、18世紀の半ばに南インドでイギリスとフランスが戦ったカーナティック戦争で、イギリスが勝利してからは、南インドでフランス勢力は衰退します。
そして、ベンガル地方でイギリスとフランスが戦ったのが、有名な1757年のプラッシーの戦いです。イギリス軍の兵力は約3000。ただし、このうちイギリス兵は950名ほどです。あとの2000名は何か。イギリスが現地で雇った傭兵。インド人の兵士です。対するフランス軍はというと、フランス兵はわずか50名。しかし、フランスは現地の支配者であるベンガル太守と同盟を結んでおり、このベンガル太守軍の兵力約6800。イギリス対フランスの戦争といいながら、戦いの中心となっているのはインド人同士というところが特徴的です。また、イギリス兵とフランス兵の少なさは、意外ですね。私たちは英仏はものすごく強く、何でも思うがままにできたというイメージを持ちがちですが、ヨーロッパからインドまで兵士を派遣するのは、イギリスもフランスも大変な負担だったのです。
話を戦いに戻すと、イギリス側3000、フランス側6800ですから、フランス側が圧倒的に有利です。ところが、この戦いでイギリスが勝利します。その立役者として活躍したのが、イギリス東インド会社のクライブです。説明が遅れましたが、イギリスの活動主体はイギリス政府ではなくて、イギリス東インド会社です。イギリス、イギリスと言っていますが、イギリス政府が指揮しているのではない。実体はイギリス東インド会社ですから、注意してください。で、そのクライブは、ベンガル太守軍の将軍に買収工作をした。太守を裏切り、イギリス側に寝返ったら、戦後、ベンガル太守の地位につけると約束をしたのです。将軍は買収に応じました。戦いが始まると、この将軍、ベンガル太守の命令を無視し、軍を動かさない。結局この裏切りの結果、イギリスが勝利することになったのです。この買収工作で、クライブは、イギリス本国で一躍英雄となりました。
この戦闘が、結果としてインドの運命を変えることになりました。イギリス東インド会社は、この後フランス勢力をインドから一掃しただけではなく、新しいベンガル太守を傀儡(かいらい)としました。1765年には、イギリス東インド会社はベンガル地方の徴税権を獲得しました。貿易会社が、他国の一地方の税金を徴収するのです。もう、貿易会社と言うより、統治機関と言っていいでしょう。事実上、ベンガル地方を支配するようになったということです。ベンガル地方というのは、現在のバングラデシュです。
これ以後、インドはイギリス産業の原料供給地兼製品市場とされていきました。
イギリス東インド会社はインドから木綿を買い付け、イギリス本国に輸出します。折からの産業革命で、発展しつつある綿織物工業の原材料です。そして、イギリスの機械制大工場で生産された綿織物が、今度はインドに輸出されます。インドは世界有数の綿織物生産国でしたが、手工業だったので、イギリスから輸出される大量生産で安価な綿織物に対抗できません。この結果、インドの綿織物工業は大打撃を受けました。「世界に冠たる織物の町」といわれたダッカの人口は、わずかのうちに15万から3万に激減しました。インド総督ベンティングは、1834年にイギリス本国に送った年次報告に「世界経済史上、このような惨状に比すべきものはほとんど見いだせない。職工たちの骨がインドの平原を白色に化している」と書いたほどです。
お金とモノの流れを単純に考えてみると、イギリス東インド会社は徴税権を持ち、インド人から税金をとる。その税金で、インド農民から原綿を買い付けると考えれば、ただで原料を手に入れている、もしくは奪っているのと同じことです。それを加工した製品をインド人に売るということは、つまり、奪った原料で作った製品を、奪った相手に売りつけているわけで、富は一方的にイギリスに流れることになります。イギリス側にとって、これほど儲かる商売はないし、インド側からみれば、最大限搾り取られているわけです。
このあと、イギリスは、インド各地の地方政権を次々に支配下に置いていきます。インド征服のための大きな戦争としては、南インドのマイソール王国とのマイソール戦争(1767~99)、マラータ同盟とのマラータ戦争(1775~1818)、シク教国とのシク戦争(1845~49)があります。
シク戦争の勝利で、イギリスによるインド征服は事実上完了しました。
-------------------------------------
イギリス東インド会社によるインド支配
--------------------------------------
イギリス東インド会社が、インドを支配するようになって、インドは重い負担に苦しむようになりました。
まず、税負担があります。イギリス東インド会社の徴税額をみると(プリントの表を参照しながら)、1765年ベンガル太守時代には、82万ポンド。1770年東インド会社時代になると234万ポンド。1790年には340万ポンドと、増加しつづけています。別の資料によると、東インド会社による地租(土地税)収奪は、1771年から72年にかけて234.2万ポンド。これを指数100とすると、1821年から22年が1372.9万ポンドで、指数589。1856年から57年が1531.8万ポンドで指数654。こちらでも、どんどん税額が増えている。
税を増やすだけでなく、東インド会社は、インド農民に高く売れる商品作物の栽培を強制します。綿布の染料に使う藍や、麻薬アヘンの原料となるケシなどです。小麦など食糧をつくるべき畑で、食糧を作れない。食糧生産量は落ちる。藍やケシをいくら栽培しても、腹の足しにはならない。この結果、飢饉が激増します。
インド大飢饉回数の表があります。
18世紀 大飢饉3回 死者数不明
1800~25 大飢饉5回 死者100万人
1826~50 大飢饉2回 死者40万人
1851~75 大飢饉6回 死者500万人
1876~1900 大飢饉18回 死者1600万人
19世紀に2000万人以上が餓死しているのです。イギリスの支配によって、インドは貧困に追い込まれたのです。
-----------------
インド大反乱
-----------------
イギリス東インド会社は、インドを支配するための軍隊を持ちました。東インド会社軍といいます。全兵力23万8千人。兵力の内訳を詳しく見ると、そのうちイギリス兵、つまりイギリス人の軍人ですが、その人数は3万8000人。残りの20万人がインド人傭兵です。このインド人傭兵のことをシパーヒー(またはセポイ)といいます。シパーヒーは上級カースト出身者が多く採用されたようです。イギリス側は、カースト制度を利用して効率よく支配するために、上級カースト出身者を採用したのでしょう。また、上級カーストの者にとって、たとえ支配者がイギリス人であっても、自分たちが支配者側の一員になることは抵抗感が少なかったのかもしれません。俺たちは偉いのだから、イギリス人が雇うのは当然、イギリス人と同じ支配者階級になるのは当然、と思っていたのかもしれません。
とにかく、この約20万のシパーヒーが、イギリス東インド会社のインド支配の最終手段、暴力装置でした。シパーヒーたちがイギリス東インド会社から離反すれば、イギリスの支配は不可能になります。イギリス東インド会社軍としては、シパーヒーを飼い慣らし、手なずけておかなければならないのですが、1857年シパーヒーの反乱が起こりました。
原因はいろいろあるのですが、そのひとつが、イギリス人のインドの伝統文化に対する無理解です。
たとえば、インドのバラモンなどの上級カーストに、サティという風習がありました。インドでは人が死ぬと、一般に火葬をするのですが、夫婦で夫が先になくなった場合に、火葬をしている炎のなかに、未亡人が飛び込んで焼身自殺をするという慣行があった。これがサティです。夫の死を悲しんで自殺をするのは、貞淑な妻の鏡である、素晴らしい行いであるとして、サティが奨励されていた。
ところが、この風習をイギリス人がみて、びっくりするわけです。自殺を奨励するというのは、とんでもないわけです。しかも、夫が死んで、妻が後を追う、というときに、皆さんは、おじいさん、おばあさんの老夫婦を思い浮かべるかもしれませんが、イギリス人が見た夫婦は全然そんなのじゃなかった。50代60代のお金持ちのバラモン男性が、年をとってから、14歳15歳の花嫁を迎えるということが当時は普通にあった。だから、60歳で死んだ夫を焼く炎のなかに飛び込むのは、まだ子供といってもいい少女たちなのです。これはひどい、と思うよね、普通は。どう考えても、こんな少女が、自ら死にたいと願っているわけがない。早く飛び込んで死なんかい、という親族一同の視線にさらされて、死なざるを得ないように精神的に追い込まれていくというのが、実際のありようだったのでしょう。
そこで、イギリスは、野蛮きわまりないとして、サティ禁止令を出した。ところが、サティはバラモン身分の者には、自分たちの身分にだけ許された美しい慣行です(低位カーストではサティは行われていませんでした)。それを、一方的に野蛮と決めつけられて、イギリスに反発する。
サティの風習を禁止すべきかどうかの判断は今は措きますが、こんな感じでイギリス人はインド人のさまざまな風俗習慣を野蛮と感じ、見下す。インド人からすれば、イギリス人とは価値観は違うかもしれないが、インドは3千年以上の歴史を持つ文明国です。一方的に野蛮人扱いされることに我慢できない。シパーヒーたちも、さまざまな不満をイギリス人に対して持つようになるのです。
そういうなかで、シク戦争が終了して、インド征服が完了すると、シパーヒーへの待遇が悪化しました。さらに、ヒンドゥー教のタブーに係わる命令が出され、シパーヒーの不満が高まりました。
どんな命令かというと、ひとつはシパーヒーに対する海外派兵。もうひとつは、新式銃の使用です。
バラモンなど上級カーストでは、インドの外に出ると身分がけがれると考えられていたので、海外派兵に反発した。
そして、新式銃というのが、反乱の直接的な原因になります。この時代、銃は基本的に日本の戦国時代と同じで、鉄砲の先端から火薬と玉を入れて、銃身底部に押し込める先込め銃でした。東インド会社軍が採用しようとした新式銃、エンフィールド銃というのですが、これも先込め銃なんですが、火薬と弾丸が一緒に筒状の油紙に包まれている。それまでは、弾を込めるときに、火薬は火薬入れから取り出し、玉は玉で別のところから出して、銃に込めていた。エンフィールド銃は、この火薬と玉がセットになっているので、いっぺんに取り出せるわけです。弾薬包みを取り出して、歯で噛みちぎり、包みから火薬を銃に流し込んだあと、油紙がついたままで弾丸を落とし込むのです。で、この油紙の油に牛と豚の脂が使われているという噂が流れた。これがシパーヒーたちの猛反発をよびました。弾丸を込めるときに油紙を噛みちぎるから口に触れる。牛はヒンドゥー教徒にとって神聖な動物で、その脂を口にするということは絶対にできない。身分がけがれてカーストから追放です。また、豚はイスラーム教では不浄の動物とされ、ムスリムのシパーヒーもこれを口にすることを拒否しました。
イギリス人の軍幹部は、牛と豚の脂は使っていないと、否定しましたが、いったん広がった噂は消すことができなかった。それまでの、イギリス側の姿勢に対する反感も手伝って、各地の部隊で不穏な雰囲気が高まっていきました。
シパーヒーへの家族からの手紙が急増したのを不審に思ったイギリス人の上官が、手紙の中身をチェックすると、「新式銃の火薬包みの使用を拒否せよ、拒否しなければカーストから追放する」と書かれてあったという。また、ある基地で、シパーヒーが民間の作業員に水を分け与えようとしたら、その作業員が「あなたはまもなく自分のカーストを失うから」と言って、水を拒否したと伝えられています。ヒンドゥー教のタブーをおかして、所属カーストから追放されると、アウトカースト、不可触民にされてしまう。そんな最低の身分の者から、水をもらえない、ということですね。新式銃の導入に伴う噂が、一般にも広がり、関心が持たれていたことがうかがわれます。
あと、これは、どういう意味があるのか今もわからないのですが、反乱の直前、インドの村から村へチャパティーがリレーされていったのを、イギリス人が目撃して報告しています。ある村から別の村へチャパティーが届けられる。すると、その村では、新たに数枚のチャパティーを焼いて、さらに別の村に届けていったという。チャパティーは小麦粉を焼いたパンのような食べ物です。このリレーにどんな意味があるのか、目撃したイギリス人には理解できなかったが、異様なものを感じて、記録したのでしょう。あとから考えると、なにか反乱の合図だったのかもしれない、ということです。同じように、東インド会社軍の部隊から部隊へと蓮の花がリレーされていて、これも何かの合図だった可能性があります。
不穏な空気が広がるなかで、1857年5月、シパーヒーが反乱を起こしました。きっかけは、メーラトという町にあった部隊での事件です。この部隊で、新式銃を使った演習が行われたのですが、イギリス人上官の命令を拒否して、90名の兵士中85名が弾薬筒に触ろうとせず演習が不能になった。軍隊にとって命令拒否は重い罪です。軍法会議の結果、問題の兵士たちは、見せしめのために、他の兵士たちが集合させられている前で、軍服をはぎ取られ足かせをはめられて牢に入れられました。残りのシパーヒーたちは、これに反発し、翌日牢に入れられた仲間を救うために蜂起し、反乱はメーラト以外の各地の基地に広がりました。
各地のシパーヒーが蜂起すると、東インド会社軍と関係のない民衆もたちあがり、インド全体が反乱状態となりました。これをインド大反乱といいます。以前は、シパーヒーの反乱、もしくはセポイの乱とも呼ばれていましたが、反乱に参加したのはシパーヒーだけではないので、現在はインド大反乱と呼んでいます。
反乱にはイギリスに滅ぼされた地方政権、インドでは藩王国と呼びますが、この藩王国の旧支配者層など、さまざまな勢力が加わりました。全インドの三分の二が反乱に参加したといいます。ただし、各地の反乱軍は、互いに連携するわけでもなく、全体の指導部もありませんでした。デリーを占領した反乱軍は、引退していたムガル帝国皇帝を、反乱軍のトップとして擁立しました。かれはイギリス東インド会社から年金を受け取り、名目だけのムガル皇帝として存在していたのです。ただし、彼はただの飾り物で、何の指導力もありませんでした。
反乱勢力は、統一した作戦や、反乱成功後の共通目標もなかったのですが、不意をつかれたイギリス側は、一時、インドから撤退しました。しかし、やがて態勢を整えて反撃を開始しました。反乱に参加していなかったシク教徒によるシク兵、イラン兵、ネパール人のグルカ兵を動員し、9月にはデリーを反乱軍から奪還、以後は各地の反乱勢力を各個撃破していきました。1859年までには、完全に反乱を鎮圧しました。
イギリスは、反乱を起こしたものたちに徹底的な報復を行いました。反乱側についた町や村の住民を虐殺したり、反乱軍の捕虜を大砲の砲身にくくりつけて吹き飛ばしたり、牛や豚の血を無理矢理飲ませてから殺すなど、見せしめ的な処刑をおこなっています。プリントの挿絵の左側に描かれているのが大砲にくくりつけられている捕虜です。右側で馬に乗っているのがイギリス人の指揮官ですね。
結局、反乱は失敗したわけですが、この反乱で活躍したインド人の武将たちは、現在も民族のヒーローとして人気があります。一人だけ紹介しておくと、インドのジャンヌ=ダルクと呼ばれているラクシュミー=バーイーという女性。彼女はジャーンシー藩王国という国の王妃でしたが、イギリスに国を奪われ、反乱が起きると女性ながらも兵士を率いてイギリス軍と戦いました。養子にした幼い子供を背負って、馬に乗っている彼女の肖像画があります。最後には戦死するのですが、ゲリラ戦でねばり強く戦いつづけた女性でした。
インドの大部分が参加した反乱だったのに、しかも、東インド会社軍の傭兵部隊シパーヒーまでが反乱側にたったのに、なぜ、反乱は敗北したのでしょうか。
最大の理由は、反乱側内部の不統一です。はじめから反乱軍は烏合の衆で指導部もありませんでしたが、加えて、地域間の対立、カースト間の対立によって、インド人どうしがひとつにまとまれませんでした。イギリス側は、このようなインド人どうしの対立を巧妙に利用していったのです。同じインド人でありながら、シク教徒がイギリス側についているのがそのよい例ですね。
--------------
その後のインド
--------------
反乱をほぼ鎮圧した1858年、イギリス本国政府は、東インド会社を解散させ、インド全土を直接支配することにします。名目だけつづいていたムガル帝国も完全に滅亡させられます。
1877年には、インドにインド帝国を成立させました。ちょっとわかりにくいですが、イギリス政府がインドに新しい国をつくったということです。その国の名前がインド帝国という。そして、インド帝国の皇帝に即位したのがイギリス国王のヴィクトリア。だから、この時点から、ヴィクトリアはイギリス国王兼インド皇帝ということですね。ただし、ヴィクトリア女王はインドに行ったりしません。ずっと、イギリスです。イギリスのエリート貴族たちが、インド帝国の高級行政官としてインドに赴任して、インド人の役人を指揮しながらインドを支配するわけです。インド帝国は、イギリスの完全な植民地です。
イギリスのインド支配は巧妙で、インドが団結してイギリスに抵抗しないよう分割統治をおこないました。インド帝国は、イギリスの直轄領と、550以上の藩王国から構成されていて、藩王国は外交権はないし、イギリスの監視付きではありますが、マハラジャとよばれる藩王の自治が認められていた。マハラジャからすれば、無理してイギリスに抵抗せず、このままマハラジャの地位を認めてもらった方が安泰です。旧勢力を温存し、旧支配者層の抵抗を薄めながら支配したのです。このインド帝国は第二次大戦後の1947年までつづきました。
イギリス東インド会社によるインド征服
--------------------------------------
ちょうどムガル帝国が衰退していくのと入れ替わるようにして、イギリスがインドに登場します。イギリスは17世紀以降、マドラス、ボンベイ、カルカッタに商館を建設し、ここを拠点として貿易を本格化させます。商館といっていますが、実際には要塞のようなもので、商売をするだけでなく、地元の権力者との交渉や戦いによって土地も獲得していきました。
フランスも、17世紀後半には、同様に商館を建設しました。フランスが拠点にしたのはシャンデルナゴルとポンディシェリで、シャンデルナゴルはベンガル地方にあってカルカッタに近い。ポンディシェリも南インドでマドラスに比較的近い。当然、イギリスとフランスは競合することになります。
一時は、フランスがイギリスを圧倒した時期もあったのですが、18世紀の半ばに南インドでイギリスとフランスが戦ったカーナティック戦争で、イギリスが勝利してからは、南インドでフランス勢力は衰退します。
そして、ベンガル地方でイギリスとフランスが戦ったのが、有名な1757年のプラッシーの戦いです。イギリス軍の兵力は約3000。ただし、このうちイギリス兵は950名ほどです。あとの2000名は何か。イギリスが現地で雇った傭兵。インド人の兵士です。対するフランス軍はというと、フランス兵はわずか50名。しかし、フランスは現地の支配者であるベンガル太守と同盟を結んでおり、このベンガル太守軍の兵力約6800。イギリス対フランスの戦争といいながら、戦いの中心となっているのはインド人同士というところが特徴的です。また、イギリス兵とフランス兵の少なさは、意外ですね。私たちは英仏はものすごく強く、何でも思うがままにできたというイメージを持ちがちですが、ヨーロッパからインドまで兵士を派遣するのは、イギリスもフランスも大変な負担だったのです。
話を戦いに戻すと、イギリス側3000、フランス側6800ですから、フランス側が圧倒的に有利です。ところが、この戦いでイギリスが勝利します。その立役者として活躍したのが、イギリス東インド会社のクライブです。説明が遅れましたが、イギリスの活動主体はイギリス政府ではなくて、イギリス東インド会社です。イギリス、イギリスと言っていますが、イギリス政府が指揮しているのではない。実体はイギリス東インド会社ですから、注意してください。で、そのクライブは、ベンガル太守軍の将軍に買収工作をした。太守を裏切り、イギリス側に寝返ったら、戦後、ベンガル太守の地位につけると約束をしたのです。将軍は買収に応じました。戦いが始まると、この将軍、ベンガル太守の命令を無視し、軍を動かさない。結局この裏切りの結果、イギリスが勝利することになったのです。この買収工作で、クライブは、イギリス本国で一躍英雄となりました。
この戦闘が、結果としてインドの運命を変えることになりました。イギリス東インド会社は、この後フランス勢力をインドから一掃しただけではなく、新しいベンガル太守を傀儡(かいらい)としました。1765年には、イギリス東インド会社はベンガル地方の徴税権を獲得しました。貿易会社が、他国の一地方の税金を徴収するのです。もう、貿易会社と言うより、統治機関と言っていいでしょう。事実上、ベンガル地方を支配するようになったということです。ベンガル地方というのは、現在のバングラデシュです。
これ以後、インドはイギリス産業の原料供給地兼製品市場とされていきました。
イギリス東インド会社はインドから木綿を買い付け、イギリス本国に輸出します。折からの産業革命で、発展しつつある綿織物工業の原材料です。そして、イギリスの機械制大工場で生産された綿織物が、今度はインドに輸出されます。インドは世界有数の綿織物生産国でしたが、手工業だったので、イギリスから輸出される大量生産で安価な綿織物に対抗できません。この結果、インドの綿織物工業は大打撃を受けました。「世界に冠たる織物の町」といわれたダッカの人口は、わずかのうちに15万から3万に激減しました。インド総督ベンティングは、1834年にイギリス本国に送った年次報告に「世界経済史上、このような惨状に比すべきものはほとんど見いだせない。職工たちの骨がインドの平原を白色に化している」と書いたほどです。
お金とモノの流れを単純に考えてみると、イギリス東インド会社は徴税権を持ち、インド人から税金をとる。その税金で、インド農民から原綿を買い付けると考えれば、ただで原料を手に入れている、もしくは奪っているのと同じことです。それを加工した製品をインド人に売るということは、つまり、奪った原料で作った製品を、奪った相手に売りつけているわけで、富は一方的にイギリスに流れることになります。イギリス側にとって、これほど儲かる商売はないし、インド側からみれば、最大限搾り取られているわけです。
このあと、イギリスは、インド各地の地方政権を次々に支配下に置いていきます。インド征服のための大きな戦争としては、南インドのマイソール王国とのマイソール戦争(1767~99)、マラータ同盟とのマラータ戦争(1775~1818)、シク教国とのシク戦争(1845~49)があります。
シク戦争の勝利で、イギリスによるインド征服は事実上完了しました。
-------------------------------------
イギリス東インド会社によるインド支配
--------------------------------------
イギリス東インド会社が、インドを支配するようになって、インドは重い負担に苦しむようになりました。
まず、税負担があります。イギリス東インド会社の徴税額をみると(プリントの表を参照しながら)、1765年ベンガル太守時代には、82万ポンド。1770年東インド会社時代になると234万ポンド。1790年には340万ポンドと、増加しつづけています。別の資料によると、東インド会社による地租(土地税)収奪は、1771年から72年にかけて234.2万ポンド。これを指数100とすると、1821年から22年が1372.9万ポンドで、指数589。1856年から57年が1531.8万ポンドで指数654。こちらでも、どんどん税額が増えている。
税を増やすだけでなく、東インド会社は、インド農民に高く売れる商品作物の栽培を強制します。綿布の染料に使う藍や、麻薬アヘンの原料となるケシなどです。小麦など食糧をつくるべき畑で、食糧を作れない。食糧生産量は落ちる。藍やケシをいくら栽培しても、腹の足しにはならない。この結果、飢饉が激増します。
インド大飢饉回数の表があります。
18世紀 大飢饉3回 死者数不明
1800~25 大飢饉5回 死者100万人
1826~50 大飢饉2回 死者40万人
1851~75 大飢饉6回 死者500万人
1876~1900 大飢饉18回 死者1600万人
19世紀に2000万人以上が餓死しているのです。イギリスの支配によって、インドは貧困に追い込まれたのです。
-----------------
インド大反乱
-----------------
イギリス東インド会社は、インドを支配するための軍隊を持ちました。東インド会社軍といいます。全兵力23万8千人。兵力の内訳を詳しく見ると、そのうちイギリス兵、つまりイギリス人の軍人ですが、その人数は3万8000人。残りの20万人がインド人傭兵です。このインド人傭兵のことをシパーヒー(またはセポイ)といいます。シパーヒーは上級カースト出身者が多く採用されたようです。イギリス側は、カースト制度を利用して効率よく支配するために、上級カースト出身者を採用したのでしょう。また、上級カーストの者にとって、たとえ支配者がイギリス人であっても、自分たちが支配者側の一員になることは抵抗感が少なかったのかもしれません。俺たちは偉いのだから、イギリス人が雇うのは当然、イギリス人と同じ支配者階級になるのは当然、と思っていたのかもしれません。
とにかく、この約20万のシパーヒーが、イギリス東インド会社のインド支配の最終手段、暴力装置でした。シパーヒーたちがイギリス東インド会社から離反すれば、イギリスの支配は不可能になります。イギリス東インド会社軍としては、シパーヒーを飼い慣らし、手なずけておかなければならないのですが、1857年シパーヒーの反乱が起こりました。
原因はいろいろあるのですが、そのひとつが、イギリス人のインドの伝統文化に対する無理解です。
たとえば、インドのバラモンなどの上級カーストに、サティという風習がありました。インドでは人が死ぬと、一般に火葬をするのですが、夫婦で夫が先になくなった場合に、火葬をしている炎のなかに、未亡人が飛び込んで焼身自殺をするという慣行があった。これがサティです。夫の死を悲しんで自殺をするのは、貞淑な妻の鏡である、素晴らしい行いであるとして、サティが奨励されていた。
ところが、この風習をイギリス人がみて、びっくりするわけです。自殺を奨励するというのは、とんでもないわけです。しかも、夫が死んで、妻が後を追う、というときに、皆さんは、おじいさん、おばあさんの老夫婦を思い浮かべるかもしれませんが、イギリス人が見た夫婦は全然そんなのじゃなかった。50代60代のお金持ちのバラモン男性が、年をとってから、14歳15歳の花嫁を迎えるということが当時は普通にあった。だから、60歳で死んだ夫を焼く炎のなかに飛び込むのは、まだ子供といってもいい少女たちなのです。これはひどい、と思うよね、普通は。どう考えても、こんな少女が、自ら死にたいと願っているわけがない。早く飛び込んで死なんかい、という親族一同の視線にさらされて、死なざるを得ないように精神的に追い込まれていくというのが、実際のありようだったのでしょう。
そこで、イギリスは、野蛮きわまりないとして、サティ禁止令を出した。ところが、サティはバラモン身分の者には、自分たちの身分にだけ許された美しい慣行です(低位カーストではサティは行われていませんでした)。それを、一方的に野蛮と決めつけられて、イギリスに反発する。
サティの風習を禁止すべきかどうかの判断は今は措きますが、こんな感じでイギリス人はインド人のさまざまな風俗習慣を野蛮と感じ、見下す。インド人からすれば、イギリス人とは価値観は違うかもしれないが、インドは3千年以上の歴史を持つ文明国です。一方的に野蛮人扱いされることに我慢できない。シパーヒーたちも、さまざまな不満をイギリス人に対して持つようになるのです。
そういうなかで、シク戦争が終了して、インド征服が完了すると、シパーヒーへの待遇が悪化しました。さらに、ヒンドゥー教のタブーに係わる命令が出され、シパーヒーの不満が高まりました。
どんな命令かというと、ひとつはシパーヒーに対する海外派兵。もうひとつは、新式銃の使用です。
バラモンなど上級カーストでは、インドの外に出ると身分がけがれると考えられていたので、海外派兵に反発した。
そして、新式銃というのが、反乱の直接的な原因になります。この時代、銃は基本的に日本の戦国時代と同じで、鉄砲の先端から火薬と玉を入れて、銃身底部に押し込める先込め銃でした。東インド会社軍が採用しようとした新式銃、エンフィールド銃というのですが、これも先込め銃なんですが、火薬と弾丸が一緒に筒状の油紙に包まれている。それまでは、弾を込めるときに、火薬は火薬入れから取り出し、玉は玉で別のところから出して、銃に込めていた。エンフィールド銃は、この火薬と玉がセットになっているので、いっぺんに取り出せるわけです。弾薬包みを取り出して、歯で噛みちぎり、包みから火薬を銃に流し込んだあと、油紙がついたままで弾丸を落とし込むのです。で、この油紙の油に牛と豚の脂が使われているという噂が流れた。これがシパーヒーたちの猛反発をよびました。弾丸を込めるときに油紙を噛みちぎるから口に触れる。牛はヒンドゥー教徒にとって神聖な動物で、その脂を口にするということは絶対にできない。身分がけがれてカーストから追放です。また、豚はイスラーム教では不浄の動物とされ、ムスリムのシパーヒーもこれを口にすることを拒否しました。
イギリス人の軍幹部は、牛と豚の脂は使っていないと、否定しましたが、いったん広がった噂は消すことができなかった。それまでの、イギリス側の姿勢に対する反感も手伝って、各地の部隊で不穏な雰囲気が高まっていきました。
シパーヒーへの家族からの手紙が急増したのを不審に思ったイギリス人の上官が、手紙の中身をチェックすると、「新式銃の火薬包みの使用を拒否せよ、拒否しなければカーストから追放する」と書かれてあったという。また、ある基地で、シパーヒーが民間の作業員に水を分け与えようとしたら、その作業員が「あなたはまもなく自分のカーストを失うから」と言って、水を拒否したと伝えられています。ヒンドゥー教のタブーをおかして、所属カーストから追放されると、アウトカースト、不可触民にされてしまう。そんな最低の身分の者から、水をもらえない、ということですね。新式銃の導入に伴う噂が、一般にも広がり、関心が持たれていたことがうかがわれます。
あと、これは、どういう意味があるのか今もわからないのですが、反乱の直前、インドの村から村へチャパティーがリレーされていったのを、イギリス人が目撃して報告しています。ある村から別の村へチャパティーが届けられる。すると、その村では、新たに数枚のチャパティーを焼いて、さらに別の村に届けていったという。チャパティーは小麦粉を焼いたパンのような食べ物です。このリレーにどんな意味があるのか、目撃したイギリス人には理解できなかったが、異様なものを感じて、記録したのでしょう。あとから考えると、なにか反乱の合図だったのかもしれない、ということです。同じように、東インド会社軍の部隊から部隊へと蓮の花がリレーされていて、これも何かの合図だった可能性があります。
不穏な空気が広がるなかで、1857年5月、シパーヒーが反乱を起こしました。きっかけは、メーラトという町にあった部隊での事件です。この部隊で、新式銃を使った演習が行われたのですが、イギリス人上官の命令を拒否して、90名の兵士中85名が弾薬筒に触ろうとせず演習が不能になった。軍隊にとって命令拒否は重い罪です。軍法会議の結果、問題の兵士たちは、見せしめのために、他の兵士たちが集合させられている前で、軍服をはぎ取られ足かせをはめられて牢に入れられました。残りのシパーヒーたちは、これに反発し、翌日牢に入れられた仲間を救うために蜂起し、反乱はメーラト以外の各地の基地に広がりました。
各地のシパーヒーが蜂起すると、東インド会社軍と関係のない民衆もたちあがり、インド全体が反乱状態となりました。これをインド大反乱といいます。以前は、シパーヒーの反乱、もしくはセポイの乱とも呼ばれていましたが、反乱に参加したのはシパーヒーだけではないので、現在はインド大反乱と呼んでいます。
反乱にはイギリスに滅ぼされた地方政権、インドでは藩王国と呼びますが、この藩王国の旧支配者層など、さまざまな勢力が加わりました。全インドの三分の二が反乱に参加したといいます。ただし、各地の反乱軍は、互いに連携するわけでもなく、全体の指導部もありませんでした。デリーを占領した反乱軍は、引退していたムガル帝国皇帝を、反乱軍のトップとして擁立しました。かれはイギリス東インド会社から年金を受け取り、名目だけのムガル皇帝として存在していたのです。ただし、彼はただの飾り物で、何の指導力もありませんでした。
反乱勢力は、統一した作戦や、反乱成功後の共通目標もなかったのですが、不意をつかれたイギリス側は、一時、インドから撤退しました。しかし、やがて態勢を整えて反撃を開始しました。反乱に参加していなかったシク教徒によるシク兵、イラン兵、ネパール人のグルカ兵を動員し、9月にはデリーを反乱軍から奪還、以後は各地の反乱勢力を各個撃破していきました。1859年までには、完全に反乱を鎮圧しました。
イギリスは、反乱を起こしたものたちに徹底的な報復を行いました。反乱側についた町や村の住民を虐殺したり、反乱軍の捕虜を大砲の砲身にくくりつけて吹き飛ばしたり、牛や豚の血を無理矢理飲ませてから殺すなど、見せしめ的な処刑をおこなっています。プリントの挿絵の左側に描かれているのが大砲にくくりつけられている捕虜です。右側で馬に乗っているのがイギリス人の指揮官ですね。
結局、反乱は失敗したわけですが、この反乱で活躍したインド人の武将たちは、現在も民族のヒーローとして人気があります。一人だけ紹介しておくと、インドのジャンヌ=ダルクと呼ばれているラクシュミー=バーイーという女性。彼女はジャーンシー藩王国という国の王妃でしたが、イギリスに国を奪われ、反乱が起きると女性ながらも兵士を率いてイギリス軍と戦いました。養子にした幼い子供を背負って、馬に乗っている彼女の肖像画があります。最後には戦死するのですが、ゲリラ戦でねばり強く戦いつづけた女性でした。
インドの大部分が参加した反乱だったのに、しかも、東インド会社軍の傭兵部隊シパーヒーまでが反乱側にたったのに、なぜ、反乱は敗北したのでしょうか。
最大の理由は、反乱側内部の不統一です。はじめから反乱軍は烏合の衆で指導部もありませんでしたが、加えて、地域間の対立、カースト間の対立によって、インド人どうしがひとつにまとまれませんでした。イギリス側は、このようなインド人どうしの対立を巧妙に利用していったのです。同じインド人でありながら、シク教徒がイギリス側についているのがそのよい例ですね。
--------------
その後のインド
--------------
反乱をほぼ鎮圧した1858年、イギリス本国政府は、東インド会社を解散させ、インド全土を直接支配することにします。名目だけつづいていたムガル帝国も完全に滅亡させられます。
1877年には、インドにインド帝国を成立させました。ちょっとわかりにくいですが、イギリス政府がインドに新しい国をつくったということです。その国の名前がインド帝国という。そして、インド帝国の皇帝に即位したのがイギリス国王のヴィクトリア。だから、この時点から、ヴィクトリアはイギリス国王兼インド皇帝ということですね。ただし、ヴィクトリア女王はインドに行ったりしません。ずっと、イギリスです。イギリスのエリート貴族たちが、インド帝国の高級行政官としてインドに赴任して、インド人の役人を指揮しながらインドを支配するわけです。インド帝国は、イギリスの完全な植民地です。
イギリスのインド支配は巧妙で、インドが団結してイギリスに抵抗しないよう分割統治をおこないました。インド帝国は、イギリスの直轄領と、550以上の藩王国から構成されていて、藩王国は外交権はないし、イギリスの監視付きではありますが、マハラジャとよばれる藩王の自治が認められていた。マハラジャからすれば、無理してイギリスに抵抗せず、このままマハラジャの地位を認めてもらった方が安泰です。旧勢力を温存し、旧支配者層の抵抗を薄めながら支配したのです。このインド帝国は第二次大戦後の1947年までつづきました。
| 参考図書紹介・・・・もう少し詳しく知りたいときは 書名をクリックすると、インターネット書店「アマゾン」のページに飛んで、本のデータ、書評などを見ることができます。購入も可能です。 | ||
| インド大反乱一八五七年 (中公新書 606) | (第100回関連) 長崎暢子著。中公新書。講義で紹介したチャパティのリレーの話は、この本で読みました。インド大反乱に関する最も手頃な入門書だったのに、今は、絶版になっているようで、ビックリしました。たいていの図書館にはあると思うので、インド大反乱を詳しく知りたい人には一読を勧めます。 | |
 第100回 イギリスのインド支配 おわり
第100回 イギリスのインド支配 おわり