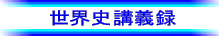第47回 ティムール帝国・イスラム文化
----------------------------
モンゴル帝国とティムール帝国
----------------------------
カリフの宗教的権威で何とかつづいていたアッバース朝が1258年にフラグの率いるモンゴル軍に滅ぼされたことは前回話しました。モンゴル軍はアフリカ大陸までは、行けなかったけれども、ほぼアジア全域を支配下に置いた。
フラグはイラン・イラク方面にイル=ハン国(1260~1353)を建てました。モンゴル人はこの地域を支配するために土着勢力と協力せざるを得ない。13世紀末に即位した第七代、ガザン=ハンの時にイスラムに改宗しています。
モンゴルの時にも話しましたが、この王の時の大臣が有名なラシード=アッディーン。セルジューク朝の名大臣ニザーム=アルムルクを手本にして、イラン人になじみやすいようにモンゴルの行政を改めたのと、『集史』というモンゴル史を軸にした歴史の本を書いたので有名。

中央アジアに作られたチャガタイ=ハン国も14世紀にはイスラム化していきました。
イル=ハン国もチャガタイ=ハン国も14世紀には衰退して在地勢力が各地で自立しはじめます。
再びこの地域を統一し、イラクから中央アジアにまたがる大帝国となったのがティムール帝国(1370~1500)です。
建国者はティムール(?~1405)。この人はチャガタイ=ハン国の武将でしたが、やがて自立して、サマルカンドを都に大帝国を建設した。日本ではあまり馴染みがないけれど中央アジアのトルコ民族の間では今でも人気のある英雄の一人です。
簡単に言えばチンギス=ハーンの再来みたいな男で、残忍なことも平気でやりながら勢力を拡大した。ただ、チンギス=ハーンよりも陽気で明るいイメージで伝えられています。チンギス=ハーンが信長なら、ティムールは秀吉ですね。
瞼が異様に分厚く垂れ下がっていて、つり上げないと前が見えなかったとか、片足が萎えていて歩行が困難だったとか、どこまで本当かはわかりませんが、かれの「異人」ぶりも伝えられています。
ティムールはチンギス=ハーンの血を引いていると自称しています。多少はチンギス=ハーンの血が流れていたかもしれない。だから、ティムールはバラバラに分解してしまったモンゴル帝国を復活させるのだと考えているのですね。積極的な領土拡大の原動力はここにある。
ただし、ティムールの民族をあえて言えば、モンゴル人というよりはトルコ人です。この時代のモンゴル人とトルコ人の違いというのも曖昧なものなのですが、中央アジアに進出したモンゴル人たちは混血によって事実上はトルコ民族化していると考えておいてください。
ティムールはイル=ハン国とチャガタイ=ハン国の領域をほぼ統一したあと、小アジアに進みます。ちょうど、ここにはオスマン朝というトルコ系のイスラムの王朝が力を伸ばしつつありました。このオスマン朝とティムール朝が激突したのがアンカラの戦い(1402)。ティムールが勝って、オスマン朝は大打撃を受け一時は滅亡寸前にまでなります。
ただし、オスマン朝はこのあと復活してやがて古代ローマ帝国にも劣らないような大帝国を作り上げて、最終的には20世紀まで存続する王朝になります。覚えておいてください。
アンカラの戦いはイスラム東西両雄の決戦といったところです。
このあとティムールは軍を東方に向けます。実はこの間に中国では元が滅んで明という漢民族の王朝が生まれています。
ティムールはモンゴル帝国の復活を目指していますから、中国遠征、明の討伐を計画した。アンカラの戦いの2年後、1404年1月、20万の大軍を率いてサマルカンドを出発した。「チムールは…武器、兵糧をはこぶために騎兵一人について、それぞれ10人ずつの輸卒をつけさせた。穀物数千荷は軍用車ではこばれたが、これは道すがら種子をまいて帰路の兵糧に供するためであった。なお、さらに7年間をささえるに足る乾草飼料を用意し、そのほか各人が乳牛二頭、乳羊10頭ずつをたずさえて、途中の食糧の欠乏にそなえることにした。」(中央公論社、『世界の歴史9』)というから、すごい作戦です。
これが最後まで実行されていたら、中国の歴史はまったく変わったものになったかもしれないのですが、この遠征は途中で中止になった。ティムール自身が死んでしまったのです。最後までスケールの大きな英雄児でした。
ティムール帝国はティムールの死後徐々に衰えて、やがていくつかの地方政権に分裂していきました。
--------------------
イスラムの学問・文化
--------------------
イスラム世界では、地域や民族を越えて同一の学問文化が広がります。
イスラムでは学問を「外来の学問」と「固有の学問」に分けています。
「外来の学問」はイスラム教と直接関係のない他民族の学問のことをいいます。具体的には、ヘレニズム文化、ペルシア文化、インドの学問などです。イスラム世界はこれをアラビア語に翻訳して、独自に発展させていきます。
特にインドから影響を受けた数学はわれわれにもおなじみですね。数学で使っている数字、これはアラビア数字というのですよ。インドからゼロという概念を導入したのは数学の発展に計り知れない功績です。
漢字でもローマ字でもゼロという数字はない。たとえば230というのを漢字で書くと二百三十というのが、伝統的な書法です。百が二つと十が三つあるという発想ですね。ローマ数字も同じ発想で、一の位がどれだけあるかについては触れない。一度やってみたらわかりますが、漢数字だけで計算するのは、すごく困難です。アラビア数字のありがたみがわかります。
医学、哲学も外来の学問として発展します。特に医学は同時代のヨーロッパと比べて格段に進んでいた。というか、ヨーロッパの水準が低すぎるのですが。
代表的な学者がイブン=シーナー(980~1037)。この人が書いた医学書が『医学典範』。イスラム世界最高の医学書で、ヨーロッパでも17世紀までは医科大学の教科書に採用されていたといいます。また、アリストテレス哲学者としても抜きんでていて、なにやら難しい存在論について考えていた。
イブン=ルシュド(1126~98)。この人も医学の本を書き、また、アリストテレス哲学を再現しようとした。ほとんど全てのアリストテレスの本に注釈をつけたので有名。かれの学問はヨーロッパ中世の学問に大きな影響を与えた。
「固有の学問」というのは、イスラム法学です。イスラム世界では、社会生活の全てがコーランを基礎にして組み立てらているけれど、現実の社会のいろいろな出来事をコーラン一冊では判断できないわけです。だから、コーランをどう現実社会に当てはめるかという理論が必要になる。
そういう理論をイスラム法学という。これを教える学校をマドラサ、イスラム法学を修めた知識人のことをウラマーといい、現在でもウラマーはイスラム世界では社会の指導者、地域の相談役みたいな位置にあります。イスラム世界で一見お坊さんみたいに見える人がウラマーです。スンナ派、シーア派それぞれに法学理論が発展していきました。
固有の学問として教科書に出てくるのがイブン=ハルドゥーン(1332~1406)の『世界史序説』。文明の進んだ都市と、遅れた砂漠のような田舎との緊張関係から歴史の理論を考えた本です。
もう一つがイブン=バトゥータ(1304~68?)の『三大陸周遊記』。モロッコ生まれのこの人は、巡礼でメッカに行ったついでにインドからスマトラ、中国の北京まで旅行をする。ちょうどモンゴル帝国の時代なのですね。帰ってから今度はイベリア半島に渡り、その次はサハラ砂漠を越えてニジェール川を探検している。その旅行記です。
何年も旅をして収入はどうなっているのかと思うと、かれは法学者、ウラマーなのですね。で、旅行先で先生として迎えられて教えている。地方の君主の招待を受けたりしながら旅をする。実に気軽に成りゆきにまかせてどこでも行ってしまう。面白いことにイブン=バトゥータがアジアからエジプトに帰って来たときに、北京で知り合った人の兄弟と偶然出会っている。これは、イブン=バトゥータだけでなく、イスラム教の人々が実に活発に移動していることの一例ですね。
イスラム教には神秘主義というものがある。11世紀頃から流行しだした。
正統的なイスラムでは満足できない人たちの間から生まれてきたものです。ムハンマドが最後の預言者とすれば、二度と神が人間に話しかけてくれることはないわけですね。残された人類に出来ることは法学者のようにコーランを解釈することだけです。「これではつまらん!神を実感したい」という修行者が現れてくる。こういう修行者をスーフィーといいます。スーフィーはいろいろな難行苦行をして自分の内面に神を感じようとするのです。資料集にはトルコの「踊る教団」の写真がある。この人たちはこうしてクルクル回転するのが修行。目がまわってクラクラするその時に神を感じるんでしょうね。ほかにも色々な教団があるそうです。
イスラム教がアラブ人以外の民族に広まっていったのにはスーフィー教団の活動が大きかったといわれています。修行する姿というのは共感を呼びやすいのですね。
この神秘主義を理論化したひとがガザーリー(1058~1111)です。
セルジューク朝の宰相ニザーム=アルムルクに認められ、スンナ派の最高の学者としてバグダードのニザーミア学院で教授をしていたのですが、37歳の時に教授の地位も家族も友人も財産もすべてを捨てて修行者として放浪の旅に出た。理論ではなく、自分自身の内面に神を感じたいと思い詰めたらしいです。
文学では、『アラビアン・ナイト』。『千夜一夜物語』という名前でも有名ですね。16世紀はじめ頃に現在の形にまとまった。この中に「アリババと40人の盗賊」とか「シンドバットの冒険」とかいろいろな話が入っています。イスラム商人たちが活躍した地域の話が取り込まれているので中国やインドの話なども出てきます。
子供向けにアレンジされたシンドバットやアラジンと魔法のランプの話などは、知っている人もいると思うけれど、子供向けに直していないのを読んだことある人いますか。
すごいよ。この『アラビアン・ナイト』は、まるでポルノです。私は高校時代に何気なく岩波文庫で読んでびっくりしました。滅茶苦茶スケベな物語なんです。教室で細かく紹介することは出来ませんが、とにかくどの話にも男と女が出てきて必ずそういうシーンがある。うんざりするくらいです。今はどうか知りませんが、10年くらい前はエジプトでは発行禁止でした。昔、外国で『アラビアン・ナイト』を映画化したことがあって私も当然勉強のために見に行きました。そうしたら、案の定、映倫に厳しくチェックされてボカシだらけの画面でした。
映画はいろいろな話がバラバラのオムニバス形式でしたが、『アラビアン・ナイト』全体の話はこんな形です。
最初にイスラムの王様が出てきます。この王様、妃を愛しているのですが、弟に妃が浮気をしていることを教えられます。本当かどうか確かめるために、王様、ある日妃に外出を告げて、こっそり帰ってきて、妃の振る舞いを見張っていた。そうしたら、妃は男奴隷や女奴隷を集めて乱交に及ぶんだ。王様、カッとなって妃も奴隷もみんな殺してしまった。
以後、王様は女性不信に陥る。あんなに愛していた妃が不貞をはたらいた、というわけですべての女性に復讐をはかる。どうするかというと、毎晩自分の国の乙女を一人ずつ宮殿によんで、一夜の供をさせたあと殺していくのです。女の子を宮殿に連れてくるのは大臣の役目なんですが、王様が毎晩女の子を殺してしまうので、国にはもう乙女がいなくなってしまった。最後に残ったのは自分の娘なんですが、仕方がない。とうとう、自分の娘を王のもとに届けることになった。この娘の名が、シェーラザードといいます。
王はいつのものように彼女と寝たあと殺そうとするのですが、その時シェーラザードが「王様、私面白いお話をしましょう。」と話をはじめる。彼女も殺されたくありませんから必死です。王もどうせ暇ですから、殺すのは後回しにして話をさせてみるとこれが面白い。熱中して聞いているうちに夜明けが来る。そうするとシェーラザードは話をうんと盛り上げておいて「このつづきは、次の夜にしましょ。」と言うんだね。王様、話のつづきを聞きたいために、殺すのを延期します。
こんなふうにして、シェーラザードは毎晩毎晩死なないために話を続け、王は、話を聞きたいために殺すのを先延ばしにします。結局シェーラザードは1000夜、話をつづけて、話が終わったときには王様は心を入れ替えて、女性に復讐するのをやめましたとさ、という結末です。
このシェーラザードの話の中にシンドバッドやアラジンやアリババが出てくるのです。
話の舞台はアッバース朝のカリフ、ハールーン=アッラシ-ド時代のバグダードが多いです。この時代がイスラムの栄光の時代という認識があるのでしょう。
話の中でランプの魔人とか指輪の魔人とか出てきて、願い事をかなえてくれたりするでしょ。欲しいものは何でも手に入る。イスラム世界の中心、世界中から商人たちが運び込んだ商品がある。そういうバグダードを象徴しているような気もしますね。
それから詩です。ウマル=ハイヤーム(1048~1131)だけ覚えておけばよいです。作品名は『ルバイヤート』。この人はセルジューク朝に仕えていて、詩だけではなく科学者としても有名です。「ジャラーリー暦」という正確な暦を残している。実は詩はイスラム世界では有名ではないらしい。19世紀にイギリスのE.フィッツジェラルドという人が英語に翻訳して、この翻訳が素晴らしかったらしく世界的に有名になりました。原語でならばこの程度の詩人はたくさんいるということです。
建築の特徴としては特にモスクの建築様式なのですが、ドームと塔が特徴です。塔はミナレットといいます。ドームの周囲に四本立っているのがミナレット。それから建築物の壁などを飾る文様をアラベスクといいます。クニャクニャした幾何学紋様です。イスラムでは偶像崇拝の否定から人の姿を描きませんから、こういう複雑な幾何学紋様が発達しました。
絵画はミニアチュールと呼ばれる細密画が有名です。これは受験知識として覚えておけばよい。

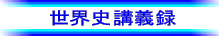
モンゴル帝国とティムール帝国
----------------------------
カリフの宗教的権威で何とかつづいていたアッバース朝が1258年にフラグの率いるモンゴル軍に滅ぼされたことは前回話しました。モンゴル軍はアフリカ大陸までは、行けなかったけれども、ほぼアジア全域を支配下に置いた。
フラグはイラン・イラク方面にイル=ハン国(1260~1353)を建てました。モンゴル人はこの地域を支配するために土着勢力と協力せざるを得ない。13世紀末に即位した第七代、ガザン=ハンの時にイスラムに改宗しています。
モンゴルの時にも話しましたが、この王の時の大臣が有名なラシード=アッディーン。セルジューク朝の名大臣ニザーム=アルムルクを手本にして、イラン人になじみやすいようにモンゴルの行政を改めたのと、『集史』というモンゴル史を軸にした歴史の本を書いたので有名。

中央アジアに作られたチャガタイ=ハン国も14世紀にはイスラム化していきました。
イル=ハン国もチャガタイ=ハン国も14世紀には衰退して在地勢力が各地で自立しはじめます。
再びこの地域を統一し、イラクから中央アジアにまたがる大帝国となったのがティムール帝国(1370~1500)です。
建国者はティムール(?~1405)。この人はチャガタイ=ハン国の武将でしたが、やがて自立して、サマルカンドを都に大帝国を建設した。日本ではあまり馴染みがないけれど中央アジアのトルコ民族の間では今でも人気のある英雄の一人です。
簡単に言えばチンギス=ハーンの再来みたいな男で、残忍なことも平気でやりながら勢力を拡大した。ただ、チンギス=ハーンよりも陽気で明るいイメージで伝えられています。チンギス=ハーンが信長なら、ティムールは秀吉ですね。
瞼が異様に分厚く垂れ下がっていて、つり上げないと前が見えなかったとか、片足が萎えていて歩行が困難だったとか、どこまで本当かはわかりませんが、かれの「異人」ぶりも伝えられています。
ティムールはチンギス=ハーンの血を引いていると自称しています。多少はチンギス=ハーンの血が流れていたかもしれない。だから、ティムールはバラバラに分解してしまったモンゴル帝国を復活させるのだと考えているのですね。積極的な領土拡大の原動力はここにある。
ただし、ティムールの民族をあえて言えば、モンゴル人というよりはトルコ人です。この時代のモンゴル人とトルコ人の違いというのも曖昧なものなのですが、中央アジアに進出したモンゴル人たちは混血によって事実上はトルコ民族化していると考えておいてください。
ティムールはイル=ハン国とチャガタイ=ハン国の領域をほぼ統一したあと、小アジアに進みます。ちょうど、ここにはオスマン朝というトルコ系のイスラムの王朝が力を伸ばしつつありました。このオスマン朝とティムール朝が激突したのがアンカラの戦い(1402)。ティムールが勝って、オスマン朝は大打撃を受け一時は滅亡寸前にまでなります。
ただし、オスマン朝はこのあと復活してやがて古代ローマ帝国にも劣らないような大帝国を作り上げて、最終的には20世紀まで存続する王朝になります。覚えておいてください。
アンカラの戦いはイスラム東西両雄の決戦といったところです。
このあとティムールは軍を東方に向けます。実はこの間に中国では元が滅んで明という漢民族の王朝が生まれています。
ティムールはモンゴル帝国の復活を目指していますから、中国遠征、明の討伐を計画した。アンカラの戦いの2年後、1404年1月、20万の大軍を率いてサマルカンドを出発した。「チムールは…武器、兵糧をはこぶために騎兵一人について、それぞれ10人ずつの輸卒をつけさせた。穀物数千荷は軍用車ではこばれたが、これは道すがら種子をまいて帰路の兵糧に供するためであった。なお、さらに7年間をささえるに足る乾草飼料を用意し、そのほか各人が乳牛二頭、乳羊10頭ずつをたずさえて、途中の食糧の欠乏にそなえることにした。」(中央公論社、『世界の歴史9』)というから、すごい作戦です。
これが最後まで実行されていたら、中国の歴史はまったく変わったものになったかもしれないのですが、この遠征は途中で中止になった。ティムール自身が死んでしまったのです。最後までスケールの大きな英雄児でした。
ティムール帝国はティムールの死後徐々に衰えて、やがていくつかの地方政権に分裂していきました。
--------------------
イスラムの学問・文化
--------------------
イスラム世界では、地域や民族を越えて同一の学問文化が広がります。
イスラムでは学問を「外来の学問」と「固有の学問」に分けています。
「外来の学問」はイスラム教と直接関係のない他民族の学問のことをいいます。具体的には、ヘレニズム文化、ペルシア文化、インドの学問などです。イスラム世界はこれをアラビア語に翻訳して、独自に発展させていきます。
特にインドから影響を受けた数学はわれわれにもおなじみですね。数学で使っている数字、これはアラビア数字というのですよ。インドからゼロという概念を導入したのは数学の発展に計り知れない功績です。
漢字でもローマ字でもゼロという数字はない。たとえば230というのを漢字で書くと二百三十というのが、伝統的な書法です。百が二つと十が三つあるという発想ですね。ローマ数字も同じ発想で、一の位がどれだけあるかについては触れない。一度やってみたらわかりますが、漢数字だけで計算するのは、すごく困難です。アラビア数字のありがたみがわかります。
医学、哲学も外来の学問として発展します。特に医学は同時代のヨーロッパと比べて格段に進んでいた。というか、ヨーロッパの水準が低すぎるのですが。
代表的な学者がイブン=シーナー(980~1037)。この人が書いた医学書が『医学典範』。イスラム世界最高の医学書で、ヨーロッパでも17世紀までは医科大学の教科書に採用されていたといいます。また、アリストテレス哲学者としても抜きんでていて、なにやら難しい存在論について考えていた。
イブン=ルシュド(1126~98)。この人も医学の本を書き、また、アリストテレス哲学を再現しようとした。ほとんど全てのアリストテレスの本に注釈をつけたので有名。かれの学問はヨーロッパ中世の学問に大きな影響を与えた。
「固有の学問」というのは、イスラム法学です。イスラム世界では、社会生活の全てがコーランを基礎にして組み立てらているけれど、現実の社会のいろいろな出来事をコーラン一冊では判断できないわけです。だから、コーランをどう現実社会に当てはめるかという理論が必要になる。
そういう理論をイスラム法学という。これを教える学校をマドラサ、イスラム法学を修めた知識人のことをウラマーといい、現在でもウラマーはイスラム世界では社会の指導者、地域の相談役みたいな位置にあります。イスラム世界で一見お坊さんみたいに見える人がウラマーです。スンナ派、シーア派それぞれに法学理論が発展していきました。
固有の学問として教科書に出てくるのがイブン=ハルドゥーン(1332~1406)の『世界史序説』。文明の進んだ都市と、遅れた砂漠のような田舎との緊張関係から歴史の理論を考えた本です。
もう一つがイブン=バトゥータ(1304~68?)の『三大陸周遊記』。モロッコ生まれのこの人は、巡礼でメッカに行ったついでにインドからスマトラ、中国の北京まで旅行をする。ちょうどモンゴル帝国の時代なのですね。帰ってから今度はイベリア半島に渡り、その次はサハラ砂漠を越えてニジェール川を探検している。その旅行記です。
何年も旅をして収入はどうなっているのかと思うと、かれは法学者、ウラマーなのですね。で、旅行先で先生として迎えられて教えている。地方の君主の招待を受けたりしながら旅をする。実に気軽に成りゆきにまかせてどこでも行ってしまう。面白いことにイブン=バトゥータがアジアからエジプトに帰って来たときに、北京で知り合った人の兄弟と偶然出会っている。これは、イブン=バトゥータだけでなく、イスラム教の人々が実に活発に移動していることの一例ですね。
イスラム教には神秘主義というものがある。11世紀頃から流行しだした。
正統的なイスラムでは満足できない人たちの間から生まれてきたものです。ムハンマドが最後の預言者とすれば、二度と神が人間に話しかけてくれることはないわけですね。残された人類に出来ることは法学者のようにコーランを解釈することだけです。「これではつまらん!神を実感したい」という修行者が現れてくる。こういう修行者をスーフィーといいます。スーフィーはいろいろな難行苦行をして自分の内面に神を感じようとするのです。資料集にはトルコの「踊る教団」の写真がある。この人たちはこうしてクルクル回転するのが修行。目がまわってクラクラするその時に神を感じるんでしょうね。ほかにも色々な教団があるそうです。
イスラム教がアラブ人以外の民族に広まっていったのにはスーフィー教団の活動が大きかったといわれています。修行する姿というのは共感を呼びやすいのですね。
この神秘主義を理論化したひとがガザーリー(1058~1111)です。
セルジューク朝の宰相ニザーム=アルムルクに認められ、スンナ派の最高の学者としてバグダードのニザーミア学院で教授をしていたのですが、37歳の時に教授の地位も家族も友人も財産もすべてを捨てて修行者として放浪の旅に出た。理論ではなく、自分自身の内面に神を感じたいと思い詰めたらしいです。
文学では、『アラビアン・ナイト』。『千夜一夜物語』という名前でも有名ですね。16世紀はじめ頃に現在の形にまとまった。この中に「アリババと40人の盗賊」とか「シンドバットの冒険」とかいろいろな話が入っています。イスラム商人たちが活躍した地域の話が取り込まれているので中国やインドの話なども出てきます。
子供向けにアレンジされたシンドバットやアラジンと魔法のランプの話などは、知っている人もいると思うけれど、子供向けに直していないのを読んだことある人いますか。
すごいよ。この『アラビアン・ナイト』は、まるでポルノです。私は高校時代に何気なく岩波文庫で読んでびっくりしました。滅茶苦茶スケベな物語なんです。教室で細かく紹介することは出来ませんが、とにかくどの話にも男と女が出てきて必ずそういうシーンがある。うんざりするくらいです。今はどうか知りませんが、10年くらい前はエジプトでは発行禁止でした。昔、外国で『アラビアン・ナイト』を映画化したことがあって私も当然勉強のために見に行きました。そうしたら、案の定、映倫に厳しくチェックされてボカシだらけの画面でした。
映画はいろいろな話がバラバラのオムニバス形式でしたが、『アラビアン・ナイト』全体の話はこんな形です。
最初にイスラムの王様が出てきます。この王様、妃を愛しているのですが、弟に妃が浮気をしていることを教えられます。本当かどうか確かめるために、王様、ある日妃に外出を告げて、こっそり帰ってきて、妃の振る舞いを見張っていた。そうしたら、妃は男奴隷や女奴隷を集めて乱交に及ぶんだ。王様、カッとなって妃も奴隷もみんな殺してしまった。
以後、王様は女性不信に陥る。あんなに愛していた妃が不貞をはたらいた、というわけですべての女性に復讐をはかる。どうするかというと、毎晩自分の国の乙女を一人ずつ宮殿によんで、一夜の供をさせたあと殺していくのです。女の子を宮殿に連れてくるのは大臣の役目なんですが、王様が毎晩女の子を殺してしまうので、国にはもう乙女がいなくなってしまった。最後に残ったのは自分の娘なんですが、仕方がない。とうとう、自分の娘を王のもとに届けることになった。この娘の名が、シェーラザードといいます。
王はいつのものように彼女と寝たあと殺そうとするのですが、その時シェーラザードが「王様、私面白いお話をしましょう。」と話をはじめる。彼女も殺されたくありませんから必死です。王もどうせ暇ですから、殺すのは後回しにして話をさせてみるとこれが面白い。熱中して聞いているうちに夜明けが来る。そうするとシェーラザードは話をうんと盛り上げておいて「このつづきは、次の夜にしましょ。」と言うんだね。王様、話のつづきを聞きたいために、殺すのを延期します。
こんなふうにして、シェーラザードは毎晩毎晩死なないために話を続け、王は、話を聞きたいために殺すのを先延ばしにします。結局シェーラザードは1000夜、話をつづけて、話が終わったときには王様は心を入れ替えて、女性に復讐するのをやめましたとさ、という結末です。
このシェーラザードの話の中にシンドバッドやアラジンやアリババが出てくるのです。
話の舞台はアッバース朝のカリフ、ハールーン=アッラシ-ド時代のバグダードが多いです。この時代がイスラムの栄光の時代という認識があるのでしょう。
話の中でランプの魔人とか指輪の魔人とか出てきて、願い事をかなえてくれたりするでしょ。欲しいものは何でも手に入る。イスラム世界の中心、世界中から商人たちが運び込んだ商品がある。そういうバグダードを象徴しているような気もしますね。
それから詩です。ウマル=ハイヤーム(1048~1131)だけ覚えておけばよいです。作品名は『ルバイヤート』。この人はセルジューク朝に仕えていて、詩だけではなく科学者としても有名です。「ジャラーリー暦」という正確な暦を残している。実は詩はイスラム世界では有名ではないらしい。19世紀にイギリスのE.フィッツジェラルドという人が英語に翻訳して、この翻訳が素晴らしかったらしく世界的に有名になりました。原語でならばこの程度の詩人はたくさんいるということです。
建築の特徴としては特にモスクの建築様式なのですが、ドームと塔が特徴です。塔はミナレットといいます。ドームの周囲に四本立っているのがミナレット。それから建築物の壁などを飾る文様をアラベスクといいます。クニャクニャした幾何学紋様です。イスラムでは偶像崇拝の否定から人の姿を描きませんから、こういう複雑な幾何学紋様が発達しました。
絵画はミニアチュールと呼ばれる細密画が有名です。これは受験知識として覚えておけばよい。
 第47回 ティムール帝国・イスラム文化 おわり
第47回 ティムール帝国・イスラム文化 おわり