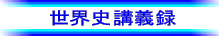第50回 ノルマン人の移動・封建制
----------------
ノルマン人の移動
----------------
ゲルマン人の一派にノルマン人がいます。別名ヴァイキング。海賊の代名詞になっています。現在のデンマーク、ノルウェー、スエーデンの沿岸部に住んでいた。かれらはゲルマン人の大移動の時には移動しなかった。北の辺境地帯に住んでいたから、フン族もローマ帝国も関係なかったんだね。ところが、ゲルマン人の大移動が一段落した9世紀以降、かれらは船に乗って移動をはじめた。人口の増加が直接の原因らしい。
はじめはブリテン島やヨーロッパの沿岸地帯を襲って略奪をしていた。河川をさかのぼって内陸部深くまでも略奪します。とくに、教会や修道院が財産を蓄えていたので襲われたようです。
ノルマン人の移動
----------------
ゲルマン人の一派にノルマン人がいます。別名ヴァイキング。海賊の代名詞になっています。現在のデンマーク、ノルウェー、スエーデンの沿岸部に住んでいた。かれらはゲルマン人の大移動の時には移動しなかった。北の辺境地帯に住んでいたから、フン族もローマ帝国も関係なかったんだね。ところが、ゲルマン人の大移動が一段落した9世紀以降、かれらは船に乗って移動をはじめた。人口の増加が直接の原因らしい。
はじめはブリテン島やヨーロッパの沿岸地帯を襲って略奪をしていた。河川をさかのぼって内陸部深くまでも略奪します。とくに、教会や修道院が財産を蓄えていたので襲われたようです。
はじめは季節的だった略奪が、やがて一年中おこなわれるようになっていく。各地の支配者たちはノルマン人の襲撃を撃退できないんだね。ノルマン人は各地を占領して国を建てていきます。
具体的に見ていこう。
北フランスの海岸地帯には、911年ノルマンディー公国を建てた。建国者はロロといいます。「ろろ」だよ。「くちぐち」じゃないからね。
フランス王はここに侵入したノルマン人たちを追い払うだけの実力がなかったので、かれらの占領を公式に認めて、そのかわり臣下にした。ノルマンディー公国という国名に注意してください。王国ではなくて公国なのです。国にもランクがあって、一番権威が高いのが帝国、帝国の下が王国。王国の下が公国。フランス王国のなかにノルマンディー公国があって、ノルマンディー公国の君主の称号はノルマンディー公。ノルマンディー公はフランス王の家来です。ただし、実際にはフランス王よりノルマンディー公の方が強い。ロロは「名」より「実」を取ったのだ。領地を正式に認めさせるという「実」です。
ブリテン島やアイルランド島にもノルマン人は侵入した。
ブリテン島の南部イングランドにはノルマン人の一派であるデーン人が侵入します。デーン人は今のデンマークに住んでいた人たち。イングランドにはアングロ・サンクソン族が国をつくっていたのですが11世紀にはデンマーク王クヌートが一時ここを占領してイングランド王になりました。クヌートはイングランド、デンマーク、ノルウェーの王を兼ねて北海地方に大きな勢力をふるいますが、その死後この王国は崩壊して、イングランドではアングロ・サクソン族の王家が復活します。
しかし、1066年、イングランドは再びノルマン人に征服されます。征服したのがノルマンディー公ウィリアム。ノルマンディー公国を建てたロロの子孫です。ここからはじまるイギリスの王朝がノルマン朝。この征服をノルマン=コンクェストという。
面白いのはイングランドを征服したノルマンディー公はフランス王の家臣だということです。だから、これ以後、イギリス王は王としてはフランス王と対等ですが、ノルマンディー公としてはフランス王の家臣である、というややこしい関係になる。また、フランス国内のノルマンディー公国は、フランスの領土ではあるけれど、その領主はイギリス王でもある。要するにフランス国内にイギリス王の領土があるというわけですね。
何とも複雑ですが、実は中世ヨーロッパではこういう関係は結構あった。ノルマンディー公のようなのが封建領主の典型ですが、こういう封建領主同士が複雑に主従関係を結んでいたのです。
イスラム教徒が支配していたイタリア半島の南端とシシリー島を征服したノルマン人グループもありました。かれらがここに建てたのがシチリア王国。
バルト海からロシアの川をさかのぼって黒海からイスラム圏に通じる交易ルートがあって、ノルマン人はフランスからさらってきた奴隷をこのルートでイスラム教国に売っていたようです。
9世紀にロシアにノヴォゴロド王国、キエフ公国という国ができるのですが、ノルマンの一派であるルス族がこれらの国の成立に関連があったという説もある。ロシアという国名はルス族がなまったというのです。
原住地にとどまったノルマン人はデンマーク、ノルウェー、スウェーデンを成立させました。
------
封建制
------
9世紀から約200年間続いたノルマン人の略奪や移動、フランク王国の分裂で西ヨーロッパは大混乱になった。
西や東のフランク国王は侵入するノルマン人を撃退するだけの力がないので、侵入をうけた各地の人々は自力で地域を防衛するしかなかったのです。そのため、地域防衛の中心となった地方の領主が諸侯として自立していった。カロリング朝断絶後フランス王位についたカペー家もそうして力をつけてきた諸侯でした。
武力を持った領主はお互い同士でも戦います。基本的にヨーロッパ中世というのは無政府状態。王も皇帝も名ばかりだから、領地が欲しければ力ずくで奪ったって構わない。誰も文句を言えない。ノルマン人が各地を占領して建国するのと同じです。領地の奪い合いで常に戦争状態だと考えてください。
各地の領主が領地争いを繰り広げるうちに弱い領主は自分の領地を守るために強い領主の家臣になるという形で、領主のあいだで主従関係の系列ができてきます。君主になった大領主は家臣になった小領主の領地を守ってやるかわりに、臣下になった小領主は君主に忠誠を誓って、戦争になったときは軍役奉仕をする。
領主間の主従関係のピラミッドができあがって、その頂点にあるのが国王です。その下の領主が諸侯。自分に臣従する領主をもたない最低ランクの領主が騎士とよばれる。
日本の戦国時代の大名やその家臣の関係と似ていなくもない。ただ、大きな違いは、ヨーロッパの諸侯は複数の君主に仕えてもいいのです。たとえば、諸侯Zが、諸侯Aに臣従を誓っているけれど、それだけでは不安なら諸侯Bの家臣になっても構わない。AもBもZを裏切り者とは考えない。その辺はドライな契約関係です。
こういう場合にAとBが戦争したら、両方に仕えているZはどうするか。Zが年間10日間軍役奉仕するという契約を結んでいるなら、まずはAの指揮下でBと10日間戦って、決着がついてもつかなくても、今度はBのもとへいってAと10日間戦います。そのあとは、戦争が終わっていなくても契約の軍役はすんだのでさっさと自分の領地に帰ってあとは関係なしです。そういう契約なので、AもBもそれ以上は期待しないし要求できない。契約以上の義理人情の忠誠心はありません。
君主が臣下に対する保護も契約の範囲でしかないのは同じです。こういうのを双務的契約関係という。
諸侯のもとには農民たちも集まってくる。略奪から守ってもらうためだね。諸侯は農民を庇護するかわりに農民は諸侯に隷属するようになる。これが農奴のはじまりです。諸侯は農奴から年貢をとるだけでなく、かれらに対する裁判権など、いろいろな特権を農奴に対してもっていました。
たとえば結婚税。結婚する農奴の新郎から領主が受け取っていた。なぜ、こんな税金があるかというと、もともと領主は初夜権というのをもっていて、農奴同士が結婚するとき新婚初夜の新婦を自分の館に連れ込んでそれから新郎に渡したんだ。新郎としてはこんなのはたまりません。初夜権をお金で買い取った。これが結婚税のはじまりといいます。死んだときには葬式税をとられたり、領主の館に労働奉仕をしにいったり、農奴は領主に経済的にも人格的にも隷属していたのです。
というわけで、農奴は不自由身分で移動の自由も職業選択の自由もありませんでした。
諸侯が持つ領地が荘園です。農奴たちはここで働いた。
諸侯間の主従関係、諸侯と農奴と荘園の関係、これらをひっくるめて西欧中世の封建制度といいます。
------------
教皇権の隆盛
------------
封建制度ができあがるのと同じように、ローマ教会の教会組織が整備されます。聖職位階制といって、ピラッミッド型に聖職者の上下関係が作られた。トップはもちろんローマ教皇です。そのもとに大司教、司教、司祭という僧侶がいる。司祭が一般の信者と接触する村や町の神父さんです。
このピラミッド型の教会組織とは別に修道院というのがある。これは教皇に直属している。
修道院というのは俗世間を捨てて禁欲生活を送る修道士たちの共同生活の場です。シリアやエジプトではじまったものですが、ヨーロッパで最初に作られたのがベネディクトゥス(480~543?)が建てたモンテ=カッシーノ修道院。ここではただ禁欲生活するだけではなくて、労働も重視した。「祈り、働け」というのがここのモットーで、このあとヨーロッパにできる修道院の伝統になる。
修道士は当時はインテリです。かれらが集まって共同生活しながら、自給自足で農作業する。自然に修道院は新しい農法の実験場にもなって、新しい農法がここから開発されて、農民の暮らしを向上させていきました。
また、修道院は教皇を頂点とする聖職位階制からはずれた存在なので、官僚的になりがちな教会組織に新しい活力をあたえることもありました。
10世紀から11世紀ころまでに教会の世俗化がすすみます。
たとえば、妻帯したり、荘園を所有したりと、聖職者や教会が俗世間の領主とかわらなくなってくる。
これに対して、教会の改革運動をはじめたのがクリュニュー修道会です。これは、「服従・清貧・貞潔」という戒律を厳しく守るまじめな修道会でした。ここが、教会組織の堕落を批判するのです。そしてやがてはクリュニュー修道会出身の僧侶がローマ教皇になるようなった。
ローマ教皇グレゴリウス7世(位1073~85)がそうです。かれは、教会改革を始めた。
まずは、聖職売買の禁止。聖職を貴族たちが金で売ったり買ったりすることが当時はあった。荘園をたくさんもっている教会の聖職にありつければいい暮らしができますからね。貴族の次男坊以下にとってはおいしい生活手段なのです。これを禁止した。
さらに、聖職者の妻帯を禁止。
そして、神聖ローマ皇帝による聖職者の任命権を否定した。ドイツ国内にも教会はたくさんあります。そして、ドイツ国内の教会の聖職者はドイツ皇帝、つまり神聖ローマ皇帝ですが、が任命するという慣習があった。
これに対してグレゴリウス7世は、ドイツ国内の教会であろうともローマ教会傘下の教会であるならばその任命権はローマ教皇にあるのだ、と主張したわけです。両者ともに譲らず、ここに皇帝対教皇の争いが始まる。
これを、聖職叙任権闘争といいます。
当時の神聖ローマ皇帝はハインリヒ4世(位1056~1106)。グレゴリウス7世とやりあうことになるんですが、ドイツ国内でハインリヒ4世の立場は非常に微妙だった。実は、ドイツは、古いゲルマン部族集団が比較的崩れずに残っていて、その流れをひく大諸侯たちの勢力が大きかった。皇帝の地位ははじめから大諸侯の中の第一人者という面が強かったのです。何かあったら、皇帝の足をすくって、混乱に乗じて自分が皇帝になりたいとか、領地をぶんどってやりたいとか、野心をもっている諸侯がかなりいた。かれらは、皇帝に反抗するきっかけを待っていた。
そこに起こったのが叙任権闘争です。
グレゴリウス7世は武力はありませんが、神に仕える身です。敵を追いつめる独特の手段があった。それが破門です。キリスト教にとって教会や聖職者の役目はそもそも何かというと、信者が死んだあと天国にいけるように神さまに「とりなす」ことです。ローマ教会の「とりなし」がなければ天国にいけない。破門にするということは、「とりなしてやらない。お前のためには祈ってやらない。」ということだね。
グレゴリウス7世は、この武器を使った。ハインリヒ4世を破門にしたのです。ハインリヒ4世が、どれだけ真剣に天国や地獄や教会の「とりなし」を信じていたかはわかりませんが、本当に信じていればこの破門は滅茶苦茶恐ろしいはずです。なにしろ地獄行きが確定するのですから。
信仰上の恐怖だけでなく、この破門はドイツ国内の有力諸侯たちに反抗の口実をあたえることになってしまった。諸侯たちは、「ローマ教皇から破門されたような人物を皇帝にはできない。一年以内に破門が解かれなければ、あんたには皇帝をやめてもらうで。」と言いだした。
ハインリヒ4世、これには困ってしまった。何とか破門を解いてもらわなければならなくなった。
聖職者叙任権どころか、自分の来世と皇帝の地位が危なくなってしまったハインリヒ4世は、グレゴリウス7世の所に詫びを入れにいきました。ドイツからアルプスを越えてイタリア側のアルプス山麓のカノッサ城に出向いた。教皇はローマではなくカノッサ城にこもっていたのです。1077年のことです。冬のアルプスを家族を連れて越えたというから、かなり難儀な旅だったでしょう。
カノッサ城までやって来たハインリヒ4世ですが、教皇は面会もしてくれなければ城内に入れてもくれない。破門を解いて欲しければ誠意を見せろと言われてしまう。ハインリヒ4世、誠意なんて見せようがありませんからね。結局門の外で、裸足に粗末な衣装を身につけただけの姿で三日三晩泣きながら詫びつづけたといいます。しかも雪の降る中で。
この事件のことを「カノッサの屈辱」といいます。
結局、その甲斐があって破門は解かれることになりました。
危機を脱したハインリヒ4世は、こののち逆にグレゴリウス7世を追いつめて廃位して、「カノッサの屈辱」の復讐をするのですが、皇帝ともあろうものが、教皇の前で立ちんぼうで泣きながら詫びたという事実は消えない。
この事件をきっかけにして、西ヨーロッパでローマ教皇の権威が高まっていきました。
叙任権闘争に関しては、この後も皇帝と教皇のあいだの争いはつづくのですが、1122年のヴォルムス協約で両者の妥協が成立しました。
さて、教皇の権威が高まっていく過程で有名な教皇が二人。
ひとりがウルバヌス2世(位1088~99)。この人は1095年、クレルモンの公会議で十字軍を提唱したので有名。十字軍については次回にやります。長期に渡る大遠征の火付け役になった人です。
もうひとりが、インノケンティウス3世(位1198~1216)。教皇の権威が絶頂になった時代の人です。政治的にも有能で、破門という武器を最大限利用しながらイギリスやフランスの政治に介入しました。かれの言葉として伝えらえているのが「教皇は太陽、皇帝は月」というせりふ。教皇権の絶頂ぶりがうかがえるね。
最後に修道院の話に戻りますが、教会組織を改革していったクリュニュー修道会も時代とともにその役割を終えていく。
13世紀にはそれまでになかった托鉢修道会というものが現れます。その代表が、フランチェスコ修道会とドミニコ修道会。この修道会は修道院をもたない。修道士は何の財産も持たずに托鉢しながら、野宿して暮らす。徹底的な禁欲生活を送るのです。
フランチェスコ修道会の設立者、聖フランチェスコは、こんなことを言っている。自分たちが雨に濡れ飢えと寒さで震えながら、どこかの町の教会堂にたどり着き、一晩の宿と食事をもらおうとして扉をたたく。そうしたら教会堂の門番が出てきて、ゆすりたかりの悪党と間違えられて、骨が折れるほど棍棒で殴りつけられる。「その時私達が受難のキリストの苦悩を思い、それを喜んで耐えることができたら、そこにこそ完全な喜びがあるのだ」だって。
聖フランチェスコはもともとはなに不自由のない裕福な商人の家に育った。青年時代はさんざん悪さもしたらしい。それが、信仰の道に目覚めて徹底的に禁欲的な生活に入るんです。諸国を托鉢遍歴しながら民衆に罪を悔い改めよを説いた。私なんかは、何となく一遍上人と重なる人です。
ともかく、以前のクリュニュー修道会のように托鉢修道会も民衆の信頼をあつめ、キリスト教組織を活性化する役割を果たしました。

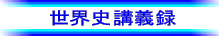
具体的に見ていこう。
北フランスの海岸地帯には、911年ノルマンディー公国を建てた。建国者はロロといいます。「ろろ」だよ。「くちぐち」じゃないからね。
フランス王はここに侵入したノルマン人たちを追い払うだけの実力がなかったので、かれらの占領を公式に認めて、そのかわり臣下にした。ノルマンディー公国という国名に注意してください。王国ではなくて公国なのです。国にもランクがあって、一番権威が高いのが帝国、帝国の下が王国。王国の下が公国。フランス王国のなかにノルマンディー公国があって、ノルマンディー公国の君主の称号はノルマンディー公。ノルマンディー公はフランス王の家来です。ただし、実際にはフランス王よりノルマンディー公の方が強い。ロロは「名」より「実」を取ったのだ。領地を正式に認めさせるという「実」です。
ブリテン島やアイルランド島にもノルマン人は侵入した。
ブリテン島の南部イングランドにはノルマン人の一派であるデーン人が侵入します。デーン人は今のデンマークに住んでいた人たち。イングランドにはアングロ・サンクソン族が国をつくっていたのですが11世紀にはデンマーク王クヌートが一時ここを占領してイングランド王になりました。クヌートはイングランド、デンマーク、ノルウェーの王を兼ねて北海地方に大きな勢力をふるいますが、その死後この王国は崩壊して、イングランドではアングロ・サクソン族の王家が復活します。
しかし、1066年、イングランドは再びノルマン人に征服されます。征服したのがノルマンディー公ウィリアム。ノルマンディー公国を建てたロロの子孫です。ここからはじまるイギリスの王朝がノルマン朝。この征服をノルマン=コンクェストという。
面白いのはイングランドを征服したノルマンディー公はフランス王の家臣だということです。だから、これ以後、イギリス王は王としてはフランス王と対等ですが、ノルマンディー公としてはフランス王の家臣である、というややこしい関係になる。また、フランス国内のノルマンディー公国は、フランスの領土ではあるけれど、その領主はイギリス王でもある。要するにフランス国内にイギリス王の領土があるというわけですね。
何とも複雑ですが、実は中世ヨーロッパではこういう関係は結構あった。ノルマンディー公のようなのが封建領主の典型ですが、こういう封建領主同士が複雑に主従関係を結んでいたのです。
イスラム教徒が支配していたイタリア半島の南端とシシリー島を征服したノルマン人グループもありました。かれらがここに建てたのがシチリア王国。
バルト海からロシアの川をさかのぼって黒海からイスラム圏に通じる交易ルートがあって、ノルマン人はフランスからさらってきた奴隷をこのルートでイスラム教国に売っていたようです。
9世紀にロシアにノヴォゴロド王国、キエフ公国という国ができるのですが、ノルマンの一派であるルス族がこれらの国の成立に関連があったという説もある。ロシアという国名はルス族がなまったというのです。
原住地にとどまったノルマン人はデンマーク、ノルウェー、スウェーデンを成立させました。
------
封建制
------
9世紀から約200年間続いたノルマン人の略奪や移動、フランク王国の分裂で西ヨーロッパは大混乱になった。
西や東のフランク国王は侵入するノルマン人を撃退するだけの力がないので、侵入をうけた各地の人々は自力で地域を防衛するしかなかったのです。そのため、地域防衛の中心となった地方の領主が諸侯として自立していった。カロリング朝断絶後フランス王位についたカペー家もそうして力をつけてきた諸侯でした。
武力を持った領主はお互い同士でも戦います。基本的にヨーロッパ中世というのは無政府状態。王も皇帝も名ばかりだから、領地が欲しければ力ずくで奪ったって構わない。誰も文句を言えない。ノルマン人が各地を占領して建国するのと同じです。領地の奪い合いで常に戦争状態だと考えてください。
各地の領主が領地争いを繰り広げるうちに弱い領主は自分の領地を守るために強い領主の家臣になるという形で、領主のあいだで主従関係の系列ができてきます。君主になった大領主は家臣になった小領主の領地を守ってやるかわりに、臣下になった小領主は君主に忠誠を誓って、戦争になったときは軍役奉仕をする。
領主間の主従関係のピラミッドができあがって、その頂点にあるのが国王です。その下の領主が諸侯。自分に臣従する領主をもたない最低ランクの領主が騎士とよばれる。
日本の戦国時代の大名やその家臣の関係と似ていなくもない。ただ、大きな違いは、ヨーロッパの諸侯は複数の君主に仕えてもいいのです。たとえば、諸侯Zが、諸侯Aに臣従を誓っているけれど、それだけでは不安なら諸侯Bの家臣になっても構わない。AもBもZを裏切り者とは考えない。その辺はドライな契約関係です。
こういう場合にAとBが戦争したら、両方に仕えているZはどうするか。Zが年間10日間軍役奉仕するという契約を結んでいるなら、まずはAの指揮下でBと10日間戦って、決着がついてもつかなくても、今度はBのもとへいってAと10日間戦います。そのあとは、戦争が終わっていなくても契約の軍役はすんだのでさっさと自分の領地に帰ってあとは関係なしです。そういう契約なので、AもBもそれ以上は期待しないし要求できない。契約以上の義理人情の忠誠心はありません。
君主が臣下に対する保護も契約の範囲でしかないのは同じです。こういうのを双務的契約関係という。
諸侯のもとには農民たちも集まってくる。略奪から守ってもらうためだね。諸侯は農民を庇護するかわりに農民は諸侯に隷属するようになる。これが農奴のはじまりです。諸侯は農奴から年貢をとるだけでなく、かれらに対する裁判権など、いろいろな特権を農奴に対してもっていました。
たとえば結婚税。結婚する農奴の新郎から領主が受け取っていた。なぜ、こんな税金があるかというと、もともと領主は初夜権というのをもっていて、農奴同士が結婚するとき新婚初夜の新婦を自分の館に連れ込んでそれから新郎に渡したんだ。新郎としてはこんなのはたまりません。初夜権をお金で買い取った。これが結婚税のはじまりといいます。死んだときには葬式税をとられたり、領主の館に労働奉仕をしにいったり、農奴は領主に経済的にも人格的にも隷属していたのです。
というわけで、農奴は不自由身分で移動の自由も職業選択の自由もありませんでした。
諸侯が持つ領地が荘園です。農奴たちはここで働いた。
諸侯間の主従関係、諸侯と農奴と荘園の関係、これらをひっくるめて西欧中世の封建制度といいます。
------------
教皇権の隆盛
------------
封建制度ができあがるのと同じように、ローマ教会の教会組織が整備されます。聖職位階制といって、ピラッミッド型に聖職者の上下関係が作られた。トップはもちろんローマ教皇です。そのもとに大司教、司教、司祭という僧侶がいる。司祭が一般の信者と接触する村や町の神父さんです。
このピラミッド型の教会組織とは別に修道院というのがある。これは教皇に直属している。
修道院というのは俗世間を捨てて禁欲生活を送る修道士たちの共同生活の場です。シリアやエジプトではじまったものですが、ヨーロッパで最初に作られたのがベネディクトゥス(480~543?)が建てたモンテ=カッシーノ修道院。ここではただ禁欲生活するだけではなくて、労働も重視した。「祈り、働け」というのがここのモットーで、このあとヨーロッパにできる修道院の伝統になる。
修道士は当時はインテリです。かれらが集まって共同生活しながら、自給自足で農作業する。自然に修道院は新しい農法の実験場にもなって、新しい農法がここから開発されて、農民の暮らしを向上させていきました。
また、修道院は教皇を頂点とする聖職位階制からはずれた存在なので、官僚的になりがちな教会組織に新しい活力をあたえることもありました。
10世紀から11世紀ころまでに教会の世俗化がすすみます。
たとえば、妻帯したり、荘園を所有したりと、聖職者や教会が俗世間の領主とかわらなくなってくる。
これに対して、教会の改革運動をはじめたのがクリュニュー修道会です。これは、「服従・清貧・貞潔」という戒律を厳しく守るまじめな修道会でした。ここが、教会組織の堕落を批判するのです。そしてやがてはクリュニュー修道会出身の僧侶がローマ教皇になるようなった。
ローマ教皇グレゴリウス7世(位1073~85)がそうです。かれは、教会改革を始めた。
まずは、聖職売買の禁止。聖職を貴族たちが金で売ったり買ったりすることが当時はあった。荘園をたくさんもっている教会の聖職にありつければいい暮らしができますからね。貴族の次男坊以下にとってはおいしい生活手段なのです。これを禁止した。
さらに、聖職者の妻帯を禁止。
そして、神聖ローマ皇帝による聖職者の任命権を否定した。ドイツ国内にも教会はたくさんあります。そして、ドイツ国内の教会の聖職者はドイツ皇帝、つまり神聖ローマ皇帝ですが、が任命するという慣習があった。
これに対してグレゴリウス7世は、ドイツ国内の教会であろうともローマ教会傘下の教会であるならばその任命権はローマ教皇にあるのだ、と主張したわけです。両者ともに譲らず、ここに皇帝対教皇の争いが始まる。
これを、聖職叙任権闘争といいます。
当時の神聖ローマ皇帝はハインリヒ4世(位1056~1106)。グレゴリウス7世とやりあうことになるんですが、ドイツ国内でハインリヒ4世の立場は非常に微妙だった。実は、ドイツは、古いゲルマン部族集団が比較的崩れずに残っていて、その流れをひく大諸侯たちの勢力が大きかった。皇帝の地位ははじめから大諸侯の中の第一人者という面が強かったのです。何かあったら、皇帝の足をすくって、混乱に乗じて自分が皇帝になりたいとか、領地をぶんどってやりたいとか、野心をもっている諸侯がかなりいた。かれらは、皇帝に反抗するきっかけを待っていた。
そこに起こったのが叙任権闘争です。
グレゴリウス7世は武力はありませんが、神に仕える身です。敵を追いつめる独特の手段があった。それが破門です。キリスト教にとって教会や聖職者の役目はそもそも何かというと、信者が死んだあと天国にいけるように神さまに「とりなす」ことです。ローマ教会の「とりなし」がなければ天国にいけない。破門にするということは、「とりなしてやらない。お前のためには祈ってやらない。」ということだね。
グレゴリウス7世は、この武器を使った。ハインリヒ4世を破門にしたのです。ハインリヒ4世が、どれだけ真剣に天国や地獄や教会の「とりなし」を信じていたかはわかりませんが、本当に信じていればこの破門は滅茶苦茶恐ろしいはずです。なにしろ地獄行きが確定するのですから。
信仰上の恐怖だけでなく、この破門はドイツ国内の有力諸侯たちに反抗の口実をあたえることになってしまった。諸侯たちは、「ローマ教皇から破門されたような人物を皇帝にはできない。一年以内に破門が解かれなければ、あんたには皇帝をやめてもらうで。」と言いだした。
ハインリヒ4世、これには困ってしまった。何とか破門を解いてもらわなければならなくなった。
聖職者叙任権どころか、自分の来世と皇帝の地位が危なくなってしまったハインリヒ4世は、グレゴリウス7世の所に詫びを入れにいきました。ドイツからアルプスを越えてイタリア側のアルプス山麓のカノッサ城に出向いた。教皇はローマではなくカノッサ城にこもっていたのです。1077年のことです。冬のアルプスを家族を連れて越えたというから、かなり難儀な旅だったでしょう。
カノッサ城までやって来たハインリヒ4世ですが、教皇は面会もしてくれなければ城内に入れてもくれない。破門を解いて欲しければ誠意を見せろと言われてしまう。ハインリヒ4世、誠意なんて見せようがありませんからね。結局門の外で、裸足に粗末な衣装を身につけただけの姿で三日三晩泣きながら詫びつづけたといいます。しかも雪の降る中で。
この事件のことを「カノッサの屈辱」といいます。
結局、その甲斐があって破門は解かれることになりました。
危機を脱したハインリヒ4世は、こののち逆にグレゴリウス7世を追いつめて廃位して、「カノッサの屈辱」の復讐をするのですが、皇帝ともあろうものが、教皇の前で立ちんぼうで泣きながら詫びたという事実は消えない。
この事件をきっかけにして、西ヨーロッパでローマ教皇の権威が高まっていきました。
叙任権闘争に関しては、この後も皇帝と教皇のあいだの争いはつづくのですが、1122年のヴォルムス協約で両者の妥協が成立しました。
さて、教皇の権威が高まっていく過程で有名な教皇が二人。
ひとりがウルバヌス2世(位1088~99)。この人は1095年、クレルモンの公会議で十字軍を提唱したので有名。十字軍については次回にやります。長期に渡る大遠征の火付け役になった人です。
もうひとりが、インノケンティウス3世(位1198~1216)。教皇の権威が絶頂になった時代の人です。政治的にも有能で、破門という武器を最大限利用しながらイギリスやフランスの政治に介入しました。かれの言葉として伝えらえているのが「教皇は太陽、皇帝は月」というせりふ。教皇権の絶頂ぶりがうかがえるね。
最後に修道院の話に戻りますが、教会組織を改革していったクリュニュー修道会も時代とともにその役割を終えていく。
13世紀にはそれまでになかった托鉢修道会というものが現れます。その代表が、フランチェスコ修道会とドミニコ修道会。この修道会は修道院をもたない。修道士は何の財産も持たずに托鉢しながら、野宿して暮らす。徹底的な禁欲生活を送るのです。
フランチェスコ修道会の設立者、聖フランチェスコは、こんなことを言っている。自分たちが雨に濡れ飢えと寒さで震えながら、どこかの町の教会堂にたどり着き、一晩の宿と食事をもらおうとして扉をたたく。そうしたら教会堂の門番が出てきて、ゆすりたかりの悪党と間違えられて、骨が折れるほど棍棒で殴りつけられる。「その時私達が受難のキリストの苦悩を思い、それを喜んで耐えることができたら、そこにこそ完全な喜びがあるのだ」だって。
聖フランチェスコはもともとはなに不自由のない裕福な商人の家に育った。青年時代はさんざん悪さもしたらしい。それが、信仰の道に目覚めて徹底的に禁欲的な生活に入るんです。諸国を托鉢遍歴しながら民衆に罪を悔い改めよを説いた。私なんかは、何となく一遍上人と重なる人です。
ともかく、以前のクリュニュー修道会のように托鉢修道会も民衆の信頼をあつめ、キリスト教組織を活性化する役割を果たしました。
 第50回 ノルマン人の移動・封建制 おわり
第50回 ノルマン人の移動・封建制 おわり