



第57回 ルネサンス(1)
--------------
ルネサンスとは
--------------
14世紀頃から16世紀頃にかけてヨーロッパ文化が新たな展開を迎えます。これをルネサンスといいます。ルネサンス期は天才的な芸術家がいっぱいでた。文化史上実に刺激的な時代です。
ルネサンスの以前と以後ではヨーロッパ人のモノの見方、考え方ががらっと変わる。
プリントの絵を見てください。これはルネサンス以前と以後の植物図鑑の絵です。マンドラゴラ草を描いているんですが、ルネサンス以前の絵はどう見ても変でしょ。この根は薬草として使われたのですが、人間の形に描かれている。根には魔力があって危険なので根っこを採集するときには犬に紐をくくりつけて引き抜いたという言い伝えがあるのですが、この絵にはご丁寧に犬まで描いている。こんな形の根があるはずないし、描いている人も知っているはずだと思うのです。なのに、なぜこんな絵を描くのか。
ところが、ルネサンス以後の植物図鑑では、同じマンドラゴラ草がなんでもない植物として描かれています。私は本物のマンドラゴラ草を見たことないから、こっちの絵が正確かどうかは知りませんけどね、でもこちらは本当の姿に似せようとしているね。
同じように、王の肖像画やイエスやマリアを描いた宗教画もルネサンス以後では明らかに描き手の「本物に近く、できるだけリアルに」という気持ちが感じられるようになります。
これがルネサンスの精神です。
迷信とか思い込み、そういうものを捨て去って、まっさらな気持ちで世界を見たらどう見えるか、先入観なく見たもの感じたものをそのまま表現する。そういうことがはじまるのです。
で、この時代のヨーロッパ人にとって、迷信とか先入観の最たるものは何かわかりますか。ヨーロッパ人の発想を縛っているもの。それは、キリスト教なの、もっと具体的に言うとローマ教会ですね。ローマ教会が教えるキリスト教的な世界観を捨て去って世界を見ることからルネサンスははじまりました。
さて、ルネサンスは「再生」という意味です。
何を再生するのか。ローマ=カトリックが広がることによって、いつのまにか消え去ってしまったキリスト教以前の文化です。キリスト教以前にどんな文化があったか。ギリシア・ローマ文化です。
古代ギリシア・ローマ文化の研究がまずイタリアでおこなわれるようになり、ここからルネサンスが生まれることになります。
十字軍などによってビザンツ帝国との交流が頻繁になってくるでしょ。ビザンツ帝国はローマ帝国の後継者だし、その領土はギリシアを含んでいるからギリシア・ローマ文化を引き継いでいるのです。ビザンツからイタリアに学者が来てイタリア半島では失われてしまったギリシア文化を教えたりする。また、イスラム世界でもアリストテレスの哲学などは翻訳研究されていて、東方との貿易が活発になってくるとそれらも輸入されてきます。
そうなってくると、古代ローマ・ギリシア文明はすごかったなあ、ということになる。ところが、もともとイタリアは古代ローマ帝国の本拠地なわけで、ローマ市内を散歩していればゴロゴロ昔の遺跡が転がっているのですよ。ああ、ここにあったんだ、と思うと失われた文化を研究してそれを再生させようという情熱が一気に高まってくるんだね。
こういう古代ギリシア・ローマの文化研究のことをヒューマニズムといいます。日本語では人文主義と訳す。
古代ギリシア・ローマの学問や芸術はキリスト教以前のものですから、原罪とか最後の審判とか復活とか、そういう生まれる前か死んだ後のややこしい教義とは関係ない。イタリア人にはそれが新鮮な驚きなのです。人間中心主義、合理主義、現実主義、そういった思考方法をイタリア人たちは学んでいった。
現在「人間性の尊重」とか「人道主義」とか訳されているヒューマニズムという言葉はここから生まれたものです。
人文主義がすすんでキリスト教的な世界観から自由になってみると、実に人生は素晴らしい、美しい、喜びにあふれたものとして感じられる。キリスト教では生きることは憂鬱で暗いのが当たり前だったからね。人生は原罪をつぐなってあの世で救われるための準備期間で、楽しむものではなかったのです。
ルネサンス期のイタリア人でロレンツォ=デ=メディチ(1449~92)という人がいます。この人の詩。
青春はうるわしくも
あわれはかなきかな
今をこそ楽しみてあれ
何ごとも明日ありとは定かならねば
見事にルネサンスの精神をあらわしている。「今をこそ楽しめ!」と言っているんですよ。来世ではなく。
次はドイツの詩人、フッテン(1488~1523)の言葉。
おお世紀よ、芸術は栄え
知識はよみがえる
生きることは喜びなるかな
「知識はよみがえる」。具体的に何かはもうわかりますね。古代ギリシア・ローマの知識ですよ。そして、「生きることは喜び」とつづく。
ぱーっと目の前の霧が晴れて、世界が鮮明に明るく見えてくる。近視の人がはじめて眼鏡をかけたような気分でしょうかね。これがルネサンスの精神です。
はっきりと世界が見えてくるとこれをとことん見極めて、自分の持てる力を最大限発揮してさらに世界を広げよう、という発想も生まれてくる。人間が自然を征服することだって不可能ではないかもしれない、とも思えてくる。
何でもできる「万能の天才」と呼ばれる人がルネサンス期の理想的な人間像になる。またそんな人が登場してきます。その代表がレオナルド=ダ=ヴィンチ(1452~1519)です。ダ=ヴィンチの『モナリザ』は知っているね。画家として超有名ですが、あの人は画家じゃないんですよ。少なくとも本人はそう思ってはいなかった。自分では「万能の天才」と思っている。自分を領主に売り込むための推薦状が残っているんですが、敵の城壁を打ち破る大砲が作れるとか、いろいろ自分の得意な技能を紹介して最後に絵も描けます、と付け足しみたいに書いている。
実はダ=ヴィンチには人体のスケッチが結構あって、資料集にも載っていますが筋肉や腱が骨とどうつながっているか、熱心に描いている。ダ=ヴィンチは人間を描くとき、できるだけ正確に描こうと思う。そうすると、皮膚の内側が気になってくるのね。筋肉ってどうなってるんだろうとか。気になると、見てみたくて仕方がない。人体解剖をすれば見られるわけですよ。でも、そんなことできないです。
それでも好奇心を抑えられないダ=ヴィンチは、新しい死人が出たと聞くと真夜中に墓場にいって、墓を暴いて死体を解剖したのです。で、ランプの光で必死にスケッチをする。見つかったら死刑、八つ裂きの刑ですよ。なんだか、鬼気迫る光景ですね。30数体の解剖をしたという。
この胎児の絵も、好奇心に駆られたダ=ヴィンチが臨月で死んだ女性を解剖してスケッチしたのかもしれませんね。多分、そうだね。
法律や常識なんか吹っ飛ばしてしまうこの好奇心とバイタリティーはすごい。才能もある。このダ=ヴィンチが、「ルネサンスが生んだ最大の天才」と呼ばれるのです。
ルネサンスは14世紀から16世紀と長いですが、ダ=ヴィンチに代表されるような新しい精神を持っていればルネサンス期の人物として分類しています。
大航海時代の背景にも同じような好奇心があったと思います。コロンブスやマゼランもそういう意味ではまさしくルネサンスの人物です。
----------------
ルネサンスの背景
----------------
ルネサンスの文化が生まれ発展した背景を見ておきます。
1,十字軍によるイスラム・ビザンツ文化との接触。
これが、ヨーロッパ人を大いに刺激した。イスラムやビザンツの文化に対する憧れが生まれます。
2,ビザンツ帝国の滅亡による学者のイタリアへの亡命。
イスラム教のオスマン帝国によって1453年にコンスタンティノープルが陥落しビザンツ帝国は滅亡しました。イスラムの支配を恐れたビザンツ帝国の学者たちがイタリアに亡命してきます。かれらはギリシア・ローマ文化を受け継いでいたのです。そこで、イタリアでギリシア・ローマの古典の勉強がブームになりました。
多くのイタリア人がギリシア語の講義とかを聞きにいくようになる。
3,イタリアの都市国家の成長。諸都市の有力者による学問・芸術の保護
誰が、ビザンツの学者のパトロンになったかというと、商人たちです。イタリアでは統一国家が生まれずに都市国家どうしが戦国状態です。ヴェネツィア、ピサ、ジェノバなどの海上貿易でさかえる都市のほかに、ミラノ、フィレンツェという毛織物工業で発展していた都市もあって、おおむねイタリア北部の諸都市は裕福で、商人階級は経済的にゆとりがあった。学問文芸を保護することが、一流の商人のステイタスのようになっていきます。そこで、豪商や諸都市が争って才能ある学者を招いたり、一流の芸術家に教会を作らせたり肖像を作らせたりするようになる。
たとえば、先ほど紹介したロレンツォ=デ=メディチはフィレンツェを支配した豪商です。ルネサンス芸術のパトロンとして、フィレンツェのメディチ家は覚えておいてください。
----------------------
ルネサンス期の人と文化
----------------------
まず、イタリアから。
ペトラルカ(1304~74)。
著書『叙情詩集』。人文主義の先駆けの一人。ラテン語、ギリシア語の古典研究者です。ラテン語というのは古代ローマの言葉ですよ。ペトラルカは古典研究よりも、はじめて近代的な登山をしたことで有名です。近代的な登山とは何か。昔から世界中で人間は山に登っているんですが、登山の目的はちゃんとあるのね。薬草を摘みにいくとか、羊の放牧とか、一番多いのが信仰登山です。ところがペトラルカの場合は、そういう目的はないのです。ただ、登ってみたくなったから登ってしまった。これが近代登山です。
かれは、ある日突然広々とした景色を見てみたいという衝動に駆られた。それで、弟をつれてヴァントゥー山という山に登ろうと思い立った。ずんずん歩いていって山の麓までいくと羊飼いのおじいさんがいた。山頂までの道をきくと、ここから先に行ったものはいないから引き返しなさい、と諭されるんですね。誰も登山なんてするものはいないのです。それでも、ペトラルカと弟は登っていった。ペトラルカ、山頂に着いた。そこで何をするかというと、風に吹かれながらひととき読書をする。アウグスティヌスの『告白』のこんな一節です。「そしてひとびとはそこへ行き、高山と広い潮と力強くざわめく流れと大洋と天体の運行に感嘆して、われを忘れる。」
かれは山の上で宇宙を感じているのですね。何か粋でしょ。こういう探求心、好奇心がルネサンス的なんです。新しい登山がここに始まりました。そこに山があるから登るのね。人から見て、無意味に見えても本人に意味があれば、いいんです。
ダンテ(1265~1321)。
『神曲』という小説を書きます。ダンテ自身が主人公で、地獄、煉獄、天国というあの世の三世界を旅する話。煉獄というの天国に行けるほど善人でもないけれど、地獄へ行くほど悪くもない人が天国へ行く修行をする世界です。
で、作品中で地獄と煉獄を案内するのがヴェルギリウス。ヴェルギリウスというのは古代ローマの大詩人。ダンテはこの詩人にあこがれていたわけで、ルネサンスですね。
ダンテはこの作品をトスカナ語で書いている。これは受験的にはけっこう出る。トスカナ語というのは現在のイタリア語につながる当時の方言のひとつです。これが、どうして重要かというと、当時学者文人が文章を書くときはラテン語で書くのがあたりまえ。文章といえばラテン語をさしていた。トスカナ語のような俗語で文を書くということは恥ずべきことなのです。でも、ダンテは平気でトスカナ語を使った。自分の表現のためには常識を無視した。ルネサンス的でしょ。
ボッカチオ(1313~75)。
著作は『デカメロン』。デカというのはデシリットルの「デ」と同じで10という意味です。『十日物語』と訳す事もありますね。物語は、ペストの大流行で、病気を避けて貴族の男女10人が郊外の別荘に逃れる。そこは田舎でやることもなく暇でしょうがない。で、暇つぶしに十人が十日間、物語りをするんです。だから『デカメロン』。いろいろな話が次々に展開していくという内容で、構成的には『アラビアンナイト』の真似ですね。
話の中身では、キリスト教会をおちょくっていて、聖職者のセックススキャンダル話がたくさんある。従来の権威にたてついているところがルネサンス的。
絵画にいきましょう。
ボッティチェリ(1444頃~1510)。
代表作が『春』、『ヴィーナスの誕生』。世界的な名画だから見たことはあると思います。
一番右端。空中に浮かんでいる青白いこの男が西風の神「ゼフィロス」。西風というと日本では寒い冬の風ですが、ヨーロッパでは偏西風は暖かい春の風です。
西風ゼフィロスがフーッと春風を吹き付けているのが大地の女神ニンフ。ニンフは西風ゼフィロスにつかまれるのを振り払って、逃げようとしているようです。ニンフがゼフィロスの求愛を拒否しているとも取れる。拒否しているのですが、彼女の口を見てください。何かがこぼれ落ちているでしょ。これ、草花です。嫌がっていても春風にあたって思わず花が咲いてしまう、ということらしい。
ニンフの左は花の女神フローラ。フローラはニンフが変身した姿で、全身花におおわれている。どう転んでも春になってしまうのです、というメッセージのようです。
フローラの横、一段と高いところに立って超然としているように見えるのが、愛と美の女神ヴィーナス、アフロディーテです。
さて、その左には三人の女神が踊っているように手を組んでいる。これは、三美神といってそれまでもしばしば描かれていたテーマなのですが、ボッティチェリはこれに新しい意味を与えています。
三人の中で一番右にいるのが「美」の女神。左端が「愛」の女神。「愛」というと抽象的で分りにくいので思い切って「愛欲」、もうちょっとがんばって「肉欲」の女神と言ってしまいましょう。結った髪が乱れているでしょ。そういうことです。
そして、真中が「貞節」の女神。これも意訳すれば「禁欲」の女神。この人はきっちりと髪を結って乱れがない。
「愛欲」も「禁欲」も「美」と手をつないでいます。そして、「愛欲」「禁欲」もお互いに手をつないでいるのですが、このつなぎ方は押し合っているようにも見える。そうなんです、この二人の女神は相容れないですから、お互いに押し合って勝負をつけようとしているのです。作者ボッティチェリはどちらの応援をしているか。当然「愛欲」にエールを送っていると考えられるのです。根拠は二つ。ひとつは「禁欲」は絵を見るわれわれに背中を見せているのね。堂々とこちらを見ていない。
もうひとつは、画面中央のヴィーナスの上。ここに天使が浮かんでいる。これは恋のキューピット。キューピットは目隠しをして適当に矢を放つ。その矢にあたった人は恋に落ちるというんですね。ここに描かれているキューピットもお約束どおりに目隠しをして矢をつがえています。この矢の方向をテン、テン、テン、と追っていくと、ね、ちゃんと「禁欲」さんにあたる事になっている。「あんた、固いことを言わないで、もっと自由に生きなさいよ。」と「愛欲」さんに言われて「だめよ、だめよ。」と抵抗する「禁欲」さんですが、次の瞬間にはキューピットの矢があたって恋する女神に変貌することを暗示しています。ニンフがフローラに変身するのと同じテーマを描いているわけです。そして、中央のヴィーナスがすべてをつかさどっている。彼女は「愛と美」の女神の真打ですからね。
画面左端の男性ですがこれは戦いの神マーキュリーです。かれが、なぜここに描かれているのか、何をしているのか、これは諸説紛紛ではっきりした解釈がないそうです。とりあえずここでは無視しておきましょう。
この絵の解釈はたくさんあって、今の説明が絶対のものではありませんが、大筋は同じようなものです。そして、この題名が『春』。
もうひとつの『ヴィーナスの誕生』では貝殻に乗った女神がフルヌードで近づいてくるでしょ。ボッティチェリはルネサンステンコ盛りです。
ルネサンスは「Renaissance」とつづるのですが、ローマ字式に無理やり読むと「レンアイサンセイ」。ルネサンスは「恋愛賛成」の時代を切りひらいたのです。

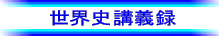
ルネサンスとは
--------------
14世紀頃から16世紀頃にかけてヨーロッパ文化が新たな展開を迎えます。これをルネサンスといいます。ルネサンス期は天才的な芸術家がいっぱいでた。文化史上実に刺激的な時代です。
ルネサンスの以前と以後ではヨーロッパ人のモノの見方、考え方ががらっと変わる。
プリントの絵を見てください。これはルネサンス以前と以後の植物図鑑の絵です。マンドラゴラ草を描いているんですが、ルネサンス以前の絵はどう見ても変でしょ。この根は薬草として使われたのですが、人間の形に描かれている。根には魔力があって危険なので根っこを採集するときには犬に紐をくくりつけて引き抜いたという言い伝えがあるのですが、この絵にはご丁寧に犬まで描いている。こんな形の根があるはずないし、描いている人も知っているはずだと思うのです。なのに、なぜこんな絵を描くのか。
| 当時の人たちは図鑑に植物のあるがままの姿を描こうとは始めから考えていなかったのではないか。そうとしか思われないのですよ。みんなが信じているように描く、そうあるべき形に描く。魔力的な効能を持つ薬草マンドラゴラの根っこは、摩訶不思議な形をしているべきなのね。本当はどういう形なのかは問題ではない。そういう一方的な思い込みの中で世界を見るのがルネサンス以前の目です。 |
同じように、王の肖像画やイエスやマリアを描いた宗教画もルネサンス以後では明らかに描き手の「本物に近く、できるだけリアルに」という気持ちが感じられるようになります。
これがルネサンスの精神です。
迷信とか思い込み、そういうものを捨て去って、まっさらな気持ちで世界を見たらどう見えるか、先入観なく見たもの感じたものをそのまま表現する。そういうことがはじまるのです。
で、この時代のヨーロッパ人にとって、迷信とか先入観の最たるものは何かわかりますか。ヨーロッパ人の発想を縛っているもの。それは、キリスト教なの、もっと具体的に言うとローマ教会ですね。ローマ教会が教えるキリスト教的な世界観を捨て去って世界を見ることからルネサンスははじまりました。
さて、ルネサンスは「再生」という意味です。
何を再生するのか。ローマ=カトリックが広がることによって、いつのまにか消え去ってしまったキリスト教以前の文化です。キリスト教以前にどんな文化があったか。ギリシア・ローマ文化です。
古代ギリシア・ローマ文化の研究がまずイタリアでおこなわれるようになり、ここからルネサンスが生まれることになります。
十字軍などによってビザンツ帝国との交流が頻繁になってくるでしょ。ビザンツ帝国はローマ帝国の後継者だし、その領土はギリシアを含んでいるからギリシア・ローマ文化を引き継いでいるのです。ビザンツからイタリアに学者が来てイタリア半島では失われてしまったギリシア文化を教えたりする。また、イスラム世界でもアリストテレスの哲学などは翻訳研究されていて、東方との貿易が活発になってくるとそれらも輸入されてきます。
そうなってくると、古代ローマ・ギリシア文明はすごかったなあ、ということになる。ところが、もともとイタリアは古代ローマ帝国の本拠地なわけで、ローマ市内を散歩していればゴロゴロ昔の遺跡が転がっているのですよ。ああ、ここにあったんだ、と思うと失われた文化を研究してそれを再生させようという情熱が一気に高まってくるんだね。
こういう古代ギリシア・ローマの文化研究のことをヒューマニズムといいます。日本語では人文主義と訳す。
古代ギリシア・ローマの学問や芸術はキリスト教以前のものですから、原罪とか最後の審判とか復活とか、そういう生まれる前か死んだ後のややこしい教義とは関係ない。イタリア人にはそれが新鮮な驚きなのです。人間中心主義、合理主義、現実主義、そういった思考方法をイタリア人たちは学んでいった。
現在「人間性の尊重」とか「人道主義」とか訳されているヒューマニズムという言葉はここから生まれたものです。
人文主義がすすんでキリスト教的な世界観から自由になってみると、実に人生は素晴らしい、美しい、喜びにあふれたものとして感じられる。キリスト教では生きることは憂鬱で暗いのが当たり前だったからね。人生は原罪をつぐなってあの世で救われるための準備期間で、楽しむものではなかったのです。
ルネサンス期のイタリア人でロレンツォ=デ=メディチ(1449~92)という人がいます。この人の詩。
青春はうるわしくも
あわれはかなきかな
今をこそ楽しみてあれ
何ごとも明日ありとは定かならねば
見事にルネサンスの精神をあらわしている。「今をこそ楽しめ!」と言っているんですよ。来世ではなく。
次はドイツの詩人、フッテン(1488~1523)の言葉。
おお世紀よ、芸術は栄え
知識はよみがえる
生きることは喜びなるかな
「知識はよみがえる」。具体的に何かはもうわかりますね。古代ギリシア・ローマの知識ですよ。そして、「生きることは喜び」とつづく。
ぱーっと目の前の霧が晴れて、世界が鮮明に明るく見えてくる。近視の人がはじめて眼鏡をかけたような気分でしょうかね。これがルネサンスの精神です。
はっきりと世界が見えてくるとこれをとことん見極めて、自分の持てる力を最大限発揮してさらに世界を広げよう、という発想も生まれてくる。人間が自然を征服することだって不可能ではないかもしれない、とも思えてくる。
何でもできる「万能の天才」と呼ばれる人がルネサンス期の理想的な人間像になる。またそんな人が登場してきます。その代表がレオナルド=ダ=ヴィンチ(1452~1519)です。ダ=ヴィンチの『モナリザ』は知っているね。画家として超有名ですが、あの人は画家じゃないんですよ。少なくとも本人はそう思ってはいなかった。自分では「万能の天才」と思っている。自分を領主に売り込むための推薦状が残っているんですが、敵の城壁を打ち破る大砲が作れるとか、いろいろ自分の得意な技能を紹介して最後に絵も描けます、と付け足しみたいに書いている。
| 実際にかれの残したスケッチを見ると、飛行機や潜水艦、ヘリコプターの設計図、いっぺんにたくさんの弾を発射できる大砲の絵とかが描いてある。不思議なのがこれ、プリントに張ってある絵ですが、胎児だね。どう見てもこれは生まれる前ですね。赤ん坊は丸くなった姿勢で、へその緒がくっついています。なぜ、こんな絵を描いたんだろう。しかも何を見て描いたのか。 |
それでも好奇心を抑えられないダ=ヴィンチは、新しい死人が出たと聞くと真夜中に墓場にいって、墓を暴いて死体を解剖したのです。で、ランプの光で必死にスケッチをする。見つかったら死刑、八つ裂きの刑ですよ。なんだか、鬼気迫る光景ですね。30数体の解剖をしたという。
この胎児の絵も、好奇心に駆られたダ=ヴィンチが臨月で死んだ女性を解剖してスケッチしたのかもしれませんね。多分、そうだね。
法律や常識なんか吹っ飛ばしてしまうこの好奇心とバイタリティーはすごい。才能もある。このダ=ヴィンチが、「ルネサンスが生んだ最大の天才」と呼ばれるのです。
ルネサンスは14世紀から16世紀と長いですが、ダ=ヴィンチに代表されるような新しい精神を持っていればルネサンス期の人物として分類しています。
大航海時代の背景にも同じような好奇心があったと思います。コロンブスやマゼランもそういう意味ではまさしくルネサンスの人物です。
----------------
ルネサンスの背景
----------------
ルネサンスの文化が生まれ発展した背景を見ておきます。
1,十字軍によるイスラム・ビザンツ文化との接触。
これが、ヨーロッパ人を大いに刺激した。イスラムやビザンツの文化に対する憧れが生まれます。
2,ビザンツ帝国の滅亡による学者のイタリアへの亡命。
イスラム教のオスマン帝国によって1453年にコンスタンティノープルが陥落しビザンツ帝国は滅亡しました。イスラムの支配を恐れたビザンツ帝国の学者たちがイタリアに亡命してきます。かれらはギリシア・ローマ文化を受け継いでいたのです。そこで、イタリアでギリシア・ローマの古典の勉強がブームになりました。
多くのイタリア人がギリシア語の講義とかを聞きにいくようになる。
3,イタリアの都市国家の成長。諸都市の有力者による学問・芸術の保護
誰が、ビザンツの学者のパトロンになったかというと、商人たちです。イタリアでは統一国家が生まれずに都市国家どうしが戦国状態です。ヴェネツィア、ピサ、ジェノバなどの海上貿易でさかえる都市のほかに、ミラノ、フィレンツェという毛織物工業で発展していた都市もあって、おおむねイタリア北部の諸都市は裕福で、商人階級は経済的にゆとりがあった。学問文芸を保護することが、一流の商人のステイタスのようになっていきます。そこで、豪商や諸都市が争って才能ある学者を招いたり、一流の芸術家に教会を作らせたり肖像を作らせたりするようになる。
たとえば、先ほど紹介したロレンツォ=デ=メディチはフィレンツェを支配した豪商です。ルネサンス芸術のパトロンとして、フィレンツェのメディチ家は覚えておいてください。
----------------------
ルネサンス期の人と文化
----------------------
まず、イタリアから。
ペトラルカ(1304~74)。
著書『叙情詩集』。人文主義の先駆けの一人。ラテン語、ギリシア語の古典研究者です。ラテン語というのは古代ローマの言葉ですよ。ペトラルカは古典研究よりも、はじめて近代的な登山をしたことで有名です。近代的な登山とは何か。昔から世界中で人間は山に登っているんですが、登山の目的はちゃんとあるのね。薬草を摘みにいくとか、羊の放牧とか、一番多いのが信仰登山です。ところがペトラルカの場合は、そういう目的はないのです。ただ、登ってみたくなったから登ってしまった。これが近代登山です。
かれは、ある日突然広々とした景色を見てみたいという衝動に駆られた。それで、弟をつれてヴァントゥー山という山に登ろうと思い立った。ずんずん歩いていって山の麓までいくと羊飼いのおじいさんがいた。山頂までの道をきくと、ここから先に行ったものはいないから引き返しなさい、と諭されるんですね。誰も登山なんてするものはいないのです。それでも、ペトラルカと弟は登っていった。ペトラルカ、山頂に着いた。そこで何をするかというと、風に吹かれながらひととき読書をする。アウグスティヌスの『告白』のこんな一節です。「そしてひとびとはそこへ行き、高山と広い潮と力強くざわめく流れと大洋と天体の運行に感嘆して、われを忘れる。」
かれは山の上で宇宙を感じているのですね。何か粋でしょ。こういう探求心、好奇心がルネサンス的なんです。新しい登山がここに始まりました。そこに山があるから登るのね。人から見て、無意味に見えても本人に意味があれば、いいんです。
ダンテ(1265~1321)。
『神曲』という小説を書きます。ダンテ自身が主人公で、地獄、煉獄、天国というあの世の三世界を旅する話。煉獄というの天国に行けるほど善人でもないけれど、地獄へ行くほど悪くもない人が天国へ行く修行をする世界です。
で、作品中で地獄と煉獄を案内するのがヴェルギリウス。ヴェルギリウスというのは古代ローマの大詩人。ダンテはこの詩人にあこがれていたわけで、ルネサンスですね。
ダンテはこの作品をトスカナ語で書いている。これは受験的にはけっこう出る。トスカナ語というのは現在のイタリア語につながる当時の方言のひとつです。これが、どうして重要かというと、当時学者文人が文章を書くときはラテン語で書くのがあたりまえ。文章といえばラテン語をさしていた。トスカナ語のような俗語で文を書くということは恥ずべきことなのです。でも、ダンテは平気でトスカナ語を使った。自分の表現のためには常識を無視した。ルネサンス的でしょ。
ボッカチオ(1313~75)。
著作は『デカメロン』。デカというのはデシリットルの「デ」と同じで10という意味です。『十日物語』と訳す事もありますね。物語は、ペストの大流行で、病気を避けて貴族の男女10人が郊外の別荘に逃れる。そこは田舎でやることもなく暇でしょうがない。で、暇つぶしに十人が十日間、物語りをするんです。だから『デカメロン』。いろいろな話が次々に展開していくという内容で、構成的には『アラビアンナイト』の真似ですね。
話の中身では、キリスト教会をおちょくっていて、聖職者のセックススキャンダル話がたくさんある。従来の権威にたてついているところがルネサンス的。
絵画にいきましょう。
ボッティチェリ(1444頃~1510)。
代表作が『春』、『ヴィーナスの誕生』。世界的な名画だから見たことはあると思います。
| これが『春』。ルネサンスの象徴のような絵です。どこがルネサンス的か。 まずは題材。ここに描かれているのはすべて神様です。キリスト教の神ではなくて、古代ギリシア・ローマの神々です。たくさんの女神が描かれていますが、みんな薄衣をまとっているだけでほとんどヌードでしょ。今では、別に何ということもありませんが、当時ではけっこう刺激的、スキャンダラスだったんではないでしょうか。 さて、この絵にはいろいろな意味が隠されている。神々に皆意味があるのです。 |
西風ゼフィロスがフーッと春風を吹き付けているのが大地の女神ニンフ。ニンフは西風ゼフィロスにつかまれるのを振り払って、逃げようとしているようです。ニンフがゼフィロスの求愛を拒否しているとも取れる。拒否しているのですが、彼女の口を見てください。何かがこぼれ落ちているでしょ。これ、草花です。嫌がっていても春風にあたって思わず花が咲いてしまう、ということらしい。
ニンフの左は花の女神フローラ。フローラはニンフが変身した姿で、全身花におおわれている。どう転んでも春になってしまうのです、というメッセージのようです。
フローラの横、一段と高いところに立って超然としているように見えるのが、愛と美の女神ヴィーナス、アフロディーテです。
さて、その左には三人の女神が踊っているように手を組んでいる。これは、三美神といってそれまでもしばしば描かれていたテーマなのですが、ボッティチェリはこれに新しい意味を与えています。
三人の中で一番右にいるのが「美」の女神。左端が「愛」の女神。「愛」というと抽象的で分りにくいので思い切って「愛欲」、もうちょっとがんばって「肉欲」の女神と言ってしまいましょう。結った髪が乱れているでしょ。そういうことです。
そして、真中が「貞節」の女神。これも意訳すれば「禁欲」の女神。この人はきっちりと髪を結って乱れがない。
「愛欲」も「禁欲」も「美」と手をつないでいます。そして、「愛欲」「禁欲」もお互いに手をつないでいるのですが、このつなぎ方は押し合っているようにも見える。そうなんです、この二人の女神は相容れないですから、お互いに押し合って勝負をつけようとしているのです。作者ボッティチェリはどちらの応援をしているか。当然「愛欲」にエールを送っていると考えられるのです。根拠は二つ。ひとつは「禁欲」は絵を見るわれわれに背中を見せているのね。堂々とこちらを見ていない。
もうひとつは、画面中央のヴィーナスの上。ここに天使が浮かんでいる。これは恋のキューピット。キューピットは目隠しをして適当に矢を放つ。その矢にあたった人は恋に落ちるというんですね。ここに描かれているキューピットもお約束どおりに目隠しをして矢をつがえています。この矢の方向をテン、テン、テン、と追っていくと、ね、ちゃんと「禁欲」さんにあたる事になっている。「あんた、固いことを言わないで、もっと自由に生きなさいよ。」と「愛欲」さんに言われて「だめよ、だめよ。」と抵抗する「禁欲」さんですが、次の瞬間にはキューピットの矢があたって恋する女神に変貌することを暗示しています。ニンフがフローラに変身するのと同じテーマを描いているわけです。そして、中央のヴィーナスがすべてをつかさどっている。彼女は「愛と美」の女神の真打ですからね。
画面左端の男性ですがこれは戦いの神マーキュリーです。かれが、なぜここに描かれているのか、何をしているのか、これは諸説紛紛ではっきりした解釈がないそうです。とりあえずここでは無視しておきましょう。
この絵の解釈はたくさんあって、今の説明が絶対のものではありませんが、大筋は同じようなものです。そして、この題名が『春』。
もうひとつの『ヴィーナスの誕生』では貝殻に乗った女神がフルヌードで近づいてくるでしょ。ボッティチェリはルネサンステンコ盛りです。
ルネサンスは「Renaissance」とつづるのですが、ローマ字式に無理やり読むと「レンアイサンセイ」。ルネサンスは「恋愛賛成」の時代を切りひらいたのです。
| 【参考図書】 ルネッサンスの光と闇(上) - 芸術と精神風土 (中公文庫)、高階秀彌 ルネッサンスの光と闇(下) - 芸術と精神風土 (中公文庫)、高階秀彌
|

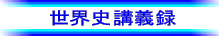
 第57回 ルネサンス1 おわり
第57回 ルネサンス1 おわり