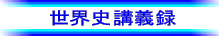第60回 宗教改革(2)
--------------------
カルヴァンの宗教改革
--------------------
ルターに影響されて各地で宗教改革者があらわれるのですが、そのなかで重要なのがカルヴァン(1509~64)です。フランス生まれですが、宗教改革者としての活動が受け入れられず亡命します。当時スイスではルターの影響で宗教改革に熱心な都市がいくつかあって、カルヴァンはジュネーブに招かれて宗教改革をおこないました。
やがては事実上のジュネーブの支配者として神権政治を実施した。カルヴァンは滅茶苦茶に厳格な人ですから、飲酒・賭博など聖書の教えに背く不道徳なことは絶対許さない。酒場は皆店を閉じて、町は火の消えたようになった。カルヴァンの命令に逆らったら死刑にされることさえあるので、ある意味では恐怖政治みたいなピリピリした状態だったようです。
カルヴァン | このカルヴァンの教えには画期的なところがあって、やがてかれの説はルター派よりも広くヨーロッパ各地に広まっていきます。 カルヴァンの主著は『キリスト教綱要』(1536)。 ここで説かれているかれの教えで絶対に覚えなければいけないのが「予定説」というものです。 予定の「予」は「あらかじめ」、「定」は「決定している」という意味。なにがあらかじめ決定しているのかというと、われわれ一人ひとりが天国にいけるかどうかが、あらかじめ決定してる、という意味です。 |
ところが、カルヴァンは、そんなことはない!と言いきる。カルヴァンによれば神というのはものすごく超越的なもので、神がどういうふうに考えて、世界をどう動かすかなどということは、人間ごときが想像してわかるものではない。一所懸命信仰すれば救われるなどというのは人間の勝手な思いこみで、神は自分の偉大さを示すために人間の努力などの及ばないところで誰を救うかをあらかじめ決めているのだ、というのです。
あらかじめというのは、その人が生まれる前から決まっているということです。だから、神様に選ばれている人は、悪いことをさんざんしても、極端に言えば神を信じなくても救われる。選ばれていない人は、いくら教会に熱心に通い、祈り、善行を積んでも救われない、という理屈になる。人間には、神が何を規準に救う人救わない人を分けるのかはわからない。わからないことこそが神の偉大さなのです。
これは、恐ろしい考え方で、予定説が正しいとすれば、信仰しても信仰しなくても結果は同じ。だったら教会も神様も全部無視して好き勝手に生きればいいという考えになりそうでしょ。
カルヴァンは言うわけですよ。信者に向かって、「あなたが救われるかどうかは誰にもわからない。」「一所懸命神に祈っても無駄である」。こういう言葉でしゃべったかどうかはわかりませんが、内容はそういうことです。
でも、カルヴァンの教えが広く受け入れられた核心部分がこの予定説なのです。なぜでしょうか。
多分こういうことだったのではないか。
カルヴァンに誰が救われるかはわからないと言われたときに、ほとんどの人は自分が救われない人とは思わない。「自分は神に選ばれているに違いない」、もっと露骨に言えば「他の全部が地獄に堕ちても私だけは神に選ばれているはずだ」と考えたのです。自分だけは大丈夫というやつです。
そう考えると、次には「神様、私を選んでくれてありがとう」と思う。自分を選んでくれた神様におのずから感謝を捧げる気持ちになる。熱心に信仰するようになる、というわけです。一見厳しい教義ですが、はまった人にとってはエリート意識をくすぐられるのではないかと想像します。
ただ、信者は自分が選ばれている人間だと思うものの、何の証拠もない。少しでも自分が選ばれた人間である手がかりが欲しいと思うものです。
そこで、カルヴァンは神は偉大すぎて誰が救われるか我々にはわからない、としながらもこんなことを言う。神に選ばれて救われる人が誰かを知る方法はない。ただ、神から選ばれた人は運がよい。だから、選ばれたものは現世で成功する確率も高いのではないか、と。職業というのは神からあたえられた使命だから、おのおのが自分の職業でがんばって成功するならば、その人は神から選ばれた者である可能性が高い。
では、成功はどうやってはかるのか。カルヴァンの答えは単純です。「お金が貯まること。」お金を貯めればためるほど成功の証拠になる。
まとめます。カルヴァンは職業的成功が救済の証拠になると説いた。成功は蓄財によって証明されるので、カルヴァンは必然的に蓄財を肯定します。
この点がそれまでのキリスト教と違うところ。カトリックは蓄財を肯定しません。お金を貯めることは卑しいことなんです。もし必要以上にお金を貯めたならそれは教会に寄付すべきなのです。個人で使い切れないお金を持つのは不道徳。イエスは金持ちは天国に入りにくいと教えていたのですから。
ところがカルヴァンは「お金を貯めなさい。どんどん貯めなさい。」と言ってくれる。だからカルヴァンの教えが最も広がったのは新興の市民階級でした。商工業に従事している人たちです。蓄財に関する罪悪感をカルヴァンは見事に取り払ってくれたのです。
おもしろいのは、かれらはお金をどんどん貯めますが、貯めて贅沢をしようとは全然考えない。贅沢三昧したらお金が減ってしまいます。貯めること自体が目的なのですから。貯めて貯めて貯めまくって、自分の救済の確信を得たいのです。
だから、カルヴァン派の信者は勤勉に働いてお金を貯めるけれど、生活は質素で倹約的です。かれらは生活のためではなく神の栄光のために働く。修道院で修道士が働くのに限りなく近いと思います。
こののち商工業が発達する地域にカルヴァン派はどんどん広まっていきます。ネーデルラント(今のオランダ、ベルギー)、フランス、イギリス等です。資本主義の発展とカルヴァン派の教義に関係があるという説もあって、興味深いところです。
あとカルヴァン派の教会制度で「長老制度」というものを覚えておくこと。ローマ教会と違ってルター派もカルヴァン派も、個人の救済を神に「とりなす」教会や教皇、神父の役割を認めません。だから、両派とも神と人をつなぐ聖職者=神父はいない。ローマ教会で神父にあたるものをプロテスタントでは牧師と呼びます。が、牧師は信者に聖書を教える教師であり、神との関係で特別の地位にあるのではないので注意して置いてください。
カルヴァン派の場合は特に一般信者の代表を長老といい、この長老が牧師とともに教会を運営しました。誰が救われるかもわからないのに特権的な聖職者を置く必要はないと考えたのです。ある意味では身分社会の序列をやぶる画期的なものだったと思います。
ヨーロッパ各地でのカルヴァン派の呼称を覚えてください。試験には出る。
オランダ・・・ゴイセン
イギリス・・・ピューリタン
フランス・・・ユグノー
スコットランド・・・プレスビテリアン
------------------
イギリスの宗教改革
------------------
イギリスでも宗教改革が起こりますが、これはルターやカルヴァンとは違って教義の内容、信仰の問題ではなく、政治問題からはじまったものです。その意味では少し毛色が違う。
発端は国王の離婚問題です。
イギリス国王はヘンリ8世(位1509~47)。ばら戦争のあとチューダー朝を建てたヘンリ7世の子供です。ヘンリ8世には奥さんがいた。カザリンといいます。カザリンはスペイン出身で、コロンブスの航海を援助したイザベラ女王の娘。政略結婚でイギリスに請われて輿入れしてきた人です。当時のイギリスはまだまだ貧しく弱い三流国です。スペインは飛ぶ鳥も落とす勢い。アメリカ植民地経営で絶頂期です。しかも、ヘンリ8世の在位時はスペイン国王はカルロス1世。カザリンの甥にあたります。このカルロス1世は父親がハプスブルグ家出身だったので、同時に神聖ローマ帝国皇帝となっている。神聖ローマ帝国皇帝としての名前がカール5世です。ルターの宗教改革で登場した人。スペイン王カルロス1世と神聖ローマ帝国カール5世は同一人物ですからね。
実はカザリンにとってヘンリ8世は二人目の夫でした。最初の夫は誰かというと、ヘンリ8世のお兄さん。そもそも、この兄の方が王位を継ぐ予定だったので、父ヘンリ7世はスペインからカザリンを妻としてめあわせました。ところがこの兄さんが即位する前に病気で死んでしまった。弟だったヘンリ8世が急遽皇太子となった。おまけにお兄さんの嫁さんも押しつけられてしまったというわけです。
あまりにも露骨な政略結婚ですから、ヘンリ8世としてはあまりカザリンに愛情を抱けない。そんなヘンリ8世はカザリンの侍女を好きになってしまった。侍女の名前がアン=ブーリンです。
ヘンリ8世がカザリンとの仮面夫婦を続けて、こっそりとアン=ブーリンを愛人にしておけば問題はなかったのですが、ヘンリ8世はアン=ブーリンと正式に結婚したいと思った。当然ですが、アン=ブーリンと結婚するにはカザリンと離婚しなければならない。
この離婚がやっかいだったんです。今みたいに役所に離婚届を出して、はいオーケーというわけにはいかない。キリスト教徒同士の結婚ですからね、テレビで見たことあると思いますが、カトリックの結婚式では神父さんの前で「この女を生涯妻とすることを誓いますか?」「はい、誓います」という儀式をやっている。誓います、というのは神に誓っているのですね。離婚するということは神への誓いを破ることになるわけです。破るには破るなりの正当な理由がなければ教会は離婚を許してくれない。教会は当然ローマ教会ですよ。ローマ教会は信者と神をつなぐ「とりなし」役ですから、ローマ教会が許可してくれてはじめて信者の離婚は正式に認められる。
当然ヘンリ8世はローマ教会に離婚を申請します。政治的にプレッシャーをかける。
ところが、カザリンは別れたくない。カザリンの甥っ子が神聖ローマ皇帝カール5世でしたね。カール5世はおばさんの味方です。ヘンリ8世の離婚を認めてはならんと、これもローマ教会にプレッシャーをかける。
ドイツではルターの宗教改革がはじまって、ローマ教会としては是非ともカール5世のバックアップは欲しいところです。結局ローマ教会はヘンリ8世の願いを受け入れない。
どうしても離婚したいヘンリ8世は怒った。それなら、ローマ教会なんか抜けてやる、とローマ教会の信者をやめてしまった。国王ですから、ルターやカルヴァンみたいに布教活動を地道にする必要もない。イギリス国民全体を信者にして新しい教会組織を作ってしまったのです。これを定めた法律が1534年国王至上法(首長法)。新しい教会がイギリス国教会。教会の最高指導者、ローマ教皇にあたるのがイギリス国王です。
イギリス国教会は、教義はプロテスタントの影響を受けていますが、儀式などはローマ教会に近い。折衷的です。
国民の反応はというとジェントリという地方の有力者層は国王を支持した。なぜかというと、ローマ教会からの離脱にともなって、国王はイギリス国内の修道院の土地財産を没収して払い下げた。これを譲り受けたのがジェントリたちだったのです。儲けさせてもらって不満なはずがありません。
イギリスの宗教改革はイギリス王室とローマ教会の土地財産をめぐる闘争という面があったということですね。
ローマ教会の立場からヘンリ8世の宗教改革に反対しまくったのがイギリス大法官トマス=モア。『ユートピア』の著者。結局王の怒りをかって処刑されしまいます。
ヘンリ8世のその後ですが、めでたくアン=ブーリンと結婚し、二人のあいだには女の子が産まれたのですが、王子が欲しかったヘンリ8世はまた別の女性に目移りして、邪魔になったアン=ブーリンをロンドン塔に幽閉したうえ処刑してしまった。
結局死ぬまでに6回結婚して、そのうち二人を殺すというとんでもない男でした。
ヘンリー8世が死んで、ただ一人の王子が即位します。エドワード6世。この人の名前は覚える必要はありません。ヘンリ8世の三番目の奥さんが生んだ子でまだ少年だった。ローマ教会はヘンリ8世がなくなれば、またイギリスはローマ教会に復帰してくれるのではないかと期待していたのですが、エドワード6世を支える重臣たちはヘンリ8世の遺言を守ってイギリス国教会を維持します。期待が裏切られてがっくり肩を落としているローマ教皇たちを描いた当時の風刺画がこれです。
エドワード6世は即位してまもなく死んでしまいますが、アメリカの作家マーク=トゥエインの『王子と乞食』のモデルにされたことで少しだけ有名です。
エドワード6世がなくなったあと、王位を継いだのがヘンリ8世の娘メアリ1世(位1553~58)です。メアリの母はカザリン。当然ですが、メアリは自分の母を離婚した父親ヘンリ8世が好きでないし、離婚の結果できたイギリス国教会も大嫌い。メアリは母親と同じようにローマ教会を信じているわけです。そこで、彼女は即位するとイギリス国教会をやめてローマ教会に復帰しました。ジェントリたちにとってはローマ教会から没収した財産がどうなるのか、滅茶苦茶心配です。自分たちの財産を守るためにもイギリス国教会の方がよい。
さらにメアリ1世はスペイン国王フェリペ2世と結婚しました。フェリペ2世はカール5世(カルロス1世)の息子で当然ローマ=カトリックです。メアリ1世がフェリペ2世の子供を生んで、この子がスペイン王とイギリス王を兼ねれば、イギリスという国がなくなってしまう可能性だってあったわけです。
当然メアリ1世は人気がない。メアリは自分の宗教政策に反対する臣下をどんどん処刑していく。彼女についたあだ名が「ブッラド・メアリ」「血のメアリ」です。今ではカクテルの名前になっています。
ところがメアリ1世は即位5年で死んでしまった。次に王位についたのがエリザベス1世(位1558~1603)です。エリザベスはヘンリ8世とアン=ブーリンのあいだの子供です。メアリの腹違いの妹にあたる。この姉妹は当然仲が悪い。メアリは自分が王位についているあいだ妹のエリザベスをロンドン塔に幽閉していました。いつ処刑されるかわからない状態だったのですが、メアリの突然の死で王位がころがりこんできた。
エリザベスはイギリス国教会を復活させます。1559年、信仰統一法という法律でイギリス国教会を確立した、と覚えてください。このあとエリザベスは50年近く在位しますから、この時期に国教会は完全に定着し2度とローマ教会復帰の動きは起こりませんでした。
--------------------
カトリックの改革運動
--------------------
ルター派、カルヴァン派、イギリス国教会などローマ教会から分離した教会が成立して、ローマ教会の勢力は衰えます。特にヨーロッパ北部には新教の勢力が多くなります。
これに危機感をもったローマ教会は、組織の点検、改革に取り組み、巻き返しをはかろうとしました。これを対抗宗教改革といいます。
そのために開かれた会議がトレント公会議。これは1545年から63年まで実に20年近くつづく。この会議で、教皇の至上権の確認、異端の取り締まりの強化、具体的には宗教裁判や禁書の強化が決定されていきました。とくに、ローマ教会の勢力が強固なイタリア半島、イベリア半島では宗教裁判が頻繁におこなわれます。魔女狩り、魔女裁判というのはこの時期が一番多いのです。また、地動説も目の敵にされてガリレオが自説を撤回させられたのもこの時期なのです。
対抗宗教改革の盛り上がりの中でつくられました組織にイエズス会があります(1534年)。イエズス会はアジアで積極的に布教活動をおこなったことで有名。ヨーロッパで衰えたローマ教会の勢力を、世界への布教で挽回しようとしたわけです。
設立したのがイグナティウス=ロヨラ。スペイン北部のバスク地方出身。城を持っているくらいの貴族の生まれです。軍人として活躍するのですがフランスとの戦争で両足を負傷して入院。ケガで軍人として以前のように活躍はできないロヨラは自分の今後の生き方を悩んでいたのでしょうね。かれの出身地のバスク地方というのは今でもスペインからの独立運動をやっているような地域で、スペイン人の本流である人たちとは言語や風習がかなり違う。バスク人であるロヨラが、今後スペイン政界で大きな活躍のできないことは、はっきりしている。
あれこれ悩みながら、入院中のロヨラは読書三昧です。そのときにイエスの伝記を読んで、「これだ!」と今後の人生を神に捧げることを決心した。
もともと活力のある人だったのでしょう。思い立ったら即行動です。神に仕えるためには本格的に神学の勉強をしなければならないと考えて、退院後パリ大学に入学します。このとき38歳です。今の感覚よりも当時の38歳はもっと老けたイメージだと思います。この年齢で大学に入るというのはすごい精神的なパワーですよ。まわりの学生はみんな二十歳そこそこです。当時の大学は全寮制です。そこに38歳の元軍人の大人が加わる。若い学生たちはロヨラにどんどん感化されて、かれの同志になっていきます。
大学卒業と同時にロヨラが同志6人と結成したのがイエズス会です。このときの創立メンバーにあのフランシスコ=ザビエルもいました。ザビエルもバスク地方の貴族でハビエル城という城持ちの貴族だったんですが、スペインの支配下に入ってしまって、閉ざされた活躍の場を布教活動に求めた人のようです。
イエズス会は軍隊的組織に特徴がありました。軍人だったロヨラは会の組織を軍隊と同じにします。トップである総長の命令には絶対服従。会員はどんな困難な命令でも従わなければならない。この厳しい規律のおかげでアジアに信者を増やしていくことができたのですね。イエズス会はポルトガル王の保護のもとでポルトガル商人の出入りするアジア地域に進出します。幹部であるザビエルもその一人です。
ザビエルはインド方面で布教をしているのですが、マラッカで日本人ヤジローと出会います。ヤジローという人は薩摩の人。殺人を犯して、薩摩に出入りしていたポルトガル商人にすがってマラッカまで逃げてきていた。面白いですね。鎖国以前の日本人は驚くほど活動範囲が広いです。
ヤジローはポルトガル語もまあまあできて、頭脳明晰、論理的に物事を考えられる人だった。それを見てザビエルは日本人には布教をしやすいのではと考えた。そこでヤジローをつれて日本に向かいます。マカオまではポルトガル商船で行って、そこからは中国商人の船を雇います。ついたのが薩摩。1549年のことです。ここから日本でのキリスト教がはじまりました。
ザビエルはイエズス会の大幹部ですから、彼が直接一般の日本人に布教することが本来の仕事ではありません。特命全権大使みたいなもので、日本の支配者たちにキリスト教を受け入れさせること、布教の許可を得ること、できることなら何らかの特権を獲得すること、それがザビエルの仕事。だから、九州各地や山口で守護大名に面会する。天皇に面会しようと京都まで上るのですが、応仁の乱後の大混乱で京都はすっかり荒れ果てていた。そこで、京都はあきらめてまた九州に戻ります。
ザビエルは1551年には中国布教をめざして日本を去って翌年病死します。ただ、ザビエル以外のイエズス会士は日本に残り布教活動をつづけ、九州の大名はポルトガルとの貿易が有利になると考え、キリスト教を受け入れていきます。このキリシタン大名たちがローマ教会に使節を送ったのが1582年。有名な天正の遣欧使節です。
イエズス会士に引率されて九州出身の4人のキリシタン少年がローマまでいきました。日本史では有名な出来事ですが、当時のヨーロッパでも大歓迎されるのです。ローマ教会としては、いかに世界の果てまで信者がいるかという生きた証拠ですからね。広告塔としては申し分ないです。プロテスタント諸派の中で日本に信者がいる教会はあるか?ないです。だからローマ教会の勝ち、というわけです。
使節はスペインではフェリペ2世と会い、ローマでは教皇グレゴリウス13世に拝謁します。グレゴリウス13世は、今我々が使っている太陽暦、グレゴリウス暦を制定した人です。
その後もヨーロッパ各地をまわり、1590年に長崎に帰ります。このとき印刷機を持ってくる。ルネサンスですね。
かれらは日本を統一していた豊臣秀吉に謁見します。これがかれらの最後の絶頂期です。やがて、徳川時代にキリスト教の禁令が出されたあとは、キリスト教を捨てたもの、国外追放になったもの、信仰を守って処刑されたものなど、さまざまな運命をたどりますが、そこは日本史で勉強してください。
宗教改革の波紋が、日本にまで及んでいるということを感じてもらえれば結構です。
 第60回 宗教改革2 おわり
第60回 宗教改革2 おわり