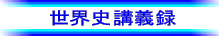第63回 イギリスの革命
--------------------
ステュアート朝の成立
--------------------
イギリスのエリザベス1世は1603年、独身のまま死去しました。独身でしたが、彼女の部屋に出入りするお気に入りの臣下は何人かいたので、ヴァージン・クィーンのあだ名どおりの実体だったかどうかは定かではありません。しかし、子供がいなかったのはれっきとした事実。
問題になるのは、跡継ぎです。王が死んで、後継者がいない場合どうなるのか。ヨーロッパではこういう場合、議会などが次の王を選考する。このときも、イギリス議会はエリザベス1世と家系的につながりのある候補者を何人かピックアップして、最終的にスコットランド王に白羽の矢を立てた。
今まで、イギリス、イギリスと言ってきましたが、正確にはイングランド。現在のイギリスを思い浮かべると、間違えます。現在のイギリスは大ブリテン島にアイルランド島の東北部をあわせたものですが、これをイギリスと呼んでいるのは日本だけで、正確には「グレート・ブリテンおよび北アイルランド連合王国」、略してユナイテッド・キングダムという。U.K.です。連合王国というのは、複数の王国がくっついてできたということで、イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドが一つになってできている。
これら四つの地方が一つの国になっても、いまだに各地方では独立心が旺盛です。スコットランド出身の人に「ああ、イギリス人ですね。」なんていったら、相手は多分怒る。「イングランド人なんかと一緒にするな。」ってね。
サッカーのワールドカップでも、イングランド、スコットランド、ウェールズなど、別のナショナルチームで出場します。ラグビーには五カ国対抗戦という伝統の試合があるのですが、この五カ国というのが、イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドにあと一つがフランスです。
日本人は国というときには、非常にかっちりした組織を連想しがちですが、ヨーロッパ人にとっては国というものは、輪郭の曖昧な、フニャフニャしたものかもしれませんね。
エリザベス1世時代のイングランドは、現在の大ブリテン島の南半分しかありませんでした。ちっちゃい国です。北はスコットランドという別の国。ここの王様をイングランド王に迎えようというのです。
スコットランド王はイギリス議会からの誘いを承諾して、イギリス王になった。これがジェームズ1世です。かれから始まる王朝をステュアート朝という。ジェームズ1世はイギリス王になりますが、スコットランド王をやめるわけではない。ひとりで二つの国の王位を兼ねるのです。この辺の感覚は、われわれには理解しにくいですが、ここからヨーロッパ人の国というものに対する感覚を感じ取ってもらったらと思います。
ジェームズ1世はイギリス王になるために、スコットランドから旅をして南に向かいます。国境には、イギリス議会の代表たちが新しい王を出迎えにきていた。イギリスに入ったジェームズ1世は議会代表たちと一緒にロンドンに向かって旅をつづけた。
この旅の途中で一つの事件がおこります。一行がスリを捕まえたのです。犯罪者ですね。当然、このスリはイギリスの法に照らして処罰しなければならないのですが、ここでジェームズ1世が口出しをして「そのスリは死刑にしろ」と言った。議会の一行は驚いた。スリのような軽犯罪、裁判にかけても死刑にするようなものではない。だけれども、王の命令だから仕方がありません。スリは死刑にされてしまった。このときに、議会代表のイギリス人たちは、将来に不安を感じたのです。「この王様は、議会の言うことを聞いてくれるだろうか。議会や国民の権利を無視してわがまま勝手をするのではないか。」ということです。
ロンドンで即位したジェームズ1世は、王権神授説を信奉して、予想通りイギリス議会を軽視した政治をおこなった。かれの言葉です。「聖書の中で王は神と呼ばれており、かくして彼らの権力は神の権力にもたとえられる・・・。・・・(王は)臣下全員に対し、あらゆる裁き手であり、しかも神以外の何ものにも責任を負わない。」王は何をしてもいいんだ、ということです。
また、ジェームズ1世はイギリス国教会を国民に強制しようとしてピューリタンを圧迫しました。商工業者やジェントリにはピューリタンが多く、かれらは議会にも進出していたので、王と議会の関係はなおさら悪くなりました。
ジェームズ1世が死んで、あとを継ぐのが息子のチャールズ1世(位1625~49)。チャールズ1世も父親譲りの思想の持ち主で、議会に対して強圧的な態度に出ます。しかも、ピューリタンに対して激しい弾圧をしました。ピューリタンの説教を禁止して、反対するものを鞭打ち、耳そぎ、鼻そぎの刑にした。かなりえげつないやり方です。また、宿代を払わずに兵士を民家に宿泊させるなど、国民の権利を無視するような行為がつづいた。
そこで、議会は王に対して議会と国民の権利を尊重するように要請書を提出した。これが「権利の請願」(1628)です。具体的には、議会の承認なしに課税をしない、法律を無視して勝手に国民を逮捕しないことを王に確認させた。
しかし、チャールズ1世も絶対主義の王様ですから、議会の要請をハイそうですかと、受け入れたくはない。翌年王は議会を解散して、以後11年間は議会なしで専制政治をおこなった。
この間に、王がイギリス国教会を強制しようとして、スコットランドで反乱が起きた。チャールズ1世は自ら軍隊を率いて、反乱鎮圧に出かけたのですが、反乱軍の勢いが激しくて引き返してきた。その後も、チャールズ1世は戦費が足りなくて苦戦。とうとうスコットランド軍は国境線を超えて攻め込んできて、王は賠償金を支払って降伏する事になった。
-----------------
ピューリタン革命
-----------------
ところが、この賠償金を支払うには増税しなければならない。新たな課税をするには議会を開かなければならない。というわけで、チャールズ1世は議会を開きますが、とたんに議会はそれまでの王の専制政治を批判して、王と対立した。
その結果、王と議会はそれぞれ軍隊を組織して戦争になったのです。内乱ですね。これが、ピューリタン革命(1642~49)。議会の多数派がピューリタンだったのでこう呼ばれます。
王を支持する貴族たちのグループを王党派、議会のグループを議会派という。王党派は、みんな戦争のプロだから、軍事的には圧倒的に強かった。議会派は、ジェントリや商工業者が中心ですから、戦争のやり方なんかわからない。兵士も義勇兵や地方の民兵中心でみんな素人です。
軍事的には押されっぱなしの議会派を勝利にみちびいたのがクロムウェルという人物です。出身階層はジェントリ、宗教はピューリタン。典型的な議会派ですね。かれは、鉄騎隊という部隊を組織して、王党派軍をめざましい勢いで破って注目されます。この鉄騎隊がそれまでの他の部隊と違うのは、敬虔なピューリタンの信者を選りすぐって兵士に採用したことです。戦闘前夜にはクロムウェルを中心にして跪いて神に祈りを捧げたりする。宗教的な団結力のある部隊でした。
しかも、クロムウェルは兵士たちにきちんと給料を払った。給料の遅配、欠配が当たり前だった時代ですから、これは画期的です。兵士たちもやる気が出ますね。
そして、兵士に能力があれば身分が低くても抜擢して隊長に任命した。靴屋や馬飼い出身の隊長がいたという。当時のヨーロッパは完全な身分制社会ですから、能力本位の人材抜擢は非常に珍しいことだった。
部隊に規律と信頼、そしてやる気をあたえたことが、鉄騎隊の強さになりました。
鉄騎隊の活躍で、やがて議会派の軍隊すべてが、鉄騎隊をモデルにした新型軍に改革され、クロムウェルは事実上その司令官になった。
新型軍は1645年にネイズビーの戦いで王党派軍に勝利しました。その後、ゆきづまったチャールズ1世はスコットランドに逃げ込みますが、スコットランド軍につかまってイギリス議会に引き渡された。
このころには議会派は三つのグループに分かれていた。長老派、独立派、水平派です。長老派は穏健なグループで、国王に対して妥協的。革命に対してあまり熱心ではない。王と妥協せず、きっちり革命をやりきろうというのが独立派。ジェントリが多く、ピューリタン革命の中心勢力で、クロムウェルもこの派です。水平派は最も過激なグループで人民主権を主張した。人民が一番偉い、王なんかなくしてしまえ、と主張した。貧しい農民出身の兵士に影響力があった。
王を捕らえたあと、クロムウェルは王に妥協的な長老派を追放して、王を処刑してしまった。国王の罪名は「暴君、反逆者、殺戮者」。
これは王を処刑したときの絵です。広場に処刑台が設けられて、そのまわりを議会派の兵士たちが取り巻いて警備しています。王党派が王を奪還しにくるのを防ぐためですね。処刑台の上には覆面をつけた男たちがいる。これは首切り役人。恨まれないように顔を隠しているのです。ひとりは血の付いた斧を持っている。今、チャールズ1世の首を切り落としたところなのです。台の上に首のない死体が小さく描かれています。よく見ると、首の切り口からピューッと血が吹き出ています。もうひとりの覆面男が、首を持った腕を伸ばして、これがチャールズの首だ、と集まった観衆に示しているところです。手前左側に大きく描かれてこちらをみているのが、この国王処刑の仕掛け人、クロムウェルです。
国王処刑の瞬間に居合わせた人物が、そのときの模様を書き残している。それによると、、チャールズ1世の首を切ったその瞬間、「オゥー」という何とも言えない暗いどよめきが起きたそうです。「ああ、本当に王様を殺してしまった。成りゆきじょう仕方なかったとはいえ、とんでもないことをしてしまったなあ」という意味のどよめき。悪い王様をやっつけた、万歳!という雰囲気ではなかったそうです。
このあと、王のいない政治体制が10年ほどつづきます。イギリス史上唯一の共和政の時代です。
政治を取り仕切ったのはクロムウェル。かれは水平派の勢力も弾圧し、独立派のリーダーとして事実上イギリスの独裁者になりました。
共和政時期のクロムウェルの政策をみておきます。
まず、アイルランド征服(1649)。イギリスは王党派の地盤となっていたアイルランドに軍隊を送り、この島を占領します。征服されたアイルランドの人口は半減したというからすさまじい。クロムウェルはアイルランド人の土地を徹底的に没収した。この結果、耕地の三分の二はイギリス軍将校と、戦費を出資していたロンドン商人のものになった。アイルランドの農民は小作人ととして徹底的に搾取され、飢餓すれすれの生活を送るようになります。これ以後、アイルランドは20世紀になるまでイギリスの植民地となるのです。
次に、航海法(1651)の制定。イギリスの海外貿易上最大のライバル、オランダに打撃を与え、イギリスの産業を保護するための法律。オランダの貿易船がイギリスとその植民地に入港できないようにした。
この法律が原因でオランダとの間に戦争も起きている。第一次英蘭戦争(1652~54)です。何回かの海戦がおこなわれて、勝敗はつきませんでしたが、講和条約はイギリスに有利に結ばれました。
クロムウェルは1653年、護国卿という地位についた。護国卿になったクロムウェルは紫のマントを羽織ってみんなの前に出てきたという。紫というのは、ヨーロッパでは皇帝や王のシンボルカラーです。ちなみに中国では皇帝の色は黄色ですよ。
だから紫の色を着ていたというのは、護国卿という地位が限りなく王に近いものだったということです。日本で言えば、豊臣秀吉がなった関白、太閤みたいな雰囲気でしょうか。 クロムウェルは王になりたかったけれど、軍隊に反対されたので護国卿で我慢したという説や、反対に、王になるつもりはなかったけれど、イギリス国民は王様がいないと不安がってしょうがないので、王のような格好をして国民の要望に応えた、という説もあるようです。
イギリスは、主要先進国中いまだに王室が残る珍しい国です。その理由を考えていくと、この護国卿というのは面白いテーマですね。
クロムウェルは1658年に死去します。死ぬまで護国卿として独裁政治をつづけましたが、晩年にはその政治に対して不満を持つ勢力も出てきていました。とにかく、クロムウェルの政治は、厳格で暗かった。かれは熱心なピューリタンだったから、酒や賭事は禁止されていて、庶民にとっては楽しみの少ない時代だったと思います。クロムウェルの時代にはみんな我慢していたけれど、クロムウェル死後、息子のリチャードが護国卿の地位を継ぐと不満が爆発した。リチャードは父親ほど政治的な手腕がなかったので、政治運営に行きづまり翌年には政権を放り出してしまった。
-------------------
王政復古と名誉革命
-------------------
誰が、政権を担当するのか混乱する中で、議会が王政を復活させるという結論を出した。ピューリタン革命で処刑されたチャールズ1世の息子、チャールズ2世が王としてイギリスに招かれます。チャールズ2世は父親1世が処刑されたあとはフランスなどヨーロッパ各地を転々として落ちぶれた生活をしていました。
チャールズ2世が即位したのが1660年。これを王政復古といいます。ステュアート朝が復活しました。
チャールズ2世は即位するときに、ピューリタン革命中の人々の言動を罪に問わないこと、ピューリタンの信仰も認めることを約束します。革命中の政策も一部は認めるのです。航海法などはこのあとも実施されています。王政が復活したからといって、すべてが革命前に戻ったわけではないということです。
チャールズ2世にしてみれば、議会に逆らって、父親のように処刑されてはたまらんと考えていたはずです。だから、最初はおとなしくしている。
ところが、だんだん絶対主義的な王様になりたくなってきた。同時期にフランスではルイ14世という絶対主義の典型的な王が、それこそおもう存分権力をふるっているのをみて、俺だって、と思いはじめた。
チャールズ2世はカトリックの信者を官僚に任命して、自分の手足として動かそうとしました。イギリス国王はイギリス国教会の首長という立場があるのですが、チャールズ2世は隠れカトリック信者だったので、カトリックの官僚を使って専制政治をおこなおうとしたのです。
これに対して、議会は1673年に「審査法」という法律を作った。これは、イギリス国教会信者以外は官職につけないという法律。カトリック信者を官僚にしないためのものですね。
さらに、1679年、人身保護法を制定して、王による不当逮捕と投獄を禁じた。
このようにして、議会と国王の対立は徐々に高まってきた。
やがて、チャールズ2世が死去すると、弟のジェームズ2世が即位した。
このジェームズ2世も政治的には絶対主義をおこなおうとした。しかも、ジェームズ2世はカトリックであることを公言していた。イギリス国教会の首長としてふさわしくない。しかも、絶対主義の信奉者です。これで、議会とうまくいくわけがない。ところが、議会は我慢をする。なぜかというと、即位したのが52歳。このときに息子がいなかった。年齢的にいって、これから王子が生まれる可能性はまずない。だから、もう少し我慢すれば王は死んで、跡取りがいないから、そのときは適当な血縁のものをヨーロッパのどこかから呼んだらよいと考えたんだ。
ところが、そのジェームズ2世に息子が誕生した。これで、話は変わってくる。だいたい、ステュアート朝のここまでの四人の王はみんな同じタイプ。議会とイギリスの伝統を無視して専制的な政治を行おうとする王ばかりです。この息子もまだ赤ちゃんだけど、大人になったら、父親や祖父と同じような王になるに違いない。こう考えたら、議会も、もう我慢ができなくなった。
議会はジェームズ2世を追放して、新しい王を呼ぶ相談を始めた。これを知ったジェームズ2世はビビッた。へたに議会に抵抗して父親のチャールズ1世のように革命で命を落としてはたまりませんからね。夜の闇に紛れてロンドンを流れるテムズ川に船をこぎだし、川を下って亡命してしまった。
王の方から勝手に逃げていってくれたので、議会は一滴の血を流すこともなく革命に成功した。これを名誉革命といいます(1688)。流血がなかったことが名誉なのです。だから、国王を処刑してしまったピューリタン革命は名誉ではない。現在のイギリス人でもあまり思い出したくない歴史的事件のようです。
ジェームズ2世に代わって、イギリスの王として招かれたのは、オランダ総督のウィレムとその妻のメアリ。メアリはジェームズ2世の娘です。二人はイギリス王として招かれるにあたってイギリス議会の要請を受け入れて、議会の権利、伝統的な国民の権利などを守ることを宣言します。これを「権利の章典」(1689)という。成文憲法のないイギリスで、国民の権利を定めた法律として現在でも重要です。
ウィレムとメアリ夫妻はイギリス王としてはウィリアム3世(位1689~1702)、メアリ2世(位1689~94)と呼ばれます。二人は同時に王になっていますから注意しておいてください。こういうのを共同統治という。ヨーロッパでは時々こういう形式があります。名誉革命以後は、イギリスの王は政治上の主導権をあまり発揮せず、基本的には議会にお任せするという政治形式になっていきます。
1714年にステュアート朝は断絶し、ドイツのハノーヴァーから遠縁の貴族がイギリス王として招かれました。これが、ハノーヴァー朝のジョージ1世。この人は生まれも育ちもドイツ。要するにイギリス王位が転がり込んできたけれど、根っからのドイツ人です。イギリスに来ては見たものの、英語はほとんど分からないし、ふるさとのドイツが恋しくて仕方がない。政治向きのことは大臣に任せて、自分はドイツに帰って、ほとんどイギリスでは暮らさない。大臣は王様に任された責任があるので一所懸命政治にはげまざるを得ない。こうして、イギリスでは責任内閣制というのが発展しはじめました。
イギリス王の特徴として有名な「君臨すれども統治せず」ですね。統治しないのですから、失敗はありません。だから、政治的な事件があっても王自身は傷つかず、その地位は安泰です。現在までイギリス王室が存続している理由の一つでしょう。
17世紀末の段階で、イギリスとほかのヨーロッパ諸国を比較すると、こういうことになる。
フランスはこのとき絶対主義の全盛期です。
ドイツやロシアなどは絶対主義以前の段階で、王が何とか貴族・諸侯の力を抑えたいと悪戦苦闘している。
そして、イギリスはもう絶対主義の時代が終わってしまっている。これは、王の権力をコントロールするほどに議会が力をつけてきたということ。誰が議会なのか。海外貿易や産業を支配している市民階級です。イギリスはオランダとならんでいち早く市民階級が権力を握るようになった国だということができます。
これら四つの地方が一つの国になっても、いまだに各地方では独立心が旺盛です。スコットランド出身の人に「ああ、イギリス人ですね。」なんていったら、相手は多分怒る。「イングランド人なんかと一緒にするな。」ってね。
サッカーのワールドカップでも、イングランド、スコットランド、ウェールズなど、別のナショナルチームで出場します。ラグビーには五カ国対抗戦という伝統の試合があるのですが、この五カ国というのが、イングランド、スコットランド、ウェールズ、アイルランドにあと一つがフランスです。
日本人は国というときには、非常にかっちりした組織を連想しがちですが、ヨーロッパ人にとっては国というものは、輪郭の曖昧な、フニャフニャしたものかもしれませんね。
エリザベス1世時代のイングランドは、現在の大ブリテン島の南半分しかありませんでした。ちっちゃい国です。北はスコットランドという別の国。ここの王様をイングランド王に迎えようというのです。
スコットランド王はイギリス議会からの誘いを承諾して、イギリス王になった。これがジェームズ1世です。かれから始まる王朝をステュアート朝という。ジェームズ1世はイギリス王になりますが、スコットランド王をやめるわけではない。ひとりで二つの国の王位を兼ねるのです。この辺の感覚は、われわれには理解しにくいですが、ここからヨーロッパ人の国というものに対する感覚を感じ取ってもらったらと思います。
ジェームズ1世はイギリス王になるために、スコットランドから旅をして南に向かいます。国境には、イギリス議会の代表たちが新しい王を出迎えにきていた。イギリスに入ったジェームズ1世は議会代表たちと一緒にロンドンに向かって旅をつづけた。
この旅の途中で一つの事件がおこります。一行がスリを捕まえたのです。犯罪者ですね。当然、このスリはイギリスの法に照らして処罰しなければならないのですが、ここでジェームズ1世が口出しをして「そのスリは死刑にしろ」と言った。議会の一行は驚いた。スリのような軽犯罪、裁判にかけても死刑にするようなものではない。だけれども、王の命令だから仕方がありません。スリは死刑にされてしまった。このときに、議会代表のイギリス人たちは、将来に不安を感じたのです。「この王様は、議会の言うことを聞いてくれるだろうか。議会や国民の権利を無視してわがまま勝手をするのではないか。」ということです。
ロンドンで即位したジェームズ1世は、王権神授説を信奉して、予想通りイギリス議会を軽視した政治をおこなった。かれの言葉です。「聖書の中で王は神と呼ばれており、かくして彼らの権力は神の権力にもたとえられる・・・。・・・(王は)臣下全員に対し、あらゆる裁き手であり、しかも神以外の何ものにも責任を負わない。」王は何をしてもいいんだ、ということです。
また、ジェームズ1世はイギリス国教会を国民に強制しようとしてピューリタンを圧迫しました。商工業者やジェントリにはピューリタンが多く、かれらは議会にも進出していたので、王と議会の関係はなおさら悪くなりました。
ジェームズ1世が死んで、あとを継ぐのが息子のチャールズ1世(位1625~49)。チャールズ1世も父親譲りの思想の持ち主で、議会に対して強圧的な態度に出ます。しかも、ピューリタンに対して激しい弾圧をしました。ピューリタンの説教を禁止して、反対するものを鞭打ち、耳そぎ、鼻そぎの刑にした。かなりえげつないやり方です。また、宿代を払わずに兵士を民家に宿泊させるなど、国民の権利を無視するような行為がつづいた。
そこで、議会は王に対して議会と国民の権利を尊重するように要請書を提出した。これが「権利の請願」(1628)です。具体的には、議会の承認なしに課税をしない、法律を無視して勝手に国民を逮捕しないことを王に確認させた。
しかし、チャールズ1世も絶対主義の王様ですから、議会の要請をハイそうですかと、受け入れたくはない。翌年王は議会を解散して、以後11年間は議会なしで専制政治をおこなった。
この間に、王がイギリス国教会を強制しようとして、スコットランドで反乱が起きた。チャールズ1世は自ら軍隊を率いて、反乱鎮圧に出かけたのですが、反乱軍の勢いが激しくて引き返してきた。その後も、チャールズ1世は戦費が足りなくて苦戦。とうとうスコットランド軍は国境線を超えて攻め込んできて、王は賠償金を支払って降伏する事になった。
-----------------
ピューリタン革命
-----------------
ところが、この賠償金を支払うには増税しなければならない。新たな課税をするには議会を開かなければならない。というわけで、チャールズ1世は議会を開きますが、とたんに議会はそれまでの王の専制政治を批判して、王と対立した。
その結果、王と議会はそれぞれ軍隊を組織して戦争になったのです。内乱ですね。これが、ピューリタン革命(1642~49)。議会の多数派がピューリタンだったのでこう呼ばれます。
王を支持する貴族たちのグループを王党派、議会のグループを議会派という。王党派は、みんな戦争のプロだから、軍事的には圧倒的に強かった。議会派は、ジェントリや商工業者が中心ですから、戦争のやり方なんかわからない。兵士も義勇兵や地方の民兵中心でみんな素人です。
軍事的には押されっぱなしの議会派を勝利にみちびいたのがクロムウェルという人物です。出身階層はジェントリ、宗教はピューリタン。典型的な議会派ですね。かれは、鉄騎隊という部隊を組織して、王党派軍をめざましい勢いで破って注目されます。この鉄騎隊がそれまでの他の部隊と違うのは、敬虔なピューリタンの信者を選りすぐって兵士に採用したことです。戦闘前夜にはクロムウェルを中心にして跪いて神に祈りを捧げたりする。宗教的な団結力のある部隊でした。
しかも、クロムウェルは兵士たちにきちんと給料を払った。給料の遅配、欠配が当たり前だった時代ですから、これは画期的です。兵士たちもやる気が出ますね。
そして、兵士に能力があれば身分が低くても抜擢して隊長に任命した。靴屋や馬飼い出身の隊長がいたという。当時のヨーロッパは完全な身分制社会ですから、能力本位の人材抜擢は非常に珍しいことだった。
部隊に規律と信頼、そしてやる気をあたえたことが、鉄騎隊の強さになりました。
鉄騎隊の活躍で、やがて議会派の軍隊すべてが、鉄騎隊をモデルにした新型軍に改革され、クロムウェルは事実上その司令官になった。
新型軍は1645年にネイズビーの戦いで王党派軍に勝利しました。その後、ゆきづまったチャールズ1世はスコットランドに逃げ込みますが、スコットランド軍につかまってイギリス議会に引き渡された。
このころには議会派は三つのグループに分かれていた。長老派、独立派、水平派です。長老派は穏健なグループで、国王に対して妥協的。革命に対してあまり熱心ではない。王と妥協せず、きっちり革命をやりきろうというのが独立派。ジェントリが多く、ピューリタン革命の中心勢力で、クロムウェルもこの派です。水平派は最も過激なグループで人民主権を主張した。人民が一番偉い、王なんかなくしてしまえ、と主張した。貧しい農民出身の兵士に影響力があった。
王を捕らえたあと、クロムウェルは王に妥協的な長老派を追放して、王を処刑してしまった。国王の罪名は「暴君、反逆者、殺戮者」。
これは王を処刑したときの絵です。広場に処刑台が設けられて、そのまわりを議会派の兵士たちが取り巻いて警備しています。王党派が王を奪還しにくるのを防ぐためですね。処刑台の上には覆面をつけた男たちがいる。これは首切り役人。恨まれないように顔を隠しているのです。ひとりは血の付いた斧を持っている。今、チャールズ1世の首を切り落としたところなのです。台の上に首のない死体が小さく描かれています。よく見ると、首の切り口からピューッと血が吹き出ています。もうひとりの覆面男が、首を持った腕を伸ばして、これがチャールズの首だ、と集まった観衆に示しているところです。手前左側に大きく描かれてこちらをみているのが、この国王処刑の仕掛け人、クロムウェルです。
国王処刑の瞬間に居合わせた人物が、そのときの模様を書き残している。それによると、、チャールズ1世の首を切ったその瞬間、「オゥー」という何とも言えない暗いどよめきが起きたそうです。「ああ、本当に王様を殺してしまった。成りゆきじょう仕方なかったとはいえ、とんでもないことをしてしまったなあ」という意味のどよめき。悪い王様をやっつけた、万歳!という雰囲気ではなかったそうです。
このあと、王のいない政治体制が10年ほどつづきます。イギリス史上唯一の共和政の時代です。
政治を取り仕切ったのはクロムウェル。かれは水平派の勢力も弾圧し、独立派のリーダーとして事実上イギリスの独裁者になりました。
共和政時期のクロムウェルの政策をみておきます。
まず、アイルランド征服(1649)。イギリスは王党派の地盤となっていたアイルランドに軍隊を送り、この島を占領します。征服されたアイルランドの人口は半減したというからすさまじい。クロムウェルはアイルランド人の土地を徹底的に没収した。この結果、耕地の三分の二はイギリス軍将校と、戦費を出資していたロンドン商人のものになった。アイルランドの農民は小作人ととして徹底的に搾取され、飢餓すれすれの生活を送るようになります。これ以後、アイルランドは20世紀になるまでイギリスの植民地となるのです。
次に、航海法(1651)の制定。イギリスの海外貿易上最大のライバル、オランダに打撃を与え、イギリスの産業を保護するための法律。オランダの貿易船がイギリスとその植民地に入港できないようにした。
この法律が原因でオランダとの間に戦争も起きている。第一次英蘭戦争(1652~54)です。何回かの海戦がおこなわれて、勝敗はつきませんでしたが、講和条約はイギリスに有利に結ばれました。
クロムウェルは1653年、護国卿という地位についた。護国卿になったクロムウェルは紫のマントを羽織ってみんなの前に出てきたという。紫というのは、ヨーロッパでは皇帝や王のシンボルカラーです。ちなみに中国では皇帝の色は黄色ですよ。
だから紫の色を着ていたというのは、護国卿という地位が限りなく王に近いものだったということです。日本で言えば、豊臣秀吉がなった関白、太閤みたいな雰囲気でしょうか。 クロムウェルは王になりたかったけれど、軍隊に反対されたので護国卿で我慢したという説や、反対に、王になるつもりはなかったけれど、イギリス国民は王様がいないと不安がってしょうがないので、王のような格好をして国民の要望に応えた、という説もあるようです。
イギリスは、主要先進国中いまだに王室が残る珍しい国です。その理由を考えていくと、この護国卿というのは面白いテーマですね。
クロムウェルは1658年に死去します。死ぬまで護国卿として独裁政治をつづけましたが、晩年にはその政治に対して不満を持つ勢力も出てきていました。とにかく、クロムウェルの政治は、厳格で暗かった。かれは熱心なピューリタンだったから、酒や賭事は禁止されていて、庶民にとっては楽しみの少ない時代だったと思います。クロムウェルの時代にはみんな我慢していたけれど、クロムウェル死後、息子のリチャードが護国卿の地位を継ぐと不満が爆発した。リチャードは父親ほど政治的な手腕がなかったので、政治運営に行きづまり翌年には政権を放り出してしまった。
-------------------
王政復古と名誉革命
-------------------
誰が、政権を担当するのか混乱する中で、議会が王政を復活させるという結論を出した。ピューリタン革命で処刑されたチャールズ1世の息子、チャールズ2世が王としてイギリスに招かれます。チャールズ2世は父親1世が処刑されたあとはフランスなどヨーロッパ各地を転々として落ちぶれた生活をしていました。
チャールズ2世が即位したのが1660年。これを王政復古といいます。ステュアート朝が復活しました。
チャールズ2世は即位するときに、ピューリタン革命中の人々の言動を罪に問わないこと、ピューリタンの信仰も認めることを約束します。革命中の政策も一部は認めるのです。航海法などはこのあとも実施されています。王政が復活したからといって、すべてが革命前に戻ったわけではないということです。
チャールズ2世にしてみれば、議会に逆らって、父親のように処刑されてはたまらんと考えていたはずです。だから、最初はおとなしくしている。
ところが、だんだん絶対主義的な王様になりたくなってきた。同時期にフランスではルイ14世という絶対主義の典型的な王が、それこそおもう存分権力をふるっているのをみて、俺だって、と思いはじめた。
チャールズ2世はカトリックの信者を官僚に任命して、自分の手足として動かそうとしました。イギリス国王はイギリス国教会の首長という立場があるのですが、チャールズ2世は隠れカトリック信者だったので、カトリックの官僚を使って専制政治をおこなおうとしたのです。
これに対して、議会は1673年に「審査法」という法律を作った。これは、イギリス国教会信者以外は官職につけないという法律。カトリック信者を官僚にしないためのものですね。
さらに、1679年、人身保護法を制定して、王による不当逮捕と投獄を禁じた。
このようにして、議会と国王の対立は徐々に高まってきた。
やがて、チャールズ2世が死去すると、弟のジェームズ2世が即位した。
このジェームズ2世も政治的には絶対主義をおこなおうとした。しかも、ジェームズ2世はカトリックであることを公言していた。イギリス国教会の首長としてふさわしくない。しかも、絶対主義の信奉者です。これで、議会とうまくいくわけがない。ところが、議会は我慢をする。なぜかというと、即位したのが52歳。このときに息子がいなかった。年齢的にいって、これから王子が生まれる可能性はまずない。だから、もう少し我慢すれば王は死んで、跡取りがいないから、そのときは適当な血縁のものをヨーロッパのどこかから呼んだらよいと考えたんだ。
ところが、そのジェームズ2世に息子が誕生した。これで、話は変わってくる。だいたい、ステュアート朝のここまでの四人の王はみんな同じタイプ。議会とイギリスの伝統を無視して専制的な政治を行おうとする王ばかりです。この息子もまだ赤ちゃんだけど、大人になったら、父親や祖父と同じような王になるに違いない。こう考えたら、議会も、もう我慢ができなくなった。
議会はジェームズ2世を追放して、新しい王を呼ぶ相談を始めた。これを知ったジェームズ2世はビビッた。へたに議会に抵抗して父親のチャールズ1世のように革命で命を落としてはたまりませんからね。夜の闇に紛れてロンドンを流れるテムズ川に船をこぎだし、川を下って亡命してしまった。
王の方から勝手に逃げていってくれたので、議会は一滴の血を流すこともなく革命に成功した。これを名誉革命といいます(1688)。流血がなかったことが名誉なのです。だから、国王を処刑してしまったピューリタン革命は名誉ではない。現在のイギリス人でもあまり思い出したくない歴史的事件のようです。
ジェームズ2世に代わって、イギリスの王として招かれたのは、オランダ総督のウィレムとその妻のメアリ。メアリはジェームズ2世の娘です。二人はイギリス王として招かれるにあたってイギリス議会の要請を受け入れて、議会の権利、伝統的な国民の権利などを守ることを宣言します。これを「権利の章典」(1689)という。成文憲法のないイギリスで、国民の権利を定めた法律として現在でも重要です。
ウィレムとメアリ夫妻はイギリス王としてはウィリアム3世(位1689~1702)、メアリ2世(位1689~94)と呼ばれます。二人は同時に王になっていますから注意しておいてください。こういうのを共同統治という。ヨーロッパでは時々こういう形式があります。名誉革命以後は、イギリスの王は政治上の主導権をあまり発揮せず、基本的には議会にお任せするという政治形式になっていきます。
1714年にステュアート朝は断絶し、ドイツのハノーヴァーから遠縁の貴族がイギリス王として招かれました。これが、ハノーヴァー朝のジョージ1世。この人は生まれも育ちもドイツ。要するにイギリス王位が転がり込んできたけれど、根っからのドイツ人です。イギリスに来ては見たものの、英語はほとんど分からないし、ふるさとのドイツが恋しくて仕方がない。政治向きのことは大臣に任せて、自分はドイツに帰って、ほとんどイギリスでは暮らさない。大臣は王様に任された責任があるので一所懸命政治にはげまざるを得ない。こうして、イギリスでは責任内閣制というのが発展しはじめました。
イギリス王の特徴として有名な「君臨すれども統治せず」ですね。統治しないのですから、失敗はありません。だから、政治的な事件があっても王自身は傷つかず、その地位は安泰です。現在までイギリス王室が存続している理由の一つでしょう。
17世紀末の段階で、イギリスとほかのヨーロッパ諸国を比較すると、こういうことになる。
フランスはこのとき絶対主義の全盛期です。
ドイツやロシアなどは絶対主義以前の段階で、王が何とか貴族・諸侯の力を抑えたいと悪戦苦闘している。
そして、イギリスはもう絶対主義の時代が終わってしまっている。これは、王の権力をコントロールするほどに議会が力をつけてきたということ。誰が議会なのか。海外貿易や産業を支配している市民階級です。イギリスはオランダとならんでいち早く市民階級が権力を握るようになった国だということができます。
 第63回 イギリスの革命 おわり
第63回 イギリスの革命 おわり