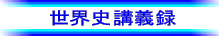第64回 フランスの絶対主義貴
------------
ユグノー戦争
------------
フランスでは1562年から1598年までの間、内乱がありました。ユグノー戦争という。ちょうど、ネーデルラント独立戦争、イギリスではエリザベス1世が即位していた時です。
ユグノー戦争は宗教戦争です。フランスはカトリックの国ですが、宗教改革の影響で新教、とくにカルヴァン派の影響力が強まっていて、宗教対立が激しくなってきた。その結果起きた戦争です。カルヴァン派のことをフランスではユグノーというのです。
国王を中心とするカトリック勢力とユグノーの諸侯が対立しダラダラと内戦がつづきました。細かい経過は必要ないですが、内戦中の事件を一つだけ覚えておくこと。
サン=バルテルミの虐殺事件(1572)です。国王側と、新教側が和解することになって、王の妹マルグリットがユグノーの指導者ブルボン家のアンリと結婚した。この結婚を祝うために、全国からユグノーの有力者がパリに集まってきたのですが、国王側がかれらをだまし討ちで虐殺したという事件です。せっかく、平和になるかもしれなかったのに、ますます内乱は激しくなってしまった。
サン=バルテルミというのは聖人の名前で、虐殺のはじまった日がこの聖人の祝日だったので事件名になっています。
ところで、この虐殺事件の影の演出者として悪名高いのが王の母親カトリーヌ=ド=メディシス。イタリアの名門メディチ家出身の女性です。この女性が虐殺事件をおこしたわけではないのですが、イタリア女ということで、虐殺事件の責任者にされてしまって悪役扱いです。
彼女の名前は非常に細かいところなので覚える必要はないと思いますが、フランスにはこんなふうにイタリアの名門貴族から王妃を迎えることがしばしばあった。どういうことかというと、まだこの時期は、イタリアがヨーロッパ文化の先進地域で、産業もフランスより発達していたのですね。だから、フランス王族もイタリア女性にあこがれた。カトリーヌ=ド=メディシスのようにイタリアからやって来た女性によって、フランスの文化は徐々に洗練されていくのです。
さて、ユグノー戦争はどうなったか。戦争がダラダラつづく中で、王家ヴァロワ家の血統が絶えてしまって、王の妹マルグリットを妻にしていたブルボン家アンリに王位がめぐってきました。かれはユグノーのリーダーでしたね。
こうして成立したのがブルボン朝。アンリは即位してアンリ4世(位1589~1610)となる。このとき35歳でした。
ところが、フランスの大部分はかれを王と認めませんでした。なぜなら、フランス人はカトリックが多数派でユグノーは少数。アンリ4世はユグノーですから、カトリック勢力の強い地域では誰もいうことをきかない。アンリ4世をフランス王と認めたのは全土の六分の一しかなかったのです。かれは首都パリに入ることもできなかった。
そこで、アンリ4世は裏技を使った。カトリックでなければフランス王と認められないのならカトリックになってしまえ、ということで、カトリックに改宗してしまった。信仰というのは心の奥底、人格と切り離せないようなものでしょう。そう簡単に改宗できるものではないと思うのですが、アンリ4世は政治家としての利害に自分の信仰心を従属させた。これは、本心からの改宗ではない、と当時も非難されましたが、カトリック側にとって悪い気はしない。とりあえず、これでカトリック側はかれの味方についた。
一方、激怒するのがユグノー勢力です。今まで自分たちがリーダーと仰いでいた人物が王になったとたん、敵側の宗教に寝返ったのですから、当然許せない。王としては、彼らの怒りも鎮めて、自分の王権に服属してもらわないと、内乱がいつまでもつづく。
1598年、この問題を解決するために、王は「ナントの勅令」を発布した。ナントは、王がこの法律を出した町の名前。内容は、カトリック、ユグノーの両派に信仰の自由を認めるというもの。ユグノーでも弾圧しませんよ、ということです。
今の感覚では、信仰の自由なんて当たり前ですが、当時はカトリックの国が国民に違う宗派の信仰を認めるというのは、画期的なことだったのです。スペインやイタリアではカトリック以外を信じていたら火あぶりの刑ですからね。
信仰の自由が認められて、ユグノー勢力もアンリ4世を認め、ユグノー戦争はようやく終わりました。この内乱でフランスの大諸侯の力が衰えました。そのため、アンリ4世につづくブルボン朝の王様たちにとって、絶対主義を実現しやすい条件ができあがりました。
------------------
フランスの絶対主義
------------------
アンリ4世をついだのがルイ13世(位1610~43)。かれに仕えた宰相がリシュリュー。リシュリューの名前はしっかりと覚えてください。『三銃士』などで敵役として登場するキャラクターですが、実際のリシュリューはフランスを発展させるために誠心誠意努力した人物。「余の第一の目標は国王の尊厳であり、第二は王国の盛大である」とはリシュリューの言葉。
ドイツで起きた三十年戦争にも介入して、領土を拡大するなど、この時代にフランスはヨーロッパの政治に大きな影響力を持つようになります。
次の王がルイ14世(位1643~1715)。フランス絶対主義を代表する王です。
わずか5歳で即位したので、小さい頃は宰相マザランが政治を運営しました。マザランもリシュリューと同じようにフランス王国と王権の発展をめざした。王権を強化するために貴族階級などの既得権を奪おうとしたため、貴族が反乱を起こす。これがフロンドの乱(1648~53)。一時期反乱軍がパリを占領し、マザランは幼いルイ14世をつれてパリから逃れたほどでしたが、最終的に反乱は鎮圧され、結果的に中央集権化が進みました。
1661年、成年に達したルイ14世の親政がはじまります。親政というのは、王が自分で政治をするということですよ。
ルイ14世の政治を見ていきましょう。
経済政策。コルベールという人物を大蔵大臣に任命して、重商主義政策を展開した。開店休業状態だったフランス東インド会社を再建し、海外貿易に乗り出しました。
文化奨励。今のわれわれがイメージとして思い浮かべるヨーロッパの王侯貴族の暮らしを作り出したのが、ルイ14世です。
宮廷貴族の礼儀作法、ファッションなど、この時代に確立したものが多い。
象徴的なのが、ヴェルサイユ宮殿の造営です。場所はパリから南西約20キロ離れたところ。ここに大規模で豪華な宮殿を建設した。宮殿には王、貴族、官僚など5000人が住んでいた。そして、宮殿の周囲の付属の建物に兵士や召使いなど1万5000人ほどが住んでいたという。宮殿というけれど、王が住むだけではなく政府の機能もここに移したから、新しい都市を建設したといった方がよい。
この写真はヴェルサイユ宮殿の中でも有名な鏡の間。幅10メートル、奥行き75メートルの大宴会場です。ここに大きなガラスと鏡がずっと並べられているわけだ。鏡というのは大きくすればするほどゆがみも大きくなる。当時、ゆがみの小さい、大きな鏡を作れるのはイタリアの特別なガラス工房しかなかった。一枚の鏡でも非常に高価だったそうで、それを惜しげもなく使っているのが鏡の間のミソ。文字通り夢の世界だったわけ。
こんな宮殿を造営した国王ルイ14世の威光は高まるばかり。ヨーロッパ中の君主のあこがれの的。のちに、ヴェルサイユ宮殿を真似した宮殿が世界中で造られます。日本の赤坂離宮、今は迎賓館になっていますが、これもヴェルサイユ宮殿をまねたものです。
フランスの貴族たちは、かつてのように王権に反抗するだけの力はない。王から年金をもらって暮らしているものもいる。少しでもルイ14世に「お近づきになりたい」と思っていたようです。王あっての貴族なのです。
ヴェルサイユ宮殿には王以外に貴族たちが住んでいたと言いました。貴族は全体としてはものすごい人数がいるので、ヴェルサイユ宮殿に住めるのはルイ14世のお気に入りの貴族だけです。ヴェルサイユ宮殿に住めるだけで貴族としての箔がつく。
ルイ14世も、そういう貴族心理をうまく見抜いて、自分をスーパースターとして演出していた。
朝起きる時から、着替え、食事、散歩と、すべての王の行動は儀式化されていて、選ばれた貴族たちがその儀式に参加することができる。コップやハンカチを王に渡す役が、貴族たちに割り振られていて、そういう役目をもらったら名誉なのです。食事がすんだら朝の散歩ですが、どの貴族が散歩にお供できるかは、王の指名によります。だから、散歩の前には貴族たちが宮殿の広間に詰めかける。王は、ぐるりと貴族たちを見渡して、「○○公爵、●●伯爵、・・・・」と、その日の散歩のお供を指名する。指名された貴族たちは、それこそ天にも昇る心持ちで散歩について行くわけです。
こういうときにルイ14世は、どういう基準で選ぶかというと、豪華でお金のかかった衣装・装飾を着けている者を選んだ。王のお供をする者は、ゴージャスでなければならないのです。だから、王の寵愛を得ようとするためには、借金をしてでもドレスアップをしなければならなかった。ファッションでフランスがヨーロッパ文化の華となるのには、こんな事情があったのです。ただし、こういうむなしい贅沢をつづけなければならないので、貴族たちの経済的な負担は大変でした。多くの貴族はますます政府、というのはルイ14世ですが、に頼らなければ経済的に成り立っていかなくなっていった。
ついでにファッションの話もしておこう。ルイ14世の肖像画、これが、ヨーロッパ最新のファッション。貴族のあこがれの的です。ズボンは短くて、足にぴったりのタイツをはいています。われわれが今はいているような長ズボンは、下層民の服で、貴族ははきません。
ヘアースタイルも特徴的。このくしゃくしゃとした長い髪、これは、カツラです。フランスでのカツラの大流行が、やがてヨーロッパ中に広がり、そのご正装として定着しました。モーツアルトやベートーベンの肖像画、見たことあるでしょう。かれらも長髪パーマでしょ。あれもカツラ。かれらはルイ14世の時代から100年以上あとの人たちです。イギリス国会上院の議長は今でもカツラをしている。さすがに伝統の国ですね。(ベートーベンのぼさぼさ頭の肖像画はカツラはつけていないそうです。ご指摘ありがとうございました。)
なぜ、カツラをするようになったかというと、ルイ13世に原因がある。ルイ13世は若禿でした。それで、カツラをかぶるようになったのですが、王様一人がカツラをかぶっていると禿をかくしているのがバレバレなので、取り巻きの貴族たちも同じようにカツラをするようになった。どうせするなら派手に、ということでこんな奇抜なカツラが誕生し、ルイ14世時代になると、これが正装にまでなったというわけ。
ちなみにルイ13世時代というのは、ユグノー戦争の混乱の余韻が残っていて、宮廷のマナーというのは滅茶苦茶だった。これではいかん、と考えた貴族の婦人たちによって、サロンというのがつくられて、ここから貴族らしいエチケットやマナー、おしゃれな会話がだんだんと普及するようになった。
それでも、ルイ13世の頃はまだまだひどかったらしい。とくにルイ13世その人が、エチケットとは縁遠い人だった。ルイ13世の成長記録が残っていて、それによると、かれが初めて入浴したのが7歳、顔を洗ったのが9歳だという。ヨーロッパではペストの流行以降、入浴の風習が廃れたんですね。入浴で感染すると考えられたのです。でも、ルイ13世は極端です。全然体を洗わない。当然臭い。ルイ13世のそばに仕えた女性によると、王に近づくと「腐った肉のようなにおい」がしたという。たまらんね。王を臭いと言っている女性も、入浴する風習がないから臭いわけ。やっぱり臭いのはイヤです。そこで、体臭を誤魔化すためにフランスで香水が発達した。体臭を誤魔化そうと考えることも、エチケットの観念が普及してきた証拠。
しかし、ルイ13世自身はそういうエチケットの観念とは対極にあった人で、気にくわない相手に口の中のモノを吐きかけたり、ズボンを穿いたままジャジャーッとオシッコをして、自分の不快感を表現したと伝えられている。野蛮人ですね。
宮廷のマナーが確立してくるのがルイ14世の時代。洗練された文化の中心としてヴェルサイユがヨーロッパのあこがれとなるのですが、それでも、今のわれわれの感覚で考えると、まだまだ変な風習はたくさんある。
有名なのはヴェルサイユ宮殿のトイレの話。ヴェルサイユ宮殿は住んでいる人の数に較べて、トイレの数が極端に少なかった。どこで用を足すかというと、オマルですね。ところが、みんながちゃんとオマルで用を足すわけではない。人のあまり通らない階段の踊り場などには、結構してあったという。それから、オマルの中身はどこに捨てるかというと、召使いの人たちがオマル抱えて庭園に出て、草木の陰にジャバッと捨てる。だから、見た目はきれいなヴェルサイユ宮殿の庭園も、香ばしい匂いが漂っていて、へたに林の中に足を踏み入れると、グチャッ、ということもあった。
話が、だいぶそれてしまいました。ルイ14世の政治に戻ります。
ルイ14世は、フランスの領土拡張のために積極的に外征をおこなった。
南ネーデルラント継承戦争(1667~68)、オランダ侵略戦争(1672~78)、ファルツ継承戦争(1689~97)。
さらに、スペイン継承戦争(1701~13)です。スペインのハプスブルク王家が途絶えたあと、ルイ14世は自分の孫をスペイン王にしようと考えた。そうなると将来は両国が合体するかもしれない。ブルボン家があまりにも大きくなりすぎるのを警戒した周辺諸国が、ルイ14世の孫の即位に反対する。その結果起きた戦争です。
この戦争は1713年のユトレヒト条約で終結します。この条約で、ルイ14世は自分の孫をスペイン王にする事を列国に認めさせることができました。ただし、将来にわたってフランスとスペインが合体しないことを条件として。また、この条約で、海外の植民地の多くを失いました。領土と引き換えに反対する国を買収したということです。特にイギリスが北アメリカや地中海に領土を増やして得をしました。
ルイ14世のフランスは、たびかさなる戦争で、少しばかり領土を拡大しますが、戦争の負担は重税という形で国民にのしかかった。これが、徐々にフランスの経済を悪化させていきます。
もう一つルイ14世の失政がある。これが、1685年の「ナントの勅令の廃止」です。この結果、信仰の自由を認められなくなったユグノーは、フランスから逃れてオランダなどに移住した。ユグノーは豊かな商工業者が多かったから、結果として富裕な市民階級がフランスからごっそりいなくなってしまった。結局、政府の税収は減るし、産業の発展という意味でも大きな損失となった。
ルイ14世治世の末期には、人口の一割が乞食同様だったという記録もある。農民反乱もしばしば起こりました。見た目の華やかさの陰で、フランスの政治、経済の矛盾は大きくなっていった。この矛盾が爆発するのが、ルイ14世の次の次の王、ルイ16世の時。フランス革命です
(20020226改稿)
サン=バルテルミの虐殺事件(1572)です。国王側と、新教側が和解することになって、王の妹マルグリットがユグノーの指導者ブルボン家のアンリと結婚した。この結婚を祝うために、全国からユグノーの有力者がパリに集まってきたのですが、国王側がかれらをだまし討ちで虐殺したという事件です。せっかく、平和になるかもしれなかったのに、ますます内乱は激しくなってしまった。
サン=バルテルミというのは聖人の名前で、虐殺のはじまった日がこの聖人の祝日だったので事件名になっています。
ところで、この虐殺事件の影の演出者として悪名高いのが王の母親カトリーヌ=ド=メディシス。イタリアの名門メディチ家出身の女性です。この女性が虐殺事件をおこしたわけではないのですが、イタリア女ということで、虐殺事件の責任者にされてしまって悪役扱いです。
彼女の名前は非常に細かいところなので覚える必要はないと思いますが、フランスにはこんなふうにイタリアの名門貴族から王妃を迎えることがしばしばあった。どういうことかというと、まだこの時期は、イタリアがヨーロッパ文化の先進地域で、産業もフランスより発達していたのですね。だから、フランス王族もイタリア女性にあこがれた。カトリーヌ=ド=メディシスのようにイタリアからやって来た女性によって、フランスの文化は徐々に洗練されていくのです。
さて、ユグノー戦争はどうなったか。戦争がダラダラつづく中で、王家ヴァロワ家の血統が絶えてしまって、王の妹マルグリットを妻にしていたブルボン家アンリに王位がめぐってきました。かれはユグノーのリーダーでしたね。
こうして成立したのがブルボン朝。アンリは即位してアンリ4世(位1589~1610)となる。このとき35歳でした。
ところが、フランスの大部分はかれを王と認めませんでした。なぜなら、フランス人はカトリックが多数派でユグノーは少数。アンリ4世はユグノーですから、カトリック勢力の強い地域では誰もいうことをきかない。アンリ4世をフランス王と認めたのは全土の六分の一しかなかったのです。かれは首都パリに入ることもできなかった。
そこで、アンリ4世は裏技を使った。カトリックでなければフランス王と認められないのならカトリックになってしまえ、ということで、カトリックに改宗してしまった。信仰というのは心の奥底、人格と切り離せないようなものでしょう。そう簡単に改宗できるものではないと思うのですが、アンリ4世は政治家としての利害に自分の信仰心を従属させた。これは、本心からの改宗ではない、と当時も非難されましたが、カトリック側にとって悪い気はしない。とりあえず、これでカトリック側はかれの味方についた。
一方、激怒するのがユグノー勢力です。今まで自分たちがリーダーと仰いでいた人物が王になったとたん、敵側の宗教に寝返ったのですから、当然許せない。王としては、彼らの怒りも鎮めて、自分の王権に服属してもらわないと、内乱がいつまでもつづく。
1598年、この問題を解決するために、王は「ナントの勅令」を発布した。ナントは、王がこの法律を出した町の名前。内容は、カトリック、ユグノーの両派に信仰の自由を認めるというもの。ユグノーでも弾圧しませんよ、ということです。
今の感覚では、信仰の自由なんて当たり前ですが、当時はカトリックの国が国民に違う宗派の信仰を認めるというのは、画期的なことだったのです。スペインやイタリアではカトリック以外を信じていたら火あぶりの刑ですからね。
信仰の自由が認められて、ユグノー勢力もアンリ4世を認め、ユグノー戦争はようやく終わりました。この内乱でフランスの大諸侯の力が衰えました。そのため、アンリ4世につづくブルボン朝の王様たちにとって、絶対主義を実現しやすい条件ができあがりました。
------------------
フランスの絶対主義
------------------
アンリ4世をついだのがルイ13世(位1610~43)。かれに仕えた宰相がリシュリュー。リシュリューの名前はしっかりと覚えてください。『三銃士』などで敵役として登場するキャラクターですが、実際のリシュリューはフランスを発展させるために誠心誠意努力した人物。「余の第一の目標は国王の尊厳であり、第二は王国の盛大である」とはリシュリューの言葉。
ドイツで起きた三十年戦争にも介入して、領土を拡大するなど、この時代にフランスはヨーロッパの政治に大きな影響力を持つようになります。
次の王がルイ14世(位1643~1715)。フランス絶対主義を代表する王です。
わずか5歳で即位したので、小さい頃は宰相マザランが政治を運営しました。マザランもリシュリューと同じようにフランス王国と王権の発展をめざした。王権を強化するために貴族階級などの既得権を奪おうとしたため、貴族が反乱を起こす。これがフロンドの乱(1648~53)。一時期反乱軍がパリを占領し、マザランは幼いルイ14世をつれてパリから逃れたほどでしたが、最終的に反乱は鎮圧され、結果的に中央集権化が進みました。
1661年、成年に達したルイ14世の親政がはじまります。親政というのは、王が自分で政治をするということですよ。
ルイ14世の政治を見ていきましょう。
経済政策。コルベールという人物を大蔵大臣に任命して、重商主義政策を展開した。開店休業状態だったフランス東インド会社を再建し、海外貿易に乗り出しました。
文化奨励。今のわれわれがイメージとして思い浮かべるヨーロッパの王侯貴族の暮らしを作り出したのが、ルイ14世です。
宮廷貴族の礼儀作法、ファッションなど、この時代に確立したものが多い。
象徴的なのが、ヴェルサイユ宮殿の造営です。場所はパリから南西約20キロ離れたところ。ここに大規模で豪華な宮殿を建設した。宮殿には王、貴族、官僚など5000人が住んでいた。そして、宮殿の周囲の付属の建物に兵士や召使いなど1万5000人ほどが住んでいたという。宮殿というけれど、王が住むだけではなく政府の機能もここに移したから、新しい都市を建設したといった方がよい。
この写真はヴェルサイユ宮殿の中でも有名な鏡の間。幅10メートル、奥行き75メートルの大宴会場です。ここに大きなガラスと鏡がずっと並べられているわけだ。鏡というのは大きくすればするほどゆがみも大きくなる。当時、ゆがみの小さい、大きな鏡を作れるのはイタリアの特別なガラス工房しかなかった。一枚の鏡でも非常に高価だったそうで、それを惜しげもなく使っているのが鏡の間のミソ。文字通り夢の世界だったわけ。
こんな宮殿を造営した国王ルイ14世の威光は高まるばかり。ヨーロッパ中の君主のあこがれの的。のちに、ヴェルサイユ宮殿を真似した宮殿が世界中で造られます。日本の赤坂離宮、今は迎賓館になっていますが、これもヴェルサイユ宮殿をまねたものです。
フランスの貴族たちは、かつてのように王権に反抗するだけの力はない。王から年金をもらって暮らしているものもいる。少しでもルイ14世に「お近づきになりたい」と思っていたようです。王あっての貴族なのです。
ヴェルサイユ宮殿には王以外に貴族たちが住んでいたと言いました。貴族は全体としてはものすごい人数がいるので、ヴェルサイユ宮殿に住めるのはルイ14世のお気に入りの貴族だけです。ヴェルサイユ宮殿に住めるだけで貴族としての箔がつく。
ルイ14世も、そういう貴族心理をうまく見抜いて、自分をスーパースターとして演出していた。
朝起きる時から、着替え、食事、散歩と、すべての王の行動は儀式化されていて、選ばれた貴族たちがその儀式に参加することができる。コップやハンカチを王に渡す役が、貴族たちに割り振られていて、そういう役目をもらったら名誉なのです。食事がすんだら朝の散歩ですが、どの貴族が散歩にお供できるかは、王の指名によります。だから、散歩の前には貴族たちが宮殿の広間に詰めかける。王は、ぐるりと貴族たちを見渡して、「○○公爵、●●伯爵、・・・・」と、その日の散歩のお供を指名する。指名された貴族たちは、それこそ天にも昇る心持ちで散歩について行くわけです。
こういうときにルイ14世は、どういう基準で選ぶかというと、豪華でお金のかかった衣装・装飾を着けている者を選んだ。王のお供をする者は、ゴージャスでなければならないのです。だから、王の寵愛を得ようとするためには、借金をしてでもドレスアップをしなければならなかった。ファッションでフランスがヨーロッパ文化の華となるのには、こんな事情があったのです。ただし、こういうむなしい贅沢をつづけなければならないので、貴族たちの経済的な負担は大変でした。多くの貴族はますます政府、というのはルイ14世ですが、に頼らなければ経済的に成り立っていかなくなっていった。
ついでにファッションの話もしておこう。ルイ14世の肖像画、これが、ヨーロッパ最新のファッション。貴族のあこがれの的です。ズボンは短くて、足にぴったりのタイツをはいています。われわれが今はいているような長ズボンは、下層民の服で、貴族ははきません。
ヘアースタイルも特徴的。このくしゃくしゃとした長い髪、これは、カツラです。フランスでのカツラの大流行が、やがてヨーロッパ中に広がり、そのご正装として定着しました。モーツアルトやベートーベンの肖像画、見たことあるでしょう。かれらも長髪パーマでしょ。あれもカツラ。かれらはルイ14世の時代から100年以上あとの人たちです。イギリス国会上院の議長は今でもカツラをしている。さすがに伝統の国ですね。(ベートーベンのぼさぼさ頭の肖像画はカツラはつけていないそうです。ご指摘ありがとうございました。)
なぜ、カツラをするようになったかというと、ルイ13世に原因がある。ルイ13世は若禿でした。それで、カツラをかぶるようになったのですが、王様一人がカツラをかぶっていると禿をかくしているのがバレバレなので、取り巻きの貴族たちも同じようにカツラをするようになった。どうせするなら派手に、ということでこんな奇抜なカツラが誕生し、ルイ14世時代になると、これが正装にまでなったというわけ。
ちなみにルイ13世時代というのは、ユグノー戦争の混乱の余韻が残っていて、宮廷のマナーというのは滅茶苦茶だった。これではいかん、と考えた貴族の婦人たちによって、サロンというのがつくられて、ここから貴族らしいエチケットやマナー、おしゃれな会話がだんだんと普及するようになった。
それでも、ルイ13世の頃はまだまだひどかったらしい。とくにルイ13世その人が、エチケットとは縁遠い人だった。ルイ13世の成長記録が残っていて、それによると、かれが初めて入浴したのが7歳、顔を洗ったのが9歳だという。ヨーロッパではペストの流行以降、入浴の風習が廃れたんですね。入浴で感染すると考えられたのです。でも、ルイ13世は極端です。全然体を洗わない。当然臭い。ルイ13世のそばに仕えた女性によると、王に近づくと「腐った肉のようなにおい」がしたという。たまらんね。王を臭いと言っている女性も、入浴する風習がないから臭いわけ。やっぱり臭いのはイヤです。そこで、体臭を誤魔化すためにフランスで香水が発達した。体臭を誤魔化そうと考えることも、エチケットの観念が普及してきた証拠。
しかし、ルイ13世自身はそういうエチケットの観念とは対極にあった人で、気にくわない相手に口の中のモノを吐きかけたり、ズボンを穿いたままジャジャーッとオシッコをして、自分の不快感を表現したと伝えられている。野蛮人ですね。
宮廷のマナーが確立してくるのがルイ14世の時代。洗練された文化の中心としてヴェルサイユがヨーロッパのあこがれとなるのですが、それでも、今のわれわれの感覚で考えると、まだまだ変な風習はたくさんある。
有名なのはヴェルサイユ宮殿のトイレの話。ヴェルサイユ宮殿は住んでいる人の数に較べて、トイレの数が極端に少なかった。どこで用を足すかというと、オマルですね。ところが、みんながちゃんとオマルで用を足すわけではない。人のあまり通らない階段の踊り場などには、結構してあったという。それから、オマルの中身はどこに捨てるかというと、召使いの人たちがオマル抱えて庭園に出て、草木の陰にジャバッと捨てる。だから、見た目はきれいなヴェルサイユ宮殿の庭園も、香ばしい匂いが漂っていて、へたに林の中に足を踏み入れると、グチャッ、ということもあった。
話が、だいぶそれてしまいました。ルイ14世の政治に戻ります。
ルイ14世は、フランスの領土拡張のために積極的に外征をおこなった。
南ネーデルラント継承戦争(1667~68)、オランダ侵略戦争(1672~78)、ファルツ継承戦争(1689~97)。
さらに、スペイン継承戦争(1701~13)です。スペインのハプスブルク王家が途絶えたあと、ルイ14世は自分の孫をスペイン王にしようと考えた。そうなると将来は両国が合体するかもしれない。ブルボン家があまりにも大きくなりすぎるのを警戒した周辺諸国が、ルイ14世の孫の即位に反対する。その結果起きた戦争です。
この戦争は1713年のユトレヒト条約で終結します。この条約で、ルイ14世は自分の孫をスペイン王にする事を列国に認めさせることができました。ただし、将来にわたってフランスとスペインが合体しないことを条件として。また、この条約で、海外の植民地の多くを失いました。領土と引き換えに反対する国を買収したということです。特にイギリスが北アメリカや地中海に領土を増やして得をしました。
ルイ14世のフランスは、たびかさなる戦争で、少しばかり領土を拡大しますが、戦争の負担は重税という形で国民にのしかかった。これが、徐々にフランスの経済を悪化させていきます。
もう一つルイ14世の失政がある。これが、1685年の「ナントの勅令の廃止」です。この結果、信仰の自由を認められなくなったユグノーは、フランスから逃れてオランダなどに移住した。ユグノーは豊かな商工業者が多かったから、結果として富裕な市民階級がフランスからごっそりいなくなってしまった。結局、政府の税収は減るし、産業の発展という意味でも大きな損失となった。
ルイ14世治世の末期には、人口の一割が乞食同様だったという記録もある。農民反乱もしばしば起こりました。見た目の華やかさの陰で、フランスの政治、経済の矛盾は大きくなっていった。この矛盾が爆発するのが、ルイ14世の次の次の王、ルイ16世の時。フランス革命です
 第64回 フランスの絶対主義 おわり
第64回 フランスの絶対主義 おわり