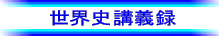第76回 北アメリカの植民地化
-----------------------------------
17世紀における北アメリカの植民地化
-----------------------------------
アメリカ合衆国の成立の話をする前に、北アメリカ大陸にヨーロッパ人がどのようにやってきたのかみておこう。
先住民はモンゴロイド系のアメリカン・インディアン。17世紀の北アメリカ大陸には、約100万人がいた。国家を形成していません。部族数500、言語系統が50あったというから、バラバラですね。生活の仕方も部族ごとにさまざまで、狩猟採集生活をしている部族もあれば、農耕をおこなっている部族もいた。
ここにヨーロッパ人がやってきた。来たのはスペイン、フランス、イギリスです。
最初にアメリカ大陸にやってきたスペインは、北米大陸の中西部を領有します。しかし、中南米や西インド諸島の経営が中心だったので、形式的なものにすぎなかった。地図の上で、ここはスペイン領ですよといっているだけです。実際に北アメリカの奥深くスペイン人が入り込んでいくわけではない。だから、アメリカ・インディアンたちも自分たちの住んでいる土地がスペインの領土になっているなんて、全然知らずに昔ながらの生活をしていました。
フランスは、セントローレンス川沿いとミシシッピ川沿いを領有する。それぞれカナダ、ルイジアナと呼ばれます。フランス人は、先住民との毛皮取引中心の植民地経営をおこなった。だから、先住民の土地を奪うこともなく、両者の関係は比較的友好的です。
イギリスは東海岸沿いに植民地を建設しました。イギリス人たちは、家族ぐるみで移住してきて、先住民から土地を奪って、農業をはじめる。ここが、スペインやフランスと違うところでした。ただ、イギリスも最初から農業をするつもりではありませんでした。どうして、農業をするようになったかみておきましょう。
最初にアメリカ大陸にやってきたイギリス植民者は、キャプテン・スミスという男に率いられた約100人のグループでした。この100人は全員が男です。これは、どういうことかというと、定住するつもりはないのです。定住するつもりなら、家族を連れてくるから、当然女性もいるはずなのです。
さて、キャプテン・スミスたちは何をしに来たかというと、黄金を探しにきた。インカやアステカみたいな黄金の国があるのではないかと、一攫千金を求めてやってきた連中でした。しかし、東海岸では黄金は出ません。かれらはそんなことはわからないから必死に探す。どうやって探すかというと、先住民を捕まえて、黄金の在処を聞こうとするのです。聞いてもないものは答えようがないのですが、スミスたちは、隠していると思って拷問まがいのこともしたらしい。はじめは、スミスたちと友好関係にあった先住民の部族も、当然ながら敵対するようになる。
1607年、スミスたちがつくった最初の町がジェームズタウンという。復元写真がありますから見てください。三角形の壁に囲まれた変わった形の町です。先住民アメリカン・インディアンの襲撃をさけるためにこんな作りになっているのです。
黄金探しはうまくいかない。やがて冬が近づいてきて、食料が底をついてきます。イギリスの船もなぜか到着しない。飢えに苦しんだジェームズタウンの住民は、先住民から食料をわけてもらうために奥地に出かけた。一行はキャプテン・スミスに率いられて、ポウハタン族という部族の集落へ行き、そこで酋長ポウハタンに食料をわけてくれるように交渉する。そのときの酋長の言葉が伝わっている。こんなことを言った。
「キャプテン・スミス殿。あなたがこの地に来たことについて、私は疑問をもっている。私は親切にしてあげたいのだが、この疑問があるので、それほど親切に救い手をさしのべるわけにはいかないのだ。というのは、あなたがこの土地に来たのは、交易のためでなく、私の人民を侵し、私の国をとってしまうためだ、と多くの人がいっているからだ。この人たちがあなたにトウモロコシをもって来ないのは、あなたがこの通り部下に武装させているのを見ているからだ。この恐怖をとり払ってわれわれを元気づけるよう、武器を船においていらっしゃい。ここでは武器は要らない。われわれはみな友人なのだから…
非常に筋が通っている。武器を船においていらっしゃい、というセリフを見るとスミスたちがそれまでどういう態度をとっていたか、想像できますね。
さて、こういわれたキャプテン・スミスはどうしたか。一説によると、いきなり酋長の横に立っていた弟を、ぐいっと引き寄せて、その頭にライフルの銃口を突きつけながらこう言った。
「トウモロコシを船に積め、さもないとお前らの死体を積むぞ」。
滅茶苦茶です。武器で脅されて、ポウハタン族はイギリス人に食料を供給することになり、ジェームズタウンの人々は冬を乗り切った、というのです。
ところが、これとはまったく違う話も伝わっています。
このバージョンでは、食料を求めて奥地に分け入ったキャプテン・スミスたちはポウハタン族に捕らえられる。村の広場に連行されたスミスたちは処刑されることになった。スミスが広場の真ん中に引き出されて、両手両足を押さえられてうつぶせに寝かされる。そして、今まさにスミスの首が切り落とされるというそのときに、一人の乙女が飛び出してきてスミスの上にかぶさって、命乞いをするのです。「この白人の男は、きっと悪い人ではありません。どうか命を助けてやって下さい」とね。この女性がポカホンタスといって、酋長ポウハタンの娘でした。娘の願いに負けてしまって、酋長はスミスたちを許す。さらに、食料までもらってジェームズタウンに帰ることができた、という。ポカホンタスもスミスとともにジェームズタウンへ行った。
なぜ、ポカホンタスがキャプテン・スミスを助けたかというと、これは一目惚れということです。
全然違う二つの話。どちらを信じますか。常識的に考えて、ポカホンタス・バージョンはイギリス人たちが作り上げた伝説でしょうね。
ただ、ポカホンタスというアメリカン・インディアンの娘は実在しているのです。実際に、ジェームズタウンに住んでイギリス男性と結婚して子どもも生まれています。ただし、夫になったのは、キャプテン・スミスではなくて、ジョン・ロルフという人物ですが。
実際のポカホンタスは、人質として、ジェームズタウンに無理矢理連れてこられたのではないでしょうか。ただ、現在のアメリカ合衆国の主流派である白人たちにとっては、少々後ろめたい話なので、それを、恋愛物語に仕立てて語り伝えてきたのではないかと思います。このポスター、覚えがある人いますか。ディズニー映画で数年前に公開された『ポカホンタス』。恋愛バージョンの話を映画化したものです。
ともかく、先住民の娘ポカホンタスはジェームズタウンでイギリス人と一緒に生活するようになった。彼女は先住民の農業をイギリス人に教えました。そして、ここが重要なのですが、彼女はタバコ栽培を教えた。
コロンブス以来、ヨーロッパに喫煙の風習が伝えられて、流行しはじめていました。だから、タバコを栽培してヨーロッパに輸出すればいい儲けになる。ジェームズタウンの人々は黄金は発見できなかったけれど、タバコ栽培で成功したのです。これ以後、イギリスからタバコ栽培目的で移住してくる人が増える。イギリスの植民地が農業中心になるのはこれ以来です。
ジェームズタウンのある場所は、ヴァージニア植民地という。現在は、ヴァージニア州。今でも、タバコ栽培をやっている。ヴァージニア・スリムというタバコの宣伝、見たことあるでしょ。
ヴァージニア植民地がイギリス最初の植民地で、その後、いろいろなグループが移住してきて植民地を建設します。アメリカ大陸に移住するグループはそれぞれ国王から場所を指定した許可状を交付される。それぞれにナントカ植民地という名前を付けます。基本的には植民地どうしの横のつながりはありません。
なかには、イギリス本国で迫害を受けたピューリタンたちが信仰の自由を求めて建設した植民地もあります。1620年、ピルグリム=ファーザーズというグループが建設したプリマス植民地です。
1732年に成立したジョージア植民地までで、13の植民地が成立します。13植民地が発展して、現在のアメリカ合衆国になるのです。
----------------
13植民地の暮らし
----------------
13植民地の人々はどんな暮らしぶりだったのでしょうか。13植民地でベストセラーになった『貧しきリチャードの暦』を通して見てみたいと思います。『貧しきリチャードの暦』を出版したのはベンジャミン・フランクリン(1706~1790)という人です。
フランクリンは名前を聞いたことがあると思う。現在のアメリカでも人気のある人です。いろいろな分野で活躍して名前を残しているのですが、かれの人生は、アメリカ人の理想像の典型です。
フランクリンは父親の代にアメリカ大陸に移住してきて、父親はボストンでロウソクや石鹸をつくっていた。家は貧しかったので、小学校も満足に行っていません。12歳で印刷屋をやっていたお兄さんのところで働きはじめるのですが、兄貴とうまくいかず、17歳の時に無一文でボストンを離れて、フィラデルフィアにやってきます。ここで、印刷工として働いて、22歳の時には独立して自分の印刷所を持つようになる。
とにかくまじめに働くし、いろいろなことに好奇心を持って、自分の頭で考えることが大好きな人だったのです。
当時、印刷所はカレンダーをつくって売っていました。今でも、カレンダーは印刷会社が作るんだけれど、たいていの家庭では、買わないでしょ。仕事の関係とか、どこかのお店で年末になるとくれるよね。フランクリンの時代の13植民地では、誰もカレンダーをくれたりしない。買うしかないので、カレンダーは絶対売れます。だから、どこの印刷所でもカレンダーを印刷して販売していた。ところで、カレンダーというのは、1から31までの数字と曜日さえ書いてあればいいので、どこの印刷所のカレンダーも同じようなものです。
フランクリンは、ここで知恵をしぼった。たくさん売れるためには独自性を出さないといけない。そこで思いついたのが、カレンダーの余白に「ことわざ」を印刷することでした。聖書をはじめとするいろいろな本から、人生訓的なものを探し出してカレンダーを埋め尽くす。足りなかったら、自分でことわざをつくる。そうして、出来上がったのが『貧しきリチャードの暦』というカレンダー。これが、ものすごい人気を呼んで、売れる売れる。これで、フランクリンは有名になり、金持ちになる。『貧しきリチャードの暦』はロングセラーにもなって、ことわざを入れ替えながら、これ以後25年間出版されつづけます。これだけ売れたのは、「ことわざ」を入れるという工夫のせいだけではなくて、フランクリンの選んだ「ことわざ」そのものに、当時の植民地の人々を揺り動かす何かがあったと考えられます。
いったいどんな「ことわざ」が載っていたのか。
「女と灯火のない家庭は魂のない人のようだ」
「軽い財布、重い心」
「よく愛し、よく鞭打て」
「生きるために食い、食うために生きるのではない」
「金をためすには火、女をためすには金、男をためすには女」
「寝ている狐は一羽の鳥も捕まえない」
「怠惰は何でもことをむずかしくするが、勤勉はすべてをたやすくする」
「仕事を追い、仕事に追われるな」
「早起きは人を健康に、金持ちに、賢くする」
「必要のないものを買えば、まもなく必要のあるものを売らなければならなくなる」
「御馳走が多いと意志がやせる」
「天は自ら助くるものを助く」
「今日の一日は明日の二日」
「空の袋は立ちにくい」
どこかで聞いたことのあるようなものばかりでしょ。フランクリンの「ことわざ」をずうっと読んでいくと、共通点がいくつか見えてきます。かれが繰り返し繰り返し訴えているのは、勤勉、節約、蓄財、です。働きなさい、無駄遣いはいけません、貯めなさい。まさしくカルヴァン派、ピューリタンの教えですね。言っていることは理解できます。理解できますが、現在の日本に住んでいる私たちにとってはピンとこないところもある。
たとえば、「早起きは人を健康に、金持ちに、賢くする」ということわざ。「早起きは三文の得」と翻訳されて、日本でも有名です。しかし、早起きすれば健康にはいいだろうけれど、金持ちになりますか。9時から仕事が始まるサラリーマンが朝の4時に起きて5時に会社についても、給料あがりません。まだ、シャッターは閉まっています。
しかし、13植民地の人々は、このことわざを読んで、なるほど、そうだ、早起きして金持ちになろうと、納得したに違いない。そうでなければ、『貧しきリチャードの暦』がベストセラーになるはずがないのです。
早起きしたら金持ちになる仕事ってなんですか。それを、実感できる仕事とは。
農業ですよ。植民地に渡ってきた人たちの多くは農業をしている。しかも、特別な環境だった。なぜなら、土地はいくらでもある。未開の荒野がいくらでも広がっているのです。早起きして、一坪でも開墾すれば、それが自分の農地となり、翌年の収穫増加につながる。働けば働くほど土地が手にはいるという環境だったのが、当時の13植民地なのです。そして、フランクリンは農民たちに、気を抜かずに頑張りや、と応援をしているというわけ。
NHKで何度も再放送されている『大草原の小さな家』、あのドラマにでてくるインガルス家のお父さん、あのイメージです。大きな農場を経営しているような農民ではなく、自分の力だけでやっている自営農民です。
頑張るのは、あくまでも自分です。「天は自ら助くるものを助く」。自助努力の精神とかフロンティア・スピリットとか、アメリカ人の精神的な柱のようなものがつくられてくるのです。
そして、頑張れと言っているフランクリン自身が、自分の才覚と努力で一文無しから大金持ちになっているわけで、アメリカンドリームを最初に実現した人だから、説得力がある。
フランクリンの言葉を紹介しておこう。
「ヨーロッパでは名門に価値があるが、…アメリカでは他人のことを『あの人はどういう身分か?』とは聞かないで、『あの人は何ができるか?』と聞くのである。その人に有用な技能があれば歓迎されるし、それをやってうまくできれば、彼を知る者から尊敬される。だが、ただ家柄がよいというだけの人が、そのためだけの理由で、何か官職か俸給を得て、社会に寄食しようとすれば、軽蔑され無視されるであろう」
フランクリンは印刷所で成功を収めたあとは、別の分野に興味を持つ。
当時、発達しはじめていた科学のなかでも電気科学の分野はいろいろな仮説が出されていた。フランクリンは持ち前の好奇心で電気の研究を始めます。
有名なのが雷の研究。フランクリンは、雷は電気ではないかという説を立てて、嵐の日に凧を飛ばす。有名な実験です。そしたら、見事に凧に雷が落ちた。凧には電線がつけてあって、フランクリンの足下に置かれた蓄電池に、見事に電気が伝わってきたのです。この研究で、電気科学の研究者としてヨーロッパでも有名になります。ちなみに、凧を持っていたフランクリンはなぜ感電しなかったのかと思うでしょ。運がいいんです。フランクリンの実験を知って、スウェーデンかどこかの科学者が追試をしたのですが、その人は感電して死んでしまった。本当の話です。
そのほか、フランクリンの活動はとどまるところを知りません。ストーブの改良、アメリカではじめての図書館の設立、奴隷制度反対協会設立、等々。晩年は政治家、外交官としても活躍して、アメリカ独立に貢献した。独立宣言の起草者の一人でもあります。肖像画を見ても、好々爺でしょ。人なつっこそうな表情で、誰にでも陽気に声をかけて冗談をとばしそう。「最初のアメリカ人」なのです。
最後にフランクリンと先住民との関係について。
さきほど、未開の荒野が無限に広がっていると言いましたが、その荒野には遙か昔から先住民が住んでいる。だから、自営農民たちにとってはアメリカン・インディアンは邪魔です。いなくなって欲しい存在。農民にエールを贈るフランクリンの立場も同じです。奴隷制度に反対していたフランクリンがインディアンに関してこんな言葉を残しています。
「ラム酒はインディアンを消してしまうために、神が我々にあたえたもうた」
白人たちが、インディアンから土地を奪うときによく使った手なのですが、ラム酒を持ってインディアンの村に挨拶に行く。一緒に食事をして、「飲め飲め」とラム酒をすすめる。ラム酒は強いお酒です。インディアンたちはそんな強い酒を飲んだことがないから、ぐでんぐでんに酔っぱらってしまう。前後不覚になったところで、土地の譲渡契約書に無理矢理サインをさせて、さっと引き上げる。
翌日になると、インディアンの土地に杭を打ち込んで囲い込みます。インディアンが抗議に来ると、契約書を見せて、お前はこの土地を俺に譲ると署名したんだ、とつっぱねる。合法性をよそおって、先住民から土地を奪うためのツールがラム酒だったのです。フランクリンはそのラム酒を讃えているというわけ。
この辺が、アメリカ史の複雑なところです。
フランスは、セントローレンス川沿いとミシシッピ川沿いを領有する。それぞれカナダ、ルイジアナと呼ばれます。フランス人は、先住民との毛皮取引中心の植民地経営をおこなった。だから、先住民の土地を奪うこともなく、両者の関係は比較的友好的です。
イギリスは東海岸沿いに植民地を建設しました。イギリス人たちは、家族ぐるみで移住してきて、先住民から土地を奪って、農業をはじめる。ここが、スペインやフランスと違うところでした。ただ、イギリスも最初から農業をするつもりではありませんでした。どうして、農業をするようになったかみておきましょう。
最初にアメリカ大陸にやってきたイギリス植民者は、キャプテン・スミスという男に率いられた約100人のグループでした。この100人は全員が男です。これは、どういうことかというと、定住するつもりはないのです。定住するつもりなら、家族を連れてくるから、当然女性もいるはずなのです。
さて、キャプテン・スミスたちは何をしに来たかというと、黄金を探しにきた。インカやアステカみたいな黄金の国があるのではないかと、一攫千金を求めてやってきた連中でした。しかし、東海岸では黄金は出ません。かれらはそんなことはわからないから必死に探す。どうやって探すかというと、先住民を捕まえて、黄金の在処を聞こうとするのです。聞いてもないものは答えようがないのですが、スミスたちは、隠していると思って拷問まがいのこともしたらしい。はじめは、スミスたちと友好関係にあった先住民の部族も、当然ながら敵対するようになる。
1607年、スミスたちがつくった最初の町がジェームズタウンという。復元写真がありますから見てください。三角形の壁に囲まれた変わった形の町です。先住民アメリカン・インディアンの襲撃をさけるためにこんな作りになっているのです。
黄金探しはうまくいかない。やがて冬が近づいてきて、食料が底をついてきます。イギリスの船もなぜか到着しない。飢えに苦しんだジェームズタウンの住民は、先住民から食料をわけてもらうために奥地に出かけた。一行はキャプテン・スミスに率いられて、ポウハタン族という部族の集落へ行き、そこで酋長ポウハタンに食料をわけてくれるように交渉する。そのときの酋長の言葉が伝わっている。こんなことを言った。
「キャプテン・スミス殿。あなたがこの地に来たことについて、私は疑問をもっている。私は親切にしてあげたいのだが、この疑問があるので、それほど親切に救い手をさしのべるわけにはいかないのだ。というのは、あなたがこの土地に来たのは、交易のためでなく、私の人民を侵し、私の国をとってしまうためだ、と多くの人がいっているからだ。この人たちがあなたにトウモロコシをもって来ないのは、あなたがこの通り部下に武装させているのを見ているからだ。この恐怖をとり払ってわれわれを元気づけるよう、武器を船においていらっしゃい。ここでは武器は要らない。われわれはみな友人なのだから…
非常に筋が通っている。武器を船においていらっしゃい、というセリフを見るとスミスたちがそれまでどういう態度をとっていたか、想像できますね。
さて、こういわれたキャプテン・スミスはどうしたか。一説によると、いきなり酋長の横に立っていた弟を、ぐいっと引き寄せて、その頭にライフルの銃口を突きつけながらこう言った。
「トウモロコシを船に積め、さもないとお前らの死体を積むぞ」。
滅茶苦茶です。武器で脅されて、ポウハタン族はイギリス人に食料を供給することになり、ジェームズタウンの人々は冬を乗り切った、というのです。
ところが、これとはまったく違う話も伝わっています。
このバージョンでは、食料を求めて奥地に分け入ったキャプテン・スミスたちはポウハタン族に捕らえられる。村の広場に連行されたスミスたちは処刑されることになった。スミスが広場の真ん中に引き出されて、両手両足を押さえられてうつぶせに寝かされる。そして、今まさにスミスの首が切り落とされるというそのときに、一人の乙女が飛び出してきてスミスの上にかぶさって、命乞いをするのです。「この白人の男は、きっと悪い人ではありません。どうか命を助けてやって下さい」とね。この女性がポカホンタスといって、酋長ポウハタンの娘でした。娘の願いに負けてしまって、酋長はスミスたちを許す。さらに、食料までもらってジェームズタウンに帰ることができた、という。ポカホンタスもスミスとともにジェームズタウンへ行った。
なぜ、ポカホンタスがキャプテン・スミスを助けたかというと、これは一目惚れということです。
全然違う二つの話。どちらを信じますか。常識的に考えて、ポカホンタス・バージョンはイギリス人たちが作り上げた伝説でしょうね。
ただ、ポカホンタスというアメリカン・インディアンの娘は実在しているのです。実際に、ジェームズタウンに住んでイギリス男性と結婚して子どもも生まれています。ただし、夫になったのは、キャプテン・スミスではなくて、ジョン・ロルフという人物ですが。
実際のポカホンタスは、人質として、ジェームズタウンに無理矢理連れてこられたのではないでしょうか。ただ、現在のアメリカ合衆国の主流派である白人たちにとっては、少々後ろめたい話なので、それを、恋愛物語に仕立てて語り伝えてきたのではないかと思います。このポスター、覚えがある人いますか。ディズニー映画で数年前に公開された『ポカホンタス』。恋愛バージョンの話を映画化したものです。
ともかく、先住民の娘ポカホンタスはジェームズタウンでイギリス人と一緒に生活するようになった。彼女は先住民の農業をイギリス人に教えました。そして、ここが重要なのですが、彼女はタバコ栽培を教えた。
コロンブス以来、ヨーロッパに喫煙の風習が伝えられて、流行しはじめていました。だから、タバコを栽培してヨーロッパに輸出すればいい儲けになる。ジェームズタウンの人々は黄金は発見できなかったけれど、タバコ栽培で成功したのです。これ以後、イギリスからタバコ栽培目的で移住してくる人が増える。イギリスの植民地が農業中心になるのはこれ以来です。
ジェームズタウンのある場所は、ヴァージニア植民地という。現在は、ヴァージニア州。今でも、タバコ栽培をやっている。ヴァージニア・スリムというタバコの宣伝、見たことあるでしょ。
ヴァージニア植民地がイギリス最初の植民地で、その後、いろいろなグループが移住してきて植民地を建設します。アメリカ大陸に移住するグループはそれぞれ国王から場所を指定した許可状を交付される。それぞれにナントカ植民地という名前を付けます。基本的には植民地どうしの横のつながりはありません。
なかには、イギリス本国で迫害を受けたピューリタンたちが信仰の自由を求めて建設した植民地もあります。1620年、ピルグリム=ファーザーズというグループが建設したプリマス植民地です。
1732年に成立したジョージア植民地までで、13の植民地が成立します。13植民地が発展して、現在のアメリカ合衆国になるのです。
----------------
13植民地の暮らし
----------------
13植民地の人々はどんな暮らしぶりだったのでしょうか。13植民地でベストセラーになった『貧しきリチャードの暦』を通して見てみたいと思います。『貧しきリチャードの暦』を出版したのはベンジャミン・フランクリン(1706~1790)という人です。
フランクリンは名前を聞いたことがあると思う。現在のアメリカでも人気のある人です。いろいろな分野で活躍して名前を残しているのですが、かれの人生は、アメリカ人の理想像の典型です。
フランクリンは父親の代にアメリカ大陸に移住してきて、父親はボストンでロウソクや石鹸をつくっていた。家は貧しかったので、小学校も満足に行っていません。12歳で印刷屋をやっていたお兄さんのところで働きはじめるのですが、兄貴とうまくいかず、17歳の時に無一文でボストンを離れて、フィラデルフィアにやってきます。ここで、印刷工として働いて、22歳の時には独立して自分の印刷所を持つようになる。
とにかくまじめに働くし、いろいろなことに好奇心を持って、自分の頭で考えることが大好きな人だったのです。
当時、印刷所はカレンダーをつくって売っていました。今でも、カレンダーは印刷会社が作るんだけれど、たいていの家庭では、買わないでしょ。仕事の関係とか、どこかのお店で年末になるとくれるよね。フランクリンの時代の13植民地では、誰もカレンダーをくれたりしない。買うしかないので、カレンダーは絶対売れます。だから、どこの印刷所でもカレンダーを印刷して販売していた。ところで、カレンダーというのは、1から31までの数字と曜日さえ書いてあればいいので、どこの印刷所のカレンダーも同じようなものです。
フランクリンは、ここで知恵をしぼった。たくさん売れるためには独自性を出さないといけない。そこで思いついたのが、カレンダーの余白に「ことわざ」を印刷することでした。聖書をはじめとするいろいろな本から、人生訓的なものを探し出してカレンダーを埋め尽くす。足りなかったら、自分でことわざをつくる。そうして、出来上がったのが『貧しきリチャードの暦』というカレンダー。これが、ものすごい人気を呼んで、売れる売れる。これで、フランクリンは有名になり、金持ちになる。『貧しきリチャードの暦』はロングセラーにもなって、ことわざを入れ替えながら、これ以後25年間出版されつづけます。これだけ売れたのは、「ことわざ」を入れるという工夫のせいだけではなくて、フランクリンの選んだ「ことわざ」そのものに、当時の植民地の人々を揺り動かす何かがあったと考えられます。
いったいどんな「ことわざ」が載っていたのか。
「女と灯火のない家庭は魂のない人のようだ」
「軽い財布、重い心」
「よく愛し、よく鞭打て」
「生きるために食い、食うために生きるのではない」
「金をためすには火、女をためすには金、男をためすには女」
「寝ている狐は一羽の鳥も捕まえない」
「怠惰は何でもことをむずかしくするが、勤勉はすべてをたやすくする」
「仕事を追い、仕事に追われるな」
「早起きは人を健康に、金持ちに、賢くする」
「必要のないものを買えば、まもなく必要のあるものを売らなければならなくなる」
「御馳走が多いと意志がやせる」
「天は自ら助くるものを助く」
「今日の一日は明日の二日」
「空の袋は立ちにくい」
どこかで聞いたことのあるようなものばかりでしょ。フランクリンの「ことわざ」をずうっと読んでいくと、共通点がいくつか見えてきます。かれが繰り返し繰り返し訴えているのは、勤勉、節約、蓄財、です。働きなさい、無駄遣いはいけません、貯めなさい。まさしくカルヴァン派、ピューリタンの教えですね。言っていることは理解できます。理解できますが、現在の日本に住んでいる私たちにとってはピンとこないところもある。
たとえば、「早起きは人を健康に、金持ちに、賢くする」ということわざ。「早起きは三文の得」と翻訳されて、日本でも有名です。しかし、早起きすれば健康にはいいだろうけれど、金持ちになりますか。9時から仕事が始まるサラリーマンが朝の4時に起きて5時に会社についても、給料あがりません。まだ、シャッターは閉まっています。
しかし、13植民地の人々は、このことわざを読んで、なるほど、そうだ、早起きして金持ちになろうと、納得したに違いない。そうでなければ、『貧しきリチャードの暦』がベストセラーになるはずがないのです。
早起きしたら金持ちになる仕事ってなんですか。それを、実感できる仕事とは。
農業ですよ。植民地に渡ってきた人たちの多くは農業をしている。しかも、特別な環境だった。なぜなら、土地はいくらでもある。未開の荒野がいくらでも広がっているのです。早起きして、一坪でも開墾すれば、それが自分の農地となり、翌年の収穫増加につながる。働けば働くほど土地が手にはいるという環境だったのが、当時の13植民地なのです。そして、フランクリンは農民たちに、気を抜かずに頑張りや、と応援をしているというわけ。
NHKで何度も再放送されている『大草原の小さな家』、あのドラマにでてくるインガルス家のお父さん、あのイメージです。大きな農場を経営しているような農民ではなく、自分の力だけでやっている自営農民です。
頑張るのは、あくまでも自分です。「天は自ら助くるものを助く」。自助努力の精神とかフロンティア・スピリットとか、アメリカ人の精神的な柱のようなものがつくられてくるのです。
そして、頑張れと言っているフランクリン自身が、自分の才覚と努力で一文無しから大金持ちになっているわけで、アメリカンドリームを最初に実現した人だから、説得力がある。
フランクリンの言葉を紹介しておこう。
「ヨーロッパでは名門に価値があるが、…アメリカでは他人のことを『あの人はどういう身分か?』とは聞かないで、『あの人は何ができるか?』と聞くのである。その人に有用な技能があれば歓迎されるし、それをやってうまくできれば、彼を知る者から尊敬される。だが、ただ家柄がよいというだけの人が、そのためだけの理由で、何か官職か俸給を得て、社会に寄食しようとすれば、軽蔑され無視されるであろう」
フランクリンは印刷所で成功を収めたあとは、別の分野に興味を持つ。
当時、発達しはじめていた科学のなかでも電気科学の分野はいろいろな仮説が出されていた。フランクリンは持ち前の好奇心で電気の研究を始めます。
有名なのが雷の研究。フランクリンは、雷は電気ではないかという説を立てて、嵐の日に凧を飛ばす。有名な実験です。そしたら、見事に凧に雷が落ちた。凧には電線がつけてあって、フランクリンの足下に置かれた蓄電池に、見事に電気が伝わってきたのです。この研究で、電気科学の研究者としてヨーロッパでも有名になります。ちなみに、凧を持っていたフランクリンはなぜ感電しなかったのかと思うでしょ。運がいいんです。フランクリンの実験を知って、スウェーデンかどこかの科学者が追試をしたのですが、その人は感電して死んでしまった。本当の話です。
そのほか、フランクリンの活動はとどまるところを知りません。ストーブの改良、アメリカではじめての図書館の設立、奴隷制度反対協会設立、等々。晩年は政治家、外交官としても活躍して、アメリカ独立に貢献した。独立宣言の起草者の一人でもあります。肖像画を見ても、好々爺でしょ。人なつっこそうな表情で、誰にでも陽気に声をかけて冗談をとばしそう。「最初のアメリカ人」なのです。
最後にフランクリンと先住民との関係について。
さきほど、未開の荒野が無限に広がっていると言いましたが、その荒野には遙か昔から先住民が住んでいる。だから、自営農民たちにとってはアメリカン・インディアンは邪魔です。いなくなって欲しい存在。農民にエールを贈るフランクリンの立場も同じです。奴隷制度に反対していたフランクリンがインディアンに関してこんな言葉を残しています。
「ラム酒はインディアンを消してしまうために、神が我々にあたえたもうた」
白人たちが、インディアンから土地を奪うときによく使った手なのですが、ラム酒を持ってインディアンの村に挨拶に行く。一緒に食事をして、「飲め飲め」とラム酒をすすめる。ラム酒は強いお酒です。インディアンたちはそんな強い酒を飲んだことがないから、ぐでんぐでんに酔っぱらってしまう。前後不覚になったところで、土地の譲渡契約書に無理矢理サインをさせて、さっと引き上げる。
翌日になると、インディアンの土地に杭を打ち込んで囲い込みます。インディアンが抗議に来ると、契約書を見せて、お前はこの土地を俺に譲ると署名したんだ、とつっぱねる。合法性をよそおって、先住民から土地を奪うためのツールがラム酒だったのです。フランクリンはそのラム酒を讃えているというわけ。
この辺が、アメリカ史の複雑なところです。
 第76回 北アメリカの植民地化 おわり
第76回 北アメリカの植民地化 おわり