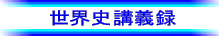第90回 19世紀中頃のロシア
-------------
クリミア戦争
------------
ロシアは、19世紀半ばになってもツァーリズムと呼ばれる皇帝の専制政治がつづき、自由主義思想は厳しく弾圧されていました。ウィーン体制崩壊後のヨーロッパの政治の流れから完全に取り残されているのですが、広大な領土と、強大な陸軍力でヨーロッパの国際関係の中で大きな位置を持ちつづけます。
ロシアは18世紀中頃から、南下政策という外交戦略を立てています。ロシアは領土は広いが、内陸部が多く、わずかな海岸線は緯度が高い。冬になると港は皆凍ってしまうのです。海外貿易をすすめていくうえで、冬でも凍らない不凍港が是非とも欲しかった。そのため南へ南へと領土を拡大してきた。
ロシアの南にあるのがオスマン帝国です。16世紀の最盛期には、東地中海をとりまく大帝国としてヨーロッパ諸国に脅威をあたえていましたが、17世紀後半からじょじょに衰えています。19世紀にはいると、ギリシアが独立、エジプトも自立。そして、何度かの戦争で、ロシアに北方の領土を少しずつ削り取られていきます。
衰えかけているオスマン帝国をねらって、ロシアだけでなく、イギリスやフランスがこの地域に勢力を拡大する機会をうかがいはじめます。オスマン帝国をめぐるヨーロッパ列国の利権争いが、19世紀の国際紛争の焦点です。これを東方問題という。
さて、ロシアが不凍港を求めて南下政策をすすめながら、目標としたのが黒海です。地図で場所と形を確認して下さいね。オスマン帝国が元気なときは、黒海の周囲はすべてオスマン帝国領でしたが、18世紀末エカチェリーナ2世の時代に、黒海北岸のクリミア半島を獲得しました。黒海は冬でも凍りません。これで、不凍港を手に入れたわけですが、大きな問題があった。黒海にロシア船を浮かべることができても、地中海へ出なければ、どこにも行けません。ところが、黒海と地中海のあいだには、滅茶苦茶に狭い海峡が二カ所もある。ボスフォラス海峡とダーダネルス海峡です。必ず地図で確認すること。ボスフォラス海峡はオスマン帝国の首都イスタンブールに面する海です。重要な軍事的要所でもある。オスマン帝国にとって宿敵ロシアの船が、この海峡を通過するのに「はいはい、どうぞ」と通してくれるはずがないのです。
だから、次の段階として、ロシアはオスマン帝国から海峡の通航権を得なければならない。
ロシアは18世紀末以降もオスマン帝国と紛争を繰り返し、そのたびに両海峡の通航権をあたえられたり停止されたりしています。1829年以後、ロシアは商船の通航権を得て、小麦を大量に輸出するようになる。ただ、通航できるのは商船だけで、軍艦は許可されていませんでした。
ところが、1831年から33年までと、1839年から1840年の二回にわたってエジプト・トルコ戦争という戦争がおきて、この時にオスマン帝国は、ロシアに軍艦の通航を許可する。
エジプトはもともとオスマン帝国の領土ですが、ナポレオンのフランス軍に一時占領されたあと、総督のムハンマド=アリーという人物が、オスマン帝国から事実上独立した。そして、さらに領土を拡大しようとしておこした戦争が、エジプト・トルコ戦争。
エジプトは、連戦連勝。しかも、そのバックにはフランスがついているのです。フランスは、エジプトを援助して利権を拡大しようという魂胆がある。
オスマン帝国は、これに対抗するため、ロシアに海峡の軍艦通航権をあたえて味方につけようとしたわけです。
エジプトが勝てばフランス、オスマン帝国が勝てばロシアが、この地域に勢力を拡大することになる。それをおそれたイギリスが、この戦争に介入してくる。当時イギリスが最強ですし、外交手腕も抜群でした。だから、最後はイギリス主導で戦争の決着がつけられた。
エジプトは占領した領土をオスマン帝国に返す。そのかわりムハンマド=アリーの一族がエジプト総督の地位を世襲することを認められる。事実上のエジプト王国です。オスマン帝国に対しては、ロシアにあたえた海峡の軍艦通航権を取り消させました。結局、ロシアの南下政策はイギリスによって挫折したのです。
この間、1838年、イギリスはオスマン帝国と不平等条約を結んでいます。イギリスもオスマン帝国を狙っているのです。だから、南下政策をくわだてるロシアと利害が激しく対立するようになる。
1853年から56年にかけて、ロシアとイギリス、フランス、オスマン帝国のあいだでおきたのがクリミア戦争です。
戦争のきっかけは、フランスがオスマン帝国から聖地イェルサレムの管理権を得たのに対抗して、ロシアがオスマン帝国に、オスマン帝国領土内のギリシア正教徒保護権を要求して、拒否されたこと。わかりにくいですね。
オスマン帝国は、現在のルーマニア、ブルガリア、セルビアなどがあるバルカン半島を支配していました。ここは、キリスト教のギリシア正教の信者が多数。そして、ロシアはギリシア正教徒の保護者であると自認しているので、保護権を要求した。そのことによって、バルカン半島に勢力を拡大しようとしているわけです。オスマン帝国としては、ロシアが自国の領土に干渉してくることは、当然拒否する。そこで、戦争となった。
すぐに、ロシアの南下を阻止したいイギリスとフランスが、オスマン帝国と同盟を結び、参戦します。また、イタリア半島の小国サルディニア王国も、英仏側にたって参戦しました。
主戦場が黒海に突き出たクリミア半島。そこで、クリミア戦争という名がつけられている。とくに、クリミア半島にあるロシアのセヴァストーポリ要塞の攻防戦は両軍ともに多数の死傷者を出した激戦として有名です。
この戦争は、産業革命によって工業化を進めつつあるイギリス・フランスと、遅れをとったロシアとの力の違いをはっきりと世界にしめしました。
ロシアは兵力100万。しかも戦場は、自国もしくはその周辺。英仏はあわせて兵力7万。しかも、本国から遠く離れた戦場です。これだけ見れば、ロシアが圧倒的に優勢なはずですが、ふたを開けてみればロシアは大苦戦して、1856年パリ条約で事実上敗北を認めた。
ハッキリ言って、ロシア軍の装備はナポレオン戦争の時からほとんど進歩がない。ロシア軍の大砲の着弾距離は、英仏軍の半分しかなかったといいます。技術力の違いです。さらに、ロシアは戦場に武器弾薬糧食、兵員を輸送するのに、荷馬車を使った。道路は舗装されていないので、雨でも降ると道はぬかるんで馬車はすすめない。思うように、戦場に物資が輸送できなかった。一方の英仏は、蒸気船で本国からどんどん物資を輸送する。さらに、港から戦場まで鉄道を敷設して前線に武器弾薬を運んだ。部隊の駐屯地には水道も設けた。工業力の違いがはっきりと出たのです。本国から遠い英仏軍の方が、輸送が円滑、兵士への補給は順調。
また、ロシア軍の一般兵士や輸送の人夫は、農奴が徴発されて嫌々やっている。戦争に勝とうが負けようがどうでもいい。早く終わって無事に家に帰りたいだけです。一方の英仏は、すでに市民社会が成立している。自分たちが払った税金でおこなわれている戦争の成り行きに注目している。イギリスの新聞社は、戦場に特派員を派遣して、毎日の戦況を報道しているくらいです。これは、世界初の従軍記者です。最新のニュースは、蒸気船や発明されて間もない電信で伝えられる。現代の報道の原型が、クリミア戦争ですでにあらわれているのですね。
イギリスのナイチンゲールが従軍看護婦として活躍して有名になったのも、この戦争です。ナイチンゲールは、新聞報道で激戦の様子を知り、負傷者の看護をしたいと考えたのです。仲間の看護婦を募って戦場に出かけて負傷者の看護に尽くしました。野戦病院の衛生状態を改善して、負傷者の死亡率を40%から2%に引き下げたという。劇的な改善ですね。
彼女の偉いところは、敵味方の区別なく、すべての負傷者の手当をしたこと。この人道的なおこないが、のちの1864年の国際赤十字の設立につながっていきます。もうひとつの功績は、看護婦の地位を高めたことです。看護婦というのは、ナイチンゲールが有名になるまでは下層階級の女性がおこなうどちらかというと卑しい仕事、召使いの仕事と見られていました。確かに、他人の血や膿に触れたりするし、下の世話も必要だし、伝染病がうつるかもしれないし、楽できれいで安全な仕事ではない。ところが、ナイチンゲールは、上流階級のお金持ちのお嬢さんだったにもかかわらず、この仕事に誇りを持って取り組んだ。彼女の活動が、看護婦を女性の仕事として価値あるものに高めたのです。
ちなみに、肖像画を見ると、ナイチンゲールは黒い服を着ていますね。彼女は黒衣の貴婦人。看護婦が白衣の天使になるのはもっと後のことのようです。(現在は看護師とよび、男女の区別をしませんが、今日のように女性の社会進出が一般的ではなかった時代には、働く女性の代表的な仕事でした。現在の視点から19世紀のナイチンゲールを看護師と表現するのはそぐわないと考えて、あえて看護婦としています)。
余談ついでに、もうひとつ。カーディガンという服がありますね。あれがつくられたのもクリミア戦争が原因です。前線で負傷した兵士がどんどん野戦病院に運ばれてきます。胸や腹に銃弾を受けている。治療のために服を脱がせなければならない。当時は防寒のためにセーターを着ていた。すっぽりと頭からかぶって着ますね。ところが治療のために、脱がせるためには万歳しなければならない。苦痛でもだえている負傷兵に万歳させてセーターを脱がせるのが一苦労だった。そこでカーディガン伯爵というイギリス軍人が、脱がなくても前を開けられるように発明したのがカーディガン。
ナイチンゲールにしろカーディガンにしろ、クリミア戦争がそれまでにない激しい戦争だったことのあらわれですね。ロシア軍は100万と言いましたが、そのうち52万が死亡したという数字もあるくらいです。
1856年、パリ条約で戦争は終結します。黒海の中立化によって、軍艦の航行は禁止され、ロシアの南下政策はまた挫折。ただ、ギリシア正教徒が多数を占めるルーマニアがオスマン帝国から独立し、ロシアの顔も少しはたてられた。
------------
ロシアの改革
------------
クリミア戦争の敗北は、ロシアにとって大ショックでした。クリミア戦争を始めた皇帝ニコライ1世は、戦争中に亡くなっていますが、死因は薬の飲みすぎ。戦況を苦にして、事実上の自殺ではないかといわれています。ニコライ1世は、19歳の時にイギリスに旅行して議会を見学していますが、市民たちが議論しながら法律を決めていく様子を見て嫌悪感を抱いたという。そのイギリスに敗れたのだから、ショックが大きかったのでしょう。
ニコライ1世の跡を継いだのが、アレクサンドル2世。かれは、やはり考えざるを得ない。圧倒的な兵力と地理的優位にも関わらず「なぜ、ロシアは敗れたのか?」
答えは簡単で、イギリスとは政治経済制度が全然違う。イギリスは、すでに工業社会にはいっているのに、ロシアではまだ農奴制がつづいているのです。そこでアレクサンドル2世は自由主義的改革をはじめます。
ちなみに、クリミア戦争がはじまった1853年は、日本にペリーが来航した年です。黒船ショックで、幕末の争乱と明治維新がはじまるのと時期も状況もそっくりです。幕末の志士たちが「何とかしなくちゃ、日本は滅びる」と考えたのと同じように、アレクサンドル2世も「何とかしなくちゃ」と思ったわけです。
アレクサンドル2世の自由主義的改革の目玉が、1861年の農奴解放令。当時ロシアには2000万の農奴がいた。かれらが自由な市民となり、ロシア国民としての自覚をもつことでロシアは生まれ変わることができると皇帝は考えた。ところが、実際に農奴を支配している貴族たちは、本気で農奴を解放する気はありません。形だけの解放になる。身分は自由になっても、土地は貴族のものですから、結局変化はない。農奴時代の年貢よりも高い小作料を払わされて、かえって生活が苦しくなったりするのです。農奴解放といわれて期待していただけ、農民の失望と怒りは大きくて、農民一揆が続発します。1862年に884件、1863年には509件の農民蜂起が起きている。皇帝としては、せっかく自由を与えてやったのに農民どもは何をやっているのだ、と逆に農民に対する不信感が増す。
さらに、1863年には、アレクサンドル2世の自由主義的政策に刺激されてポーランドで独立反乱が起きます。これは、またもやロシア軍に鎮圧されて失敗するのですが、皇帝はこれらの経験を通じて、自由をあたえれば臣民たちは増長し、勝手な振る舞いをして、国を乱すだけである。こんな連中は、やはり上から押さえつけるしかない、と考えるようになってしまった。
キュリー夫人として知られているノーベル賞を取った女性科学者マリー=キュリーは、この独立運動鎮圧後のポーランドで少女時代をおくっていて、伝記をみるとロシアの支配のようすがわかって面白いです。ポーランドの学校では、ロシア語で授業をさせられ、ポーランドの歴史など民族主義的な授業は禁止されていた。ところが、生徒も先生もポーランド人なので、ロシア人の監督官の目を盗んで、先生はポーランド語でポーランドの歴史を教える。監督官が学校にやってくるのが窓から見えると、先生はサッと黒板を消して、生徒は机の中からロシア語の教科書を出して、さも今までロシア語の勉強をしていましたという振りをするんです。監督官が教室に入ってくると、先生はマリーをあてる。小さい頃から賢かったから、あてられたマリーはロシア語でスラスラと答える。それを見て、監督官は満足そうにうなづいて、教室から出ていく。そんなことをやっていたそうです。そういう中で、ロシアへの反感と、独立への想いがいっそう強くなっていくのです。人の心は強制できない見本のような話です。
それはともかく、結局アレクサンドル2世は、自由主義的政策をやめて、180度方向転換。ツァーリズムとよばれる皇帝による専制政治を一層強化していきました。
しかし、西ヨーロッパの自由主義的政治体制を理想と考え、ツァーリズムに反対する知識人や学生が、当時のロシアにはある程度生まれていました。イギリスやフランスに留学して、ロシアの後進性を肌で感じている人が結構いるのです。こういう知識人のことをロシアではインテリゲンツィアという。略してインテリ。日本語になっていますね。
こういう反体制派のインテリたちが、政治改革をめざして1870年代から80年代にかけておこなったのがナロードニキ運動です。「ヴ=ナロード(人民の中へ)」というスローガンをかかげたのでナロードニキ運動という。
これは、学生たちが農村へどんどん入っていって、政治意識の遅れた農民たちに啓蒙運動をしようという運動です。貧困で苦しむ農民の意識を変えなければ、ロシアは変わらないと考えたのですが、彼らの行動や考えは農民にはなかなか理解されなかった。
農民からすれば、いきなり都会の若者が村にやってきて政治宣伝を始める。「自分で働きもしない貴族か金持ちの坊ちゃんが何を言うとる」、という目でインテリたちを見るのは当然です。活動家たちは、「農民よ、めざめよ、立ち上がれ、皇帝政治に反対せよ、革命だ!」と説いてまわる。普通の意識の農民たちからすると、ビックリするような危険なことを言っている。多くの農民たちは、皇帝に対しては素朴な敬愛の感情を持っていたそうですから、とんでもないことを言う怪しい連中だと思ったようです。
レーピンというロシアの画家に「ナロードニキの逮捕」という絵がある。これはナロードニキ運動の活動家が逮捕された瞬間を描いている。場所は農民の家の中。若い学生が、農民の家を訪問して、皇帝の専制政治を批判したのでしょう。驚いた家の者が一人こっそり役所に知らせにいった。知らせを聞いて駆けつけた警察官に逮捕された所です。若者は拘束され、鞄の中の書類を調べられています。部屋の奥の暗いところにいるのが、この家の農民たち。暗くて表情はわかりませんが、若者に対して何の共感も抱いていないようですね。
政府によるナロードニキ運動に対する弾圧は激しく、逮捕された若者の多くがシベリアに流刑になった。農民の支持を得られなかったナロードニキ運動は、80年代を過ぎると衰えていきます。そのなかで、一部の活動家は、テロリズムに走りました。まどろっこしい啓蒙活動よりも、直接的暴力でツェーリズムを倒そうと考えたわけだ。何度か、皇帝の暗殺未遂事件が企てられ、ついに1881年、アレクサンドル2世は、乗っていた馬車に爆弾を投げつけられて命を落としました。しかし、皇帝を暗殺しても、次の皇帝によって専制政治は引き継がれ、何の解決にもなりませんでした。
| 参考図書紹介・・・・もう少し詳しく知りたいときは 書名をクリックすると、インターネット書店「アマゾン」のページに飛んで、本のデータ、書評などを見ることができます。購入も可能です。 | ||
|
アレクサンドル2世暗殺〈上〉ロシア・テロリズムの胎動
|
エドワード・ラジンスキー (著), 望月 哲男 (翻訳), 久野 康彦 (翻訳) 日本放送出版協会 (2007/09) ドストエフスキーの「カラマーゾフの兄弟」をようやく読了しました。 高校時代から、何回も挑戦しつづけ、必ず上巻で挫折してきました。新しい翻 訳で売れているというので、再挑戦したのでした。ただし、私が呼んだのは昔 買った古い新潮文庫版。 社会の教師をやっているのだから、これくらい有名な本は教養として読んで おかなければと思いつつ、挫折がつづいたのは、とにかく、ドストエフスキー の饒舌さについて行けなかったことがあります。 登場人物が、しゃべり始めると、せりふが最低3ページ分はつづく。読んで いるうちに、何についての話だったのかわからなくなってくる。 しかも、話の内容が、キリスト教神学的なもので、不死とか、赦しとか、非 キリスト教者にとっては、なんの関心もわかない。というか、おもしろくない。 ドストエフスキーは理屈をこねくり回して、論理で遊んで楽しい人です。 一方、同じロシアの文豪のトルストイは、晩年キリスト教的立場から説話を たくさん書きましたが、ストーリーはどんどん単純化していきました。理屈を どんどん捨てていった。「イワンの馬鹿」など。 私は、トルストイ派のようで、「戦争と平和」は何回も読みました。ボルコ ンスキーとか、ベズウーホフとか、名前に慣れれば、すっと物語の中に入り込 めました。 しかし、ドストエフスキー。物語に入る前に、観念的な長ゼリフに、はじき 飛ばされてきた30年でしたが、今年、とうとう「カラマーゾフの兄弟」読了 です。 はじめてわかったのですが、この本は、殺人事件の話だったのでした。犯人 は誰か、という話なのですが、それは、読んでのお楽しみ。(多分、殺人事件 の推理小説として読むと、文学の先生からは叱責されます)。 ところで、話のなかで、カラマーゾフの長兄が遺産相続で父親ともめている のですが、農奴付きで村を一つ丸ごと相続云々、というセリフが出てくる。農 奴制ロシアが物語の背景にあります。主要登場人物も貴族か資産家の市民のよ うです。階級社会の上層部の人々の話です。 ドストエフスキー自身は若い頃、ツァーリズムに反対する政治運動に係わり、 逮捕され死刑判決を受けました。刑場に引き出され、あと数十分の命というと ころで、恩赦が出されるという劇的な体験をします。 シベリアの流刑から帰り、作家として成功をおさめていた時の皇帝がアレク サンドル2世。この皇帝は、改革の意欲にあふれ、1861年農奴解放令で農奴制 を廃止しましたが、その後、専制政治に回帰していきました。1881年、ナロー ドニキ運動の流れをくむ若者たちによるテロでアレクサンドル2世は暗殺され ます。 この犯人グループのアジトがあったアパートの同じ階の隣室に晩年のドスト エフスキーが住んでいたのです。しかも、アレクサンドル2世暗殺の直後に、 そのアパートで病死。ドストエフスキーが暗殺に係わっていなかったにしても、 犯人グループの動きを知っていたのではないか。そのことが、死に至る発作を 誘発したのではないか。 こんな刺激的な推理をしているのが、ラジンスキー『アレクサンドルⅡ世暗 殺(上・下)』(NHK出版、2007)。ドストエフスキーつながりで思い出し ました。皇帝の立場から描いたロシア史として興味深い本でした。 | |
| 世界の歴史 22 近代ヨーロッパの情熱と苦悩 (中公文庫 S22-22) | 谷川稔 他 著 結構広い時代をカバーしていますが、ウィーン体制以後のヨーロッパ全体の流れをつかむには適している。 | |
 第90回 19世紀中頃のロシア おわり
第90回 19世紀中頃のロシア おわり