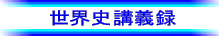第98回 エジプトの自立
---------------------
オスマン帝国の衰退
----------------------
16世紀半ば、スレイマン1世の時代に全盛期を迎えたオスマン帝国は、その後、徐々に衰退していきます。
1683年、第二次ウィーン包囲失敗が、衰退の大きなきっかけとなりました。第一次ウィーン包囲(1529)以後も、オーストリアとは断続的に武力衝突が起きていましたが、第二次ウィーン包囲失敗後は、オーストリアやロシアなどとの戦争になり、敗北したオスマン帝国は、1699年、カルロヴィッツ条約で、ハンガリーなどをオーストリアに割譲しました。
その後も、ロシアとの戦争で、18世紀後半には黒海北岸の領土を失います。
国内的には、地方総督の自立化傾向、帝国内の諸民族の独立運動が起きてくるのですが、オスマン政府は有効な対策がうてず、ずるずると衰えていきます。
---------------------------
ワッハーブ王国の成立と崩壊
---------------------------
オスマン帝国の衰退を象徴する最初の事件がワッハーブ王国の成立です。
18世紀半ば、アラビア半島でイブン=アブドゥル=ワッハーブという人物が、ワッハーブ派という宗派をおこしました。彼によれば、当時のイスラムのあり方は、ムハンマドの教えからはずれている。だから、ムハンマド時代の教えに帰れ、というのです。確かに、当時多くのムスリムの心をとらえていたスーフィズム(神秘主義)や、聖者崇拝などは、コーランのどこを探しても出てきません。イスラムがアラブ人以外の民族に広がるなかで、つけ加えられていったものです。(現在でも、スーフィズムや聖者崇拝はあります)
ワッハーブが唱えたのは、コーランに書いていないことはダメ、というガチガチのイスラム原理主義です。これは、当時の状況を考えると、トルコ人のオスマン帝国に支配されているアラブ人が、宗教をつうじて自己主張しているととらえることができます。
やがて、このワッハーブ派を信奉したアラビア半島中央部、ネジド地方の豪族サウード家が、オスマン帝国の支配にさからい、半島にワッハーブ王国を建設しました。やがて、領土を拡大しはじめ、19世紀はじめには、メッカとメディナの2聖都を支配するまでに発展した。
オスマン帝国にとっては、メッカ、メディナを失うというのは大失態で、辺境アラビアの出来事と、放って置くわけにはいかなくなりました。ところが、この時すでに、オスマン帝国は、独力でこれを討伐する力がなかった。そこで、またあとでのべるようにエジプト総督の力をかりてようやくワッハーブ王国を滅ぼしました(1818年)。
しかし、このあと1823年、ワッハーブ王国は復興し、89年にまた滅亡しますが、20世紀初頭、サウジアラビア王国という名前で、再度復活します。現在のサウジアラビアです。
------------------
ギリシアの独立
-------------------
1821年にはギリシアで独立戦争が始まりました。当時、ヨーロッパ列国はウィーン体制のもとで、民族運動には冷淡だったのですが、ギリシアといえばヨーロッパ文明の故郷、イギリスの有名な詩人バイロンが義勇軍として独立戦争に参加したり、フランスの画家ドラクロワが「シオの虐殺」というオスマン軍によるギリシア人虐殺事件を描いたりして、しだいにヨーロッパ人に注目されます。
また、南下政策をとるロシアが、この機会にバルカン半島に勢力を拡大しようと考え、ギリシアを支援してオスマン帝国と開戦。イギリス、フランスもギリシア独立に介入して、1829年のアドリアノープル条約で、ギリシアは独立を達成しました。
バルカン半島には、独立したギリシア以外にも、スラブ人、ギリシア正教徒が多数住んでいますから、かれらもこのあとオスマン帝国からの自立を求めて運動を活発化させるし、オーストリアやロシアがこれを援助しますから、オスマン帝国政府は、ますます難しい状況になっていきます。
----------------
エジプトの自立
----------------
すでに18世紀くらいから、アフリカ北岸地域では、在地勢力が、オスマン帝国の宗主権を認めながら、地方政権をたてていました。そのなかで、今からエジプトの話をするわけですが、なぜ特にエジプトなのかというと、エジプトはオスマン帝国から自立しただけでなく、ヨーロッパをモデルに国家建設をめざしたからです。しかも、それが一時は、成功しそうになる。最終的には、失敗してイギリスの植民地になってしまうわけですが。だから、19世紀のエジプトの歴史は、アジア・アフリカ諸民族が、最も早い時期に欧化をめざし失敗した先駆的な例となりました。ヨーロッパがアジア・アフリカを従属化、植民地化していくひとつの典型なのです。
また、エジプトの試みが、オスマン帝国の衰退と絡み合いながら進行していったことも重要です。
エジプトの自立はナポレオンの遠征から始まります。1798年、ナポレオン率いるフランス軍がエジプトを占領しました。これに対抗して、イギリスはエジプトに軍隊を派遣しましたが、エジプトはオスマン帝国の領土なので、当然、オスマン帝国政府も各地の部隊をエジプトに送り込みました。この時、派遣されたオスマン軍の将校だったのが、ムハンマド=アリーです。アルバニア系と言われています。エジプト人でもなければ、トルコ人でもないということです。このムハンマンド=アリーが、徐々に頭角を現して、やがて、エジプト派遣軍を掌握します。そして、1801年と1803年にフランス軍とイギリス軍がそれぞれ撤退した後、カイロの有力者たちの支持を取りつけて、1805年にはエジプト総督を名のります。オスマン帝国政府は、これを追認するしかありませんでした。この段階で、オスマン帝国の宗主権のもとに、ムハンマド=アリーのエジプトが自立したのです。
ムハンマド=アリーは、フランス軍やイギリス軍を、その目で見て、実際に戦っているわけですから、ヨーロッパの軍隊がどういうものか、その軍事力、組織力の高さを知っています。そこで、エジプトの支配者となったムハンマド=アリーは、ヨーロッパを目標としてエジプトの近代化を進めていきました。
具体的には、西洋式の陸海軍の創設、造船所、官営工場、印刷所を建設し、近代化をになう人材養成のため教育制度改革などをおこないました。印刷所は、イギリスやフランスの本をアラビア語に翻訳出版するために作られたもので、アラブ地域でつくられた最初の官営印刷所だそうです。
また、マムルークたちを、式典参加を理由に集合させ、一挙に虐殺する、ということもやった(1811年)。かれらは、ナポレオンの遠征以前から、エジプトで一定の政治的勢力を持ち続けており、中央集権化をすすめるには邪魔な存在だったのです。
近代化政策の財源は、農業です。「エジプトはナイルの賜」ですから、農業生産は高い。ムハンマド=アリーは、農産物輸出事業を独占し、その利益を財源としました。
こうして、急速に軍事力を高めたエジプトが、その実力を見せたのが、1818年のワッハーブ王国の撃破でした。メッカ、メディナを占領したワッハーブ王国の討伐をオスマン帝国から依頼され、アラビア半島に出兵し、これを破ったのでしたね。
なぜ、ムハンマド=アリーは、オスマン帝国の要請にしたがったかということですが、エジプトは自立していますが、あくまでも自立であって、独立ではない。エジプトは、オスマン帝国の宗主権を認めており、正式にはオスマン帝国の一部。ムハンマド=アリーの肩書きは、オスマン皇帝から任命されたエジプト総督なのです。
オスマン帝国からすると、強くなったエジプトは、言うことを聞いてくれるのであれば、非常に頼りがいのある舎弟です。このあと、ギリシア独立戦争がはじまると、オスマン帝国は、また、エジプトに出兵を要請しました。
エジプトは、これにも応じて、ギリシアに出兵します。オスマン帝国側は、その見返りとしてシリアの支配権を与える約束をしていました。ところが、ギリシア独立戦争が終わっても、オスマン帝国側が、約束を果たさない。そこで、エジプトはシリアの領有を要求してオスマン帝国と開戦しました。これを、第一次エジプト・トルコ戦争という(1831~33)。
この戦争は、エジプトが勝利し、シリアを領有することになりました。
この戦争で、南下政策を実現させたいロシアは、恩を売るためにオスマン帝国を支援しています。また、エジプトの利権をねらうフランスはエジプトを支援しました。
この地域は、アフリカ、アジア、ヨーロッパにまたがっており戦略的に重要な場所だから、ただでさえヨーロッパ列国の関心が高い。ここでの紛争は、ヨーロッパ列国にとって、利権を得たり拡大するチャンスです。もはや、オスマン帝国、エジプトという当事者だけの争いでは、収まらなくなっているのです。また、当事者よりも、バックに控えるヨーロッパ列国の方が、経済的にも軍事的にも圧倒的に優位なので、いつのまにか、当事者を飛び越えて、ヨーロッパ列国が紛争を仕切って、自分たちに都合のいい秩序を作り上げていくことになるのです。
1838年、イギリスがオスマン帝国とトルコ=イギリス通商条約を結びました。オスマン帝国に関税自主権のない不平等条約でした。この結果、オスマン帝国の領土であるエジプトにもこの条約が適用され、エジプトの貿易は大打撃を受けました。
オスマン帝国から完全に独立すれば、この条約から逃れることができます。そこで、ムハンマド=アリーはオスマン帝国にエジプトの独立を求め、1839年、第二次エジプト=トルコ戦争が始まりました。
ここで、登場するのがイギリスです。イギリスは、第一次エジプト=トルコ戦争の結果に不満を持っていた。エジプトの領土が拡大し、それにともなって、この地域でフランスの勢力が増したことが気にくわなかったのです。そこで、第二次エジプト=トルコ戦争が始まると、早速、この戦争の調停に乗りだしました。フランスやロシアとの外向的な駆け引きの末、翌1840年、ロンドン会議で、イギリスは自分のつくった調停案をエジプトに押しつけて戦争を終わらせました。
その内容は、エジプトはシリアを放棄する。ひきかえにムハンマンド=アリー家がエジプト総督位を世襲する、というものでした。
ムハンマド=アリーはこの内容に不満でしたが、イギリスの軍事的圧力の前に、これを飲まざるを得ませんでした。
結局、正式に独立することはできませんでしたが、ムハンマド=アリー家による総督世襲が認められたので、普通はこれ以後のエジプトを、独立国家として扱っています。(書物や年表によっては、1805年をムハンマド=アリー朝の成立としているものもあります。)
--------------
スエズ運河
----------------
ムハンマド=アリーの死後、エジプト総督位はその子孫が継いでゆき、ムハンマド=アリーが始めた近代化政策は、その後も引き継がれていきました。
さまざまな事業の中で、エジプトの運命に大きな影響を与えたのがスエズ運河建設です。スエズ運河建設をはじめたのは、第4代総督サイイド=パシャでした。かれは、ムハンマド=アリーの三男で、少年時代にカイロに来ていたフランス人外交官レセップスを家庭教師にしていた。レセップスにかなりなついていたようです。三男だから、本来は総督位を継ぐ立場ではなかったのですが、兄や甥が次々と死んでいったため、総督になってしまったのです。
サイイド=パシャが総督になると、フランスに帰っていたレセップスがエジプトにやってきて、総督との個人的な関係を利用して、スエズ運河建設を売り込んだのです。総督は、レセップスにスエズ運河建設の許可を与えました(1854年)。
レセップスはスエズ運河株式会社を設立し、資金を集めて1859年に着工、10年に及ぶ難工事を経て、1869年に運河は完成しました。全長167キロメートル、幅60~100メートル、深さ8メートル。総工費は当初の予算2億フランの倍を超える4億5千フラン、工事に駆り出されたエジプト農民の死者は12万人に及びました。
建設費はエジプト政府も負担し、その費用はフランスからの借り入れに頼り、完成後のスエズ運河は、エジプトとフランスの共同所有となりました。
スエズ運河の開通によって、ヨーロッパからアジアに向かう船はアフリカを廻らなくてもインド洋に抜けることができ、費用、時間は大幅に短縮されました。現在でも、活発に利用されているスエズ運河は、歴史的な大事業だったと言っていいでしょう。
スエズ運河開通の時のエジプト総督は、サイイド=パシャをついだイスマーイール=パシャです。イタリアの作曲家ベルディによる「アイーダ」という有名なオペラがあります。これは、スエズ運河開通記念に建てられたカイロの大歌劇場で上演するために、イスマーイール=パシャがベルディに作曲を依頼した作品です。ストーリーの原案をイスマーイール=パシャが考えたという説もあります。エジプト総督がスエズ運河の開通を飾るのに、オペラの作成を依頼するというのは、どれだけエジプトの支配層が、ヨーロッパ文化にかぶれていたかということですよね。エジプトをヨーロッパの国にしたかった、そんな気持ちがあったのかもしれません。
エジプトは、スエズ運河の航行料収入を当てにしていたのですが、これが思うようにのびず、また、アメリカ南北戦争のおかげで大きく伸びていた綿花の輸出による収入が、南北戦争の終結による合衆国の国際貿易復帰によってダウンしてしまいました。
急速な財政悪化に困ったエジプト政府は保有していたスエズ運河の株式を売りに出すことにした。1875年、これを買収したのがイギリスです。
この時のイギリスの首相がディズレーリ。積極的な帝国主義政策をとり、世界に利権を拡大していた。エジプト政府によるスエズ運河株式売却のニュースを知ると、このチャンスを逃してはいけないと思った。そこで、ディズレーリは議会にはからず独断でこれを買い取りました。議会の賛成を得ていないから政府からお金が出ない。そこで、大富豪ロスチャイルド家から40万ポンド(約1億フラン)を借りたという。
この結果、エジプトの領土にあるにもかかわらず、スエズ運河の所有権はエジプトにはないというという事になってしまいました。
スエズ運河株式を売ったにもかかわらず、エジプトは外国から借り入れた資金の返済ができなかった。スエズ運河以外にも、近代化政策のため外国から多額の借金をしていたのでした。
1876年、ついにエジプト政府が財政破綻すると、債権国(お金を貸している側の国のことを言います)であるイギリスとフランスが共同でエジプト財政を管理下に置きました。
------------------------
ウラービー=パシャの革命
-------------------------
このような状況の中で、「エジプト人のためのエジプト」をスローガンに、政治改革運動が起こってきました。指導者はエジプト軍の将校ウラービー=パシャです。
ムハンマド=アリー以来のエジプト総督達は、近代化には熱心でしたが、立憲政治や議会政治は取り入れず、専制政治をつづけていました。しかし、近代的な教育を受けたエジプト人の中から、立憲政治をめざす勢力があらわれてくるのは当然でしょう。
「エジプト人のためのエジプト」という言葉の中は、英仏から財政権を取り戻そうというだけではなく、アルバニア系のムハンマド=アリー朝の総督に対する批判も含まれています。
ウラービー=パシャは、1882年、権力を掌握し、自分自身は陸軍大臣となって、憲法制定などの改革に着手します。これを見て、イギリスはフランスには相談せず、単独でエジプトに軍隊を派遣し、圧倒的な軍事力でエジプト軍と市民の抵抗を鎮圧して、占領してしまいました。
これ以後、エジプトはイギリスの支配下に入り、ムハンマド=アリー朝の総督はイギリスの傀儡となりました。イギリス軍はスエズ運河警備を名目に、運河地帯に常駐しました。
改革運動の指導者ウラービー=パシャは、イギリスに逮捕されセイロン島へ島流しとなりました。失敗に終わったウラービー=パシャの改革運動は、現在は「ウラービー=パシャの革命」と言われていますが、数年前までの教科書には「ウラービーの反乱」と書かれていました。イギリスから見れば反乱だったんでしょうね。誰の視点から見るかで、同じ事件でも評価や呼び方が大きく変わる一例です。
ウラービー=パシャの改革と失敗は、同時代の日本でも大きな関心を持たれたようで、洋行する日本政府の高官が、セイロン島のウラービー=パシャを訪ねることがちょくちょくあったようです。伊藤博文の娘婿が訪問しているようです。また、農商務省大臣秘書官が東海散士というペンネームで書いた小説『佳人之奇遇』(1885)に、ウラービー=パシャが登場します。この小説は結構人気があったようですから、ウラービー=パシャは明治期の日本人にはわりと知られていたかもしれません。
エジプトの先例に学びながら、明治期の日本は国家建設をすすめたのです。
こちらもご覧ください。勉強会での発表報告です→ エジプトの早すぎた明治維新(2017.1.4)
| 参考図書紹介・・・・もう少し詳しく知りたいときは 書名をクリックすると、インターネット書店「アマゾン」のページに飛んで、本のデータ、書評などを見ることができます。購入も可能です。 | ||
| 世界の歴史〈20〉近代イスラームの挑戦 (中公文庫) | 山内昌之著. ヨーロッパ史や中国史のように、人物伝や小説などで物語的ななじみがあると、歴史書を読んでも、理解しやすいのだが、いかんせんイスラム史は(特に近代)は、とっつきにくい。この本もそうなのですが、それは、本の責任ではない。敬遠せずに、しっかり読み込んでいくことが、勉強だし、そこから徐々に面白さがわかってくるというものです。 | |
| ムハンマド=アリー―近代エジプトの苦悩と曙光と (1978年) (Century books 人と歴史シリーズ―東洋〈20〉) | 岩永博、清水書院、1984 | |
| ムハンマド・アリー―近代エジプトを築いた開明的君主 (世界史リブレット人) | 加藤博、山川出版社、2013 | |
| 新版 エジプト近現代史 ――ムハンマド・アリー朝成立からムバーラク政権崩壊まで 世界歴史叢書 | 山口直彦、明石書店、2011 | |
| 「オスマン帝国のアラブ支配とその解体」(岩波講座『世界歴史21』) | 三木亘、1971 | |
 第98回 エジプトの自立 おわり
第98回 エジプトの自立 おわり