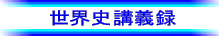モンゴル帝国の発展
-------------
チンギス=ハーンの死後大ハーンの位を継いだのが、オゴタイ=ハーン(位1229~41)です。
かれの時代に金を征服し(1234)など、モンゴル帝国はいっそうの発展をしています。
国家建設が進むにしたがって、統治機構を整える必要がでてきます。
金国を征服することによって、大規模な農耕地域を支配することになる。前回も出てきました契丹族の耶律楚材などを登用して中国人を支配する機構を整えていった。契丹族も非農耕民でありながら中国を支配した経験がある、いわばモンゴル人の先輩格ですからね。

また、オゴタイの時代にモンゴル高原北部にようやく首都を建設しました。これがカラコルム。
しかし、首都を造ってはみたものの、オゴタイは壁に囲まれた宮殿に住むのが窮屈で仕方がない。宮殿の横っちょの草原で相変わらずテント暮らしをしていたそうです。外交上の式典として必要なときだけ宮殿に出向いたという。
チンギス=ハーンの子供たちについて触れておきます。オゴタイが第二代大ハーンになったいきさつについてです。
チンギス=ハーンには四人の男児がいた。上から順番にジュチ、チャガタイ、オゴタイ、トゥルイです。必ず長男が相続する中国のような、きっちりした相続制度はモンゴル人には無かった。ただ、末子相続が一般的だったらしい。
なぜかというと、農耕民族のように土地を相続するということはないので、子供は大きくなったらある程度の馬や羊を親から分けてもらって一人立ちをしていきます。上の子からどんどん独立していくので、最後に末っ子が残る。で、親が死んだとき残った家畜の群を末っ子がそのまま相続するのです。
このパターンをハーン位継承に当てはめればトゥルイが大ハーンになるのですが、それに関しては、はっきりした決まりが無かった。そこで、遊牧民のリーダーとしてふさわしい者を有力族長会議であるクリルタイで決定することになります。
 |  オゴタイ=ハーン |
長男のジュチは、暗黙のうちに、はじめから跡継ぎとしては除外されていました。なぜかというと、かれの出生には因縁があった。まだ、弱小勢力だった頃、チンギス=ハーンは対立部族に襲われて新婚早々の妻を略奪されたことがある。一年後に、かれは復讐を果たし、奪われた妻を取り返すのですが、そのとき妻は妊娠しているの。そして、生まれたのがジュチ。
チンギス=ハーン自身、そのことでジュチを差別したりはしないんですよ。他の息子と同じように扱っています。でも、この話は公然の秘密だった。誰も口には出さないけれどみんなが知っていたのです。だから、ジュチの相続はありえなかった。ちなみにジュチというのは「客人」という意味だそうです。出生を考えると、意味深長な名前ですね。
次男のチャガタイは、大勢の前でジュチの出生のことを口に出すような軽々しいところがあって、人望がない。
残る三男と四男、オゴタイとトゥルイが本命だったのですが、チャガタイがオゴタイと組んでオゴタイ即位となりました。
生前、チンギス=ハーンはジュチに西方へ遠征させるつもりで、「西の方どこまでもモンゴルの馬蹄で蹂躙できるすべての土地をおまえにやろう。」と約束していた。ところが遠征実行前にチンギス=ハーンもジュチも死んでしまった。そこで、オゴタイはジュチの息子バトゥに対して、遠征を命じた。
これが「バトゥの西征」。1236年から大遠征軍がロシア平原に出発した。バトゥを総大将にするモンゴル軍は向かうところ敵なし。ロシア平原を制圧してそのままポーランドに侵入した。
いきなり東方からやってきた騎馬軍団にあわてたのがヨーロッパの諸侯たちです。ドイツ、ポーランドの諸侯連合軍一万がバトゥ軍別動隊三万から四万を迎え撃った。結果はモンゴル軍の圧勝。これをリーグニッツの戦い、または、ワールシュタットの戦いといいます。ワールシュタットというのは、この戦いのあとで付いた地名で「死体の森」という意味だそうです。
モンゴルが圧勝した理由は、前回話した機動力と、もう一つは集団戦法にヨーロッパ諸侯軍が対応できなかったためです。
モンゴル騎馬軍団は整然とした隊列を組んで集団で攻めてくる。これに対して、ヨーロッパの軍隊は名誉と武勲を重んじる騎士の集まりだから、集団戦をしません。平家物語の頃の武士と同じで、戦う前に「やあやあ、我こそはどこそこの領主、何とか伯である。いざ、じんじょうに勝負せよ!」とか言って、一騎打ちして勝敗を決める。これが基本です。そのつもりで騎士たちが構えていると、ろくに鎧甲も付けず、ネズミみたいに小さい馬にまたがった連中が集団でつっこんでくる。これでは、ひとたまりもありませんね。
このあともモンゴル軍が進撃を続けていれば、ヨーロッパもモンゴル帝国の一部になったかもしれないのですが、ここで事件が起こる。オゴタイ=ハーンの急死です。次の大ハーンを決めるためのクリルタイに参加せよ、という連絡がモンゴル高原より来るんですね。
バトゥは兵を返します。ただ、かれはモンゴル高原まで帰らず、ロシア平原に留まってここを自分の本拠地にします。これがキプチャク=ハーン国と呼ばれ、モンゴル帝国の一部となります。
オゴタイ=ハーンの跡を継いだのは、その子のグユクですが、かれの即位には反対が多く正式に大ハーンになるまでに何年もかかっています。また、即位してまもなく死んでしまった。オゴタイの死からグユクの死まではモンゴル帝国の混乱期です。
グユクは受験的には覚える必要なしです。
グユクの死後、またもや、大ハーン位をめぐって一族のあいだで争いが起きる。
第四代大ハーンになったのはモンケ(位1251~59)。かれは、チンギス=ハーンの末子トゥルイの子です。オゴタイ家からトゥルイ家に大ハーン位が移ったのには一族の長老バトゥの後押しがあった。チャガタイ家、オゴタイ家のチームに対して、ジュチ家、トゥルイ家は仲が良かったわけだ。
第四代モンケ=ハーンの時代になって、モンゴル帝国は再び征服戦争を開始しました。
モンケは二人の弟、フビライとフラグにそれぞれ東と西の遠征をおこなわせた。
フラグの西アジア遠征はイスラムのアッバース朝を滅ぼしました。アッバース朝は500年も続いたイスラム教の中心的王朝でした。だから、これは西アジアのイスラム世界にとってはものすごい大事件だったのです。
フラグの遠征軍の一部はエジプトまで侵入しますが、ここでまた、モンケ=ハーンが死んで、フラグには帰還命令がでます。フラグもバトゥと同じようにモンゴル高原まで帰らず、イランに留まる。ここにできるのがイル=ハン国です。西アジア全体を勢力範囲におきました。
一方、もう一人の弟フビライはチベット、雲南にあった吐蕃、大理という国を征服し、西南方面から中国の南宋を攻略します。
この対南宋戦にモンゴルは大軍を投入して、各方面から作戦を展開していた。モンケ=ハーン自身も出陣して南宋戦を指揮していて病死したのでした。
モンケの出陣中、カラコルムに留守番として残っていたのが、フビライ、フラグ達のさらに下の弟、アリクブケという人なのですが、かれがモンケの死後大ハーンになる最有力者だった。即位のためのクリルタイを召集します。フラグもこれに呼ばれる。フラグの場合はあまりにもカラコルムから遠く離れているので、モンゴル高原に帰って政争に巻き込まれるより西アジアに自分の国をつくるという選択をしたのです。
しかし、フビライは対南宋戦で指揮下にある大軍を背景にして、強引に大ハーンに就こうとした。かれは、アリクブケのクリルタイに参加せず、自分の支持者だけでクリルタイを開き、大ハーンになってしまった(1260)。
アリクブケは、フビライに対抗してカラコルムで別にクリルタイを開き大ハーンになります。しかし、かれは政治的にも、軍事的にもフビライの敵ではなく、4年後にはフビライに降伏しました。
こんなふうにしてフビライが正式な第五代目の大ハーン(位1260~94)になったのです。
ここまでの流れを見てくると、モンゴル帝国はモンゴル人の支配地域が拡がるという意味では、どんどん発展しています。
しかし、一方で内部ではチンギス=ハーンの一族の結束はだんだん緩くなり、あるいは対立するようにもなってきている。ということがいえます。
整理してみましょう。
チンギス=ハーンの長男ジュチ家はバトゥが南ロシア平原にキプチャク=ハン国を建設。
次男チャガタイ家は中央アジア(トルキスタン)を中心にチャガタイ=ハン国と呼ばれる支配地域を形成しています。
三男オゴタイ家は西北モンゴリアにオゴタイ=ハン国を形成。
四男トゥルイ家は、フラグが西アジアにイル=ハン国を建設。そして、フビライが大ハーンとして四つのハン国を束ねると同時にモンゴル高原から中国北部、チベット方面を直接支配している。
モンゴル帝国はこの段階でチンギス=ハーンの孫達がそれぞれ持っている所領の緩やかな結合体です。
フビライの即位に反対して、オゴタイの孫に当たるハイドゥが反乱(1266~1301)を起こしていますが、これはモンゴル帝国分裂の象徴的出来事として受験的には覚えておくこと。ただ、実際には大きな戦闘は一度しかなかったといいます。
フビライは実はチンギス=ハーンの一族の中では変わり者とされていた。かれのどこが変わっているかというと、中国びいきなのです。代々、モンゴルの王侯達は中国文化には関心が薄く、イラン文化に代表される西方の文化に興味を持つのが普通だった。
ところが、フビライは長い間南宋攻略をしていたので、自然と中国人と接触する機会も多かった。それで、中国びいきになったようです。
そこで、大ハーンになるとモンゴル帝国の首都をモンゴル高原のカラコルムから中国北部の大都に移した。大都は今の北京です。
さらに、国号を元とします。中国風でしょ。
1279年には南宋を滅ぼして東アジア全域を支配下に入れました。
日本、ビルマ、ヴェトナム、ジャワなどさらに遠方に遠征軍を送り出す、これらはみんな失敗に終わっています。なぜ、こんな遠征をおこなったかというと、モンゴルがそれまでに作り上げた陸のネットワークに海のネットワークを結びつけようとする試みだったという説もあります。
フビライ以後、元は中国の王朝となりました。
---------------
モンゴル帝国と東西交流
---------------
西はロシア、シリアから東は中国までユーラシア大陸の大部分を支配して、モンゴル帝国は歴史上空前絶後の領土を持つようになった。全部一つの国なんだから戦争はなくなる。これを「タタールの平和」という。タタールとはモンゴルのことです。
モンゴル帝国は東西交易路の安全を確保するために、駅伝制を整備します。駅伝のことをモンゴルではジャムチという。資料集にありますがモンゴル政府発行の通行許可証が牌子(はいず)です。これを持っていれば街道沿いにある宿駅で宿泊したり、馬を交換したりと便宜を受けながら旅をすることができた。これが駅伝制です。
駅伝を利用できなくても、交易路の安全はモンゴルによって守られていますから、商人は安全に遠隔交易をすることができました。ムスリム商人と呼ばれるイスラム教徒の商人達が特に活躍します。
安全な交通路を通ってヨーロッパからの外交使節もモンゴル高原にやってきました。
ローマ教皇インノケンティウス4世から派遣されたのがプラノ=カルピニ。ローマ教皇というのは西ヨーロッパのキリスト教会の最高指導者です。
フランス王ルイ9世もルブルクという人物を派遣した。
かれらの使命はイスラム教徒の勢力と対抗するためにモンゴルと同盟を結ぶことでした。カルピニはグユク=ハーン、ルブルクはモンケ=ハーンの時代です。モンゴル側は同盟を結ぶ気持ちなど全然ないので適当にあしらっています。
ルブルクもカルピニもジャムチを利用してカラコルムまで行っています。ルブルクはフランスから出発してとりあえずロシアまで行く。するとそこはもう遊牧の世界で、テントを張った人たちが遊牧している。カルピニは、かれらにキプチャクの大ハーンの所に案内してもらい、そこで通行許可証、牌子をもらっている。そのあとはトラブルもなくカラコルムまで行きました。
面白いのは、かれは旅の途中のオアシスの町やカラコルムで結構ヨーロッパ人に会っているのです。モンゴルの遠征で捕虜となって連れてこられたのかどうか、事情はわかりませんが、旅行記などを残さない職人や女達がかなりユーラシア大陸を大移動しているのがわかります。
また、モンゴルの宮廷にはキリスト教徒がいました。古代ローマ帝国時代に異端とされたネストリウス派キリスト教が西アジアから中央アジアにかけて拡がっていて、モンゴル王族の女性達にも信者がいました。ハーンの妻の中にもいる。モンゴル人は宗教に関してはあまり気にしない。日本人と同じような感性なんでしょうね。じゃまにならない限り自由に布教もさせていたようです。
フビライの時代に、ローマ教皇からモンテ=コルヴィノという宣教師が派遣されるのですが、かれは大都で三十年間も布教しています。
モンゴル時代の旅行者で一番有名なのはマルコ=ポーロですね。イタリアのヴェネツィア商人です。父親が遠隔貿易商人で、16歳で父と叔父に連れられて旅に出る。中国に着いて、フビライ=ハーンに会った時には20歳になっていました。若くて賢かったのでフビライに気に入られて、元の役人として中国各地で17年間働きます。
最後にイタリアに帰国するときは、イル=ハン国に嫁入りするモンゴルのお姫様を中国から、南シナ海、インド洋をまわって船で送り届ける役目を仰せつかっている。
イタリアに帰ってから、戦争で捕虜になって牢屋に入れられてしまうんですが、牢の中の暇つぶしに同室の囚人ルスチケロに自分の体験を話すんですね。あんまり、面白い話なのでルスチケロはこれを書き留めて本にした。
これが『東方見聞録』です。『世界の記述』ともいいます。
これが、ヨーロッパで広く読まれてアジアに関する関心が高まるんですね。特に「黄金の国ジパング」。ジパングでは金がザクザク採れるので宮殿は柱も屋根も金でできている、なんて書いてある。これが、のちにコロンブスが大航海を計画するきっかけの一つになったのは有名な話。
なぜ、日本がジパングなのかというと、日本という字は中国語読みすると「リーベン」という発音になる。「リー」という音は舌をグッと巻き上げて上顎の奥の方にくっつけて出します。「ジー」という音に限りなく近い。「本」の「ん」も中国語では「ng」音。それで、マルコ=ポーロはジパングと聞いたんでしょうね。これが英語のジャパンの語源になります。
ジパングの話ですが、黄金の国だなんて全然嘘なわけで、マルコ=ポーロの本の中には明らかな間違いも結構あるのですが、権力中枢にいた者しか知り得ない情報もある。研究すればするほど実に不思議な本なのです。
研究者にはマルコ=ポーロは中国まで行っていない、という人もあれば、マルコ=ポーロは実在せず、複数の旅行者の情報をマルコ=ポーロという名前に託して作り上げたのが『世界の記述』だ、という人もいます。
---------------
元朝の中国支配
---------------
フビライ=ハーンから始まる元は中国の王朝となるのですが、モンゴル人はどのように中国を支配したのか。
「モンゴル人第一主義」という。一番上の身分がモンゴル人、二番目が色目人(しきもくじん)、三番目が漢人、最後が南人という序列がつくられる。
支配者はモンゴル人ですが、人口は圧倒的に少ないし、定住農耕民を統治する行政的な技術や経験が少ないですから、行政技術者として主に西方出身のイラン人などを官僚として使いました。かれらのことを色目人というのです。色目人とは雑多な人たちという意味です。目の色が青いからではありませんよ。マルコ=ポーロなどは、まさしく色目人です。
漢人とはこの時代の特殊な使い方で、旧金朝支配下の漢民族、女真族、契丹族、高麗人を呼ぶ言い方です。
最下位の南人は旧南宋治下の漢民族のことです。
モンゴルは中国の伝統的な官僚登用試験である科挙を廃止します。儒学的教養に価値を認めないわけですね。中国の経済に寄生して、吸い取れるものは吸い取ろうということです。
マルコ=ポーロの『世界の記述』を見ていくと、マルコは中国各地を旅するのですが、中国人とはほとんど接触していない。中国語を話している形跡があまりない。同じ色目人同士でペルシア語ぐらいをはなして、日常の用は足りていたのではないかといいます。
かれらが中国を支配していながら中国人や中国文化に無関心だった具体例ですね。税金さえ取ることができればそれでよかったのです。
元の税収の中心は塩の専売税です。さらに交鈔(こうしょう)という紙幣を大量発行して中国経済の上前をはねる。
「モンゴルの平和」によって安全を確保されて中国にやってくる商人からの税収も多かった。
「五日目にザイトン(泉州)という非常にりっぱな大都市に着く。ここは海港で、インドの船はみな高価な商品、貴重な宝石類、大きいりっぱな真珠を満載してここへ入港する。また、マンジ(中国)の諸地方の商人たちもこの港に集まってくる……。さて、大汗(フビライ)はこの都会と港から実に莫大な税収を得ているが、これはインドから来る船はすべて10パーセント、すなわち彼らが持ってくるすべての商品、宝石、真珠の価格の10分の1を納めることになっているからである。……こうして、税と船賃とで商人は載んできたものの半分は差し出さねばならぬことになる。しかも残りの半分でも大変な利益があがるので、もっと沢山商品を持って、もう一度こようと考える。これをみても、大汗がこの都会から取りたてている税収がどんなに莫大なものであるか、容易に信じられるはずである。」(マルコ・ポーロ「世界の記述」より)
モンゴルというと陸の大帝国というイメージが強いですが、インド洋から南シナ海でも安定した海のネットワークができていたことに注意しておいてください。
元の時代、科挙が中止になったので、受験勉強をしていたエリート達の中には生活のために小説や芝居の台本を書く者が出てきました。それまでエリートは庶民の楽しみ、芝居・小説のたぐいは馬鹿にしていたから、中国史上前代未聞のことが起こったわけだ。知識人が小説を書くので、質の高い作品が生まれた。
この時代の芝居を元曲(げんきょく)または雑劇といいます。
有名作品としては『西廂記(せいしょうき)』『琵琶記(びわき)』。前者は若い男女の恋愛、『琵琶記』は夫婦の愛を描いたもので、内容的には女性の観客をターゲットにしているのではないかと思う。
劇は元の宮廷でも演じられたようです。面白いものは誰が見ても面白いのです。
小説では、『三国志演義』『水滸伝』『西遊記』の原型が成立します。盛り場での講談がだんだんとまとめ上げられていったようです。
文字です。
契丹族、女真族、タングート族と中国周辺の新興民族は漢字に対抗して独自の文字を開発してきましたが、フビライもチベット人パスパに命じてモンゴル語を書き写す文字を制定しました。これが、パスパ文字。文字の歴史で出題されます。
学問分野では西方からイスラム科学が導入された。
フビライの時代に、郭守敬(かくしゅけい)という人がいる。かれは運河の建設とか水利工事もやっているんですが、天文学者として有名です。イスラム暦をもとにして「授時暦」という暦をつくった。これは江戸時代の「貞享暦」のもとになった。
月の裏側にはかれの名を付けた「郭守敬」というクレーターがある。
火星と木星のあいだにある小惑星帯の小惑星2012号は、別名「郭守敬」。
雑学でした。要するに中国が誇る歴史的天文学者っていうこと。
-------------
元の征服事業
-------------
元といえば、元寇。日本とも大いに関わりがある。
鎌倉時代に二回攻めてきたわけですが、一回目が1274年、文永の役、二回目が1281年、弘安の役です。
なぜ、この時期だったのか。フビライの目的はなんだったのか。
朝鮮半島にあった高麗国がモンゴルに服属するのが1259年。高麗政府は江華島という島に逃げ込んで抵抗を続けていたのですが、最終的にモンゴルの属国になる。高麗王はモンゴルのお姫様を妃に迎えて王室にモンゴルの血が入り込むようにさえなるのです。
ところが政府がモンゴルに降伏しても、軍隊は納得せずに半島の南西海岸を転々としながらモンゴル軍に抵抗を続けました。この高麗軍を三別抄(さんべつしょう)軍といいます。三別抄軍は海上の島々を根拠地にしたので、モンゴル自慢の騎馬隊も苦戦した。
この三別抄軍が最後につぶされたのが1273年。ようやくモンゴルは朝鮮半島を平定できたわけで、その翌年に第一回目の日本遠征、文永の役となります。
フビライは1271年と1273年に趙良弼(ちょうりょうひつ)という女真族出身の政治家を外交使節として日本に派遣していますが、趙良弼は鎌倉幕府の回答をもらえないまま、帰国している。幕府の対応は外交としては実に無礼なもので、完全にモンゴルを無視する態度でした。フビライはそれに怒って日本遠征をしたのかというと、それは違う。
当時元は南宋攻略の真っ最中です。日本兵を動員すれば、東シナ海経路で南宋を攻めることができるでしょ。日本を含んだ対南宋包囲網形成というのが第一回遠征の目的だった。
しかし、この遠征は失敗に終わりました。
その後1279年に南宋は滅ぼされます。その二年後に第二回日本遠征です。このときの目的はなんだったか。
南宋を滅ぼしたあと、元は旧南宋軍の処理に困ったらしい。南宋は元との戦争で大軍を抱えていました。南宋が滅んでも、その兵士達は大勢残っているわけで、かれらに仕事をあたえるための日本遠征だったようです。
だから、はっきり言って、フビライにとって第二回遠征は成功すれば非常にうれしいけれど、負けて大軍が海の藻屑となってもやっかいばらいが出来てそれはそれで悪くない、そんなものだったのではないかと思います。
第二回の遠征軍の兵士達は船のなかに鋤とか、鍬とか農具を持ち込んでいるのです。かれらは日本を征服したあとは、そのまま故郷には帰らず、日本に住み着いて農業をするつもりでいるのね。日本人の女を妻にして。
この二回目の遠征も失敗するのですが、二回も続けて失敗した原因はなんでしょうか。
神風が吹いた、と一般にはいわれています。だけれど当時の京都の公家の日記などを見てもそんな様子はない。少なくとも大暴風が吹いたのではない。
失敗の原因は元軍の構成にあるようです。
元寇を防ぐために戦った竹崎季長(たけさきすえなが)という武士が自分の活躍を描かせた『蒙古襲来絵詞』という絵巻物があります。モンゴル軍の貴重な絵画資料なのですが、攻めてくるモンゴル兵は歩兵ですね。迎え撃っている鎌倉武士が騎兵です。モンゴルは騎馬軍団だからこそ強かったのに、これでは逆ですよね。
モンゴル軍が騎兵ではないのは船に乗ってきたから当たり前なのかもしれないけれど、理由はそれだけでしょうか。
われわれは、元寇というので、何となくモンゴル人が攻めてきたように思っていますが、いったいモンゴル人の人口はどれくらいなのかな。チンギス=ハーンの時に70万くらいというから、フビライの時代に増えているとして100万人としておこう。これが、西はロシア、シリアから東は朝鮮半島に至るまでインドとインドシナ半島をのぞく全ユーラシア大陸を支配している。ということは世界中にかれらは拡がっているわけで、日本遠征に純粋モンゴル人がどれだけ参加していたか。
司令官クラスは、モンゴル人も多くいたと思いますが、一般兵士のほとんどはモンゴル人ではないと思った方が実体に近い。そもそも、モンゴル軍というのはモンゴル帝国が拡大するにしたがって、雑多な民族の混成軍になっている。
たとえば、『蒙古襲来絵詞』のなかに顔の黒いモンゴル兵が何人か出てきます。これ、明らかに意識的に黒く描いていますね。顔つきはモンゴロイドですね。なぜ、黒いのか。
中国では宋の時代、犯罪者は顔に入墨を入れられていました。そして、刑罰代わりに強制的に兵士にされていた。黒い顔に描かれているのは多分かれらです。だから、金朝か南宋の出身と見て間違いない。
第一回遠征軍の主力は高麗人です。高麗の三別抄軍はその前の年までモンゴル軍と戦っていたわけで、遠征軍の中身がとてもしっくりいっているとは思えない。しかも、海軍の経験のないモンゴル人が司令官です。
第二回になると旧南宋の軍人も大勢混じる。かれらは、遠征軍とはいいながら棄民に近いから、士気が高かったとは思えないのです。
モンゴルに服属したばかりの諸民族の混成軍が朝鮮半島、中国大陸別々のところから出発して対馬沖で合流する。陸上生活と違って、船ですから、各軍団の司令官同士の意志疎通や連絡もうまくいかなかった。
一言でいえば、元寇のモンゴル軍は烏合の衆、ということです。
しかも、水軍に不慣れであったし、遠征軍の乗った船が第二回では4400隻というのですが、その多くは突貫工事で高麗の船大工につくらせたものです。急造の粗悪船が多かった。だから、記録にも残らないような、ちょっとした風でも船が大きい被害を受けたり、司令官達が混乱したりしたのではないか。
フビライは1287年にはビルマ遠征とヴェトナム遠征、1292年にはジャワ遠征をおこなっていますが、全て失敗しています。
拡大し続けてきたモンゴルの勢いが、人的にも経済的にも限界に近づいていたのかもしれません。
------------
元の滅亡
------------
元は14世紀中頃から、宮廷内での内紛が激しくなる。また、チベット仏教に対する信仰が深くなって、大規模な寺院の造営があいつぎ財政を圧迫しました。財政難を乗り切るために交鈔を濫発したので、中国経済は混乱して各地で反乱が続発します。
特にマニ教と仏教を混合したような白蓮教という宗教が、一般民衆に浸透していて、この白蓮教を中心にした反乱が大きかった。これを紅巾(こうきん)の乱といいます。赤色の頭巾を巻いていたのでこう呼ばれた。
元ははじめは各地で起こる反乱を鎮圧しているのですが、そのうち面倒くさくなる。中国人から搾り取るために支配しているのに、反乱鎮圧に明け暮れていたのでは、中国支配のうまみがない。
1368年、モンゴル人たちは中国を放棄してモンゴル高原へ退去しました。元は滅んだのではなく、去っていった。
かわって漢民族の王朝である明が成立するのですが、その後も元は北元とかタタールとか呼ばれてモンゴル高原に存在しつづけていくのです。
元以外の諸ハーン国はどうだったか。
オゴタイ=ハン国は14世紀はじめにはチャガタイ=ハン国に併合されて消滅。そのチャガタイ=ハン国は東西に分裂、特に西部ではイスラム化と定住化がすすんでいきます。政治的にも解体していき、ティムールによって滅ぼされた。ティムールについてはあとで触れます。
キプチャク=ハン国は、イスラム化して14世紀前半には最盛期を迎えますが、15世紀末には領内にスラブ人国家モスクワ大公国が独立、また配下の部族がそれぞれにハン国を形成し自立していき16世紀には消滅した。
イル=ハン国は13世紀末に即位したガザン=ハンの時にイスラムに改宗し、大臣ラシード=アッディーンが行政・財政で国家運営を支えました。ラシード=アッディーンは歴史家としても有名でモンゴルの歴史を軸にして『集史』という世界史の本を書いています。これは覚えておくこと。
イル=ハン国は14世紀半ばにはフラグの血統が絶えて、分裂した。
諸ハーン国では、モンゴル人の数は圧倒的に少数でした。それが広い地域を統治するためには土着勢力と協力しなければうまくいかない。婚姻関係も結ぶし、その土地の宗教を、具体的にはイスラム教ですが、信じた方がうまくいく。こうして何世代か経つうちに、どんどんモンゴルの王族も土着勢力のなかに吸収され、なし崩し的にモンゴル帝国は衰退していった。
【参考図書】 クビライの挑戦 モンゴルによる世界史の大転回 (講談社学術文庫) 杉山正明著
第42回 モンゴル帝国の発展 おわり